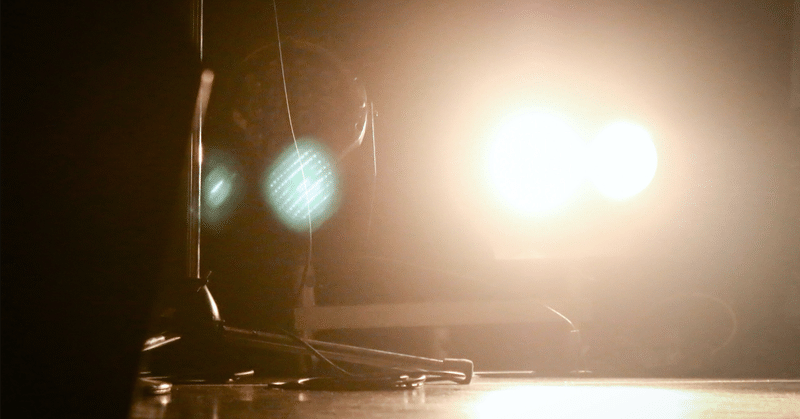
連載note小説「藤塚耳のコーライティング」第5回
「耳祭り」まで、あと6日
「耳ちゃん、残念だなァ。耳ちゃんは素敵なのに、どうして僕の好みの曲をやってくれないのかなァ。絶対そのほうが路上からのサクセスストーリー、天使の歌声きっと届くと思いマス」
そこまでフリック入力した手が震えて、ナマコはスマートフォンを地下鉄のホームに落っことした。着膨れした朝の通勤ラッシュで、棘皮動物たるかれの体壁はすっかり擦過傷だらけだ。まいにちナマコに通勤させるなんて、正気の沙汰じゃない。かれはそう思うが、日々の糧を得るためにはこのIT多重下請構造の一部になって、毎朝、毎夕、体液をちょっとずつこぼして都営地下鉄の車内を汚しながら、人間のダッフルコートやトレンチコートに揉まれて通勤するしかないのだ。長時間の通勤は、人間とちがってナマコの身体には無理がある。そのためかれは山手線内といういっけんぜいたくな立地環境に居を選び、ゆうに築50年は超えんとする、初老にさしかかったナマコよりさらに年上の古色蒼然としたアパートを新宿の職場にほど近い都心に借りるしかないのだ。それがまたナマコの生活を圧迫する。まったく、藤塚耳の歌声だけが、今やおれの救済だ、とナマコはおもった。そして愕然とする。3日前の、あのインスタグラム! ああ、ああ、ああ! このままいけば、その唯一の救済である藤塚耳の歌声すら、わけのわからないチャラいサムシングに飲み込まれていくらしい。ヒップホップか? ハードロックか? それとも、なんか、クラブで、かかっていそうな、そういう系の! ああいうやつか!「K-POPとかじゃなくてもっといろんな音楽聴いたほうがいいよ。俺の大好きな耳ちゃんなら分かってると思うけどネ(苦笑)」とせめてもの怒りをコメント欄で発散したかれは、ぬぷ、とからだをねじまげて改札を通過した。更新をわすれ、期限の切れたIC定期券が「パーポーン」といってエラーをかえすが、かれは憮然とした態度で人間には通れない改札の隙間をにゅるにゅるとすりぬけ逃亡する。
✳️
耳さん残念だなァじゃないよ、と耳は戦慄した。心をおちつかせるために、深呼吸して、スマートフォンを手から離し、少し休む。レコードマニアの父の隣で八代亜紀からキング・クリムゾン、ダリル=ホール・アンド・ジョン=オーツから電気グルーヴまでさんざん聴かされて育ったわたしに死角はないのだ、と耳は思いながら、ふたたびスマートフォンを手に取り「そうなんですね! 知らなかったです〜、すごいですね♪」とレスした。朝から気分が悪くなる。ただでさえ午前中は喉がひらかないため、歌うのに適したコンディションではない(耳の場合は)。歌いながら、歌詞にあうメロディーラインをさぐっていくのだが、頭が混乱してそれができるような状況にはおもえない。
日に日にインスタグラムをはじめとする各種SNSにおける、SSWおじさんの行動は危険をましていた。可愛さ余って憎さ百倍。もっとこんな歌を歌え、もっとこんな歌詞を書け、もっとこんな服を着ろ。その根拠となるのはいつも「路上からのサクセスストーリー」という言葉だった。男のなかで藤塚耳とは「じぶんが育てた、じぶんがコントロール可能なもの」であり、そのサクセスストーリーにのせてやるのだから、悪い話じゃないだろう、という観点から、男はつねにいわゆる「上から目線」で話すのであり、つまりはそれは説教であり、マンスプレイニングだった。マンスプレイニング。女性は物事を知らない、知識がないときめてかかって、だから教えてやるという意識・無意識の前提のうえで、男性がマウントをとって女性に説明・説教をしたがる現象。
耳は気持ちをおちつかせるため、しばらく室内を歩きまわったあと(警戒心から、音楽に必要のない外出は減少している)、自宅録音用のマイクの前にたち、すっかり書き上がった歌詞をスマートフォンのメモ帳で表示させ、片手で持ちつつ、みずからMacbookを操作して音楽制作ソフトの録音ボタンを押す。工のトラックが流れる。これにあわせてメロディーを歌う。
だが、何度歌っても同じことのくりかえしだ。亡霊が、「花束をあなたに」が首をもたげる。グローバルな、クールさとエッジを感じさせるトップライン(メロディーと歌詞の一体となったものの総称)ではなく、またしても、東京で生まれ育った耳自身のルーツが、べっとりと海藻のように耳のメロディーにこびりついていると感じられる。日本で生まれ育ち、日本の音楽を愛する耳が、その重力圏とそこに滞留するマンスプレイニングから抜け出すには、第二宇宙速度とよばれる、ある閾値を超えた速度まで一気に加速させる、そのようにも画期的なメロディーが必要なのだ。
耳はだが、もう同じあやまちは繰り返さない。ひとりでかかえこみ、創作を停滞させたりすることはない。書けなければ、信頼できる仲間に相談すればいい。そうやってコミュニティのなかで生きていくことができるのが、コーライティングという創作手法だ。
「耳祭り」まで、あと5日
JR新大久保駅の混み合う改札を抜けると、耳は早足で左にまがり、そしてすぐにもう一度左にまがり、裏路地をぬけて駅前の反対側に出た。背後に気をつけていたから、おそらくだれもついてこれていないはずだ。ひらけた通りに戻るとしばらく進み、住宅街の中にあるちいさなリハーサル・スタジオに到着した。コーヒーマシンとマガジンラック、どこの大陸に生えているのかわからない観葉植物がひとつ。せまくて急な階段をおりて地下にあるスタジオの二重ドアをあけると、工がちょうど持ち込んだMacbookとレコーディング用のコンデンサーマイクをセッティングしているところだった。
「大丈夫でした?」と開口一番ナオトがいった。ひと目につきにくいルートを通るようにすすめたのもナオトだ。
「とりあえず、誰にもみられずここまで来てるとは思います。昔いったお店の写真とかも、偽装でさっき、インスタにアップしました。」
「さすがに、大丈夫だとおもうんで、リラックスしていきましょう。今日は、ここでメロディーを固めていきます。もうトラックがあって、歌詞があるんだから、あとは歌うだけです。だけど、そのメロディーに迷ってしまった。そういうことですよね。」
「そうなんです。なんか納得いかなくて。」耳はうなずいた。
「歌詞、テキストで読ませてもらいました。工のトラックをしっかり聴き込んで、構成をうまくいかしてる歌詞になってると思いました。だから、まずはこの歌詞を信じてみましょう。もちろん、歌ってみたら、ちょっとイメージとちがった、みたいなことも大切な手がかりです。そういう箇所は、なにか重要な歌詞やメロディーのブラッシュアップのヒントになる場合がありますから。ともかく、やってみましょう。」
耳はマイクの前に立ち、ヘッドフォンをつけた。
とぅるるるるるるるるるるるる
リップロールとよばれる、レコーディング直前に喉のコンディションを整えるためのルーチンをおこなう。くちびるをふるわせながら
とぅるるるるるるるるるるるる
とくりかえす。ナオトも工も耳のボーカルをモニタリングできるようにヘッドフォンをつける。全員がヘッドフォン経由でトラックを聴くことで、室内には他の音がなくなり、耳の肉声だけがひびくので、これを録音するというわけだ。ナオトがそれを適切にディレクションし、メロディーの精度をあげて形づくっていく。工はひたすらに良い音質で、ベストパフォーマンスをのがさない。録り直す場合には、迅速に判断して別のテイクとして保管し、すべてのテイクはけっして削除せず保管しておく。各々がただ、みずからの仕事に集中する。
なんどか曲を通して歌い、「こんな感じではないか」という仮のメロディーを、耳はリラックスした声でさぐっていく。テイク1、テイク2、とかさねていく。
「あいよ」と耳がいった。「ちょっと休憩と、あと。」
「相談。」ナオトが言った。
「です。」耳がこたえた。
「なんだろうなあ」と耳はいった。「てみじかにいうと、わたし、相当自分のメロディーに、自信があるんです。こういうピアノならこう、こういうハーモニーなら、こういくとうまく歌える。うまく届く、って。」ナオトもうなずく。スタジオのだれもが、彼女のスキルとタレントに敬意をはらっている。
「でも、今回の音楽、アウェイじゃないですか。そこが心配なんです。こんなにかっこいいビートで、サビもサビっていうより、すごくビートが主役になる感じ。それで、ほら、決して忘れちゃいけない、今回の目的がありますよね。」
「防犯のためのコーライティング。」
「そうです。ストーカー行為から身を守り、ストーカーが失望することをねらって、防犯のためにK-POPスタイルの新曲をコーライティングする。それなのに、なんかなにをうたっても、良くも悪くもこれまでのわたし、これまでの藤塚耳らしさが残ってしまって。」
「防犯にならないんじゃないか、っていう?」
「そーなんですよ。」耳は苦笑した。「けっきょくこれを聴いても、またストーカーは、耳ちゃぁん、とか言って、あとをつけまわしてくるんじゃないかって。だいいち、よく考えたらそういうひとって、わたしのこと擬似恋人としかみてないと思うんです。最初から、最初から」と耳はいった。「音楽なんか、どうでもいいんじゃないかって。」
しばらく沈黙がながれたあと、耳が言った。
「ナオトさん、これ代わりにメロディー書いてくれませんか? ナオトさんもソングライターだから、それはすぐにできますよね? それにほら、コーライティングなんですよね? ひとりひとりが、コラボレーションするなら、そういう可能性も、きっとあると思うんです。それだって、このチームなら、藤塚耳の新曲として、3人がイーブンの関係でつくったものには変わりない。むしろ、藤塚耳らしさを壊す、藤塚耳らしくない、あたらしい音楽になれる。」
「藤塚耳らしくない音楽じゃなくて」とナオトが訂正する。「破壊、だけ、じゃなくて、創造もコミ、ですよね。藤塚耳を否定するんじゃなくて、あたらしい藤塚耳をつくるんですよね。」耳はうなずいた。
「だったら、せっかくなら楽しみましょうよ。」とナオトは言った。
べつに夜中までかかってもいいし、うまく歌えなくてもいい。そもそも、目的はレコーディングじゃなくて、ライブで歌う前に完成させることです。いちどレコーディングを経て、アーティストが歌い慣れると、曲がいかにも「ほんとうに完成した」というクオリティーに仕上がる、いや「さだまる」。そんな瞬間がありますよね?(耳はうなずく)。さだまっていないと、観客につたわってしまう。だから「さだめる」ためのレコーディングです。今日ここで耳さんが、歌ったメロディーに納得がいかなければ、どんなに派手な「いかにも」なメロディーでも、意味ないですよね。もちろん僕も、なんなら15分でメロディー、作ってみせますよ(ナオトは笑う)。でもそうじゃない。今回、いろいろ経てきた耳さんが、歌ってそれで、あたらしく作るメロディー。あたらしく作る藤塚耳そのもの。それを、ライブでお客さんに届けましょうよ。
「あきらかに藤塚耳だが、しかしけっしてもとの藤塚耳ではない。」というのが、とナオトは言った。「最高に防犯上の効果があります。」
耳はすとんと立ち上がって歌いはじめた。歌いはじめたメロディーには、なにも奇抜なところは見当たらなかったが、これまでより格段に工のトラックの音楽的な魅力をふかく感じ取り、なおかつナオトが指し示す安全上のゴール、すなわち「失望したストーカーがだまってライブハウス最後部のドアを蹴り飛ばして立ち去る姿」をまざまざとイメージさせるものだった。これまでめったに使うことのなかった、ファルセットとよばれる、いわゆる「裏声」ですら使わなかった、高音域のHi-G#の音も、すうっと地声で歌いこなすことができた。楽曲のクライマックスを歌い切ったとき、耳は深く息を吐き出し、かるく汗ばみながら、椅子にすとんと腰をおとした。この新しい曲を、このさきずっと歌い続けるだろう、という確信をもつことができた。それはOKをだしたナオトも、録音停止ボタンをおした工もおなじだった。深夜までつづいたレコーディングで、バッキングボーカルやフェイクといった、メインボーカルをささえる多数のサブテイクも収録を終え、ひとつのコーライティングのゴールである新曲が完成した。データのバックアップを取り、機材を撤収する工に、ありがとう、とふたりで伝えたあと、遅い時間の住宅街なんで、送っていきますよ、といって、ナオトは耳を新大久保駅前まで送っていった。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
