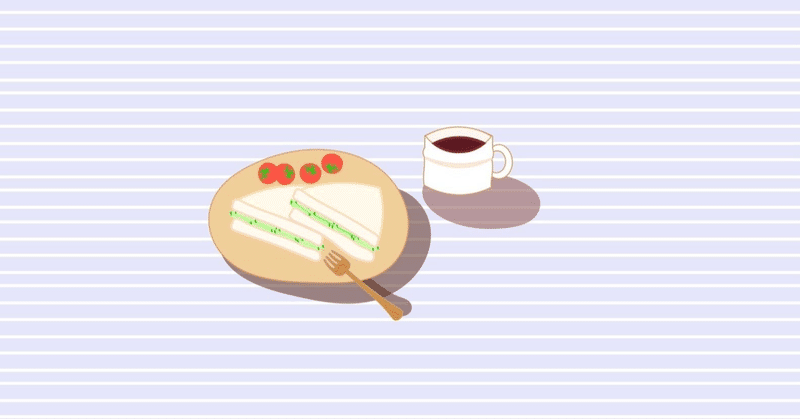
いつかふたりになるまで
「おはようございまーす」
午前9時半。開店前の薄暗い店内は静かで、わたしは少し寂しいこのひとときが好きだ。
夫と中学生の息子一人。家計は苦しくないけれど、たまには外の空気も吸いたくて、わたしは駅前のカフェでアルバイトをしている。田舎の半分死んだような商店街にある、田舎とは思えないようなお洒落なカフェで。
残念ながら、いや、当然ながら、と言った方が相応しいだろうか。店のコンセプトに反し、お洒落な人は滅多に来ない。遠くから来る人がいるかもしれない、と、店長はせっせと「ばえる」写真を撮ってSNSに載せているようだが、実際によく現れるのは、暇を持て余す近所の老人や、オーナーの友人といったところだ。
数週間前、「リール撮るんで、おぼん持ってそこ横切ってもらえますか」と店長に頼まれたわたしは、「リール」が何かも知らずに応じたのだが、のちにそれが全世界に公開されるものだと知り少々慌てたのだった。
時々、「ランチセットありますか」と聞いてくる家族連れもいる。しっかり食べたいのに、と残念そうにされると申し訳ない反面、ここはファミレスじゃないんだよ、とも思う。
「もうちょっとボリュームのあるものがあれば、お客さん増えますかね?」
店長に尋ねてみたことがあった。
「うーん…オーナーが言うには、ココのターゲットは『40〜50代マダム層』で、お腹いっぱいになることを求めてないそうで…。今のキャパだと食材増やせなそうですしね〜」
20代前半の店長が他人事のように言う。
稲作中心の超高齢片田舎におけるマダム層の集客、か…。少し非現実的な気もするが、マダムという響きでお洒落度が増すと信じているのか、店長はいたって真面目顔である。
ん?カフェでの立場上意識していなかったが、年齢だけならこのわたしもれっきとした『ターゲット層マダム』のひとりではないか。
「マダムだからってお腹を満たしたくない、とは限らないかも…」
そう言いたい衝動を抑えて、「なかなかメニュー変えるのも大変ですもんね」と話を終わらせたのだった。
若い頃は色々なバイトをしたけれど、半年から一年ほどでうまいこと理由を見つけて辞めてきた。付き合いはあっさりしたものを保つし、経営に口を挟むほど存在を懸けることもしない。物事をこじらせたくないのだ。
そしていつか習慣に別れを告げて、次にしてみたいことを始める。セピア色の写真で埋まったアルバムを閉じて、順番待ちの真っ白なアルバムを開くように、生き直す。
そうやって、やってきた。
飽きてしまうのだ。人間関係に。単調な毎日に。過ぎゆく時間に安住する自分自身に。
久しぶりのバイトとなるここは8ヶ月めになる。きっと何かがわたしをまだ留めているのだろう。たとえば、いつも同じ分量で、同じ大きさのマフィンを作ること。シンクをピカピカに磨くこと。家庭の外で、誰かのために働くことの新鮮さ。オーブンを開けるときの香ばしい甘い香りから得られる満足感。それに自分が自由にできるお金が、少しだけど毎月入ってくるという達成感。そういった諸々に、わたしはまだ飽きていない。もしかすると次が見つかっていないだけで、今の日々は夫と息子だけに向き合ってきた年月を綺麗にセピア色にしてくれている最中なのかもしれない。
時おり、こういった感覚を無性に誰かと分かち合いたくなるのだが、その相手は無論家族ではなく、たぶん家庭をもつ女友達なのだろう。けれど、あいにくわたしには気軽に胸の内を語れる友人と呼べる存在がいない。
まさか店長にこんな話をするわけにもいかないし…。確か、今年23歳になると言っていた。
23か…。
その頃付き合っていた男は、日曜日の朝によくサンドウィッチをつくってくれた。特段予定のない、前夜ふたりで遅くまで飲んだワインがまだグラスの底に残っている、気だるい朝。ツナときゅうりを、塩こしょう、マヨネーズで和えて、それを食パンにたっぷり挟んで、お皿に載せてくれる。横には美しく斜めにカットしたバナナなんかを添えて。なんでもない風にチャチャッと用意する器用な男。ワンルームの、おんぼろアパートの小さなキッチンに立つ背の高い後ろ姿を、わたしはベッドの中でモゾモゾしたまま眺めるのが好きだった。運ばれてきた(と言っても、数歩でキッチンからベッドにたどり着くのだが)ふっくらしたサンドウィッチを頬張る。
だけど、お姫様気分はごちそうさまとともに終了するのであった。
男が使ったあとのキッチンはひどく散らかっていて、おまけに彼はそれをそのままにしておくのが平気な男だった。食べた後は、満足そうに窓辺で煙草をふかしている。
つくるのは好きだが、散らかったキッチンは片付けない男。油だらけのナイフとツナ缶、飛び散ったマヨネーズ、開けっ放しの塩こしょうの蓋、投げ出されたままのバナナの皮。
放っておけばいつかは片付けたのかもしれない。だってサンドウィッチができるまではふつうのキッチンだったのだから。でもつくってもらったから、といううわべの理由と、その「いつか」が待てないという至極主観的な理由で、わたしはいつも片付けをした。黒ずみ始めたバナナの皮をつまみ、皿を洗うわたしは頭の片隅で「この人とは結婚しないんだろうな」なんていう冷静さを保ちながら恋をしていたのだった。
ベッドの横のローテーブルには彼の淹れてくれたコーヒーが待っていて、そこに行けば、彼は優しくわたしの肩を抱いてくれるのに。
いつも自分で淹れたコーヒーを飲む今のわたしは、あのサンドウィッチの男に「ありがとう」を言えるくらいにはオトナになれただろうか。
もう二度と会うことはないだろうけれど。
「オーダーお願いします」
店長の声で我にかえる。
2番テーブルにはふたり連れの50代女性。
「パスタとかない?」
「すみません、サンドウィッチなら…」
「そう。じゃ、いいわ。ホットコーヒーで」
「あたしもホット」
「はい、かしこまりました」
パスタか。ターゲット層でも食べたいときはあるよね。パスタであってもメニューに追加できないものだろうか。
わたしはパスタが大好きだ。ひとり暮らしをしていた頃、夕飯はほぼパスタだった。定番はパルメザンチーズをたっぷり振りかけたトマトソースパスタ。できれば具も用意する。具材はツナだったり、なすやパプリカ、それとも玉ねぎとベーコン、はたまた卵にソーセージ。新鮮なマッシュルームが手に入ったら、にんにくと一緒にサッと炒めて醤油を垂らして和風パスタに。海苔を刻んで夏はミニトマトや青じそを飾っても良いかもしれない。
お手軽な上に栄養も十分摂れるパスタ料理。今は家族に「また?」と言われてしまうから控えているけれど、ひとりだったら飽きずに食べるに違いない。
ゆっくりとフォークにくるくる巻いて、時間を忘れて味わう。200グラムくらいは食べたい。たとえ「マダム」だとしても、パスタにはがっつきたいのだ、わたしは。もちろんひとりで。そういう至福は、ひとりに限る。
わたしは外食では絶対にパスタは頼まない。
ミヒャエル・エンデの作品『モモ』の映画の中で、モモがおじいさんとおしゃべりしながら食べるスパゲッティは、ソースもないシンプルな、ただのスパゲッティなのだけど、オイルでふたりの唇が艶やかに光っていて、それがわたしにはどうしても美味しそうに見えたのだった。見つめあってふたりで食べるスパゲッティ。幸せな、モモとおじいさんのひととき。
このわたしにはいつか、ひとりではなくふたりで至福を味わいながら、スパゲッティを食べられる日が来るのだろうか?
電動ミルのスイッチを押し、挽き立てのコーヒーの香りを深く吸い込む。この香りがたまらない。コーヒーメーカーにフィルターと粉をセットし、水を入れて、黒い液体が落ち切るのを待つ。
「お待たせしました、ホットコーヒーです。お砂糖、ミルクはお使いになりますか?」
飲んでみないと濃さがわからないだろうとも思うのだが、置こうとすると急いで「いらない、いらない」と断るお客もいるので、少し面倒だがいつも聞くことにしている。
そういえばパスタを食べる時に啜る音を出す、あの男の食べ方も好きではなかった。
最初は声もしぐさも、思い出すとふわふわするくらい好きだったはずなのに。同じ場所にいられるだけで景色が鮮やかに見えていたはずなのに。だんだんと、思い出そうとしても輪郭は歪み、頭の中には霧がモヤモヤと立ち込めてくる。いや、むしろ幻想という雲で覆われた空が晴れてくるのかもしれない。
見えていなかったものが見えてくるのか、見えていたものが見えなくなるのか。
結婚し子どもが産まれ、もう恋なんかとは疎遠になっても、ふと追憶の材料として存在している過去が、わたしは愛おしい。人生で大恋愛をしようがしまいが、いずれにせよひとりである自分にとっては、終わりよければ全てよし、なのかもしれない。
コーヒーだけを頼んで半時間ほど談笑したご婦人方は、砂糖もミルクも2つずつ使って帰っていった。彼女たちにはわたしの淹れたコーヒーは少し濃かったのかもしれない。
テーブルを片付け、静かになった店内を見回す。汗ばむ陽気の今日は、夕方また少し人が来るかもしれないから、アイスコーヒーを作り足すことにしよう。
ひと雨降りそうな、雲行きの怪しい空だ。
「いらっしゃいませ」
店長の声がする。予想通りだ。涼しくなり始めた午後3時半。
「アイスコーヒーとツナサンド、1番にお願いします。あ、コーヒー作ってくれたんですね、ありがとうございます」
「はい、そろそろ出るかなと思って」
ツナサンドの具材を冷蔵庫から出し、パンをトーストする間に、グラスに氷を4つ入れて、アイスコーヒーを注ぐ。
1番、1番…
テーブルに近づいてわたしは目を疑った。
「あ、やっぱり。これ見て来てみたんだ」
差し出されたスマートフォンには、いつかのリール動画が写っていて、それを持つ手は、わたしが大好きだった、あの器用で大きな手だった。
灰色の空からは、何粒も何粒も大粒の雨が落ちてきて、窓を激しく濡らしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
