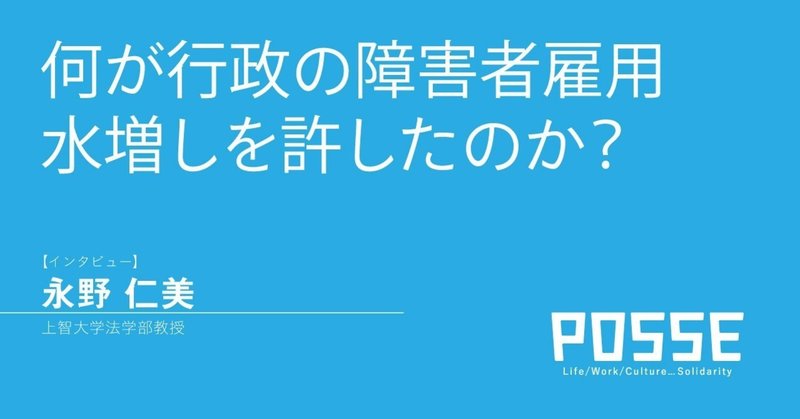
【記事公開】何が行政の障害者雇用水増しを許したのか?ー 医学モデルと社会モデルの谷間/永野仁美
2018年8月、中央省庁をはじめとする公的機関での障害者雇用の水増しが相次いで発覚しました。民間の模範となるよう法定雇用率を守るべき行政でなぜこのような過ちが起きたのでしょうか。行政の言い訳を許してきた「障害者の定義の問題」に焦点を当て、上智大学の永野仁美先生に話をうかがいました。
本インタビューは、2018年10月22日に公表された検証委員会の報告書が出る前に行われたものであり、検証委員会の報告書の内容を踏まえたものではありません。
■公的機関の障害者雇用水増しはなぜ起こったのか?
―公的機関の障害者雇用水増し問題がニュースで話題となりましたが、その原因や背景について永野さんはどのようにお考えですか。
水増しは長期間にわたりおこなわれていたと報道されています。長期間これが見逃されていた背景には、障害者雇用に対する社会の関心の低さもあったと思います。それが、現在の障害者雇用に対する関心の高まりを受けて明らかになった。水増しは残念なことですが、いままで隠されていた問題が明らかになったことは、一つの進展だと思います。
ただ、障害者雇用への関心が薄かったとしても、水増しが長期にわたり放置されて良いはずはありません。なぜこのような問題は起きたのでしょうか。推測になりますが、まず、公的部門は民間部門の「模範」とならなければならないということで、「数字をよく見せたい」という気持ちがなかったとはいえないだろうと思います。しかし、仮に「数字をよく見せたい」という気持ちがあったとしても、チェック体制がきちんとしていれば水増しは起きません。チェック体制の甘さがこのような状況を長引かせてしまった原因ではないかと思います。
それでは、公的部門の障害者雇用にはどのようなチェック体制が敷かれていたのでしょうか。民間企業に対しては、雇用率が未達成であれば納付金の支払い義務が課されます。お金が絡みますので、雇用されている障害者数を正確に公平にカウントする必要があります。そのため、民間企業では障害者を実際に雇用していることを示すために障害者手帳のコピーの提出を求められるなど、より厳しい手続きが課されていたようです。しかし、公的部門は、雇用率を達成していようとしていまいと納付金の支払いはありません。これも理由の一つとなり、制度上のチェックが甘かったのではないかと思います。もちろん、公的部門も、毎年障害者の勤務状況について厚生労働大臣に報告しなければなりません。しかし、たとえ状況が悪くても、公的部門では厚生労働大臣がそれに対して勧告を出すという程度のことしかおこなわれません。
これらのいくつかの要因が重なって、今回のような問題が起こったと言えるでしょう。そして、もう一つ根本的な原因として、障害者の法的定義のあいまいさも挙げることができます。公的部門の側からの主張として、障害者雇用促進法が定める障害者の範囲が、実はよくわからないではないかということがありました。たしかに、これをどのように解釈するべきかという問題もあったと思います。
■日本における障害者雇用促進法の歴史
―今回問題になっている障害者雇用促進法が、そもそもどういう目的や文脈で発展してきたのかについて教えてください。
日本の障害者施策は雇用に限らず、身体障害者に関するものから発展していきました。背景には、戦争で障害を負った傷痍軍人に対する施策をまず講じなければならないということがありました。そこからスタートして、次第に、知的障害者、精神障害者へと施策の対象が拡大していきました。障害種別ごとに施策は発展してきたわけです。
雇用に関しては、1960年に身体障害者雇用促進法が制定され、身体障害者を対象とする雇用義務制度が始まりました。しかし、当初は事業主に課される義務は努力義務でした。いきなり強い義務を課すと、事業主に大きな負担がかかります。そこで、まず緩やかな努力義務から始めるわけです。そして、事業主の側で障害者雇用に対する準備が進んだ段階で、法的義務が課せられることとなります。それが1976年です。法的義務になったことに伴い、納付金制度がつくられました。これにより、法定雇用率を未達成の企業は納付金を支払わなければならないということになりました。
身体障害者の雇用義務が強化されていった一方で、1980年代には、国際障害者年等の国際的な動きを背景として、知的障害者も雇用促進法の適用範囲に含めるべきではないかという考えが広まっていきます。そこでまず、知的障害者を雇用した場合には、企業は当該知的障害者を雇用した障害者としてカウントして良いことになりました。それが1987年です。知的障害者の雇用義務化はまだなされていませんから、法定雇用率の計算方法自体は変わっていません。知的障害者の雇用義務化はその10年後の1997年に実現され、以降、知的障害者の数も勘案して法定雇用率を決めることになりました。
精神障害者の雇用義務化は、2013年の法改正で実現しました。2013年の法改正は、障害者権利条約(注1)の批准に向けた国内法整備の一環でもありました。特に、2013年法改正で導入された、障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務については、権利条約の影響が非常に大きかったといえます。
精神障害者の雇用義務化については、実は2013年の法改正で実現するかどうか微妙な状況であったとも聞いています。精神障害者の雇用義務化がなされると、法定雇用率がアップします。そのため、より重い義務を課されることとなる企業側は大きな抵抗を示します。その企業側の人たちを説得してまわった当時の担当課長の尽力により、精神障害者の雇用義務化は実現したといえます。それを支えたのは、やはり権利条約の存在だったのではないかと思います。
■雇用促進法における障害者の定義の谷間
―改めて障害者雇用促進法における障害者の定義問題について教えてください。
障害者雇用促進法は、雇用義務制度以外にも様々な規定を置いています。職業リハビリテーションや差別禁止、合理的配慮提供義務などです。これらの諸規定の適用対象となるのは、第二条にその定義が書かれている「障害者」(注2)です。
それに対して雇用義務制度の適用対象者は、身体障害者、知的障害者、そして精神障害者保健福祉手帳を持っている精神障害者に限られています。ただ、身体・知的障害者をどう捉えるかということに関しては解釈の余地があり、今回公的部門の人たちの「言い分」の一部を一理あるものにしてしまっています。
―雇用促進法の対象者について、雇用義務においては手帳を基準にしている一方で、合理的配慮提供義務などの諸規定に関しては手帳の有無を問わないのはなぜなのでしょうか?
そもそも障害者か否かの線引きは非常に難しいということがあります。合理的配慮に関しては、事業主は障害の有無があいまいな状況でも必要があればこれを提供するのではないかと思います。たとえば、メンタル不調を抱える労働者に対して、企業の側は「病気かどうかはよくわからないけれどもこれは休ませたほうが良い」と考えるのではないでしょうか。しかし、雇用義務制度の適用範囲に関しては、納付金の支払いというお金も絡みますので、企業間の公平にも鑑みてその適用範囲をより明確にする必要が高まります。
この要請もあり、民間企業については、雇用義務の対象となる障害者の確認は、原則として障害者手帳を用いておこなってきました(以下、身体障害者について説明)。なぜ障害者手帳を利用するのかというと、障害者雇用促進法における身体障害者の範囲と手帳制度を定める身体障害者福祉法における障害者の範囲はほとんど同じだからです。両法が別表で示している障害者の範囲は同じです。ただ、身体障害者福祉法では、身体障害者とは「別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者」で「身体障害者手帳の交付を受けたもの」となっていますが、障害者雇用促進法では、単に「身体障害があるものであつて別表に掲げる障害があるもの」となっています。障害者雇用促進法では、「身体障害者手帳を有する者」という要件はありません。
身体障害者福祉手帳の取得は本人の意思に任されていますから、手帳を取得していない身体障害者もかなりいるのではないかと思います。公的部門ではこうした人たちを身体障害者としてカウントしていたのだという解釈もありえなくはありません(実際には、これを超える範囲でのカウントもあったようですが)。しかし、厚生労働省は、範囲を明確にする必要性もあって、民間企業に対しては原則として手帳で障害者の範囲を画するとし、障害者手帳のコピーの提出も求めてきました。障害者の範囲についての行政解釈は、手帳を有する障害者だったわけです。民間企業にも、手帳をもっていない障害者や手帳の取得の有無を企業が把握していない障害者はいるはずです。しかし、民間企業ではこれらの人たちはカウントせずに実雇用率の算定をし(低ければ企業イメージにも影響するでしょう)、法定雇用率未達成の場合には納付金を収めてきたわけです。民間部門と公的部門とでカウントの方法に差異があったことは、批判されるべき大きな問題だと思います。
―雇用の場面における障害者の定義があいまいなまま、福祉における定義(障害者手帳を持っているか否か)を援用してきたことが今回の「水増し問題」にもつながっているのですね。
そうです。ただし、障害者手帳で雇用義務制度の対象となる障害者の範囲を画すること自体にも問題はあります。身体障害者福祉法は、いわゆる医学モデルで障害を捉えています。そこから、就労の場面での障害の捉え方が医学モデルで良いのかという問いが生じ得ます。たとえば、下半身麻痺は医学的には非常に重い障害ですが、デスクワークであれば問題なくできる場合があります。その一方で、発達障害など障害のレベルとしてはそれほど重くないけれども、コミュニケーションが上手くとれず就労に対する困難性は非常に高い場合もあります。就労の場面において医学モデルで障害を捉えることの是非は問われるべきだと思います。
本記事の公開はここまでとなります。本誌掲載のインタビュー記事では、このあと社会モデルによるフランスの障害者雇用の実践や、日本の長時間労働を前提とする過酷な働き方を障害者雇用の文脈から問い直していくことの必要性などが展開されています。ご関心のある方はぜひ本誌を手にとって続きをお読みください。
***********
(注1)障害者権利条約
2006年に採択された国際条約。加盟国に対して市民的・政治的権利、教育を受ける権利、保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、障害者保護の取り組みを求める。日本は2014年に批准。
(注2)「障害者」の定義
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第6号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。(障害者雇用促進法第2条第1項より)
永野仁美 上智大学教授
専門は社会保障法。フランスの社会保障法と労働法の双方の観点から、障害者関連施策の研究をおこなう。共編著に『詳説 障害者雇用促進法―新たな平等社会の実現に向けて(増補補正版)』(弘文堂、2018年)、共著に『障害者雇用における合理的配慮』(中央経済社、2017年)など。
関連情報
・POSSE40号(特集「教員労働問題と教育崩壊」)内容紹介!
・POSSE vol.40(特集:教員労働問題と教育崩壊)入荷店一覧!
・雑誌『POSSE』ってどうやって買うの?
・最新号・バックナンバーのご購入はこちらから
・定期購読はこちらから(定期購読は20%オフです!)
POSSEの編集は、大学生を中心としたボランティアで運営されています。よりよい誌面を製作するため、サポートをお願いします。
