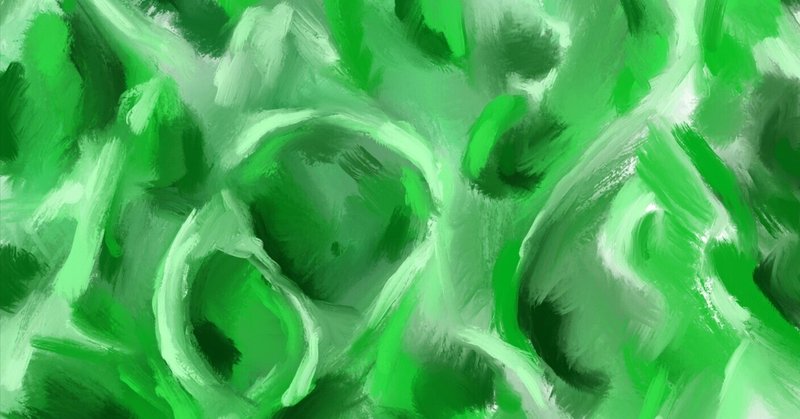
木崎みつ子『コンジュジ』
仮に小説として不出来だったとしても称賛するつもりで『コンジュジ』を手に取った。トラウマというセンシティブな問題に対峙しようとした作者を応援したい気持ちがあったからだ。読み進めるにつれ、僕の気持ちはどんどん盛り下がっていった。小説の文章が下手なのはいくらか目を瞑るつもりでいた。問題は、それが「いくらか」と言える程度に留まっていなかったことだ。
いちいち指摘していたらキリがないものの、愚にもつかない比喩の連続は目も当てられない。《水を得た魚のように》《小鳥と一緒に青空を飛べそうな》《七福神のメンバーのような人間》《遊牧民のようにバンで大学を回り》《女性用シャンプーCMの如くサラサラの髪》《洪水のように流れ出る鼻水》etc……これらのくだらない比喩は(ギャグでない限り)作品の品位を落とすだけなので、削除したほうがいい。
冒頭のせれな(主人公)と父親と内縁の妻の関係についての説明はまだいいとしよう、リアン(主人公の空想の人物)の過去について「~らしい」「~そうだ」と単調な文章が延々と続くのには辟易した。「海外のバンドマンって、こんな感じで合ってる?」と首を傾げる作者の姿が頭に浮かぶようなステレオタイプな回想――いつの時代の少女漫画に毒されているんだよ!――が何頁にも渡って延々と続く。
『もう、沈黙はしない・・性虐待トラウマを超えて』の著者・矢川冬さんが教えてくださった情報によると、『コンジュジ』の作者は小説を書くにあたり性的虐待の当事者の著書やブログを渉猟したそうだ(作者にとっては、「それらの参考文献からアイデアを得て小説を書いた」というより、「それらの参考文献を読むことで小説を書き続けることができた」という意味合いであるようだ)。閉鎖的な空間で繰り返される性的暴行、周囲の無理解によるセカンドレイプ……この作品にはサバイバー「あるある」が並べられている。
この作品のつまらなさ――というより、致命的な欠陥――は、サバイバー「あるある」描写の一個一個の精度が低いせいで、性的虐待の被害者が抱くだろう恐怖をきちんと書き出せていないことにある。端的に言えば、リアリティを欠いている、ご都合主義な展開が目立っている。
小説の中盤、高校生のせれなは《もういい、言ってしまえ。溜め込む必要はない。どうせ我が家は崩壊している。学校だって行けなくなってもいい。ホームレスになってもいい。》《殺されるかもしれないが構わなかった。》と意を決し、性的虐待の加害者たる父親に向かって暴言を吐きまくるという反撃に出る。
僕はこの時点で、この小説は終わった、と思った。作者は性的虐待の被害者の書籍やブログから知り得た知識や体験をなぞっているだけで、被害の実態、トラウマへの理解が及んでいない印象を受けた。被害者が加害者に面と向かって反撃するのは、およそ現実的と言えない。小学生の頃から性的暴行を加えてきた実の父親が相手、しかも相手と二人っきりの逃げ場のない密室であれば尚更だ(《ごぼうみたいに痩せた年寄り》と父親は描写されるが、せれなの年齢から40~50代と推測される、決して弱々しい相手とは言えないだろう)。《今でも怖い。》と取って付けたようにせれなの心情が描かれるものの、そこに生々しい恐怖の手触りはない。
僕が知らないだけで、二人っきりの密室で加害者に面と向かって挑発しまくる被害者がどこかに存在するのかもしれない。そういう闘争心あふれる勇敢な(勇敢過ぎる)当事者がいたとしても、ごくごく珍しいケースではないか? サバイバーの過酷な現実を反映させた血の通った筋書きでなく、サバイバーへの取材を欠いたまま作者が頭の中だけで組み立てたザルな筋書きに思える。内縁の妻がせれなの父親を殺害し、父親による報復の心配が消えるという展開も、あまりにご都合主義が過ぎる。
作者は、矢川さんに宛てたメールで、
「性虐待」という問題は、当事者ではない人間が安易に扱っていいものではないということは承知しているつもりなのですが、何年もずっと「こんな世の中を変えたい」という願望があり、小説というフィクションで自分の思いを表現いたしました。
と記している。
「こんな世の中を変えたい」、それは立派な心意気だ。
だとすれば、だ。
数年前は怒鳴る父を見て震え上がった。今でも怖い。だがせれなはもう親に口答えできない小学生ではない。
これは、”親に口答えできる年齢になっても(トラウマの影響によって)口答えできないでいる” 当事者に失礼ではないか。作者に悪意がなかったとしても、現在進行形でトラウマの後遺症に苦しんでいる被害者への配慮を欠いていると言える。
――もっとも、文学は道徳の教科書ではない(これは日比野コレコの小説の感想でも書いた)。「当事者」を扱うからといって、「当事者」の顔色を窺う必要はない。そうは言っても、《こんな世の中を変えたい》という立派な心意気を持った作者であれば、当然「当事者」に対してなるべく配慮したいと考えているだろう。そういう意味で、《せれなはもう親に口答えできない小学生ではない》の一文は一考の余地があるのではないかと指摘しておく。
小説の終盤、《天井から楕円形の黒い物体がふよふよと飛んできた。黒い物体はせれなの腹の上にペッタリ張りつくと、瞬きよりも早く人間のシルエットになった》といった魑魅魍魎じみたフラッシュバックの描写にはぎょっとした。僕の知るフラッシュバックと比べてあまりに異質だったからだ。僕個人の見聞が全てではない、現実にそのようなフラッシュバックを体験する当事者もいるのかもしれない。一方で、作者がフラッシュバックの実態をよく知らないまま過度に誇張しているのではないかという疑念も抱いた。三人称が客観的に物事を捉える役割を充分に果たしていると言えず、さらに全編にわたって脇の甘い表現が散見されるため、作者の意図した表現なのか作者の無知ゆえの表現なのか区別がつかないのだ。
せれなはサバイバー「あるある」の行動をなぞりながらも、肝心なところで作者の延長(コマ)としての振る舞いを見せる。作者の観察の不徹底は、父親、叔母、叔父、バイト先の同僚といった人物造形の粗雑さにもあらわれている、元妻、内縁の妻に至っては、(正確な引用ではないが)「自己中心的な頭の悪い女」「無口で大柄な異国の女」といった粗末な説明書きで済まされてしまう、描写にすらなっていないチープな説明を継ぎ接ぎして一丁上がり、作者は真面目腐った顔で「生身の人間」をなぞったつもりになっている。
せれながリアンの棺桶に入って眠りに就く結末は、残念ながら滑っている。リアンと父親のイメージを重ねるような描写をしながら、せれなをリアンの棺桶で眠らせようとする作者の意図は何か? これでは――作者が否定したとして――せれながファザコンを拗らせている解釈もできてしまう。妄想の人物との対話によって安らぎを得る当事者は現実に存在するだろうが、サバイバーが妄想の人物との対話によって自己完結的な癒しを得るオチは、「こんな世の中を変えたい」という問題提起として「最悪の一手」だと言える。
せれなの一人称を採用して解離の症状の酸いも甘いも含めて描き出すか、三人称の最大の利得である分析的な視点からサバイバーの現実を炙り出すか、いくらでも工夫はできたはず。せれなの妄想ばかりを強調し、妄想の描写と対を成すはずの現実の描写をおざなりにするくらいなら、三人称ではなく一人称を採用したほうがよかったのではないかと僕は思う(おそらく、この作者には三人称より一人称のが合っているだろう)。
『コンジュジ』の川上未映子の帯文にも引っ掛かった。
とんでもない才能。
サバイブの果てに辿り着く、
こんなに悲しく
美しいラストシーンを
わたしは他に知らない。
深く、胸を打たれた。
サバイバーの現実は、おそらく川上にとって対岸の火事なのだろう。『コンジュジ』は主人公が妄想上の過去の恋人の棺桶で眠りに就くところで幕を閉じるが、これが《サバイブの果て》――? どう考えてもサバイブの過程だろう。トラウマは、PTSD・解離の多岐に渡る後遺症は、そうそう癒えることがない。子供時代に虐待を受けた被害者は精神疾患・身体疾患のリスクが跳ね上がるというACE(adverse childhood experiences=子供時代の有害な体験)研究もあるくらいだ。
親による性虐待のむごさは、その光景が脳裏に一生浮かぶことにある。私は家族(母親、妹)にいつまでもいつまでもそんなこと言って!いい加減に忘れろ!と怒鳴られたが、自分の意志に関係なくその光景に揺さぶられるのだから、揺さぶられるな!と怒鳴った家族(母親、妹)もまた想像力の無いむごい人間だった。
川上なりのある種の文学的なポーズとして《サバイブの果て》という言葉がうってつけだったのかもしれないが(それにしても陳腐だ)、そんな書き手のナルシスティックな欲望を満たすためにサバイバーの現実を利用するのはやめろと声を大にして言いたい。川上は現実に存在する性的虐待の被害者に対する想像力が乏しいがために、トラウマを抱えた当事者の実態を甘く見積もっているのではないか、そうでなければ《サバイブの果て》などという安易な表現は畏れ多くて使えないはず――と、書きながら、僕はずいぶん前に読んだ川上の『ヘヴン』という小説を思い出した。
『ヘヴン』はいじめを受けている中学生の男の子が主人公の作品だった。いじめの描写のリアリティのなさ(一般的な中学校ではあり得ない状況下でいじめが繰り返される)、主人公の斜視が治ったおかげで世界がきらきらと美しく金色に輝いて見えたという三文小説じみた結末に愕然とした記憶がある。ここから川上の希求する虚構のリアリティレベルはユルユルということが分かる。だからこそ、川上は『コンジュジ』を読んで「これがサバイバーの現実……ッ!」と《深く、胸を打たれた》のか? 僕はそんな邪推までしてしまった。
『コンジュジ』を読みながら、僕は『愛と呪い』(ふみふみこ)という漫画を思い出した。

『コンジュジ』、『愛と呪い』、いずれも性的虐待のトラウマが主題となっている点で共通している。『コンジュジ』はサバイバー「あるある」を粗雑な筆致でなぞっただけで終わっているのに対し、『愛と呪い』は迫力ある表現でもってサバイバー固有の孤独感を炙り出している。
創作活動に優劣はない。結局のところ、作品の良し悪しは各々の読者の好みによって判断される(「文学の霊感」も例外ではない)。その上で、僕は自分の立場から評価を述べたい、『コンジュジ』が純文学の権威・すばる文学賞を受賞した小説でありながら掘り下げの浅い(ライトノベルと親和性の高い)作品とすれば、『愛と呪い』はエンタメ寄りの雑誌に掲載された漫画でありながら歴とした文学的強度を湛えた作品だ、と――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
