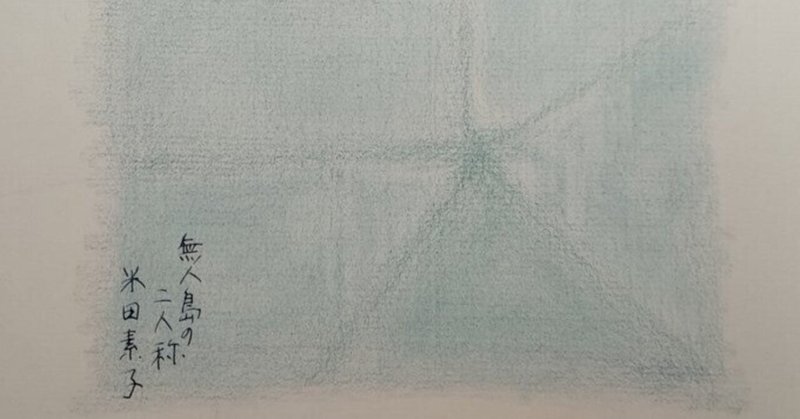
解読 ボウヤ書店の使命 ㉙-3
長編小説『無人島の二人称』読み直し続き。
《第一章
――二〇一六年 初夏
井上恵三の経営する喫茶みなみは駅から遠く、山道の途中にある。駅裏に酒店を構えている大野太一にしてみると、少し気の毒なように思えていた。
「親が選んだ場所だから、二代目として引き継ぐ僕としては、余程の事がない限りは移転できないよ」
恵三は肚を括っているらしい。「太一さんの親は先見の明があって羨ましい。親の時代には駅なんかなかっただろうけど」
「喫茶店なら隠れ家的な立地がむしろいいでしょう。恵三さんのお店が繁盛しているのは立地だけじゃなくて、味もいいからなのだろうけど」
太一はお世辞を言ったわけではない。恵三の店は場所柄、仕入れなどには苦労しているようだったが、固定客の訪問が途切れることはないようだった。
「こんな山の中にある店にまでわざわざ来てくれるんだから、嬉しいよね」
いつでも少し勝ち誇った顔も見せる。
恵三はオーディオマニアでもある。音楽鑑賞が趣味というよりは、古いアナログレコードを最善の音色で鳴らすことに興味があり、レコード屋の袋を持って太一の店に現れると、「新しい楽曲を手に入れたから、僕のシステムで鳴らすのを聴きに来てよ」と言うに決まっている。
太一としてはジャズもクラシックもそれほど興味はないのだが、誘われたら断りはしない。酒好きの酒屋というのは実に因果な商売で、そんな機会でもなければ町の呑み屋に行く気になれず出不精になる。自分の店の棚には旨いとわかっている酒がずらりと並んでそれらの原価は百も承知。呑み屋では場所代や氷などのサービス料が乗るのは当たり前で、わざわざ利ザヤを取られる外呑みに行っては、つい、原価プラスいくらだと勘定して楽しめないのだ。結果、家で呑むばかりとなる。だから恵三に誘われると音楽目当てのふりをしつつ、ここぞとばかりにとっておきのウィスキーなどを一瓶持って出掛ける。ほとんどの場合、恵三の学生時代からの友人である山岸が、早々と腰を据えてワインを呑みながら待ち受けている。ワインに合うのかどうかわからない焼き鳥や豚肉の角煮をテーブルに広げて、「太一さんも、どうぞ」と勧めるのだった。
だからその日も恵三が店に現れた時には、てっきりそのお誘いだろうと思って、ならば数日前に新しく試飲を勧められたイタリアワインでも持って行こうかとの考えが頭をよぎったのだが、恵三の手元を見るとレコード屋の袋はなく、純粋に酒を買いに来たのだろうかと珍しがっていたら、ちょっと聞いてくれと神妙な顔をして言う。
「山岸の奥さんのことなんだがね、驚くなよ」
首を後ろにひねって店内を見回し、誰もいないかを確かめていた。
梅雨明けしたばかりの夕方で、薄く開けた引き戸から風が心地よく入っていたが、恵三のシャツの背中はびっしょりと濡れている。必死で走ってきたのだろうか。太一は店全体に向けていた扇風機の旋回を止めて、彼だけに当たるようにセットした。
「すまないね」
恵三はハンカチで汗を拭き、店内に他の客がいないことがわかると、すぐに話を始めた。
「奥さんがね、一週間くらい前に急にいなくなって、一晩帰って来なかったと言うんだよ」
恵三専用の丸椅子を奥から引っ張り出し、「まあ座れよ」と勧める。
「一晩帰ってこないなんて、そんなこと山岸君だってしょっちゅうじゃないか。恵三さんが独り者であるのをいいことに何日も宿泊して、家に連絡も入れやしないのでしょう?」
「連絡を入れなくても僕の家に来ていることはわかっているんだよ。いちいち気を遣って僕が奥さんに電話を入れているの」
恵三が慣れた仕草で丸椅子を股下に引き寄せ腰かけたので、改めて扇風機の風向きを変える。前髪は大きく風になびいたが、なかなか汗がひかないらしく、ハンカチで額や首を拭く手を休めなかった。
「だけど奥さんだって子供じゃあるまいし。たまには外泊ってこともあるだろう? そういう女友達でもいないのか。たとえば夫婦喧嘩をしたから泊めてくれというような。あるいはご実家とか」
「ない」
恵三は頑なに首を横に振る。「奥さんの故郷は北海道。山岸が北海道にスキー旅行で行った時にナンパして一緒になった夫婦だから、奥さんはこっちにそんな親しい友人なんかいない」
「じゃあ、北海道まで帰ったとか」
「ないね。だって翌日すぐに戻ってきたのだから」
「結局は戻ってきたのだったらいいじゃないか。夜中まで飲ませる居酒屋も駅前まで行けばあるし、大人なんだからそれくらいしてもいいでしょう? 二十四時間やっているファミレスとかカラオケ屋とか、一人で一晩明かすための居場所なんて今時いくらでもありますよ」
太一は馬鹿らしくなって煙草に火を点けた。「美弥子なんてそんなこと結婚当初からしょっちゅうやっている。どこに行っていたのかと聞くと、実家のこともあれば高校時代の友人の集まりのこともあるし、夫婦喧嘩をして出て行った時などは、どこへ行っていたかを言わないこともあった。大騒ぎすることもないじゃないか。喧嘩でもしたんだろう?」
「そうじゃないんだ。山岸はいつも通り、何事もなく事務所で奥さんと一緒に経理の仕事をしていたと言うんだよ。それもいつも通り午後四時頃、『そうだ、今日の夕飯、肉豆腐にしましょう。買い出し行ってきます』と言って二階の自室に戻り、財布を入れている手提げを持って降りてきた後、『今日はお豆腐が安い日なの』と機嫌よく、というか、まあ、普通な感じの会話をして外出したらしい。それっきり夜中は帰って来なかった」
積極的に騙すつもりでもあるなら話は別だが、夕飯の献立まで呟いて、買い物をする先まで亭主に伝えて出て行ったなら、彼女としても帰るつもりで外に出て行ったのだろう。「で、どうしたの。山岸君は警察に行った?」
恵三はやっとハンカチをポケットにしまって頷く。
「まずは豆腐屋に行って、うちの奥さん来ましたかね、と聞いたらしい。すると、いいえ、来られなかったと言われた。献立は肉豆腐って、奥さんは言っていたから、肉屋にも行ってみたけど、やはり来ていないと言われた。ひょっとしたら、ちょっと足を延ばしてスーパーマーケットまで行ったかなと思って訪ねてみたけど、スーパーマーケットでは客が多くてわからないと言うし、知人に口を利いてもらってその時間帯の防犯カメラを確認したけど姿は映ってもいなかった。それで奥さんが出て行く直前に『今日はお豆腐が安い日なの』と言ったことを思い出し、もう一度豆腐屋に戻って、『ところで、今日、お豆腐は安い日でしたか?』と聞いたら、それも、『いいえ。いつもと同じです』と言われた」
「それでたまりかねて警察?」
「一応相談してみたらしい。でも相談した時刻が九時かそこらで、いい大人がこんな時間に帰って来ないからと言って捜索というのも早すぎるだろうという話になり、夜中になるまで待ったがやはり戻らなかった」
太一は、煙草の煙が恵三にはかからないように、横を向いてゆっくりと吐き出す。扇風機の風で、煙は部屋の中に散って消えた。「きっと婦人会とか、事務所の顧客と会ってしまって、つい長話をしてしまったとか、そういうのでしょう」
「でも連絡はなかったし、その夜は帰って来なくて、翌朝、玄関の前に座っていたというのだよ」
「座っていた?」
「そう。ぼおっと」
「何か嫌な事件にでも巻き込まれたのか?」
「一応病院でも調べたらしいのだけど、危害が加えられたような様子はどこにもなく、お財布もちゃんと奥さんの手提げの中に入っている」
「問題がなかったのならいいじゃないか」
「問題は他にもまだあるんだよ。戻ってきてから、ほとんど話をしなくなった。怒っているとか、何か隠れて付き合っていた男でもいたのに別れて機嫌が悪いとか、どうやらそういうのでもなさそうで、単に口を利かないだけなのだけれど、時々、山岸をじっと見つめていて、目が合うと少し微笑むそうな」
それを聞いて太一は大笑いした。「微笑むなんて結構なことじゃないか。恋愛感情の再来なんじゃないか。美弥子なんていつでもつんとして、長年笑顔なんか見たこともない。絵手紙の会だか何だか知らないが、社交とやらで毎日あれやこれや忙しいらしく、こちらには微笑むどころか目も合わせない。今更じっと見つめて微笑まれたりしたら、むしろぎょっとして逃げ出したくなるだろうけれど、ある意味山岸君が羨ましいよ」
「僕には奥さんがいないから、そういう気持ちはわからないけど」
恵三は上唇と鼻の間を縮めて、ふてくされたような顔をして見せた。
「山岸君の奥さん、急に鬱を発症したとか?」
「それも医者に相談したらしいけれど、突然鬱を発症したというのは聞いたことがない、検査するからしばらく通院してくれと言われたけれど、本人が大丈夫だからと言って嫌がるそうだ。まあ、普通に仕事をしていると言えば、しているらしい。もともと事務で電話応対以外の接客はなくて、一日中黙っていようと思えば黙っていられるからね」
「どこに行っていたのだと、率直に聞いてみたのか」
そう尋ねたところで、店の扉が開いた。商店街にある寿司屋「吉助」の若女将だった。
恵三は女将の方をちらりと見てから、人差し指を唇に当ててこちらに向かって「しぃっ」と言う。客が帰るまではこの話をするなと言いたいのだろう。太一は煙草を灰皿でもみ消し、女将に「いらっしゃい」と声を掛けた。仕事の途中で出てきたのか割烹着を着けたままの女将さんは、地酒の並んだ棚を見上げていた。
「新潟産のものだけ何種類か持って帰っていいかしら。新潟の地酒を好まれる客の集団から急に予約が入ってしまって」
数か月前に寿司屋「吉助」の長男と結婚したばかりで、テキパキとよく働くと評判の若女将だ。
「好きなだけ持って帰って貰っていいですよ。客が飲まなくて封を開けないままで、明日中ならまた戻してもらっていいですから。持っていかれるものを帳面に付けておきます」
女将が棚から五、六本見繕ったので、会計机で銘柄などを書き取った。「支払いは月末にまとめてでいいですよ」
女将はぺこりと頭を下げて、帰って行った。
店に誰もいなくなると、恵三は丸椅子から立ち上がった。
「そういうことで、だ。明後日、うちで緊急飲み会となった。山岸と三人で飲みながら、本件について話し合う」
「そんなデリケートな出来事があった直後なんだったら、山岸君は奥さんのそばにいた方がいいんじゃないのか?」
「奥さんの妹が北海道から来てくれたそうで、その間は子どもと奥さんを妹さんに任せるそうだよ」
「妹さんまで来るというのなら、僕が思っている以上に状態は良くないのかもしれませんね。緊急飲み会をしてどうにかなるものかわからないけれど、そういうことなら行きますよ」
太一が承諾すると、じゃあ、明後日、と言って恵三は帰って行った。
ところが、翌日。恵三から電話があり、飲み会の件は取り止めになったと言う。
「奥さんが嫌がったのだろう? そんな興味本位なことと言って」
「そうじゃなくて、似たような出来事が他の家でも起きていたことがわかって。ひとまず、飲み会は中止になった」
電話なのにひそひそ声で言う。
「似たような出来事って? どういうこと」
太一の方は堂々とした声で問い返す。まだ午後を過ぎたところで客もいない。
「ある女性が一晩いなくなって、翌日、ある場所に座っていたそうだ。やはりその後全くしゃべらない。と言っても、今朝、村役場の重役の部屋で誰かが話しているのを盗み聞ぎしただけなのだけどね」
恵三の本業は喫茶店の経営だが、同時にこの春から村役場の役員も引き受けている。
「誰にも言うなよ。耳に挟んだ情報では、村役場ではこの件を極秘事項として取り扱うらしいから」
「その女性はやはり危害も加えられていないのですか」
「この前話した山岸の奥さんの状況とそっくり」
「警察には言わないの? 個人的にどうこうするのではなく、警察が取り扱う話じゃないのか」
「その件では警察に捜索願を出す前に帰ってきたそうで、家族の意向でそのままなかったことにしようという話だよ」
「どうして。調べたらいいじゃないか」
「この村にずっと昔からあった神隠しなんだ。なんでもかんでも警察に言っても解決するわけじゃないよ」
「神隠し?」
太一はそれまで口には出さなかったが、この件は不当に高額な壺や宝石の販売会に出向いてヘソクリを丸ごと失ったとか、イケメンのホストに魅せられてお金を取られそうになったとか、そんなところだろうと考えていた。酒屋という仕事柄、飲み屋で働く人間と知り合うチャンスが多く、裏の世間に詳しい彼らの話を聞く機会には事欠かない。彼らの話によると、金のありそうな人間を見かけたらうまくけしかけてお金を引き出そうとする輩はどこにでもいるらしく、世間ずれしない主婦や会社員の方が案外引っ掛かる率が高いそうだった。だから神隠しかもしれないなどとは考えてもみなかった。
「神隠しだよ。そうでないとも言えないだろう?」
恵三はとうとう、ひそやかな声を出すのを止めた。「今回の事件では、隠されたっきりでいなくなったわけではないけど、たとえば一瞬だけ隠された。そういう神隠しだってあり得るだろ?」
恵三は本で読んだことのある神隠し事件について、いくつかの話をした。たとえば、二十歳前の女性が急にいなくなって帰って来なかったが、三十年後、山奥でその女性が生きていたのを見た人がいたというもの。女性はその時には何人もの子どもを生んで山小屋で育てながら暮らしていて、もはや元の家に帰りたくないというのでそのままにしてきた、とか。
「それは神隠しじゃなくて、人さらいじゃないか」
「それは、そうかもしれないけれど――」
恵三は口ごもる。「ほんとにここだけの話だけど、この村では昔から神隠しがよくあったらしいのだよ。それは今回のことがあったせいで、こっそり役場の書類置き場で調べてわかったんだけどね。どうやら役場では口外無用として一応封印されていて、何も起きていないかのように処理されているけれど、実はその件の研究はずっと裏で続いているみたいだ」
「研究って、村役場の秘密部署ですか」
「そうではなくて、被害者家族と、外部の研究者で結成された研究会。実は外国の研究機関もあるのだとか」
「まさか」
太一は思わず吹き出してしまった。長年ここに住んでいるのだ。それでも今までにそんな話を聞いたことは一度もない。太一自身、役場の役員もやったことがあって、内部の秘密が列挙されている文書を見たこともあるが、こんな土地、所詮貧しい一介の村でしかなく、書かれている内容は大したことはなかった。「外国にも研究機関があるだなんて、誰がそんなことを? 資料の中にそう書いてあったのか」
「山岸君が知人のコネを使って調べてきたというのだよ。法律関係の仕事をしているから役場の重役には顔が利くんでしょ。それに、やはり奥さんが話をしなくなったことが余程ショックなんだろうな、今度、その研究会に行くとまで言うのだよ。一緒に行かないかと誘われたけど、僕は断った」
「なんだ、友達甲斐がないじゃないか。一緒に行ってやればいいのに。僕にとっての山岸君は恵三さんの友人という位置付けだけど、恵三さんの立場ならもう少し面倒をみてやってもいいでしょう」
「こういうことには首を突っ込みたくないんだ。商売があるからね」
そう聞いて、恵三も冷たいものだなと、一瞬戸惑いもしたが、太一は結局、深く頷いた。商売というのは、何かたったひとつの噂でまるっきりダメになることがある。最悪、頼まれて金を貸すようなことがあったとしてもまだましで、たとえ長年の友人の為であると思えても、事実確認のしようがない噂に巻き込まれてしまうのは、死活問題として絶対に避けたいのが本音だろう。
「だったら仕方がないね。恵三さんが行かないのに、僕が行くのもおかしいから」
その日の電話はそれで終わった。
恵三が他言無用と言うのでこの件は妻の美弥子にも話さず、山岸の方から直接援助の依頼があるわけでもないので、太一としては勝手に気に病むのもつまらないことだから、もう忘れてしまおうと考えていた。
ところが、太一としてもそのまま放置するわけにはいかない出来事が起きてしまった。恵三が山岸の妻の件で店に来た日から、数日後のことだった。
「閉めようとされているところを、すみません」
寿司屋「吉助」の長男だった。板前用の着物を着て、前掛けも着けたままで慌ただしく駆け込んでくるとは、余程のことがある。
太一は帳面を見ながら、いつまで経っても慣れないパソコンの入力作業をしているところだった。
「妻が、来ませんでしたか? 夕方、ちょうど六時ころ。この前、新潟の地酒を多めにお借りして、もしも開けなかったら戻していいと言って頂いて――」
なおやは肩で息をしている。「それで、返しに行ってくると、六時頃に出て行ったきり戻ってこない」
老眼鏡をずらして壁掛け時計を見ると、もう十時を過ぎている。
「今日は来られていないですね。僕も五時からは配達もなくずっとここにいますから、間違いなく来られていない」
「どこに行ったのかなあ」
もともと色白で細面のなおやの顔がすっかり青ざめている。
「お嫁に来られたばかりで、道に迷ったとか」
「もう八か月くらい経ちますよ。いつもここには来ていますし」
それはそうだなと頷いた。「携帯は? 鳴らしてみた?」
「置いていったみたいで、二階の僕たちの部屋にあります」
「喧嘩したとか、そういうことは?」
神隠し事件のことが頭をよぎったけれど言わなかった。口止めされているし、わざわざ不安にさせることを言いたくはない。
「全く。いつも通り、機嫌よく働いてくれて、今度の休みは二人でドライブにでも行こうと耳打ちしたくらいです。うちは僕の父も母も祖母ちゃんも姉もいるでしょう? だからずっと家に居たら気疲れするだろうと思って」
「気疲れした様子だったのですか」
「それも特にそうではなかったと思うのですが――」
肩を落として今にも泣き出しそうな表情だった。
「警察には?」
なおやは首を横に振る。「警察に言うのは明日にしろと、父が言うものですから、今のところ家族で探しています」
「警察に言うくらい構わないじゃないですか」
「父が、だめだと――」
「どうして。大事なお嫁さんでしょう。よく働くと評判で。ここへ来られても愛想がよいし、僕の妻も、婦人会で会ったらいい奥さんだった、若いのに偉いね、といつも感心していますよ」
「祖母ちゃんが、明日になると帰ってくるだろうからと」
もう一度時計を見た。十時十五分。この店に酒を返しに行くと言って携帯も持たずに出て行ったのなら、財布も持っていない可能性もある。どこかに行って時間を潰そうというには不適切な時間だ。やはり、神隠し事件のことを思わずにはいられなかった。
「お父様に遠慮しないで、なおや君の判断で警察に電話したらどうですか」
「それは、そうですね」首をうなだれた。
父親には逆らえないのだろうか。三代目。親子と言っても、普通の親子とはちがって師弟関係もあるのだろう。
「じゃあ、一緒に探しましょうか」
そう言うと、なおやの目は輝いた。「そうしていただけると嬉しいです」
太一は眼鏡を外し、やりかけの帳簿の入力作業を中断して立ち上がった。
懐中電灯を持って二人で外に出る。どこもかしこも店仕舞いし、ぴたりとシャッターが下りて真っ暗だった。等間隔に灯っている街灯だけがアスファルトを弱く照らし、無数の蛾が灯りに集まっていた。
道や建物の隙間を照らしながら、女将さんが通ったと思われる辺りを隈なく探して歩いていると、ちょうど中間にある郵便局の駐車場に白いものが浮かび上がって見えた。風呂敷の包みらしい。若女将がいつも使っているものに似ている。
「あれは? 女将さんのものに似てやしないか」
太一が近寄って照らすと、なおやは、あっと声を上げた。「さっきは車が停まっていたから気付かなかったけど、そうかもしれません」
二人して駆け寄っていき、風呂敷を開けると、やはりその通りだった。店の地酒が二本入っている。それを見ると、とうとうなおやは泣き出した。「一体どこへ行ったんだ。さとこ」
太一は若女将の名前を初めて聞いたような気がした。これまで、女将さんとばかり呼んでいた。
「さとこさんはきっと、帰ってくるよ」
太一はなおやの肩に手を乗せ、いっそ、あの神隠し事件であって欲しいと思った。二度と帰って来ないなんて嫌だ。恵三の言う通りであれば、明日の朝には戻ってくるのだ。つい、「実はこの辺りでは神隠し事件が起きていて――」と伝えて、「それに従えば必ず帰ってくるだろう」とでも言いたい気持ちになったが、実際にはわからないのだから、ぐっと堪えた。明白にわかっていることでもないのに、気休めに不確かな予言をするわけにはいかない。
泣いているなおやをどうにか寿司屋まで連れて帰り、「できれば早めに警察に連絡するように」と念を押した。
翌朝の電話で、さとこが無事に戻ってきたと知らされたが、安堵したのもほんの束の間、その数時間後には
「さとこは帰ってからずっと口を利かないのです」
なおやは再び店に駆け込んできた。すっかり顔が青ざめている。
いよいよ恵三の言う神隠し事件であることが決定的になってきたなと思いつつ、太一は店の扉に「午後から営業」と書いた紙を貼った。
なおやの自宅に行くと、さとこは台所のテーブルを前にして一点を見つめ座っていた。恵三から聞いた山岸の妻の件と同じように、やはりどこにも外傷はなさそうで、表情の中にうっすらと漂っている微笑みから想像すると、強盗や暴行に遭遇したわけではないと断定してよかった。ただしほとんど口を利かず、いつもの愛嬌いっぱいの快活な様子は見当たらない。そうかと言って意気消沈しているわけでもなく、何かうっとりとしているような静けさに包まれていた。しばらくすると太一がいることに気付き、
「大丈夫です、心配しないでください」と何度か繰り返して、「酒屋さんにまで来ていただいてすみません」小さく頭を下げた。
ひょっとすると今は気が動転しているだけかもしれないと考えてはみたものの、やはり彼女を取り巻いている空気の色合いはすっかり変わってしまっていた。
透明なシャボン玉の膜にでも覆われている。外側から遮断されたのではなく、彼女の内側から膨らみ続けている泡の膜によって、こちら側と向こう側が分断されている。もっと話をしたいと思っても、刻々とその膜の強度は増していき、無言のまま、太一たちを徐々に拒絶していくかのようだった。
「しばらくそっとしておいてみましょう。いつかは元の彼女に戻るかもしれませんから」
なおやを励ましてから店に戻り、すぐに恵三に電話を掛けた。
さとこの件を話し、神隠し事件のことをなおやに教えても良いかどうか確認したかったのだ。
「さとこさんの件では、家族がまだ警察には言っていないのだろ?」
気軽に承諾してくれると思い込んでいたが、意外にも恵三は渋った。
「なおや君の親が内緒にしておこうと言っているらしい」
「ならば他の人の事件のことをなおや君に言うのはどうかなあ。役場もこの件は秘密にしておこうという流れだから」
関わりたくないのだろう。
「例の研究会に相談するのはどうだろうか。そういうのがあるんでしょう?」
太一はそれでも引き下がらなかった。
事件と関わり合いになりたくないのは恵三と同じだった。まして裏の研究会なんて中途半端な気持ちで首を突っ込むとろくなことにならないだろう。それでも、事件に遭遇したかもしれないさとこの姿を目の当たりにした後では、そうとも言っていられない気になった。さとこについては結婚して村に来た頃からずっと見てきた。知人もいない土地で不安だろうに、そんな様子も見せずに人懐っこさを振りまいていた姿をはっきりと覚えていて、どうにも見て見ぬふりができない。
電話口の恵三はしばらく黙った後で、
「太一さんがそうしてみたいと思うのだったら、そうすればいいのじゃないかな」
他人行儀に言った。「もともと秘密の会だから個人的な情報に関しては他言しないようだし、さとこという人のご家族の気が少しでも晴れるのならそれもいい。でも山岸の話を聞いていると奥さんは相変わらずで、あれから随分経つけど何か変化があるようにも思えないし、山岸本人もなんだかその状態に慣れてきたそうだよ。もう秘密の会なんかに行ってみなくてもいいかな、と言い始めている」
「慣れたって? 奥さんが話をしないことに?」
「意外と居心地がいい、とか言っていた」
「もともとおしゃべり好きではなかったのかな」
「よくしゃべる人だったよ。それが好きで山岸も結婚したんだろうだけど、いざこうしておとなしくなってしまうと、これはこれでいいかな、これから何年も結婚生活を続けていく上でこの方が楽かなと言っていた」
恵三の言葉を聞いて、太一はまた妻のことを考えた。結婚当初はよく話をしたものだったが、神隠し事件に遭わないまでも、近頃はほとんど会話などない。山岸が言うように、だからと言って不都合はなかった。食事の支度がしてあって、「行ってきます」と「ただいま」があれば別に困りはしない。知り合いの夫婦なんて何年経ってもよく喧嘩をして、それでもよく一緒に旅行に出掛けているらしく、そういう形に憧れもないと言えば嘘になるけれど、実際にはなんだか面倒くさいような気もした。夫婦なんて、ある一定期間が過ぎれば、それぞれに楽しいことをした方がずっと穏やかでいいだろう。
「明日にでも秘密の会の連絡先をもっていくよ。パンフレットみたいなのもあるんだ。秘密だと言いつつ、会員募集までしている」
電話口の恵三がひっそりと笑ったのを感じた。
最初にひどく動転してこの件を伝えに来たのは恵三だったのだが、今ではすっかり興味を失ったのか、ほのかにではあるけれど嘲笑する側に回ってしまったようだ。
太一は、「頼むよ」と言って、電話を切った。
日が暮れると、仲の良さそうな男女が来て缶酎ハイと杏露酒をひと瓶買って行き、その後、駅前のスナックと隣町の中華料理屋からは配達依頼の電話が入った。軽トラックに注文の酒類を積み込んで順番に配達し、まだ時間は早かったが、そのまま帰宅した。
自宅の灯りは点いていたけれど美弥子はいなかった。
居間のテーブルには煮物とお浸しと焼魚が置いてある。炊飯器にご飯が炊けており、ガスレンジ上の鍋には豆腐の味噌汁が入っていた。「今日は絵手紙の会です。温めて食べてください」とだけメモ書きがある。時計を見ると八時過ぎ。大人であれば出かけていても別におかしくはない時間だ。そして、いつものことでもある。
しかし、太一には壁時計の秒針の音がいつもより大きく響く気がした。美弥子も結婚生活のどこかのタイミングで「神隠し事件」に遭遇していたのではないだろうか、気付かなかっただけではないだろうかという思いが湧き起こる。結婚してから何度でも外泊していたし、その可能性が全くないとは言えない。いつの頃からか昔ほどには会話をしなくなって、もちろん喧嘩もしなくなったし、気付いたら結婚当初の彼女の明るい振る舞いではなくなっている。年を重ねればそんなものだろうと思ってきた。
鍋の味噌汁を温めて椀に移し、炊飯器からご飯をよそって食べ始めると、太一にはなぜか料理に味がないように感じた。味付けが薄いのではなく、いつも疑うことなく「妻の手料理」と思って食べていたそれらが、実はそうではなく、ただそこに置いてあっただけの食べ物に思えて食欲が湧かなかった。気のせいか、その日は美弥子の帰りもいつもより遅く感じて、珍しく携帯に電話してみようかと思って、やめた。
味気ない夕食をどうにか食べ終え、最後に味噌汁を啜ってわずかに残すと、うっすらと汁に鰹節の粉が沈んでいた。それを見て少しほっとする。いつもの出汁だ。美弥子はインスタントの出汁は使わない。
冷蔵庫から瓶ビールを取り出して栓を抜き、ちょうどよい泡が張るようにグラスに注いで、イカの塩辛も小皿に移した。
テレビを付けると、ニュース番組では沖縄の祭り特集をしていた。
大きな縄をみんなでもって綱引きをしている。豊穣祈願か。離島を旅した時に、祭りと遭遇して大綱を引かせてもらったことがあった。あの時の熱くねっとりとした空気を思い出す。
島の人たちはひと夏分の情熱を託しているのか、観光で訪れた太一には狂気のようにも見える恍惚とした表情で縄を持ち上げ、引き、声を上げていた。笑っているのか苦痛なのかわからない彼らの表情。縄を介在させながら、男も女も汗まみれの身体をぶつけ合っていた。島がひとつの身体であり、縄はそれを貫く性力だった。ガムランのような音が鳴り響く。それぞれの都合など初めからなかったかのように融け込んでいるのを見て、旅人である太一の方はむしろ醒めていった。激しさに蒼ざめたと言ってもいい。しっかりしなければ呑み込まれてしまう。だけど縄を持ってしまった以上そこから離れるのは容易ではなく、どうにか体を揺らして恍惚としたふりをしていると、対面に居た男がこちらに流し目を向けてにやりと笑った。肩の筋肉が盛り上がって頑丈そうな島男。顔を近付けてきて「流されるな」と耳元で言った。あれはどういう意味だったか。島の祭りは時に死人が出るほどの勢いだから、縄から手を放すな、身体を人々に投げ入れるなと言いたかったのだろうけれど、融け込めない気分のせいか、「祭りに気を取られて自分を忘れるなよ」と言われているように感じた。
自分を忘れるなよ、か。
神隠し事件に遭った人たちは、自分を忘れてしまったのだろうか。戻ってきたさとこの、どこか若さを失った姿を思い出す。皮膚と空気の間にある豊かで動物的な匂いが一切拭い取られ、肉体そのものは相変わらず若いとしても、その周囲を覆う空気は植物のもののようだった。それも樹木ではなくアヤメのように、すっと細く立って咲く静かな花。美しくなったと言えばそうかもしれないが、二度と手折る事のできなくなった一輪咲きにも見えた。
テレビニュースは天気予報になり、ビールの瓶が一本空いた頃、美弥子が帰宅して、
「お土産」
ビニール袋に入ったものをテーブルの上にどさっと置いた。「葡萄。会の人が葡萄狩りに行ったそうで、みんなに配ってた。食べます?」持っていた鞄を壁のフックに掛けたり、長いネックレスを外して箪笥の引き出しに仕舞ったりしている。
「冷やしてからの方がうまいのかな」
袋の中を少し開けて覗いてみた。ピオーネだろうか。巨峰よりは小さな粒の実が付いた葡萄が三房ほど入っている。一粒だけ外して口に入れた。酸っぱい。
「洗ってからにしてくださいよ」
美弥子は肩に垂らしていた髪を後頭部でまとめながら、ちらとこちらを見て窘めた。それからひと房を袋から取り出しざるに乗せ、水で洗って皿に盛り、皮入れのボールと共にテーブルの上に置く。「残りは冷やして明日いただきましょう」
美弥子も座って、葡萄をくれた女性の話を始めた。
その人は独身で、看護師さんで、それも大きな病院の婦長で、病院の社員旅行のようなもので葡萄狩りに行って、その葡萄狩りの後、収穫した葡萄を分配する時に、婦長だからというのでみんなが気を遣って、他の人よりも多めに渡されたという話だった。その婦長さんである女性は絵手紙の会に来て、「独身だからそれほど食べる人もいないので困ってしまって」と説明しながら仲の良い人に葡萄を配ったらしい。
「最初から、独身で食べきれないからと断ればいいのにね」
太一が一粒食べ、酸っぱそうに顔を歪めながら言うと、
「むしろ、やけになって、断らないんだってよ」
美弥子も一粒食べて酸っぱそうな顔をする。「美味しいけど酸っぱいわね。ワイナリーの葡萄らしい」
「別にやけにならなくてもいいのになあ。生き方は自由だよ」
「そうかしら。私はなんだか彼女の気持ちわかる」
美弥子は椅子を後ろに引いて、「お風呂のお湯入れなくちゃ」と立ち上がった。
太一は驚いた。独身の人の気持ちがわかるとはどういう意味だ。
先ほどの不安がまた少し心をよぎる。慌てて、もう一粒、葡萄を口に入れる。酸っぱい。でも、これくらい刺激があるのもよいなと思う。そうすると、神隠し事件の不安なんかに乗っ取られずに済むだろう。こっちもやけになって食べてやる。酸っぱい、酸っぱいと思いながら、次々と食べた。お風呂場から戻ってきた美弥子が、皿の上の葡萄を見てあっと言う。「よく、そんなに食べられるわね」
もう半分は食べていた。
「旨いよ、これ」もうひとつ口に入れてから、畳の部屋に移動して寝そべる。
皮も種も噛み砕いてごくりと飲み込んだ。
(第一章 了)》
※ここまでの解説
あらすじ。
場面は大野太一の酒屋に移った。第零章の終わりにちらりと出てきた喫茶店経営者井上恵三が太一のところに神隠し事件の相談を持ち込む。友人である山岸の妻が神隠しに遭ったという。やはり一夜で戻って来て、その後、人格変容してしまって話をしない。それほど深くコミットするつもりのなかった太一だが、自身の知人である寿司屋の女将さとこが同じ事件に遭遇したことから関わっていくことに。
さて、この段階で神隠しに遭っているのは女性ばかりだ。太一の長く連れ添った妻も近頃ではあまり口を利かないが、どうもそういった「会話のなさ」と「神隠し後の人格変容」は様子が異なっている。
第零章で描かれていた神隠しについて調べる研究会に太一は足を運ぼうとしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
