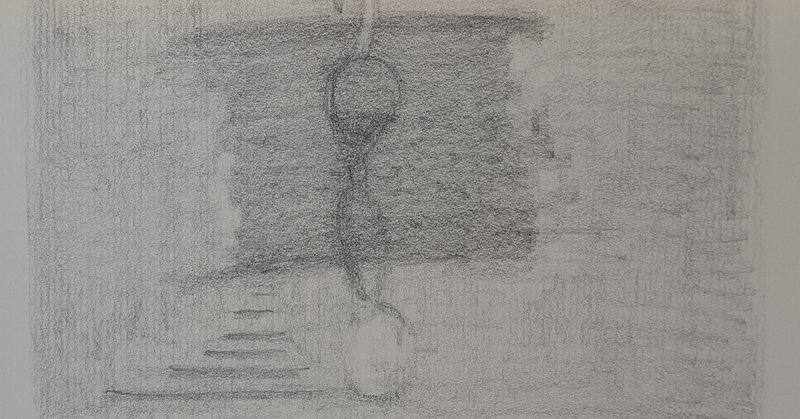
解読 ボウヤ書店の使命 ㉚-9
長編小説『ポワゾン☆アフロディテ№X』読み直し続き。
《第三章
2 動機
一之介は目覚めてすぐに窓を開け、くしゃみをした。部屋の中から外を見る限りでは、ほとんど風がないように見えた。隣家の庭木の葉も揺れない。どこからともなく集まった埃と空を覆う雲のせいで、時間も砂色に止まって見える。これで朝だと言えるだろうか。
時計を見る。午前八時半。寝坊してしまったが、一応、朝だ。
まったりとしたバタークリームのような朝の空気を見ているうちに、翔太から返却されたファイルに付着していたバニラの香りを思い出す。バニラと言ってもアイスクリームやクッキーのように食べたくなる類ではなく、嗅いでいるこちらの方が食べられそうになる個性的な香りだ。
――あれは、なんとなく、怖いバニラ。
記憶の香りに向けて深呼吸をし、さらに鼻をくんくん鳴らすと、またひとつくしゃみが出た。一之介自身のくしゃみの音がしんとした部屋に響き渡り、作りかけのプラモデルの細い軸が震えそうに思えた。尋常じゃない。なんだこの鼻の奥の痒み。むずむずする。
は、はくしょーん。
再び、大きなくしゃみがひとつ出て、部屋の空気をこわばらせた。
「直観した!」
一之介は鼻の下を指で強く擦り、ベッドから飛び起きると急いでシャワーを浴び、丁寧にひげを剃った。顎や頬を撫でるとつるつるした。クローゼットから白いシャツを取り出してアイロンをかけて袖を通し、どちらかと言えばお洒落着に分類しているチャコールグレーのスラックスを履いて、古書&アート《アフロディテ》に向かった。
風はなく、辺りに停滞している埃に朝日がほんのりと射してゆらめき、光のあるところだけはゆっくりと時間が動き出して見える。
――こういう日は匂うな。確かに、匂う。
一之介は何度も息を吸い込み、鼻を鳴らした。
直観した通り、《アフロディテ》には遠野美咲らしき人が居た。会計カウンターの向こう側でパソコンに向かって熱心に何か入力作業をしている。彼女の方から名乗り出たわけではないが、建物の中に入った途端、あの怖いバニラの香りが押し寄せてきたので遠野美咲だとわかった。暑苦しいほどの香りが部屋中に充満している。離れた位置から見てもわかるほどに化粧は濃いが、翔太が言うように、金指まるみの顔つきに似ていないこともない。
一之介が店に入ってきたことに気付くと、高く透き通るような声で「いらっしゃいませ」と言った。声優のように訓練された声だ。
――香水も化粧もそうだが、声も武装している。
髪は大正ロマンを思わせる巻き毛。朱色の口紅は唇からはみ出しそうだった。
「以前、僕はここでウルタさんの写真集を買いました。他にも、ウルタさんの本はないですかね」
一之介は書棚を眺めながら、それとなく話しかけた。他に客はいない。
「ウルタですか。どうかしら。聞いたことないわ」
遠野美咲らしき女性は入力作業を止めて、カウンターから外に出てきた。黒のタンクトップに目の覚めるようなグリーンのギャザースカート。淡い水色のレースのショールを肩に掛けている。これではまるで白雪姫じゃないか。近付くと、さらに濃厚なバニラの香りがした。
「本棚のどの辺りにあった写真集かしら。真面目エリアかそれとも――」
「真面目エリアですよ」
一之介は即答する。「『時間のマグマ 無人島ギャラリーにて ウルタ』という写真集を買いました。出版社も何も書いていない本ですけど」
「ああ、それ!」
明るく透き通る声で言い、人差し指を顎の下に当てた。「それ、たぶん、一点ものです。当たりとも言うけど」
「どういうこと?」
「ここ《アフロディテ》では、ところどころに、そう言った手作りの本を潜ませているの。工房が抱えているアーティストが制作しています」
近くで見ると、金指まるみよりも一回りくらい小柄で、まるみの顔つきに似ているとは言え、大きさはまるで違った。体型もまるみはふっくらしているが、目の前にいる遠野美咲は華奢だ。着ている服が全体にふんわりと膨らんでいるのを見て、翔太はまるみと似ていると思ったのかもしれないが、鎖骨や手首の状態から想定すると、どちらかと言えば痩せすぎの部類に入るだろう。
「そんなサプライズ商品があったのですか。この前、買ったのはこれなんだけど」
一之介はトートバッグに入れて持って来た『時間のマグマ 無人島ギャラリーにて ウルタ』を渡した。
「そうそう、これ。でも《アフロディテ》ではこんな透明シートのカバーを掛けていなかったと思うけど」
アイラインで縁どられた瞳で一之介を上目遣いに睨む。
「どれですか」
一之介は一度渡した本をもぎ取るように、急いで取り返した。
「その表紙に掛けているセロハンシート」
艶々としたネイルアートを施した長い爪先で表紙のセロハンを指していた。
「ああ、これね。僕はね、古書店で買った本にはカバーを掛けておく習慣がありましてね」
一之介は持ってきたトートバッグに速やかに本を入れた。「一点もので、ウルタさんの本はこれしかないというのなら、わかりました。残念ですが、一点ものだとわかったら、余計にこの本が好きになりました。お忙しいのに、お手数かけました。また何か、一点ものを物色に来ますよ」
一之介は滅多に出さないとっておきの営業スマイルをして見せ、そそくさと店を出た。
空は相変わらず曇っていたが、弱い風が吹き始めていた。《アフロディテ》の前に飾ってある信楽焼の狸はきょとんとした目を斜め上方に向け、誰にも見えない妄想の世界に何かを発見したかのように微笑んでいる。だから、いつも通り目が合わないが、
――いやはや、うまくいきました。
一之介は心の中で狸に話し掛けそっと頭を撫でた。いつまでも空を見つめている狸に小さくお辞儀をしてから足早に事務所に戻り、すぐに浅田欣二に連絡を取って警察まで行くと、『時間のマグマ 無人島ギャラリーにて ウルタ』を鑑識に回して「遠野美咲」の指紋を採取した。
「なるほど、翔太君に頼む必要もなく、八田さんが遠野美咲の指紋を採取してくれましたか」
警察の小さな談話室で、浅田欣二と一之介は『時間のマグマ 無人島ギャラリーにて ウルタ』の表紙に巻いたセロハンシートから取れた遠野美咲の指紋と、金指まるみのランドセルや作者不詳の日記から取れた指紋を見比べた。模様は一致している。
「遠野美咲は小柄でしたから、指も細く小さくて、子供の指紋に見せかけることはできますよ。しかし、日記についた指紋とは大きさが合わない。どういうことだろう」
一之介はアフロディテで見た美咲の姿を思い浮かべた。
「ひとまず大きさの件は横に置いて考えたとしても、遠野美咲がまるみさんに成り済まして日記を書いたり、まるみさんの家の物置に侵入して、指紋を付けまくったってことになるけれど、なんのためにそんなこと」
浅田は徴収した指紋から目が離せないでいるようだった。
「アフロディテが抱えているアーティストたちがクリエイトしたアートということじゃないですか。先日の翔太君の話によると。バーチャルな世界をリアルな世界で実現する、とか」
「動機として、そんなことは考えられないが」
「僕たちの世代には考えにくいかもしれないけど、きっとそうなんでしょう。育った時代の土壌が違う。もちろん、まだ仮説ですが」
「許されるのか、そんなこと」
「単に道義的にけしからんと逮捕することはできないでしょう。でも金指まるみのランドセルに遠野美咲の指紋が着いていたのだから、不法侵入の罪に問うことはできそうですが。浅田さんが意を決してやろうと思えば、やれるのでは?」
ふーん、と浅田は腕組みをし、うつむいたまま動かなくなった。新種の亜犯罪なので、どう処理したらいいか迷っているのだろう。まるみの行方不明事件と直接関係があるかどうかわからないし、物置から何かが盗まれたわけでもない。奇妙な話だが今のところ実害はない。
「浅田さん、どうなのですか」
と、何度言っても眠っているかのように固まってしまって動かないので、「じゃあ、また今度」 と声を掛け、一之介は外に出た。
浅田は時々文字通り寝たふりをする。しらばっくれると言うよりは、思考停止になる。思考が停止してこそ、動き出す勘もあるのかもしれない。そういう時はそっとしておく。
なんとなく気が向いて裏道に回ると、すぐ近くに洋食屋があるらしく濃い油とデミグラスソースの匂いが漂ってくる。一之介はお腹が空いていることに気が付いた。
――そう言えば、今朝は朝食が届かなかったな。
連絡もないままに朝食が届かないのは初めてのことだった。一瞬、どうしたのかとマチ子に電話で聞いてみようかと思ったが、日頃から届けなくていいと言っているのに催促しているみたいで気が引けた。実際、こうして朝食のことを気にしないでいられるのは気が楽だ。このままフェイドアウトしてくれた方が得策か。
――何か言われるまでは黙っていよう。
一之介はすっかりデミグラスソースの匂いに捕まって洋食屋に入った。壁も天井もテーブルもとろりとコクのあるソースが染み込んだかのように艶々している。壁に貼ってあるメニューの紙でさえも、口に含んで噛み締めればこっくりとした味がしそうだ。
最奥のカウンターに座るなり、
「ハンバーグ定食」
厨房で大鍋のソースを混ぜているマスターに言った。
「了解」
恰幅のいいマスターはちらりとこちらを見て、小さめのフライパンに油を引いてガスレンジで温め始める。冷蔵庫からステンレスのバットを取り出して、小分けした状態で並んでいるハンバーグの種からひと塊り分を小皿に移し、再びバットを冷蔵庫に入れてバタンと扉を閉める。小皿に置いた種を掌で軽く成形してフライパンに乗せた。ジュっと音がする。別の小鍋にデミグラスソースを入れて温める。皿には千切りキャベツとトマト、キュウリ、ポテトサラダがすでに乗っている。
――フミヤが作っていたデミグラスソースの香りに似ている気がするが。
「ソース、いい香りですね」
段取りが出来、少し動きを止めて前掛けで手を拭いているマスターに話しかけた。「やっぱり、特別な何か、あるのですか。企業秘密のような」
「そんな大げさなものはないです。普通の作り方ですよ。ブーケガルニが自前というだけで、後は学校で教わった通りにやっています。そんなに特徴を出すような店構えでもないですから。変わったものを求めて食べに行くなら、もっと表通りにある洒落たビストロにでも行くのでしょう?」
ふっくらとした体系にふさわしく低音のよく響く声だ。話しながら、温まったデミグラスソースにバターを溶かし入れていた。
「ブーケガルニ?」
「香草を組み合わせたものですよ。これが企業秘密と言えばそうなるか。だけど、そんなもの大したことはないですよ。それよりも、調理学校で教わった通り、注文ごとにちゃんと作るのがうちの方針。ぎりぎり味を左右しないところまで準備しておいて、注文を受けてからひとつずつ作る。電子レンジでチンはなし」
バターのほどよく焦げる香りがして、一之介のお腹がギュウと鳴った。
「バイトは雇わないの?」
厨房にはマスターしかいない。この広さの店舗なら誰かを雇ってもよさそうだ。
「近頃の子はちょっと叱るとすぐに止めてしまうのでね。僕が一人でやるか、あまりに忙しい時は配膳と会計をオクサンに頼むようにしています。どうせ上でテレビ観ているんで」
人差し指を上に向ける。
気付いたらハンバーグ定食は出来上がり、テーブルの上に乗った。ゆらゆらと湯気が立ち、艶やかなソースで覆われたハンバーグにはどこか貫禄がある。腹ペコの一之介にとってはもはや輝いていると言ってもいい。こうして料理が目の前に届くまではわからなかったが、ここは老舗の洋食屋と呼んでいいだろう。手抜きではない逸品が、ある程度の早さで目の前に出てくる。この辺りで老舗と言えば、洋食屋でも蕎麦屋でも寿司屋でも店構えはたいてい古色蒼然としたもので、由緒正しきというよりも、パッと見たところでは派手さもなく時には冴えないことも多いのだが、昼時になるときちんと行列ができているのでそれとわかる。むしろきらびやかな外観の老舗は嘘くさいとみなされるのか、リニューアルする場合にでも、最新の見栄えにするよりはかつての趣を残して出しゃばらないように建て替えることもあるらしい。
聞くところによると、マチ子の店で働いているフミヤもかつては老舗の洋食屋で修行をしていたのだった。それにしても粋な老舗で働いていたフミヤが、どうしてあの隅から隅まできんきらきんのマチ子の店なんかに来たのだろう。実際、あの精悍な雰囲気では老舗の方が合うように思う。
一之介はナイフでハンバーグの真ん中に切れ目を入れた。子供の頃に初めて食べた頃のハンバーグと同じような、一之介にとって違和感のないきめ細やかな内側が現れ、湯気が立ち上る。一口分を切って口の中に放り込んだ。
――ああ、これこれ。そうそう。これだ。旨い。
思わず笑みが漏れる。じっくりと噛み締め味わっていると、近くの会社が昼食時になったのか、徐々に客が増えてきた。カツカレーやメンチカツ定食、オムライスなど、当たり前ながら客たちは思い思いのメニューを注文している。マスターのオクサンが二階からエプロンを掛けながら降りてきた。ショートヘアで化粧っ気もあまりなく、特に客たちに媚びる風でもないが、いらっしゃいませと控えめな笑顔を見せていた。
「お客さん、ブーケガルニ、これですよ」
ソースを煮込む大鍋から引き揚げたブーケガルニをマスターが皿に乗せてくれた。いくつかの香草をタコ糸で縛っているらしい。
「これって、この状態で売っているの?」
「いや、作るんです。香草をそれぞれ仕入れて」
「香草の種類は教えてくれないんでしょうね。このソース、ほんとに旨い」
一之介は皿に付いたソースをフォークの縁ですくって舐めて見せた。
「そう言ってもらうと嬉しいです。企業秘密ですから種類は教えられませんが、お気に召したのであれば、この出がらしのブーケガルニを持って帰って研究なさいますか?」
マスターが客の人数分のコンソメスープを器に注ぎながら、冗談めかして言う。
「そうさせて貰えるなら、そうしたいなあ」
「いいですよ。素人にはわかりにくい香草があると思いますけどね。それが何かは秘密。もちろん脱法ハーブなんかじゃないですよ。こんなにたくさんの刑事さんが昼飯を食べに来てくださる立地でそんなものは使えませんから」
にんまりしつつ、出がらしのブーケガルニをビニール袋に入れ、口をしっかりと結んでくれた。「やっぱりお客さんも、刑事かその周辺のお仕事でしょう?」
「どうしてそう思うの?」
「店に入って来てから、目でいろんなものをチェックしている」
「いろんなものって?」
「厨房、壁に貼ったメニュー、ポスター、客の出入り、バイトがいるかどうか、妻が降りてきたこと、香り。他にもいろいろ。普通の客が一人で入ってくる時は週刊誌でも片手に持っていてどかっと椅子に座り、注文したら周りのことなんか見ない。不機嫌そうに貧乏ゆすりでもしながら週刊誌に没頭していますよ。あれこれ見るのは刑事か、その関係者か、作家くらいのものですよ」
「作家?」
「そう。作家先生というのは仮面作家でもすぐにわかる。じろじろと物色するように店の中を見る。たぶん、植木のしおれ方と商売の傾きが比例するとか、小説に書くとおもしろくなるように、勝手に因果を創り出そうと企んでるのだろうけど」
英語圏の人がするように、大袈裟に口をへの字にして見せた。
「関係ないの? 植木と商売」
「一般的にはどうか知らないけど、うちに関して言うと植木は元気よく育っているが商売はダメという時もありますからね。作家先生には悪いけど、そんなの非科学的な洞察じゃないですか」
マスターは客の人数分のご飯を皿に盛っている。「あ、いけね、ひとつカレーだった」
「僕は作家じゃなくて、警察関係者に見えますか」
「もしや作家先生でしたか。だとしたら、それは失礼しました」
「いや、どっちでもないけど、どちらかと言えば警察関係の方が近いかも」
「でしょう?」
満面の笑顔を見せてくれた。「第一、そこに座るから」
「そこって?」
「その場所。カウンターだけどそこだけは隅っこで後ろが柱でしょう。狭くて居心地が悪いのか、素人はそこには座らない。作家先生もそこはやや薄暗くて本が読めないからか座らない。座るのは限られた人種だけ。後ろから狙われないようにと用心深い玄人だけですよ」
「よく見ていますね」
「ずっとここで商売しているのですから」
ソースをフライパンに入れて温め始めた。これで話は終わりなのか急に無言となる。余計なことを言わないように気を付けているのだろう。一之介もちょうど食べ終えたところだった。ブーケガルニをくれたりして人懐っこく饒舌だったのは、なるほど、こちらの素性に探りを入れていたのか。裏が警察署という立地ならいろいろと訳アリ人間が来るだろうし、予め予防線を張っておくのも彼の仕事のうちなのかもしれない。
支払いを済ませて外に出ると、雲は薄くなっていたが柔らかく細かな雨が降っていた。傘を買ってまで差すほどでもなく、すぐに止みそうなので雨宿りがてら警察署に戻り、弁当を食べているだろう浅田刑事をロビーに呼び出した。さすがにもう思考停止は終わっているはずだ。案の定、弁当を持ったまま現れて、談話室に空きがないから廊下の隅にあるベンチ椅子に座って食べながら話をしようと言う。
「浅田刑事、そこの洋食屋だけど、行ったことありますか」
「もちろんあるよ」
浅田の言うことには、行ったことがあるどころか出前も取るし、ここの警察署員御用達の店らしい。
「さっき行ってみたら、マスターに出がらしのブーケガルニを貰いました。だからどうということはないけど、ふと思い出したことがあってね。マチ子の店でも働いていて、金指まるみと一緒にコンビニでも働いているフミヤのことだけど、昔、あの洋食屋で働いていなかったかな。なんとなく、マチ子の店で漂っているデミグラスソースの匂いと似ている気がしました」
「どんな人?」
「がっしりした体つきで、愛想のいい男、かな」
一之介が言うと、浅田は、「そんなのいっぱい居る」と答える。
「いずれにしても、ずっと以前、あの店でバイトが雇われていたことはありませんでしたか」
「それは、居たな。バイトが居た頃もあった。何度もあったよ。男のこともあれば女のこともあった。いちいち覚えちゃいないよ」
「厨房で料理を教わっている感じの人は? ただ料理を運んだり、お会計をやったりするだけじゃなくて調理師見習はいなかったか」
浅田は弁当の米粒を一つ残らず食べようと箸で摘まんでいる。
「居たような気がするな。ずいぶん前ですよ。マスターは普通のバイトには優しいのに、料理を覚えさせるバイトには厳しくて、それで叱られた人が腹を立てて、急に居なくなったんじゃなかったか。マスターがそうぼやいていたような気がするけど。それが八田さんの言うフミヤかどうかはわからない。調べた方がいいのか。いずれにしても、そのフミヤはまるみさんと一緒に働いているなら調査はすることになるけど」
「ひとまず、まるみさんの働いているコンビニの場所だけ、教えてもらえますか。本当にそこにフミヤが来るかどうか、まるみさんとどんな風に話しているかを、何度か通って調べてみようと思う」
「直接八田さんに調べてもらえるとこちらも助かります」
「フミヤについて調べる代わりに、このブーケガルニの香草の種類を調べておいてもらえるでしょうか。警察ならば専門家に頼めばすぐでしょう?」
「それはそうだけど、どうして?」
「わざわざ洋食屋のマスターが使い終わったブーケガルニを研究用にくれるなんておかしいでしょう。僕のことを警察関係者じゃないかと予想までしていたのですよ。はっきりと言いにくいが、なんとなく調べてほしいと言っているも同然」
「本当に? なんのために」
「さあ、フミヤがかつてあの店で修行をしていたのだとしたら、企業秘密のブーケガルニの配合を横取りしたことを暗に訴えたいのかもしれないし、それとは関係なく、いずれにしてもあいつはなんだか怪しいと言いたいのかもしれないし。バイトには優しいマスターが、弟子に料理を教える時だけは異様に厳しいというのも、ひょっとしたらフミヤに自主的に出て行ってもらいたかっただけかもしれない」
「八田さん、さすがですね。邪推力が突出している」
「探偵という仕事はどこまで要らぬ邪推ができるかが使命ですよ。それに、あのマスターは察しがよさそうだからね」
浅田が弁当の片隅の米粒を食べ切ったところでちょうど話は終わった。
金指まるみが働いているコンビニの位置がわかる地図を受け取り外に出た。アスファルトがほんのりと湿っている。もうミストめいた雨は止んでいた。空気が洗われて透き通り、遠くの信号が青に変わるのがくっきりと見えた。
一之介がやっとのことでそのコンビニに辿り着くと、地図の指し示す通り、その辺りはぴったりと隣町との境目になるらしく、ごく近くに並んでいる二本の電柱に貼られた住所がそれぞれ違っていた。周囲には二階建てのアパートが四棟並んでいて、まだ真昼だというのに歩いている人は誰もいない。
この辺りにあるセブンイレブンとしては贅沢すぎるほどの広い駐車場があり、そこには新品なのか、大きな車体が日光を反射してぎらつく冷蔵車が停まっている。駐車場前の道は細くて見通しが悪く、オレンジ色に縁どられたカーブミラーが角の二か所に立てられていて、その両方が冷蔵車の磨かれた車体に映り込んでいた。
立ち並ぶアパートと駐車場の横にある細い歩道沿いに、野性的な風情で成長した金木犀の樹があった。満開を過ぎたところで、離れていても強く香る。一之介は鼻を利かせて大きく息を吸い込む。確か、前に金指まるみと浅田刑事と行った駅裏のローソンでも嗅いだ。
――あの時は金木犀の姿を見つけることはできなかったが。
まさか。こんな場所から、あのローソンまで香るはずはない。しかし、時空を超えて存在を主張する時には、実際に嗅ぐよりも異様に鼻をつく香りがまとわりつくことはある。金木犀の近くまで行くと、歩道や駐車場に細かなオレンジ色の花びらがびっしりと落ちて、合成香料の添加された蜜柑ジュースがぶちまけられたかのようだ。強く匂うが、これが何だと言うのか。何を訴えたいのか。
金木犀の陰からコンビニの中を覗いてみたが、まるみとフミヤの姿はなく、ロングヘアの女の子と短髪の青年がレジ周辺に立っていた。
一之介は大きく深呼吸をする。金木犀の、自然なのにどこか人工的な香り。花なのに熟れ過ぎた蜜柑の匂い。
金木犀の樹を離れ、なんとなく駐車場周辺を歩いていると、駐車場の冷蔵車がブルブルと大きなエンジン音を立てた。
――なんだ? 人が乗っていたのか。
咄嗟に運転席を見ると、向こうからもじっとこちらを見ている。睨みつけるような視線だ。
――フミヤ? まさか。
なんとなく似ている気がする。伺っていると、冷蔵車はじりじりと発進し、ゆっくりとこちらに向かってきた。
――な、なんだ、危ないじゃないか。
急いで一之介は身をかわし、冷蔵車の横側に回り込んだ。すると、車は急ブレーキを踏み、今度は後ろ向きに発進し始めた。改めて、一之介の方にハンドルを切ろうとしているのか、タイヤがアスファルトの地面を擦りながらこちら側に方向転換した。
――ひょっとして、僕を殺す気か?
一之介は焦って車の後ろに回り込んでから、コンビニの中に飛び込んだ。
「いらっしゃいませ」
朗らかな声が店内に響く。店員の二人はコーヒーメーカーにカップを補充したり伝票整理をしたりするのに忙しく、駐車場の冷蔵車の動きを見ていないようだった。ほんの一瞬のことだし、静かな動きだから気付かなかったのか。しかし一之介の心臓は高鳴り、鼓動の激しさに胸が張り裂けそうだった。今でも運転席のフミヤらしき男が硝子越しにこちらを見ている気がする。
一之介の動揺に反して、店内には朗らかな宣伝用ラジオが流れ、新作デザートのパンナコッタの美味しさを軽妙な調子で訴えている。作業の合間に店員の二人は何か談笑している。客が一人居て、飲み物コーナーで野菜ジュースを選んでいた。
「あの冷蔵車は、ここの、搬入を、しているの?」
息も途切れながら、一之介はレジに辿り着き、店員たちに声を掛けた。二人は顔を見合わせ、
「どれですか?」
一之介の指さす方を見た。
「あれです、あの冷蔵車」
硝子窓の方に振り返って駐車場を見ると、もう冷蔵車は発進してしまったのか、姿も形もなかった。
「冷蔵車? 居た?」
女の子が青年を見る。
「さあ。居ましたか。覚えてないです」
青年が微笑みながら首を傾げた。
一之介は思考停止中の浅田刑事のように固まってしまった。
――何かおかしい。いや、僕がおかしいのか?
殺意を感じる車の動きと、店内の無邪気な朗らかさ。
「そうですか。すみません。見間違いでした」
早々に店を出る。変人扱いされるのも困る。とはいえ、まだどこかに冷蔵車が停まっていてこちらに向かって襲ってきそうに思え、恐怖で荒ぶった鼓動は静まらなかった。気が付くと、額や首元、脇下に大量の汗をかいていた。
「それは大変な目に遭いましたね」
電話口の浅田が素っ頓狂な声を上げた。
「まるでホラーですよ」
一之介はあまりの驚愕に落ち着こうとして、まずは事務所に戻ってから連絡を入れたのだが、時間が経てば経つほど身体の震えが止まらなくなるようだった。
「八田さんともあろう人が、声が震えている」
「実際の状況以上に怖かった。二つもあったカーブミラーのせいかもしれません。心理的になんとなく、気がやられた」
未だに呼吸も整わない。
「八田さんだとわかって襲ってきたのかな。それにしても随分うろたえていらっしゃる。運転手がフミヤだったことは確かですか?」
「そんな気がしただけで、確かめたわけじゃない。それに、僕を狙ったわけじゃないと思います。だって、今日、僕があの場所に行くなんて誰にもわからないはずです。浅田刑事から地図を受け取って、その足でなんとなく出向いただけですからね」
狼狽しているところを他人に知られるのは嫌いだが、そんなことを言ってはいられない状況だった。頭で考える以上に、身体が恐怖に晒されて訴えている。
「まるみさんに、バイトを辞めるように言った方がいいかなあ」
浅田は八田よりもまるみの方が心配らしい。
「早急に、辞めるように言った方がいいですね」
「八田さん、珍しいですね。いつもなら何があろうと冷静で、バイトを辞めろと言うだなんて越権行為だと反対しそうなのに」
「今回ばかりはそうは思わない。なんとなく朧げに、冷蔵車を運転していた男がフミヤだったのかなどではなく、あれだ、その、直観だ」
一之介は不必要に声を荒げた。
「わかりました。いずれにしても、まるみさんに連絡を取って、とりあえずバイトを休むように言ってみましょう。状況はわからないが、その方がよさそう」
「浅田刑事、後日、またうちの事務所でまるみさんを含めて話をしましょう。いや、話をさせてくれ」
一之介が言い放つと、浅田は、威勢よく「了解」と言って電話を切った。
*
それから二日後。
マチ子から電話があり、「フミヤを知らないか」と言う。
「どうしたの?」
「一昨日、八田さんに朝弁を届けてもらってから、無断欠勤しているのよ」
「そういうことは、初めて?」
「初めて。真面目な子なのに。事故にでも遭っているんじゃないかと思って心配なのよ」
声の本気度が高い。間違いなくフミヤはマチ子のお気に入りなのだ。
「だけど一昨日、彼はうちには来なかったよ。マチ子から連絡もなく朝食が来ないのは初めてだったから、電話してみようかと思ったけど、なにか催促するみたいだから遠慮していました」
一之介が言うと、
「すぐに連絡してくれたらよかったのに」
マチ子は受話器から耳を外したくなるほどの甲高い声を出した。
「フミヤ君がいないと困るの?」
「大いに困るわよ。誰がメインメニューを作るの。タクヤもいなくなったばっかりなのに」
「また雇えばいいじゃないか」
「あんなに優秀な人たちはそうはいないのよ」
本当に困っているらしい。泣きそうな声だ。
「もっと給料を出しておくとか、ここに朝食を運ばせるのをやめておくとか、きちんと好待遇をしておけばよかったのに」
「もう辞めてしまったみたいな言い方をしないで」
不当にこちらに怒りをぶつけてくる。
「だけど、もう来ないと思うよ」
「どうして、そんなひどいこと言うの」
ヒステリックになった。
「さあ、直観」
一之介が言うと、
「八田さんはいつも、直観、直観って、探偵のくせにばかみたい。信じたくないわ。だけど、そうは言っても――。八田さんが直観するんだったら、確かに、もう来ないかもしれない」
勢いよく言い始めたものの、だんだん声がしぼんでいった。
「住んでいるところに行ってみればいいじゃないか」
「知らないのよ」
「知らないって、そんな杜撰な」
一之介は呆れてしまう。
「最初に提出してもらった履歴書には書いてあるけど、嘘に決まっている。携帯はつながらなくなっているし」
「困ったね」
「それにしても、あれを買ってから、変なことばっかり起きる」
「あれって?」
「ペガサス」
「ああ、あれか」
一之介は玄関先のオブジェを思い出した。いつからあったのか。「変なことって、たとえば、何?」
「言いたくないわ。とにかく、もう少し探してみる」
強い口調で言い、一方的に電話は切られてしまった。
一之介は目を閉じた。
ペガサスの置物か。そう言えば、いつからあそこにあったのだろう。夜には体中に巻き付けられたライトが華々しく点滅し、まるで生き物のように見える。子供なら跨って遊べそうな大きさだし、小さな猫なら中に入って居眠りできそうだ。
――内側に入って?
あの内側に何があるのだろう。目を閉じたまま、一匹の猫になって内側に入り込むと妄想する。例えば、よく見かけるあの灰色の町猫になるのだ。内側は思いの外別世界につながっていて、ひとたび入り込んでしまったら金指まるみが連れ去られたように、外側の世界のことを忘れてしばらく過ごす。器用にその世界の屋根から屋根へと飛び移る。
――さすがに妄想か。邪推にもならない。
ぼんやりと考えていると、再び部屋の電話がけたたましく鳴った。浅田刑事からの連絡だった。
「一昨日、八田さんを襲った冷蔵車が見つかりました。河原に乗り入れて、そのまま捨てられていたようです。中からいろいろと出てきましたよ。だけど、まだフミヤという人が運転していたのかどうかはわかりません。いずれにしても、明日の午後、まるみさんと三人でひとつずつ検証することにしたいのですが、お時間は?」
「もちろん、行きます」
即答した。願ってもない。こんなもやもやした気持ちに早く終止符を打ちたい。
「じゃあ、明日、署で」
電話は切れた。部屋はしんとする。見慣れた自分自身の部屋がどこか、知らない他人の住処のように思えた。さきほどまで妄想していた通り灰色の猫になってしまった気がする。「ペガサスを買ってから変な事ばかり起こる」と言ったマチ子の言葉を思い出した。
ペガサスが関係するかどうかわからないが、確かにこれまでになく奇妙な事件だ。どこかにある神話のように、いっそみんなペガサスの内側にいるようなものなのか?
――僕は電飾が消えているからと油断していたのかもしれない。
目を閉じると、じっと動かないあの置物が脳裏に浮かぶ。イメージの中で電飾全てが一斉に灯り始めていた。
*
浅田刑事の運転する車は海岸沿いの倉庫に辿り着いた。
「ここです」
促されて車を降りると潮の匂いがして、クレーン車が出す機械音が混じった波音に包まれた。ウミネコが飛び交っている。
気味が悪いほどに空が晴れているせいで、コンクリートで岸壁を切り取られた海が着色された青いカクテルに見える。風が吹いて白波が立っていた。広々とした港にはブランド名が表記された同型のコンテナがいくつも積み上げられている。こんな場所にもしも一人で迷い込んだら二度と出られないだろう。コンテナ中の物販品はいつか街で売られる。その時、商品は手に取りやすくディスプレイされるのだろうが、海の向こうから届いたばかりでは、箱の中に納まったまま、こうして潮の匂いと太陽の光を浴びた風に晒されている。いっそ、これから魂を注入される予定の骸骨たちが並ぶ墓場のようでもある。青空高く首を伸ばすクレーン車を見て、一之介はなんだかからからに乾いた気分になった。ウミネコの鳴き声が無機質に響き渡る。
一之介を襲った冷蔵車は最初に発見された河原から、ここにある警察の倉庫に移動されたのだという。
「運ぶのに苦労しました」
浅田刑事は倉庫の重い鉄扉を開けた後、手探りでスイッチを探し灯りを点けた。蛍光灯と白熱灯の両方が灯る。天井が高く、すす臭い匂いが充満している。特殊捜査用の薬剤や拳銃が保管されているのだろうか。背の高いスチール棚が床から天井までそびえ立ち、用途のはっきりとしない木材や箱がびっしりと積まれていた。棚と棚に挟まれた中央の空間に見覚えのある冷蔵車が置いてあった。
「どうやってここに? 誰かが運転してきたのですか」
一之介は大きな車体を見上げる。コンビニの駐車場で急発進して接近してきたことを思い出して身震いした。
「いや、ガソリンが抜いてあった。河原からレッカー車で道路まで引き上げ、そこからはトレーラーを出動させてここまで。いやはや大掛かりなことだ」
浅田刑事は八の字に曲げた眉の端を人差し指で掻いていた。
車内の撮影や指紋や血液等の採取は一応終わっているらしく、
「八田さんがフミヤと言っている人の指紋も出てきました。八田さんの知り合いのマチ子さんの店で働いていたのでしょう。今、そのフミヤの行方を捜しているところです。でも、フミヤがマチ子さんに渡したという履歴書の情報もいい加減だったようだし、まるみさんと同じコンビニで働いていたらしいけど、そこでの履歴書とは一致しない。何やかや偽造して、あっちこっちに出没している輩ですね」
浅田はスーツの内ポケットから写真を取り出した。「これでしょ、八田さんが仰っているフミヤという男」
確かに、朝食を届けにきたことのある人物だった。タウンチャイルドでも話した。
まもなく倉庫の駐車場に白い小型のパトカーが停まり、中から婦人警官とまるみが出てきた。浅田刑事は走って駆け寄って行き、
「こんなところまで来てもらってわるかったね。寂しくて嫌な場所なのに」
一之介に対するのとはまるで違って、まるみには大袈裟に謝っていた。婦人警官にはやはり不愛想に「もう帰っていい」と言い、まるみだけを連れて改めて冷蔵車の前に立った。まるみはバイト先で任意同行を求められたらしく、いつものTシャツとジャージにリュックを背負って猫背気味な姿勢。まだ経緯はよくわかっていないように見えた。
「これに見覚えは?」
浅田がまるみの顔を覗き込んだ時、まるみは唇をぎゅっと合わせた。硬直したまま車を見つめ続け、やっと、
「あると言えばあるし、ないと言えばない」
無表情のままで言った。
「どういうこと?」
一之介は浅田とまるみの顔を見比べた。「まさか、まるみさんがフミヤの共犯者ってことはないでしょう?」
「八田さん、バカなこと言わないでください」
浅田が制する。「そういうことじゃなくて、ただ、見たことがありますかと聞いているだけです」
まるみは車に目をやったまま、黙っていた。
「もちろん、黙秘権があるのだから、何も言わなくてもいいですよ」
一之介が言うと、
「だからそういうことじゃなくて――」
浅田が高い声を出し、「でも、まあ、言いたくなったら教えてくれる、ということでいいです」と譲歩した。
「とりあえず、中に入ってみましょう」
浅田が車体の架装部の扉を開け、立て掛けてあったスチールのステップを設置して中に入ると、一之介とまるみも後に続いて中に入った。
「なんだ、これは?」
壁面には電子機器のぎっしりと詰まれた棚があり、一番奥には大きな液晶画面、床に黒い革製のリクライニングチェアが置いてある。ゴーグルとヘッドフォンの一体化したヴァーチャルリアリティヘッドセット。
「正確には冷蔵車ではなく冷凍車。それを改造したものだそうですよ」
車内の白熱灯を点けた。「そして八田さん、驚いたことに外側の銀色のボディも、通常の冷凍庫のスチールではなく液晶スクリーンです。まるみさんと一緒に外に降りて側面のボディを見ていてください」
一之介とまるみは再びステップを降り、外側に立った。
「今は普通の銀色のスチールボディに見えますね。ではやりますよ」
車内マイクを通した浅田の声がして、しばらくすると、側面にカーブミラーと道路の画像が映った。
「ああっ、これは!」
倉庫内に一之介の声が響いた。「あのコンビニの駐車場で見たものだ。ボディがぴかぴかに磨いてあるから鏡のようになって、あの辺りの景色を映っているのだと思っていたけど」
「ところが、これは映像です。だけど、こうしてみるとわかりますが、その時、前に立っているのに八田さん自身の姿は映っていなかったはずです。だから何か、場所が広く見えたり坂になっているかのように錯覚したりして、脳が混乱したと思いますよ。たとえ辣腕探偵の八田さんであったとしても」
映像の中ではカーブミラー横に金木犀らしきものがあり、葉が微かに風に揺れ、雀が一羽横切ったが、しばらく見ていると何ども同じ光景が繰り返されていることがわかる。確かに映像だった。
「他の映像もあります。見てください」
様々な街のシーンが映し出される。その中には、最近、酒屋からコンビニになった店らしき風景もあった。
「これ、駅前の新しいコンビニですけれど、できてからまだ一年経っていないのに、駐車場横の生垣に椿が咲いているでしょう? ですから、合成したものです」
「まるみさん、ひょっとして、これで騙されたとか? それで数週間、行方不明になっていたとか?」
一之介は直立したまま微動だにしないまるみの顔を見る。最初の頃に見た、あの目を大きく見開いた表情だった。
「まるみさんだけではなく、僕もすっかり騙されたわけですけれど」
こう言えば少しは慰めになるだろうか。
浅田刑事が車体のステップを使って軽快に降りてきて、二人の前に立ち
「ところで、この車の所有者はまるみさんの知っているフミヤ、あるいはコンビニ店員としては谷口りょうすけでよいでしょうか」
と言うと、まるみがこくんと頷いた。
「彼が今どこにいるのかわかる?」
まるみは黙って首を横に振る。
「まだ見せられないけど、この中のヴァーチャルリアリティヘッドセットが見せる映像に、まるみさんが仰っていたさやかの映像が出てくる」
浅田がぽつんと言う。「たぶん、まるみさんは、しばらくこの中に閉じ込められていたのだ。あるいは、ヘッドセットを装着したまま、この中に入り、どこかに移動し、またこの中に戻って、そして、出てきた」
「フミヤが作った装置でしょうか」
一之介はにわかには信じられなかった。こんなチャチ臭い装置でまるみが数週間も騙されることも、あの人の好さそうなフミヤがこんなものを作ることも。
「それはまだわからない。いずれにしてもフミヤ、あるいは谷口りょうすけだが、一人でここまでの装置が作れるはずはないから、仲間がいるでしょうね」
「メディアアーティスト集団、《アフロディテ》?」
「さあどうでしょうか。今のところ《アフロディテ》が確かな形をもった集団かどうかもわからないし」
一之介と浅田が、ああだこうだと話している間、まるみはずっと黙り込んでいた。
全員の逡巡を遮るように浅田の携帯が鳴り、電話口の相手に向かって「なんだって? そうか」と声を張り上げた後、
「八田さん、まるみさん、帰りましょう。フミヤこと谷口りょうすけが見つかった。署にいるらしい。まずは顔の確認からですね」
珍しく、きりりと引き締まった表情を見せた。
浅田の古いトヨタ車に乗り込んで署に着くと、フミヤは取調室の中に居た。窓から覗くと、間違いなくあの朝食を届けに来た男、タウンチャイルドの厨房に立っていた男だった。笑うと八重歯がちらりと見えてフレンドリーな雰囲気になるはずだが、今は神妙な顔つきで取り調べに応じている。
「まるみさん、あの男でいいですか。あれが、まるみさんの知っている谷口りょうすけですか」
まるみはのぞき穴からじっと見た後、黙って頷いた。
「今日の所はここまでにしましょう。フミヤことリョウスケの取り調べ結果が出たら、お二人に連絡しますよ。八田さんの事務所に集合しましょう。いいでしょう?」
浅田の言葉に、一之介は「もちろん」と応じた。
数日後、一之介の事務所に集まる約束が果たされた時、翔太にも声を掛けて同席してもらった。翔太の方でも、ちょうど遠野美咲の指紋が取れそうなものを用意したので届けたかったところだと言う。なぜ翔太が関与しているのだとまるみが驚くだろうと浅田刑事が何度も一之介に電話を寄越して言い、「これでいいだろうか」と悩んだようだが、実際に集合してしまえばそれほどの違和感もなく馴染んだ。最初から四人で捜査していたような気さえする。
最初に、浅田刑事がフミヤことリョウスケの調書を読み上げた。
<調書の内容>
フミヤこと谷口りょうすけの本名は谷文哉、三十五歳。
冷凍車の持ち主で、改造したのも本人である。漁師だった友人が先物取引に手を出したせいで破産し夜逃げする前、谷文哉はその友人から冷凍車を安く買い取ったと言う。谷文哉の家は農家で、今では誰も耕さなくなった広い空き地があり、そこにあるガレージに車を停めていても家族さえ気付かず、誰からも気付かれることはない。
谷文哉は冷凍車の構造を利用して改造し、人間の錯覚を利用した異次元空間車を創った。
谷文哉が言う事には、バイト先で知り合った金指まるみはアニメマニアで夢見がちだったから異次元空間に入り込みやすいだろうと思って「贈り先」に指定した。「贈り先」というのは文哉が作った異次元空間をプレゼントする先のこと。
まるみにヘッドセットを被せて車内に招待し、すぐに「ドッキリでした」とふざける予定だったが、まるみがそのまま覚醒してこなかったので驚き、迷った挙句、一旦、自宅の空き地まで車を運び、しばらく離れで生活させていた。まるみは半分眠ったような状態ではあるものの、何度尋ねても帰りたくないと言うので、仕方なくそのままにしていた。
先日、確かに仕事場であるセブンイレブンに車を停めていたが運転席を離れており、八田一之介を襲ってはいない。車は気付くと盗まれ、セブンイレブンの駐車場からはなくなっていた。従って、河原に放置したのは谷文哉ではない。
履歴書に嘘の名前を書いたのは、以前、本名を書くと辞めた後に就職先からメールやラインで嫌がらせを受けることがあり、その後一切偽名を使おうと決めて、そうしていた。その件に関しては申し訳なかったと思っている。
「どう思いますか」
読み上げた後、浅田刑事が一之介とまるみ、翔太の顔を見た。「まるみさん、谷文哉、というか、まるみさんにとっては谷口りょうすけの車の中に入ってしまい、それから彼の離れで生活していたと思いますか」
まるみは一点を見つめたまま、組み合わせた指を小刻みに動かしている。
「どうでしょうか」
曖昧な返事をし、緊張感はあるものの、やはりいつもの、のんびりとした空気が辺りに充満し始める。
「フミヤは僕の事をどう言っているのでしょう?」
いらいらしたのか、翔太が割り込む。
「翔太君とまるみさんが姉弟だということはまだ話していません。おそらく、知っているだろうとは思うけれど、余計な情報をこちらから提供するわけにはいかないし」
浅田が手早く答える。
「りょうすけさん、今、どうしているのでしょう」
まるみがぽつんと言う。
「両親の監視を条件に家に居るよ。また取り調べが必要になったら、署の方に来てもらうことになっている」
「私は催眠術にかかっていたことになっているのでしょうか」
「あのフミヤならそれくらい簡単だ」
翔太が吐き捨てるように言った。
「どういうこと?」
「詳しい術の掛け方はわからないけれど、フミヤはなんだって思い通りに動かす能力があるんだ。たまに厨房から出てきて客と接触すると、途端に仲良くなって、気が付くと高価な時計をその場で譲ってもらったり、手帳を置き忘れさせて中身を見たりしていた。酒になんか混ぜたのかなと思ったりもしたけど、そういうわけでもなさそう。会話というほどの会話もしないし、どうやって術を仕掛けたのかはわからない。ただフミヤが笑顔を見せると相手が確実に油断する」
翔太の言葉を聞いた一之介は、フミヤが朝食を届けに来た日のことを思い出す。とても催眠術を掛けるのが得意な危険人物には見えなかった。しかし、たった今そう言われてみれば、なんとなくこちらを油断させてしまう気のいい笑顔を見せた気もする。
「まるみさんは、どう思いますか? 彼の事。まるみさんにとってはフミヤというより、谷口りょうすけですが」
一之介はまるみの感想を聞いてみたかった。
「いい人だと思います。というか、いい人だと思っていました」
「今はどう思う?」
浅田刑事が聞く。
「さあ。――」
まるみは少し首を傾け、微かに黒目を左右に動かしている。
「姉さん、あんなやつ、姉さんを拉致したんじゃないか。いい奴のわけがないだろう」
やはり翔太が険しい表情をし、ソファの座面を手のひらでバンと叩いた。
「まあまあ、そう、怒らずに」
浅田刑事が制した。
「それにしても、八田さん、この事務所、前に来た時よりもバニラが強く香りますね」
翔太が細かく息を吸い込み、匂いを嗅ぎ始めた。
「そうなんだ。よくわかるね。僕自身そう思う。翔太君が話していた遠野美咲の香りだと思うけど。あのファイルにも付着していた香り」
「だとしても、強く香り過ぎじゃありません?」
もっと深く息を吸い込んでいる。
「翔太君が持参した指紋の証拠物件から匂うのでは?」
「いや、それは違う。しっかりと封をしてあるから」
かばんからビニール袋を取り出して見せる。確かに、袋の口の部分はきっちりとテープが張ってある。中には一冊の本が入っているらしい。
「じゃあ、どこから香るのかな」
翔太と一之介が鼻をくんくんと鳴らす間、浅田とまるみはきょとんとしている。匂う人には匂い、匂わない人には匂わないのだろうか。
「ところでその本は何?」
浅田がビニール袋を指した。
「これは、『次元間越境交流法』です。遠野美咲の指紋をこっそり取ってきました。経費でよろしくです。こっちは自腹でいいです」
翔太はそう言って、鞄の中からビニール袋に入っていない本を一冊取り出した。タイトルは『次元別時空間地図』だった。遠野美咲に勧められた本を買うことで、美咲の指紋を入手したのだと言う。確かに表面が艶々した高級感のある書籍だから、明確な指紋が取れそうだ。
「こっそり前もって全体をよく拭いておいて、売れないように棚の奥に仕舞い込み、それから遠野美咲が会計担当の日を狙ってアフロディテに行き、購入しました。そうすればレジで彼女が触れるから。もちろん、僕の指紋も着いていると思うけど」
「実を言うと、僕もその遠野美咲さんにお会いしました」
一之介は翔太に告白した。「朝起きると、寝室でこのバニラが強く香ったものだから、翔太君の話していた遠野美咲さんのことを思い出して、すぐに着替えてアフロディテに行ってね」
「マジで?」
翔太は浅田と一之介の顔を見比べる。「その朝、誰が朝食を届けたのですか」
「珍しく、届かなかったんだ」
「誰が担当だったんだろう」
「マチ子に聞いたら、フミヤ、というか、谷文哉の担当日だったそうだよ。だけど、来なかった。逃げようとしていたんだろうなあ」
「鍵は?」
翔太がせっかちに言う。
「さて、フミヤが持ったままじゃないのか」
「八田さん、まだそんなことやっているのですか。マチ子さんに言って朝食配達は止めてもらって、とっとと鍵を付け替えた方がいいですよ」
翔太は呆れたと深くソファにもたれかかり、大きく溜息をついた。
「ごもっとも」と浅田も頷く。「ひょっとしたら、この香り、谷文哉が仕掛けたのかも。例えば、蜜蝋とか固めた塩といったゆっくりと揮発する基材に仕込んで、少しずつあちこちに置く。壁に塗る。オイルに垂らしておいてランプの近くに置き、灯りを点けたら香るようにする。そして朝食は置かないでそのまま逃げた。どうして朝食を置かなかったのか。もちろん、その日、自分が来た足跡を残さないため。文哉が来たわけじゃなくても、その日、鍵を持っていたら、文哉に頼まれた誰かが侵入して、それくらいのことはできるしょう。そして香りの魔術と念力で八田さんにアフロディテに行けと指図する。最終的にはまるみさんも働いているあのセブンイレブンに行くように念じたのだ」
「念じたって、そんな、無茶な。現実主義の浅田さんにしてはおかしなことを仰います」
一之介は声を出して笑ってしまった。
「でも、実際、なぜかアフロディテに行ったんでしょ? それに八田さん自身もその程度の術は掛けられるのではなかったかな。辣腕探偵はその程度のことができないと魑魅魍魎と闘えないと仰っていたのでは?」
そう言われて、一之介は笑うのを辞め、咳払いをひとつする。
「でも、香りでそんなことできるのかな」
「できないとでも思っているのですか。香りなんて特に無意識領域に入り込みやすいでしょう? その香りを使って無意識を開き、フミヤと八田さんの間に回路を作って念力で誘導すれば可能でしょう」
「なんのために?」
一之介にしてみれば手口は理解できないこともないが、いつものように、やはり動機がわからない。
「愉快犯というのもありますよ」
浅田が口を挟む。「書類送検されるまでには至らなくても、実際にはそういう、いたずらめいた犯罪というのは山のように上がってくる」
「そう言えば、翔太君が僕の事務所に『無人島の二人称』を盗みに入った時も、どういうわけか伽羅の強い匂いがしたと言っていたな。滝田ロダンが古書に焚き占める伽羅の香りだとか。それで、不思議な焦燥感に包まれて自転車でここまで来たのだったね」
「誰の仕掛けかはわからないが、あれもなんらかの術でしょうね。あの時の気分は今にして思えば変でした。きつねにつままれたとはあのことです。すごく濃い伽羅の香り。僕もきっと彼らの術にかかっていた」
翔太が素直に認める。「それで、八田さん、術に操られてアフロディテに行った時、誰がいました?」
「だから、さっき言ったように、遠野美咲に会いましたよ。翔太君から聞いた通りの派手な女性。紛れもなく、この香りがした。小柄な――」
「小柄? 本当に、それ、美咲さん?」
翔太が首を傾げた。
「違うの?」
「美咲さんは女性としてはそれほど小柄とは言えないと思います。姉より少し大柄程度。別人かもしれない」
それを聞いた浅田はすぐに携帯電話で署から人を呼び、翔太が持ち込んだ『次元間越境交流法』を鑑識に回すように指示した。
鑑識結果を待つ間に出前で蕎麦定食を取り、食べ終える頃には署から連絡が入って、翔太の知っている遠野美咲と一之介が遭遇した遠野美咲は別人だとわかった。
「八田さん、その《アフロディテ》の店員は遠野美咲ですと名乗りました? 早とちりしたんでしょう」
浅田が恨めしそうに言う。
「そう言えばそうだな。どうして、僕は遠野美咲だと思ったんだろう」
「このバニラの香りとやらでしょう」
浅田が息を小刻みに吸い込みつつ、香りをキャッチしようとしていた。「俺にはちっとも匂ってこないけれど」
「それもあると思うけれど、名札じゃないですか」
翔太が指摘する。「アフロディテには一応、店員用の名札があります。本を買い取る時に住所と名前を聞くのだから、こちらも名乗るのが礼儀と言って、バイトも付けるようになっています。でも、さぼって付けない人も多いですけど。もしも、その小柄の女の子が遠野美咲の名札を付けていたら、確認することなく、ああ、これが遠野美咲かと思ってしまうのかも」
「名札か。記憶にはないけれど」
一之介は覚えがなかった。
「ひょっとしたら、見えそうで見えないところに付けておくとか、最初だけ付けておいて後で外すとか、小技があるのかもしれません」
「無意識を操作するのですか? なんのために?」
「だから、愉快犯というのもあるって、さっき言ったじゃない」
浅田が笑いながら、人差し指で一之介の二の腕を数回突いた。
「ところで、そういう人はいます? 小柄の派手な化粧をした遠野美咲風の――」
「いやあ、僕はそういう人は見覚えがありません」
翔太は否定した。
「だけど、その小柄な人の指紋は、まるみさんのランドセルとかファイルに付着していたものと一致したのだったね」
「私のランドセル?」
物置に入っている物全てに、まるみ以外の誰かの指紋しかないことをまるみ自身はまだ知らなかった。
「その件は、いずれ説明するから」
浅田が慌てて隠す。
「八田さん、やっぱり八田さんはフミヤに術を掛けられていますよ。掛かったところでそれほどの害もない。掛からなかったところでどういうこともない。掛かるか掛からないか、試しているだけだろうけど、今回は掛かっちゃった」
翔太が一之介を見てにやりとする。
「やられたか?」
一之介は舌打ちをして、翔太を見返す。
「ええ、たぶん」
「それにしても、フミヤと《アフロディテ》は関係があるのか」
「そこです」
翔太は金指まるみの方をまっすぐに見た。「姉さんのバイト先に《アフロディテ》のやつらが居るでしょう?」
まるみは一瞬身体をびくっとさせ、大きな目をさらに大きく見開いた。
「どうして、そんなこと言うの」
「僕は見たんだ。なんとなく姉さんのバイト先を訪れたら、《アフロディテ》のメディアアーティスツで見たことのあるやつらとフミヤや姉さんが仲良さそうに話しているのを」
「話を合わせているだけよ。確かにりょうすけさんの知り合いが頻繁に出入りするけど、それが《アフロディテ》とか言うメディアアーティストの人かどうかは知らない」
まるみはまばたきを多くした。
「姉さん、ひょっとしてフミヤなんかと付き合っているのか」
「フミヤなんかって言われても知らないわよ。私が知っているのはりょうすけさんよ」
「じゃあ、そのりょうすけさんなんかと付き合って――」
「うるさいわね、自分こそ何よ、知っていたんでしょ、あのVRのこと」
まるみはそう吐き出してから、「ああっ」と言って口を手で塞いだ。言ってはいけないことを言ってしまったらしい。
「何を言ってるの?」
翔太が力の抜けた声で言う。
「まるみさん、何か気になっていることがあったら、この際、言ってしまってください」
浅田が静かに促した。「どうせ、この後いろいろと調査すればわかることだから」
まるみは目を伏せ、肩を丸くしてじっとしている。
「まるみさん」
「姉さん、僕は何もやましいことはしていないよ。浅田さん、八田さん、信じてください。大丈夫です。姉さんが何か勘違いしていたとしても――」
「勘違いって何よ、VRにしっかりと写っていたわよ」
まるみはそう言った後、また、「ああっ」と口を手で覆う。
「何が? 僕はそのVRとやらは知らないけど」
翔太は一之介と浅田の顔を見る。
「わかりました。じゃあ、後であのVRを三人で見ましょう。いずれにしても、まるみさんはそのVRの中に翔太君の何かを見たのですね」
浅田の言葉にまるみはこくんと頷く。
「じゃあ、それで騙されたふりをしていた?」
一之介がにんまりとする。「そうですよね。だって、数週間もVRの世界に入ったまま出てこないなんて、ちょっとおかし過ぎるでしょう」
「どういうこと?」
浅田がきょとんとしている。
「まるみさんはフミヤにVR用のヘッドフォンを被せられた時、一瞬は術にかかったかもしれない。しかし、まるみさんが通っているレアマにもそういう装置はあるし、そういうものがあることを知らないわけではない。これはVRだとすぐにわかったけれど、その映像の中に翔太君の関与を疑わせるものが写っていて、翔太が犯罪めいたことに加わっているのじゃないかと考え、本当のことを言い出せなくなった。それで、眠り込んだふりをしてフミヤ、いや谷りょうすけの仕掛けの中に居座った」
一之介が推理した。「そうでしょう?」
しばらく黙り込んでいたけれど、まるみはうなずいた。
「だいたい、そんなところです。私はスマホを忘れるわけがないのに、レアマでさやかと遭遇した日はコンビニに置き忘れていたけれど、その日、りょうすけさんと組んだ日だったから、それもりょうすけさんの仕業かもしれないとすぐに思った」
「すぐに言えばよかったのに」
脱力したように翔太が言うと、
「だって、ショウくんもあいつらとグルだったらどうしようって思って。私が異世界に行ったことになっておいた方がずっといいと思って。それに――」
「それに?」
「楽しかった」
ほのかな笑顔を見せた。
「何が?」
「あの、りょうすけさんの仕掛けが」
「あれが、楽しかった?」
「そうです。いたずらだとわかっているけど、私、家族にもそれほど関心を寄せられたことがなかったし、レアマでもそんなに友達がいるわけでもないし、自分なんか居ても居なくてもいい存在だと思ってずっと生きていたのに、こんなに素晴らしい、私専用のVRを作ってくれて、ラインにまで仕掛けをしたり、わざわざ『さやか』という女性をレアマで遭遇させて、その後、映像で見せたり――」
「あの『さやか』をレアマに連れて行ったのは僕だよ」
翔太が言うと、
「ほら、やっぱり、ショウくんもグルなんじゃない!」
まるみは声を大きくした。
「ところで、VRの中には翔太君の何が写っていたのでしょうか。姿そのものですか」
一之介は喧嘩になりそうな二人の間にすっと分け入った。
「ピアスと指輪を点けたショウ君です」
「姉さん、僕のピアスと指輪を知ってるの?」
「知ってるわよ。ホストの仕事をする時だけ着けているんでしょ?」
「あれはホストじゃないけど、いずれにしても、なんでバイト先のこと知ってるの?」
「私、しょっちゅう、行ってたのよ。タウンチャイルド」
「ええっ」
一之介と浅田と翔太が同時にソファから立ち上がって、顔を見合わせた。
「いつの間に?」
「バイト先の友人としょっちゅう。私、厚化粧して変装すると年増の女になるのよ。それで黙って座っていると誰も私のことなんか相手にしない。というか、そんなことしなくても、ほとんど誰も相手にしないけど。特にショウくんは私の方をちらりと見もしなかったわ。やっぱりと思った。家と同じ」
「まさか――」
「そして、VRではあのピアスと指輪を点けたショウくんが時々横切るように合成してあった。だから驚いたのだけど、今にして思えばりょうすけさんは本当に冗談であれを作ったのだと思う。わかりすぎる冗談だもの。八田さんも刑事さんも気付いていらっしゃらないかもしれないけれど、新しくできた駅前のコンビニ、作った映像ではセブンイレブンになっている。実際にはローソンでしょう?」
まるみはくすくす笑い始めた。「私が戻ってきたと写真を撮ってラインを流した人たちも映像だった。かな? 私はあの時、本当のことをわかっていたのかな。曖昧なままで騙される演技をし続けていたのかな。もうなんだか忘れちゃった」
「そうなのか」
男たち三人はへなへなとソファに座り込んだ。
「だけど姉さん、姉さんは中学生くらいの頃、お母さんに叱られて家を飛び出して、おばあちゃんの家に行っていたはずなのに、物置から出てきたことがあったよね。お祖母ちゃんのところになんか行っていないって。あれは何?」
いっそのこと姉に関するあらゆる謎を解明しておきたいと思ったのか、翔太が畳みかけるように聞く。
「そんなこと、よく覚えているわね」
「当たり前だろう。あんな変なこと」
「あの時は、家を飛び出したら、ちょうど自宅に帰ってきたばかりの近所の子がいたから、その子に頼み込んで自転車を借りて、お祖母ちゃんのところに行ったのよ。それで、誰にも言わないでねってお祖母ちゃんに言ったのに、電話でお母さんに、まるみがこちらに来ていると言っているのが聞こえたから、私、腹が立って、それでまた自転車に乗って見つからないように辺りをふらふらして、それから夜中にそっと戻って物置に入ったの。なんだかピンときたのよ。物置がいい。ずっと物置に居たことにしようと思って」
「どうして、そんなこと?」
「愉快犯でしょ」
浅田が力なく言い、「ああっ」と口を塞いだ。「ごめん、つい、惰性で」(第三章 2 了)》
※ここまでの解説
あらすじ。
八田一之介はバニラの匂いに釣られて、《アフロディテ》に行く。遠野美咲が居るに違いないと思ったのだ。小柄の「遠野美咲」からうまく指紋を採取し浅田に届ける。
浅田の居る警察署の近くの洋食屋で昼食を取った際、店主からブーケガルニを預かって鑑識に。《タウンチャイルド》でフミヤが作るデミグラスソースの香りに似ていたからだ。フミヤはここで働いていたのではないかと考えた。そのことを洋食屋の店主はそっと教えようとしているのではないか。
その後、一之介はまるみがバイトしているコンビニに調査に行ったが、そこで冷蔵車に襲われる。後日、その冷蔵車は河原で捨てられているのが見つかり、フミヤが持ち主だと判明。VRなど、マジックのような仕掛けがたくさん施されていた。
その後の調査で、まるみが行方不明になっていた間、その冷蔵車の中に居たことが判明する。騙されて入っていたのではなく、VRの中に弟である翔太の映像が入っていたことで驚き、さらに、その仕掛けが面白かったのでだまされたふりをしたのだと言う。
ちなみに一之介が採取した「遠野美咲」の指紋と、翔太の友人であり、さやかに扮した遠野美咲の指紋は一致しなかった。別人。
まるみが子供の頃に物置に隠れていた時の謎も解き明かされる。
ずいぶん謎が解けたが、小柄の「遠野美咲」は誰なのか、その指紋がまるみのランドセルに付着していたのはなぜなのか、翔太が見たオーブ状の紫の光はなんだったのか、交番のトイレで姿をけした「さやか」の事件でも見られたその光はなんだったのか、など、細かな謎は残る。
小説はまだまだ続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
