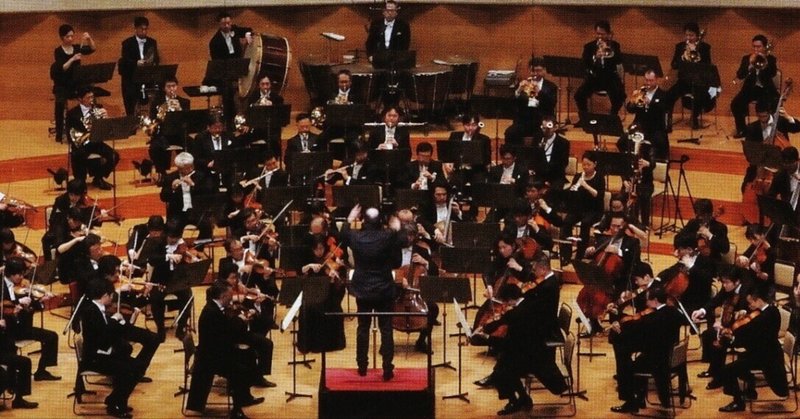
人気イマイチ指揮者の技と神髄 序文 『人気イマイチ指揮者が出来上がるまで Part.1』
1. なぜここで、スターではなく人気イマイチ指揮者なのか?
別に、ひねくれた事をやって注目されたいわけではないのだが。
クラシック音楽ビギナーの方々も視野に入れているのに、いきなり人気イマイチ指揮者を取り上げるという荒技に出たのは、もちろん、彼らへの愛ゆえである。
これからクラシック音楽を聴いてみようという皆様には、世評に惑わされず、ご自分の感性に合った演奏に出会って欲しい。
それこそ「名盤100選」なんて本を開いてしまうともう、没後も依然として人気スター指揮者であるカラヤンやバーンスタインをという事になってしまい、私には「そりゃ違うぞ」という思いがあるわけである。
それに、クラシックにお詳しい方々にとっても、評伝や研究書が出ていないアーティストを取り上げた方が楽しめるだろう。
カラヤンやバーンスタインの本なんていくらでもあるが、人気イマイチ指揮者の資料は何者かの悪意を感じるほど乏しく、それがまた彼らの人気上昇を阻むという負のスパイラルが生まれている。
アマチュア・ライターの微力ながら、誰もやらぬならこの私が阻止せねばならない。
2. 指揮者もやっぱり人気商売
クラシック音楽に詳しくない方は、完全実力主義のキビシイ世界というイメージをお持ちかもしれないが、実はオーケストラの指揮者も相当に人気商売である。
もちろん、基礎的な実力すら無い人は論外で、実力主義のキビシさは根底にがっちりある。
指揮というのが、自分は一切音を出さず、身振りとオーラで指示を伝える謎の間接的技術である以上、無能な指揮者がオーケストラ(以下「オケ」と略す)に良い演奏をさせる事など、できはしない。
しかし世界は広い。
目覚ましい才能に恵まれ、実力もたんと備えた指揮者はたくさん存在するのだ。
そして、一流オケの管理ポストに就いたり、メジャー・レーベルとレコーディングの契約ができる指揮者の枠には、残念ながら限りがある。
当然どのオケも客席を満員にしたいし、どのレコード会社も商品をたくさん売りたい。
ゆえに指揮者も結局、人気商売なのである。
これが、才能面で寸分違わず全く同じレヴェルの2人を較べた時に、よりスター性や華のある方が選ばれるという話なら、まあ諦めもつく。
しかし現実には、「さては実力よりもスター性が重視されたな」という人選も少なくないのである。
特にレコード会社などは、その辺りの思惑がかなり露骨に見え隠れする。
3. スター指揮者は多忙すぎてクオリティを落とす
指揮者たるもの、どこぞのオケの音楽監督を引き受けた途端、その街の社交界に毎晩顔を出し、企業や大富豪に顔を売ってスポンサーや資金を集め、レコード会社から録音の契約も取ってこなくてはならない。
その上、他の一流オケから客演の依頼があれば、それもできるだけ引き受けたい。
なので、スター指揮者であればこそ、自身の芸術的クオリティを落としてゆきかねない。
勉強して自分を高める時間が取れないからだ。
かつてボストン交響楽団の音楽監督を務めた小澤征爾は、ひたすら社交パーティーを避けて真面目に勉強を続けたが、地元ではよくそれを非難されていた。
熱意のある学究肌の指揮者ほど、「営業やビジネスに積極性がない」と叩かれるなんて本末転倒のおかしな話なのだが、売れっ子指揮者にまるでやる気の感じられないやっつけ演奏が時々あるのは、恐らく音楽以外の仕事で忙しすぎるという事情もある。
ゼロ年代を代表するスター指揮者の一人だったマリス・ヤンソンスは、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、バイエルン放送交響楽団という世界的トップ・オケからの音楽監督同時オファーをうれしすぎて断り切れず、両方を掛け持ちするという暴挙に出た。
音楽監督自身が定期演奏会を年間何公演指揮するとか、色々な条件さえ折り合えば、こういう一夫多妻制も許されるのだ。
バイエルンでの就任会見で興奮して舞い上がり、「このオーケストラとなら何でもできる!」と雄叫びを上げたヤンソンスだが、彼がこれらのオケと残した録音の数々に「これは凄い」と思える名演があまり無いのは、多くの音楽ファンが共有する印象だと思う。
なにしろ彼は、これらのオケと世界ツアーも回るし、ウィーン・フィルやベルリン・フィルなど一流オケからの客演依頼も当然引き受ける。
もともと病弱だった彼は、こんな激務を自分に課したため、療養による活動休止の末、ついに任期半ばで亡くなってしまった。
4. 人気ゼロではなくても、世界は広い
人気イマイチ指揮者なんて失礼な括りをしているが、彼らの人気は全く無いわけではない。
彼らは皆、どこかのオケや歌劇場のポストに就いた経験もあれば、数は少ないながらメジャー・レーベルに録音も行っている。
しかし繰り返すが、世界は広い。
上には上がいるのである。

5. 売れっ子指揮者たちの活躍状況をおさらいしよう
ご本人や関係者の方々には大変失礼ではあるが、この企画でご紹介するのは、華やかなスターにはなれなかった指揮者たちである。
ではどういう人たちがスターであったのか。ビギナーの皆様には固有名詞の羅列に見えてしまうかもしれないが、読み飛ばしてもらって構わないので、ざっとおさらいしておこう。
私がほとんど聴かないモノラル録音期はすっとばし、ここではステレオ時代以降の状況に限る。
ステレオ録音の技術が一般化したのが50年代後半(映画にカラー撮影が導入されたのとほぼ同時期である)、私がクラシックを聴き始めたのが80年代初頭。
その頃、まだ現役でトップクラスの人気があったスター指揮者がヘルベルト・フォン・カラヤンとレナード・バーンスタインで、二人とももう晩年に差し掛かる辺りだった。
片やクラシック音楽の本場ドイツ、片や文化の伝統がない新大陸アメリカの指揮者という対立構造は分かりやすく、リスナーが自分の好みを投影しやすい状況を、業界もうまく提供したわけである。
本人たちもまたお互いをライバル視し、ロックスターのように見栄えよく振る舞った。
一方、カラヤンもバーンスタインも嫌いという私のようなひねくれ者や、聴き比べのために個性の違うセカンド・チョイスも欲しいリスナーの受け皿として、ゲオルグ・ショルティ、ロリン・マゼール、ピエール・ブーレーズ、コリン・デイヴィス、カルロ・マリア・ジュリーニといった毛色の異なる指揮者達の録音も、各レーベルは抜かり無く、ふんだんに用意した(そして売れた)。
さらに、若いリスナー向けに次世代の指揮者たちもどしどし起用され、クラウディオ・アバド、ズービン・メータ、小澤征爾、リッカルド・ムーティ、ダニエル・バレンボイム、ジェイムズ・レヴァイン、ベルナルト・ハイティンク、アンドレ・プレヴィンらも、それぞれに人気アーティストと呼べる活躍をした。
80年代以降は、細分化された趣味性の強い指揮者もどんどん参戦し、シャルル・デュトワ、サイモン・ラトル、マイケル・ティルソン・トーマス、リッカルド・シャイー、ジュゼッペ・シノーポリ、チョン・ミュンフン、マリス・ヤンソンス、ヴァレリー・ゲルギエフ、パーヴォ・ヤルヴィといった人たちも売れっ子になった。
もちろんこれは、一般的にざっくりと認識されている大まかな状況であり、「おい、あの指揮者が入ってないじゃないか」的なクレームはこの際なしである。
(序文 『人気イマイチ指揮者が出来上がるまで Part.2』へ続く)リンクは下記へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
