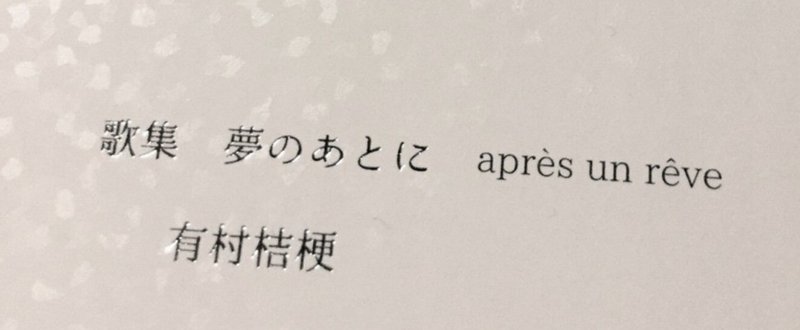
歌集『夢のあとに après un rêve 』有村桔梗さん
ついに歌集を手に入れた
短歌をお休みしてからしばらく経つ。書くことは好きだから相変わらず短編小説やことば遊びなどは続けているけれど、短歌という形でことばを紡ぐことからは遠ざかっていた。だけどやっぱり短歌は好きで、機会があるごとに少しずつ読んでいる。
実は4月末から5月上旬まで一時帰国をしていた。帰国理由はまあ置いておくとして、わたしは事前にスケジュールを調整し、楽しみにしていた5月6日開催の第二十六回文学フリマ東京に立ち寄った。Twitter上で告知されていたいくつかの作品を手に入れるためだ。そこでようやく有村桔梗さんの私家版歌集『夢のあとに après un rêve 』を手に入れることができた。同郷ということもあり、桔梗さんの初歌集ということもあって、手にするのを楽しみにしていたのだ。
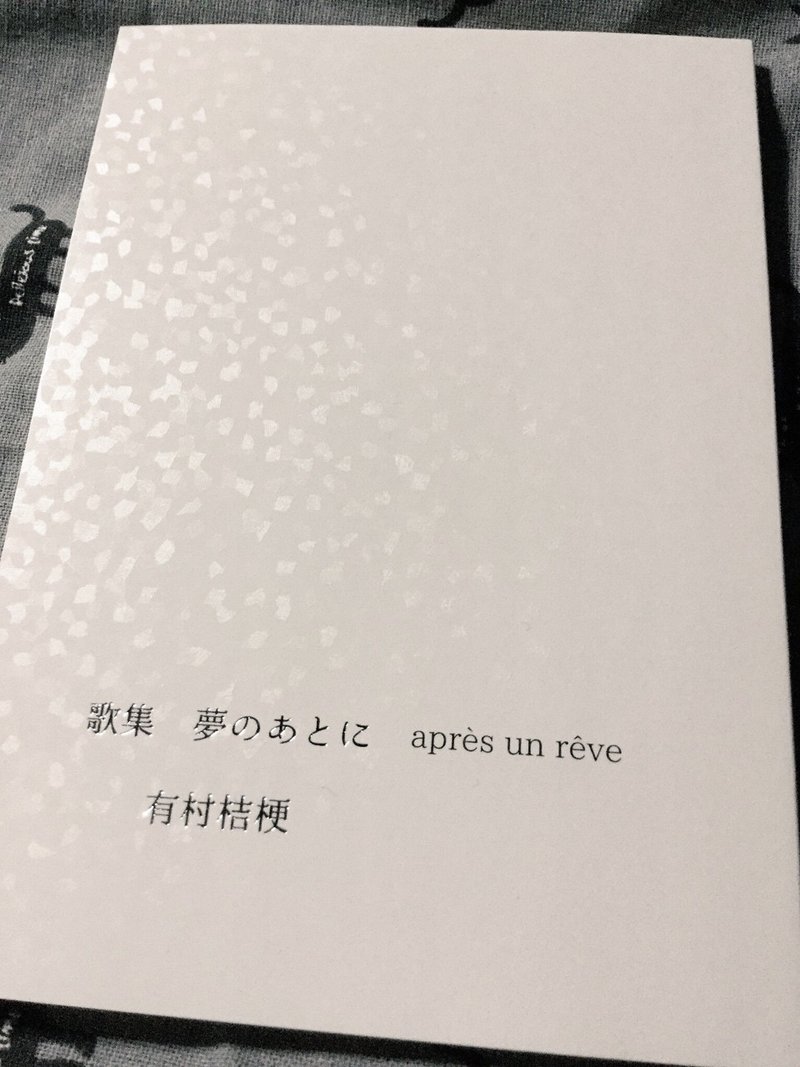
なにしろ桔梗さんが常連として参加されている「空き瓶歌会」さん(新潟市で定期的に開催される歌会)のブースでしか手に入らないことは知っていたので、当日は何が何でもと早足で駆け込んだ。そしてご本人を見つけると、わたしは緊張のせいか早口で「ください!」とまるで子供の使いのように話しかけてしまったように思う。桔梗さんとは面識もあったしお話しもしたことはあったが、わたしの素っ頓狂な様子に、桔梗さんはややびっくりした面持ちで、ご自分の初歌集を手渡してくれた。
帰国したのちに読み始めたし、荷ほどきや留守中のあれこれを片付けてから読み始めたので(しかも読み出すとあれこれ長い)感想を上げるのに少し時間がかかってしまったけれど、これから桔梗さんの歌集の感想を述べていこうと思う。
有村桔梗さんという歌人
わたしのような海外在住者は、普段は短歌投稿サイト「うたの日」や短歌×写真のフリーペーパー「うたらば」などを通してしか桔梗さんの短歌を知る機会はないのだけれど(Twitterのタイムライン上に歌が流れてくる)、わたしにとってまず桔梗さんといえば「題詠の女王」。定期的に「お題」のある短歌投稿媒体に歌を投稿されていて、どんな「お題」でも桔梗さんだとわかる作風の歌を詠んでいるイメージがある。わたしなりに例えるとすると、桔梗さんは「横溝正史の湿度と闇を、宮部みゆきの観察眼とユーモア、そして人情で割った作風を持つ雪国の魔術師」。旧かなで作歌するのも特徴だ。生と死、あの世とこの世、リアルと夢想、堅実さとユーモア。桔梗さんは、作歌においては明らかにふたつの世界を行ったり来たりしているように思う。その具体的な作風についてはこれから触れることにする。
匂い立つイメージ
桔梗さんは「ことば」の魔術師だ。もとになる素材がひとつでもあれば、呪文をかけて別次元の命を与える。
百色の色えんぴつを揃へてもわたしの雨を塗る色がない 「或る日」
ぎんいろをえらんでぬつたはずなのにぼくらのみらいがはいいろになる 「御御御御御」
うつくしい鱗のやうな付け爪が冬の海辺にひとひらひかる 「はるなつあきふゆ」
たましひの宿り木だらう木蓮はあんなにしろくしづかに燃えて 「はるなつあきふゆ」
夏空に立ち尽くしたるひまはりを戻らぬひとの墓標と思ふ 「はるなつあきふゆ」
「色えんぴつ/雨」「ぎんいろ/はいいろ」「鱗/付け爪」「ひまはり/墓標」「たましひ/木蓮」。さあ、どうだろう。特に「ひまはり/墓標」の歌がすばらしい。この歌の中のひまわりは、都会で見かける花屋のブーケにおさまっているような、夏の生命の象徴ではなく、田舎の地植えの、ひょろっといっぽん背が高く、暑い日差しの中でずっと立ちっぱなしでいるそれではないか。もう盛りを終えたひまわりが顔を下に向けたまま弱々しい姿で立っている様は、なるほど墓標のように見える。ちなみにわたしも桔梗さんと同郷だ。この歌を読むと(勝手に)悲しいほど青い夏の空を思い出してしまうのだ。世間一般では夏の生命の象徴であるひまわりを、墓標として見立てられるのは、その盛りを過ぎた姿を知っているからではないか。夏の盛りの青い空はゆっくりと始まる衰退の匂いを孕んでいて、そこに桔梗さんの描写するひまわりがぴったりとはまる。
静けさと詩的表現
次に桔梗さんの歌に特徴的なのは、歌から漂う静けさだ。漢字とひらがなの使い方のバランス、韻律の妙だろうか。描写するシーンのイメージも現実とファンタジーが交差する。
立ち尽くすわたしにルビをふるやうにただ六月の雨は降りをり 「みを」
永遠とふ文字はつめたくしんねうの延びゆく先にゐないこひびと 「夏のねぢ」
未来とはいまだ来ぬもの わたくしがいまゐる場所に栞をはさむ 「本のある風景」
いまはもうタンスの奥にゆつくりと眠らせておくくさりかたびら 「はるなつあきふゆ」
問ふことが答へと思ふ だいこんのまるがいくつも煮えてゆく夜 「はるなつあきふゆ」
例えば「六月の雨」の歌。六月なのだから梅雨時期で雨が降っているシーンを切り取っているのだろう。主体はどこか屋根の下で雨宿りでもしているのだろうか。その雨は「ルビをふるやうに」主体の体の脇を落ちてゆく。その雨の動きをこのような詩的表現を使い歌を詠む観察眼。桔梗さんの歌を読んだ先から音(例えば雨音や大根の煮える音)が消え、時(「永遠」や「未来」、「夜」)が消え、ただ静寂な一瞬だけが57577の中に閉じ込められてしまう。恐ろしい魔術だとさえ思う。
「くさりかたびら」の歌も面白い。衣替えでタンスにしまう羽織りものだろうか。それを「くさりかたびら」と呼んでしまう。その瞬間に、季節を終えた衣類のアイテムが、自分を守ってくれていたであろう「防具」として真の姿に返ってゆく。役目はもう終わったから起こさず「眠らせて」おいてあげるというのだ。なんという表現。なんという物語。ファンタジーの世界では、この世のものは本当の名を呼ばれる時、元の姿に戻るという。桔梗さんは異世界物語にも影響されているのだろうか。いつか尋ねてみたいものだ。
ひっそりとした怖さ
怖い。桔梗さんの歌はひっそりとした怖さを滲ませている。それは禍々しかったり、じわじわきたり、あっさりバサッと切り落とされたりする何かなのだけれど、大抵はうつくしさと共にある。
親指と人差し指でひらかれて点眼と云ふしづかなテロル 「しづかなテロル」
御御御御御祝祝祝と筆ペンの試されてゐる反古紙やさし 「御御御御御」
あかねさすあぢさゐの花ひと房をきみは脳(なづき)を抱くやうにして 「夏のねぢ」
約束は守らないけど忘れない小指の爪をぱちんと落とす 「ぱちん」
そのあとは思ひ出せないことばかりどこまでも曼珠沙華曼珠沙華 「花五首」
まず「点眼」の歌のホラー。目薬をさす歌でしかないのに、指でカッと見開かれた目のアップが脳内に再生される。さては拷問シーンか。「しづかなテロル」という表現の勝利だ。ホラー映画「サイコ」的な効果音も欲しいところだ。
そして「筆ペン」の歌の禍々しさといったら恐怖でしかない。「御御御御御祝祝祝」と続き、最後に「反古紙」と「やさし」を加える怖ろしさ。筆ペンの命が危ない。きっとキャップを剥ぎ取られて逆さまの状態で湖に沈められるに違いない。ここに横溝正史のイメージが重なるのだ。
ユーモア
桔梗さんの歌には、どこかくすっと笑える要素も多く、それも楽しみのひとつだ。真面目な顔をしてつい面白いことを呟く俳優や芸人さんのような歌も多い。
それはもう恋かもしれず 刻んでもかならず気づいてしまふしひたけ 「いただきました」
ゆふぐれに少年が吹くたてぶえのダースベイダーほのぼのとゆく 「或る日」
音楽性の違ひだらうか雛壇に五人囃子のひとりがゐない 「はるなつあきふゆ」
どうしてもどこに行つたか言はないが木彫りの熊がまた増えてゐる 「はるなつあきふゆ」
素麺でいいなどといふ 素麺がいいといふまで茹でぬ素麺 「はるなつあきふゆ」
「しひたけ」の歌は、運命の恋にも似たしいたけへの想いだ。ひょっとしたら桔梗さんはしいたけが苦手なのかもしれない。なるべくその姿を見ないようにしている。刻んでしまえ。みじん切りにすれば知らずにいられる。だけどなぜか目の前に現れるしいたけ。もしかしてこれって恋?運命の恋なの?そう思うと、くすっと笑ってしまう。
そして最高にくすっと笑えるのは、「木彫りの熊」の歌だ。家人がどこかへ旅行したらしい。だけどどこに行ったかは言わない。問いただしても言わない。しかしなぜか部屋に増えているものがある。例のあれだ。「木彫りの熊」といえば北海道じゃないか。さてはまた行ったな。証拠はここに!というストーリーを桔梗さんは57577の1首に収めてしまう。この真面目さの中に仕込まれたユーモアのひと粒が好きだ。
雪国
桔梗さんとわたしは同郷のよしみという話をした。雪国の住人だからこそ分かり合える歌がある。この歌集の中には雪と白鳥の歌が多く収められているが、それらの歌を十分に味わうには新潟の海と山々、そして越後平野の広さを身をもって理解しなくてはならない。その上での雪であり白鳥だ。越冬のために飛来する白鳥の鳴く声、そしてまた去ってゆく頃の灰色の空。近頃ではあまり積もらなくなった雪(いや今年はすごかった)だけれど、この雪の意味するところは、「変わらぬ季節の廻り」。そしてとどのつまり、雪国は寒い。「忍耐」あるのみだ。
とほくより雪の匂ひを連れてくる白鳥たちよおやすみなさい 「白鳥よ」
飛んでゆく声が聞こえる 白鳥はあれがさいごの一羽と思ふ 「白鳥よ」
生きてゐることは待つこと この町の最初の雪におかへりをいふ 「はるなつあきふゆ」
雪の上に残る轍を進みゆくわたくしもまただれかの轍 「はるなつあきふゆ」
雪に似たものをつかんだやうな気がしててのひらを開かずにゐる 「はるなつあきふゆ」
「さいごの一羽」の歌は、その経験のあるなしで味わい深さが違うのではないかと思う。群れを成して飛ぶ白鳥のこうこうという鳴き声に冬の賑やかさはあるのだけれど、 たった一羽の白鳥の鳴き声は、冬の寒空の寂しさをどこまでも拡張してゆく。ちなみに新潟の(平野部の)空はとんでもなく広い。
「轍」の歌は、はっとさせられる歌だ。「轍」は誰かの残してくれた道を比喩することばだけれど、それだけではなくて、それをなぞり進む自分自身もまた轍を轍として残す者だというのだ。「轍」とはレガシーであると表現している。先人が作った轍の行く道とはどんな道であっただろう。そして自分が残してゆく轍とはどんなものになるのだろう。その是非はここではわからない。そこがいい。
連作「平日」から5首
桔梗さんの歌は1首だけでも当然インパクトがあるけれど、連作も素晴らしい。平日をテーマに詠んだ10首の中から気になった5首を引いてみたが、どれもいい。確かに何気ない日常を描いているのだけれど、そこにドラマあり、気づきあり、ユーモアありでどれひとつとしてつまらないものはない。
いつまでもいきてはゐないひととゐてテトリスめいた雪をみてゐる
みなおなじ方角を向き生まれくる鯛焼きたちのうつくしき午後
平日はたぶんわたしがローラーで平らにされてゐる日の略だ
本当はきみに言ひたい事柄を餃子に聞かせてゐる夜である
選ぶとは選ばないこと 手に取つたひとつ以外のアボカドひかる
現実味が感じられない死の予感を、「テトリス」のような大粒の牡丹雪に見出す。「鯛焼き」の形の整ったうつくしさを明るい午後に重ねる。「ローラー」でぺちゃんこにされるような日々。「餃子」にだけは言える本音。アボカドが教えてくれる「選ばない」という選択。なんという気づきに溢れた毎日だろう。
桔梗さんの歌集はどこで手に入るのか
さて、ここまで桔梗さんの歌を紹介してきたけれど、わたしはラッキーにも文学フリマ東京で手に入れることができたクチだ。わたしの感想を読んで「読みたくなった!欲しい!」というひとが出てきたらどうしたらいいのだろう…困ったぞ。ちょっとご本人に訊いてみます…とここまで書いて、情報をいただきました。大阪の葉ね文庫さんで入手できるそうです(わたしも一度お邪魔したことがあります)。機会がありましたら、ぜひご一読ください。
葉ね文庫さん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
