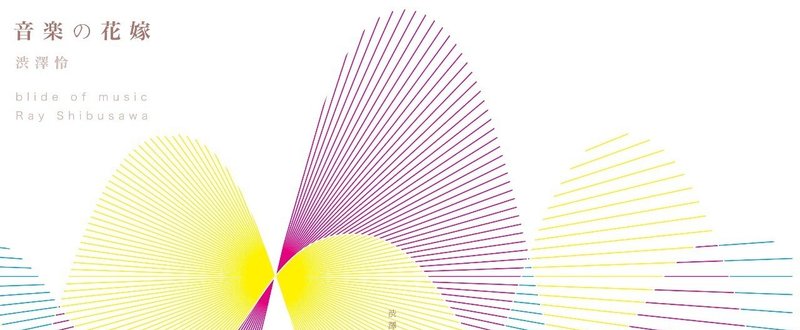
【長編小説】音楽の花嫁 17/19
初回はこちら
その時の彼の表情の変化――一瞬の出来事だったそれを私は一生忘れないだろう。まるで卵を奪われた雌鶏のように怒りで顔が膨らみ、私に掴みかかるほどの血の気で沸き立ったと思ったら直後、悲しみと安堵と諦めとがいっしょくたになって一気に顔の上を通り過ぎるように青ざめ、しぼんでいった。そして彼の顔はまるで支柱を失ったテントのように皮膚がずるずると垂れ落ち、皺が刻まれ、あっという間に私の知っているおじいさんの顔になった。と思ったらそれを更に通り越し、老衰の果てに死に目を迎えた、血の色の抜けた白い骸となった。私は取り返しのつかないことをしてしまったのだと悟った。ああ、おじいさんは、死んでしまったのだ。私が、おじいさんを、殺したのだ。アヤメ。おじいさんが最後に発した呪われたその名前は、おじいさんが私がとても小さい頃にだけ使っていた私の呼び名だった。それを今更ながら思い出した。本当はおじいさんは私にそう名付けたかった、でも母が「人を殺める」につながるからと反対した。それでもそう呼び続けたおじいさんは、孫を可愛がる資格など無い、と人殺しの自分を罰するつもりだったのか。それとももしかして、私にこうされることを知っていたのだろうか。
「ひどいよ」
胸に鉛の弾を撃ち込まれたようなショックが走った。私も死んでしまうのではないかと思った。目の奥を針で刺されたような痛みと共に涙が噴き出した。
しかし再び突風が吹きすさび、私達を軽々と舞い上げていった。天地がひっくり返ったように、私達は今まで落ちてきたのとは逆側へと落ちて行く、するとおじいさんの骸は時間に逆行するかのようにみるみるうちに肌のハリとみずみずしさを取り戻し、あっという間に少年の姿になった。そして、私の手の中のフルートを見つけると飛び上がらんばかりに喜び、それを取り上げると楽しそうに吹き始めた。
風は凪ぎ、全ての楽器の破片がその音色に聞き入るように舞いを止めた。
世の中の全ての孤独を吸い取るようなフルートの音だった。知っている、私は、この曲を。「亡き王女の為のパヴァーヌ」。銀色の空洞の中を吹きすさぶ息の音色は細く、か弱く、不安定で、でもそれが、どこに主音があるのか分からないこのメロディにぴったりそぐうのだった。周りの楽器の破片たちはそのメロディに寄り沿うように、和音を、ピチカートを鳴らし始めた。浸水した船底のように悲しみが腹の底から染み込んでどんどんよじのぼり、私の頬を涙で濡らした。だって、これで、おじいさんは。
「お前の幼さが救いだったんだよ、ありがとう」
姿は少年、声はおじいさんのジョージが私へ向けて手を差し伸べた。私は壊れるほど強くその手を握り返した。幼い、なんて言われてしまうとアヤメと呼ばれていた小さい頃の気持ちになってしまう。泣いていいんだよと言われた気がして、わんわんと声を上げて泣いてしまった。
「おじいちゃん……あんまりお見舞い行かなくて、ごめんね……てか、中学からあんまり遊びに行かなくなって……でもそれ、部活が楽しくって……おじいちゃんが、オーボエ、買ってくれたから……ありがとね、お母さん、買ってくれなかったもん」
「お母さん……そう……そうさな……」
ジョージは何か思いを巡らすように遠くを見つめた。そして吹き終わったフルートを私に手渡した。
「これは、もう、要らん。お母さんに渡してくれ」
「え……」
ジョージはおもむろに頷いた。
「もういい、さっさと行け。俺はここで死ぬ。お前は、外に出ろ、アヤメ」
おじいさんは、私が握り締めていた破片を私の手ごと胸にぐっと押し当てた。するとそれはみぞおちにめり込むほどに重くなり、私の身体を巻き込んで、正しい重力の方向を今しがた思い出したように地球の中心目がけて突き進んでいった。
何かを破ったと思ったら、ただ眩しいだけだった視界に一気に色が飛び込んできた。地面だ。ということはさっきまでの眩しくて真っ白な世界は雲の中だったのかもしれない。全身の皮膚が風に叩かれ灼けるように痛く、ものすごい速度で落ちていることが分かる。このまま地面に落ちたら間違い無く死ぬ。そう思うと熱い身体の中の心臓だけが凍りつくようにぞっとした。
その瞬間私の視界を黒が覆い尽くしたと思ったらふわふわした毛の中に抱きとめられていた。懐かしいぬくもりと、匂いで分かった。
「コンコルド! 来てくれたのね!」
「お嬢さんが私の羽根をずっと持っていてくれましたからね。外に出てきたらすぐに迎えに上がるつもりでいました」
「ネムル、ネムルは?!」
私が叫ぶと
「呼ばれて、飛び出て、じゃじゃじゃじゃーん! ここにいるよーん」
少し離れた羽の中からネムルが顔を出した。
「ネムル!」
私達は羽毛の中を掻き分け、同時に腕を伸ばしてがっしりと抱き合った。頭の上で鐘が鳴り響くような幸福が私の頭からつま先までを包み込んだ。ネムルの中へ自分を埋め込む程に強く強く抱きしめて、ネムルも同じだけ力を返した。このまま互いに互いを埋め込み合って一枚の板になってしまいそうだ、なってしまわないだろうか。いや、ならない。静かに身体を離してネムルと見つめ合った。私は既に分身とそうなっているし、そしてネムルには片割れのごとく大事なギターがあった。でも、孤独を同じ量だけ持っていれば、こうやっていつでも、互いのことを確かめ合うことが出来る。それが一番じゃないか。
「うふふー、僕、オナベちゃんだったのよー」
ネムルは猫が顔を洗うような仕草をしながら言った。珍しく気まずいようで、はにかんでいた。そう言われてネムルの顔を見ると、確かに女の子でこういう顔の子はいるかもしれないと思えてきた。
「別にいいよ。その代わり、それでも、私をお嫁さんにしておいてくれる?」
「勿論さ。子作りには励めないけどねー」
ネムルは六本目の指を私の前で振って見せた。
「ううん、私達の子供は音楽」
私はあのフルート吹きの少年が奏でた「亡き王女の為のパヴァーヌ」のメロディを再び歌い始めた。
どこへ向かうか迷うような不安定なメロディに合わせてネムルが和音をつけていった。コンコルドの背からこの世界へ送るプレゼントだ。死にゆく女王へのレクイエムだ。
高いところを舞うコンコルドからは、一度死に絶え、そして生まれ変わるこの世界の全てが見渡せた。マルタやバイタや朽ちた分身だった楽器の破片は次々と地面へ降りていき、地面に養分を与えるように溶けていく。するとあっという間にそこで草が芽吹き花が咲き木が根付いていくのだった。かつて戦場だった荒野に、まるで白い画用紙の上に子供が喜んで絵具を飛び散らかすように鮮やかな色が咲き乱れていく。
私達が奏でる音楽に合わせて、ドーン、ドーンと、遠くから大砲のような音がする。その音が鳴るごとに、草や花や木がぐんぐんと背を伸ばしていく。はっとして胸を押さえると、私の鼓動とその大砲の音は完全に同期していた。これは、私の世界。私の外でもあり中でもある世界だ。
私はネムルの心臓に手をあてて言った。
「ネムル、女王は死んで、あなたは生きてるよ。聴衆も、花も木もみんな……、生きてる」
「葬送曲と生誕祭一緒にやるようなもんだねー、あ、それと結婚行進曲! あーめでたい、めでたい。クラシックって初めて弾いたけど、悪くないねー心臓に良いわ」
そう言うとネムルは私の手ごと心臓をぱしんぱしんと叩いて、そのまま私の手をつかんで自分の口元へ持っていってキスをした。初めて会った日にもそうされたけれど、ネムルが男の子じゃないと分かっているからか、今の方が恥ずかしかった。
「ありがとう、ヒツジ。僕はもう大丈夫」
ネムルの唇と吐息が私の手の甲をくすぐった。手の中にそっと閉じ込めるようにそう言われた。その言葉は温かかったけれど、ネムルとの別れの時が近付いていることを私に知らせた。それでも、その言葉を握り締めて進んでいくしかないのだ。
世界中の織物を集めたような美しい色で埋め尽くされた地面に、コンコルドはゆっくりと着地した。
すると私達を待ち構えていたようにするすると歩み寄って来る一つの人影があった。
「お誕生日おめでとう」
私と目が合うとその人はそう言った。なんだかどこかで聞いたことのある声だなと思った。どこかで、とてもよく聞いたことがある気がした。
「お誕生日ー? 人違いじゃないの?」
相変わらずネムルは人見知りもせずぬけぬけとそう言った。
「だって、今日君は女王の腹から生まれ出て来たんだよ。産みの親を殺してね。罪深い人だ」
その男の人が後ろを見やるとそこには、まるで気球船を破裂させたような、それはもう広大な、池のように大きなだぶだぶに折り重なる皮膚の袋が打ち捨てられていた。それを見た私は、しかし、古新聞の山を見るように何の感慨も湧かなかった。新聞が古くなるように、それはなんだか仕方の無いことにしか思えなく、ただ量にのみ圧倒されて「勿体無いなあ」とくだらないことを考えた。
「アヤメと言うんだって、君」
「はい」
「ヒツジ、もうヒツジやめるのー? ま、いっか。もう彷徨える羊ちゃんでも無くなったってわけね、あ」
ネムルが男の人を指さし
「もしかして、僕にギターくれた人ー? お久しぶり、元気してるー?」
「そう、その通り、よく覚えていてくれましたね、ネムル大佐」
もしかしてこの人が、かつてバイタだったネムルが出会った紳士なのだろうか。でも今は紳士というより青年といっていい年齢だったし、身なりもずっとラフだった。
「だってその右手の甲の傷。そんなところに傷ある人いないから覚えてたんだよ」
「ああ。確かに、私は姿は変わりますが、この傷はいつも携えているのです」
彼はその傷をさすると穏やかに笑った。彼はこの世界の番人みたいな存在なのだろうか。
「アヤメ、あなたは実の祖父を殺め、女王を殺めた。あなたにも、傷を」
そう言うと男の人はおもむろに拳銃を取り出して私の胸へ狙いを定めた。
「ヒツジ、じゃなくてアヤメ、これでお別れだよ」
ネムルが駆け寄る。私達は再びきつく抱擁を交わした。目も鼻も、耳も、ネムルに触れる全ての細胞が、ネムルの記憶を刻みつけようと必死だった。
「片割れ」
宝物のようにそっとその言葉を呟いた。
「一生忘れないよ、ネムル」
「大丈夫。本当に大事なことは忘れないんだよ。身体に染みついて、忘れようにも忘れられない」
ネムルは言って、私を送り出すようにぽんぽんと肩を叩いた。ああ、その言葉こそが呪いのように私の心に入り込んで、全てのネムルの記憶を私の身体からはがれないものにしていくようだった。
ネムルから離れた私は決意を固めて、その男の人の前に立ち、言った。
「私も、傷が欲しいんです」
「上等だ」
男の人はネムルと私とに、刃物で切るような鋭い視線を送った。それは私達の眼の中に不純物が無いか見通すような、厳しい目だった。
「あ」
その視線に射抜かれて、私は前にもこの視線を受けたことがあることに気付いた。それから胸の中の氷が解けるように温かい記憶が流れ込んできた。この人は。
「戦争花嫁!」
「そう。よく思い出したね。それが君の傷の名前」
鼓膜に鉄球が叩き込まれたような爆音と共に胸に熱さが走った。流れ出す血潮で、撃たれたことを知る。
薄れゆく意識の中でネムルが私に駆け寄る姿がぼんやり見えた。
「ネムル……紺野」
私はそう言ったのを最後に、視神経を引っこ抜かれたかのようにまっ黒な世界に落とし込まれる。
スキを押すと、短歌を1首詠みます。 サポートされると4首詠みます。
