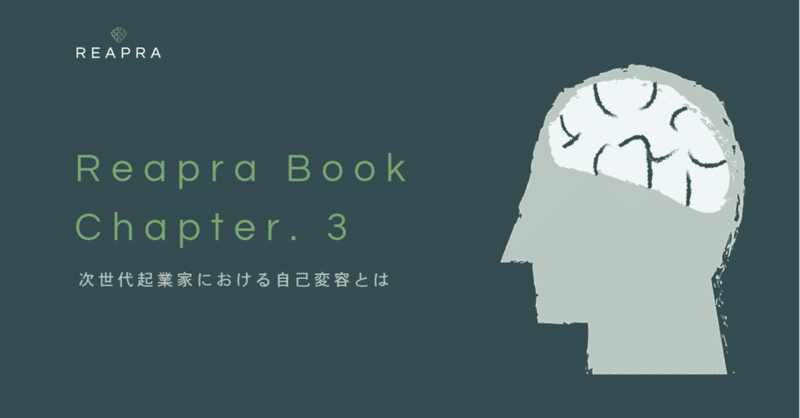
【Reapra Book連載シリーズ】第3章:次世代起業家における自己変容とは
昨年、Reapraで研究と実践の過程や得られた知識をまとめるためのプロジェクトが始まりました。それが"Reapra Book"。
Reapra Book連載シリーズも第3回目となりました。過去の記事はこちらからご覧いただけます。
第3章においては、社会と共創する起業家にとって必要な「自己変容」について論じていきます。こちらから全文をご覧いただけます。
Reapra用語のおさらい
第3章に入る前に、Reapra Bookシリーズも3回目ということで、これまでの用語の復習をしたいと思います。
次世代起業家:数世代に渡る比較的長い時間軸において、未だ不透明な市場で、長きに渡り自ら試行錯誤の学習を続け、社会と広く共創する起業家
共創:当事者とは異なる価値観や能力を有している他者や他組織と、それぞれの目的を持ちながら、ある同じ目的に向かって共働していくこと
熟達(学習):Life Missionに向かって前進していくために、自我を変容させながら必要な価値観や能力を獲得していくこと
PBF :特に"社会と共創するマスタリー"を目指す起業家にとって望ましいとReapraが考える事業領域。複雑性故にまだ規模としては小さいが、次世代に跨ぐ大きな社会課題を有しており、株式会社アプローチが有効で唯一無二のマーケットリーダを目指し得ると信じられる領域。
それでは、第3章もお楽しみください!
はじめに
第3章においては、社会と共創する起業家にとって必要な「自己変容」について論じていきます。社会と共創しながら複雑な市場=PBFにおいて新産業を創出していくためには、起業家CEO自身がしなやかに「自己」を変えていくことが必要となります。敢えてこの場では端的に説明すると、Reapraでは、自己を変えることによって捉えられる複雑性が増し、自分の見える範囲 (Reapraではユニバースともいう) を拡大し続けることができると考えているからです。
足元では小さく複雑だが将来伸びゆく領域であるPBFにおいては、起業時点では将来その領域にどのようなニーズが発生するかが不透明で、どのようにニーズを満たす(組織および自己の)能力を獲得していくかも予想することが難しいことがあります。このような領域に対する理解を深めながら同時に事業を推進していくためには、その時々での自己にとって嫌だなと思うことを小さく実践することや、学びたくないと感じるようなことを学ぶことに、意図的に自分を持っていく必要があると考えています。
そうでないと、人は自分の見たいものしか見ず、その時々の自己にとって心地よいことだけを実践し、学びたいものを学んでいくため、ユニバースを拡大することにつながらないからです。だからこそ、自分のコンフォートゾーンを離れて自己にとっての不透明な学びを続けるためには、その阻害する要因ともなる「自己の囚われ」を詳細に理解し、その囚われの限界を乗り越え続ける必要があります。
第3章の特徴
本章はその大部分を学術知見に寄っています。これは、3章のメインライターである沢津橋が、Reapraに入社後、大学院時代に触れていた理論を引用して、Reapraでの研究実践において多いに参照し、一般化を進めてきたものでであるためです。成人発達理論の研究や実践を進める方々との対話や協働が進み、今日に至ります。本章においては以上のような経緯上、成人発達理論そのものの詳細な理論理解を重視し、ケーススタディーを用いつつも、理論的な説明に記述の多くが割かれていることをご理解いただいた上で、読み進めていただけたら幸いです。
PBFにおける産業創出のため、社会と共創する熟達のために自我の発達が必要な背景
Reapraにおいては「自我」を、以下のように定義しています。
自我:意識(今気づいている自分)の中心 1。人間の意味構築活動を規定する意識構造のこと。意味構築とは、自分の人生あるいは仕事に独自の意味を築き上げる方法。 (ロバート・キーガンやオットー・ラスキー 2 らの定義を参照)
自己:意識と無意識を合わせた心全体の中心。心の中心だけではなく、心全体そのものを指すこともある *1。
1 http://rinnsyou.com/archives/317 よりユング心理学の定義を活用
2 ロバート・キーガン、オットー・ラスキーについては本章にて後述しております。
この「自我」があってこそ、私達は日常生活/社会生活/職業生活を営むことができています。昨日の自分と今日の自分が同じ自分であると認識できたり、昨日の生活(仕事)と今日の生活(仕事)が続いていると認識できたりするような、生活に連続性/一貫性をもたせることも、自我の働きであると言えます。この自我に異常を来すと(統合失調症など)、社会生活/職業生活を送ることが難しくなりうるのです。生きる上での、自我の役割とは、一貫性のある、定常的な意味構築をすることです。
しかし、まさにこの一貫性や定常性が、社会と共創するマスタリーのためにはネガティブに作用する可能性があります。社会と共創するマスタリーのためには、社会を広く包括する学びが必要であることは、第1章で確認してきました。そのような学びをしていくためには、常に、自分自身の学ぶ範囲が狭くなっていないか、つまり自我の影響でブラインドスポットができて学習捨象していないかを自覚的に探求し続ける必要があります(継続的な自己探求)。
自我があるからこそ、その人固有の人生の意味付けが生まれ、人生を通じての学習テーマの設定(Life Mission)も可能なのですが、一方でその負の側面として学習捨象も私達人間には常に発生しているのです。社会と共創するマスタリーを歩む上で、範囲を広げ続けて学習するためには、自分の自我について理解し、現在の自分の自我では捉えられない/捨象してしまう領域にまで、継続的に学習を波及させていく自覚的な営みが必要とされています。
執筆者: 沢津橋紀洋(メインライター)、松田竹生(相談役)、日比朝子(インタビュアー、ライター)、村西純奈(インタビュアー、ライター)、田中直輝(インタビュアー、ライター)、永見琉輝(ライター)、吉良慶信(ライター)、尾島恵太(インタビュアー)、渡辺康彦(インタビュアー)、山田晃義(インタビュイー)、柳沢美竣(インタビュイー)
![]()
この後、本章では、産業創造のための社会と共創する起業家における、次世代産業マーケットと自己変容の関係性を説明します。次に、自己変容のプロセスを理解するために有用である、欧米で研究が進んでいる成人発達理論の概要について紹介します。その後、自我発達段階それぞれの特徴と、Reapraとして自我次元「ステージ5」を目指すその必要性を紹介し、最後に、変容のための実質的なメソッドと、実際のケーススタディーを記載しています。
Reapra Bookはこちらから全文ご覧いただけます。フィードバックフォームもありますので、ぜひご感想、ご意見をいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
