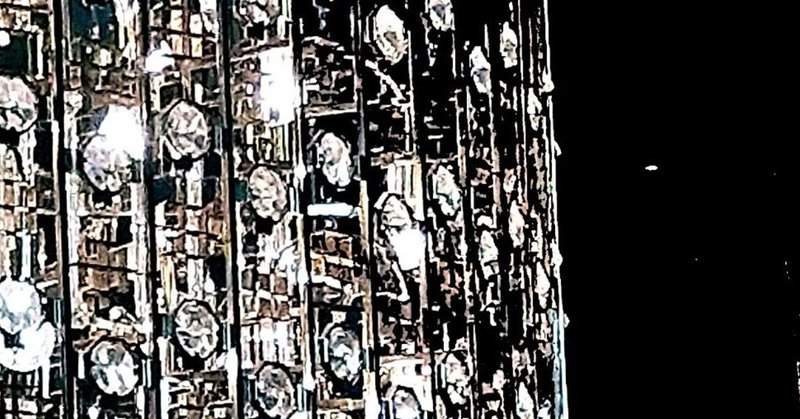
小説【船は故郷へ】1回目 (文字数11763 全4回)
船名:宇宙船ヴィーナス221
目的地:小惑星帯中継所ブランクーシ
貨物:食料及び医薬品(第三種)
出発日:10月25日 AM10:00
行程:二十日
乗員:クォート・ウィーゼル……二等機関士
ノエル・ロゼ……機関長
ギリス・ノートン……船長
ハイダ・ルジッチ……一等機関士
リュウ・オラフ……一等航海士
ロイド・グルーク……ニ等航海士
第一章 出発
曇天が相応しい、ひどい朝だった。
痛いのは判っているのに、何度も頭を振って己が二日酔いであることを確認してしまうのは何故だろう。
鏡を覗く。力無く眉をひそめた三十過ぎの男がうらめしそうな目でこちらを見ていた。残念ながら間違いなくわたしだ。ウンザリしているのはお互い様だと顎を撫でて髭を剃る。顎はさっぱりしても二等航海士はまだ当分最悪の体調を持続するつもりらしい。
やれやれ、当分地球とお別れだっていうんで、ちょっとばかりはしゃぎすぎたな。
心配なのはヨランダがいないことだ。
昨夜二人で飲み始めたときには、いいムードだったのに、こうして目が覚めれば一人きり。まあ、それ自体は珍しくも何ともない。
ちょっと顛末を思い出そうとして自分が酒場で声を張り上げてへたくそな歌を大声で歌っていた場面が浮かんだので、慌てて記憶を辿る作業を中止した。思い出すことで役に立つ過去もあれば、一生浮かび上がらせないことで役に立つ過去もある。
「……やばいな」
独り言を言ってみても予想通り時間は一秒も戻らなかった。曝してしまった醜態は取り返しがつかないものだし、彼女の心もきっと知り合う前より遠いところへ行ってしまったに違いない。
やれやれ。これから三週間、話す機会さえないというのに、いったい何をやっているんだか。
今回は小惑星軌道を回る宇宙ステーションへ薬と食料を届けるという仕事だった。同乗者は何度かチームを組んだことのある顔見知りばかり。まあ、楽と言えば楽な仕事だが、この話がわたしのところに来たのが五日前。ヴィーナス号のオリジナルチームは六人で、この仕事もその編成でスケジュールが組まれていた。ところが、乗組員の一人、ウィンディという男が事前調査でインフルエンザに罹っていることがわかって外さざるを得なくなった。そこで、何度か一緒に仕事をしたことのあるわたしのところへ依頼がきたというわけだ。まあ、正式に決まればスケジュールの調整は会社がやってくれるのだから問題はないが、それにしても三週間というのはちょっと長い。いきなりの話で準備の期間もろくにないし、こちらにもいろいろ都合というものがあるのだが、ギリス船長から直々に電話までもらったとあれば断れない。こういうところで信頼関係を強固なものにしておくのは大切なことだ。何日も同じ人間の顔を見て過ごす仕事なのだから。
かくして新聞を止め、知人の結婚式に出られなくなったと連絡をとり、予約なしの割り増し料金で健康診断を受け、酒場にツケを払い、親しくなりかけた女性を怒らせて、二日酔いになって、とまあ、忙しい時間を過ごす羽目になったのだ。
今回運ぶ貨物は医薬品、衣類、食料など、ごく当たり前のものばかりだ。なんの特別手当も出ないというのは少し寂しい。大量の化学薬品などを運ぶ危険な業務の場合はそれなりに見返りもあるのだ。薄給で日々をしのいでいる身としてはそういった臨時収入が馬鹿にできない。
子供の頃、宇宙飛行士という職業はまだ憧れの対象だった。星の海に惹かれて、いつかは自由に天(あま)駆けるアストロノウツになろうと漠然と考えていたものだ。それは無数にある贅沢な夢の一つだった。
時が過ぎ、ご多分に漏れず夢は一つずつ潰れていった。世の中を不景気が襲い、職業を選んでいる余裕はなくなり、とにかく食べるために就いたのが派遣の宇宙船乗組員という仕事だった。世間的にはあまり目立たない職種だが、実はここ数年で過酷な労働条件の代表格にまでのし上がっているという快進撃ぶりだ。
まあ、結果的に宇宙を行く船に乗るという、夢に近いものの一つに納まっていたわけだが、それに気が付いたのはずいぶん経ってからだった。
大人になったときにはもう宇宙飛行士などさほど珍しいものではなくなっていた。つまり、夢の対象の方がランクを下げてわたしに近づいてきたということか。
最近は下請けだけでなく、我々の主な雇い主である運送業界もかなり厳しい状況になっている。
一週間、船を操らなければならないというのに、二人しか乗員がいないことだってある。誰だってそれでは少ないと思うだろう。乗ってみればそれがまったく正しい感想だとわかる。本来宇宙船による運送業務には最低三人の搭乗が法律で義務づけられている。それだって四日以上になるとかなりキツイのだが、ここ数年の間に始まった同業者増加に伴う運送料の値下げ競争の影響で、まず最初に配給食料が不味くなり、航行中のアルコールが一杯目から自費扱いになり、といった具合で様々な経費が節約されるようになった。燃料の値上がりが最後の一押しとなり、ついに御法度の二人編成での業務までやるようになったのだ。もちろん公になってしまえば業務停止は間違いないのだが、これをやっていない業者はいないだろう。
人員削減のために馘首(かくしゅ)となった奴等に比べれば、まだ船に乗っていられるだけでもよしとしなければなるまい。
とりあえず今回の仕事は人数も多いし、比較的楽な仕事になるだろう。ヴィーナス号の人数が減らされていないのは、旧型で手間のかかる船だということと、積載量にかなり無理がきくという事情によるようだ。まあ、あの古株のギリス船長が最低限のラインだけは譲らずに頑張っているのかもしれない。
複数の会社で共同出資された貨物船専用宇宙港は広大な湿地帯の中にあった。
昔、この辺りには野生のワニがいたらしい。いまでは動物園でも見ることは難しいが、まだ絶滅はしていない。この敷地内でも目撃したという話を時折聞くが、本当かどうかは分からない。
延々と続く舗装路。体調は万全ではないが、車は快調に走る。左右を過ぎていく名も知らぬ木々。相変わらずの曇天だ。どうせ数時間後には天気など関係なくなるのだが、それでも出発時には晴れている方が気分がいい。太陽に向かって飛び立つことが、様々な不安を抱えた心を勇気づけてくれる。それに、青空を背景に輝く太陽の美しさをもう一度見るため、必ず帰ってこなければ、という気になるのだ。
みんな似たような感想を抱いているだろうか? 今度他の連中に聞いてみよう。
宇宙港をぐるりと囲むフェンスが右手に見えてきた。延々と走り続け、北側の端で右手に折れると大きな門。重い鉄門扉は、この時間解放されている。左手に小さな警備員室がある。窓に向かって手を振ると、中にいた初老の男が手を振り返してきた。もう何度も見ているが、彼の名前は知らない。おそらくこの先も知ることはないだろう。
敷地内は静かなものだった。最初の頃は検疫棟と倉庫の間を常に貨物が行き交う活気に溢れた場所だったが、いまでは廃墟のような閑散とした場所になっている。三つあった発着場のうち二つが閉鎖されてしまい、それこそ人間に会うのもワニと同じくらいに難しいのでは、という状況になってしまっている。
わたしの勤める派遣会社の仕事は、ほぼ全てこの宇宙港から請け負っているので、ここの業績がそのまま会社の景気に反映される。それなのにあちこちの路面がひび割れ、雑草が顔を出している有様だ。ここのところ晴天が続いているから、いまは平気だが、雨上がりには気をつけて走らないと湿地帯から大量に這い出てきた蛙を轢いてしまうおそれがある。
車を駐車場に停めてD棟へ。ここの入り口にはかつての管理人室があるが、いまでは無人になっている。ホワイトボードに本日のフライト予定がヘタクソな字で書かれており、それをなんとか解読すると本日ここから飛び立つロケットはわたしが乗り込むヴィーナス号だけらしい。まだ出発まで時間があるので誰も来ていないようだった。搭乗者控え室のロッカーに荷物を放り込み、船内用携帯鞄を開く。搭乗者が持ち込める荷物はこの鞄に入るだけ、と決められていた。もちろん、重量も制限されている。以前は多少のオーバーは大目に見てもらえたが、この燃料高騰のご時世ではそれも望めない。着替えや洗面道具を移し替え、鞄の内側に貼ってある必需品メモと比較する。このメモは便利なので、宇宙飛行士なら誰もが貼っている……というわけではない。小学生の頃から忘れ物が多いわたしのために母が考えてくれた生活の知恵というやつである。母はいなくなったが、習慣は残った。わたしがこの習慣を大人になっても守っていることを生きている間に伝えれば良かった。
荷物をまとめて長椅子に座り、販売機で買った珈琲をすする。もちろん、この珈琲のカップも船内に持ち込むわけにはいかない。
控え室の曇りガラスから柔らかな外光が溢れている。曇り空がそのまま胃の辺りに入り込んだように、わたしの気分はすぐれなかった。出航前日に、街なかにある労働者保健センターで健康検査が実施されるのだが、その結果が出るとバーへ繰り出し、馬鹿騒ぎするというのが飛行士達の習慣になっていた。会社によっては検査後のアルコールの摂取を禁じているところもあるが、わたしのところの宇宙飛行士規則には「適量ならOK」とある。そこで皆は自分の適量を知ろうと躍起になるというわけだ。わたしは今回も惜しいところで適量を知るチャンスを逃してしまったようだが。
最初の頃は誇らしげな気持ちでこの飲み会に参加していたものだが、そのうちに一人で飲むようになり、いまとなってはただの惰性で、フライトがあろうがなかろうが、構わずに飲んでいる。そんなことをやっている間に会社が傾き、いつまで飲み代(しろ)が保つか判らない状態に追い込まれている。
珈琲を飲み干すとようやく胃が落ち着いてきた。搭乗前に腹に何か入れておく必要があるだろう。
ウェイターも調理師もいない、怪しげな自動調理器が三つしかないメニューを吐き出すだけの食堂。昔は厨房で何人もの料理人が働いていたのだが、いまはカウンターの向こうに空虚な静けさが広がっているだけだ。かくれんぼをするにはもってこいの場所だが、生憎とそこまで童心を持った同業者にお目にかかったことはなかった。
自動調理器の前でどれを選ぶか少し躊躇する。どれにしたって同じぐらい不味いのだから、迷っているのも時間の浪費だが、少しでも被害を小さくしようと最善を尽くす努力はするべきだ。宇宙での食事は固形食ばかりで味気ないが、考えてみればこの食堂よりはマシかもしれない。
二百人を収容できる空間。叫べば木霊が返ってきそうだ。
元は白かったテーブルが整然と並べられ、椅子も行儀良く揃えられている。その規則正しい景色にぽつりとアクセントがつけられている。管制官のジョルドが座っていた。
彼はわたしに手を振った。
トレーを持ってそちらへ向かう。
酒を頻繁に飲みに行くほどの仲ではないが、知らない振りをするほどの宿敵でもない。
正面に座る。ありがたいことにもう彼の容器はほとんど空だった。
わたしはラグビーもサッカーも見ないので、こういう場所での世間話というのがひどく苦手なのだ。
ジョルドが壁に掛かった時計をフォークで指した。
「早いじゃないか。まだ打ち上げにはかなりあるぞ」
わたしはどろどろの何かをほおばりながらうなずいた。販売機のボタンにシチューと書いてあったはずので、たぶんそうなのだろう。あるいはいつの間にか「燃えないゴミ」のボタンが新設され、気づかないうちに押していたという可能性も否定できない。
「ひどい二日酔いなんだ。とっとと乗り込んで眠っておこうと思って」
と正直に答えておく。
「ああ、カプセルか」
長期フライトに備えて、船の中には身体を固定して使用する睡眠用設備がある。正式な名称は長くて覚えるのが困難だが、皆は単にカプセルと呼んでいた。
もちろん、操縦を行うものが寝ているわけにはいかないが、わたしの番が回ってくるのは出発後十二時間たってからだ。打ち上げ時に遅番の者がカプセルを使用するのは、少なくともわたしの周りでは一般的だった。
もちろん細かいことを言えば、カプセル自体が宇宙船の発着時には使用を禁止されているのだが、実際には守られてはいないルールだった。かつては、出発時に寝ていることで自分の剛胆さをアピールするという意味もあったらしいが、いまでは船の安全性もかなり向上したので、乗組員がやるべきこともほとんどない。ギリス船長も、その辺りに関してはうるさく言ってこない人だ。今までに十回以上、彼の下で働いているので、こうして事前に潜り込んで眠っているという選択も可能だが、これが初めて一緒に組むチームとなると、さすがに出発時に寝ているわけにはいかない。どの程度まで緩さが通用するのか見極める能力がわたしのような立場では非常に重要だ。
「半日たったときに体調を万全にしておかなきゃならんからな。なにしろその後は十時間ばかり緊張の連続だ」
相手が飛行士ではないので、とりあえずそのような適当なことを言うと、彼は「なるほど」と頷いた。半日後の体調を万全にすることも確かに大切だが、そんなことを言う前に、いま二日酔いでいることこそが問題なのだが。
「だからさ、今日の担当の管制官に言っといてくれ。搭乗予定者のロイドは先に乗り込んで眠ってるってさ」
そう頼むと彼は「俺も徹夜明けだ。もう帰るけど、その前に一度管制塔を見ておくよ」とうなずいた。
管制官は自分が担当する船に正しい荷物が積まれているか、乗員は乗り込んだか、燃料は万全か、ということを最終的に確認する役割を担っている。打ち上げ後も定期的に連絡を取って安全な運行がなされていることを確認する。
今回のわたしのように先に船に潜り込んで眠る場合にはあらかじめ言っておくのが礼儀ってもんだ。もちろん、出発時の乗員確認で気がつくだろうし、船長がオペレータに伝えればそれでことは足りるのだが、それだと相手がヘソを曲げる場合もある。なんだかよくわからないが、組織にはいろんな立場の人間がいて、思いがけないところに隠れた面子ってものがあるようなので要注意だ。
「だんだん徹夜がきつく感じられるようになってきたなあ」
ジョルドは自分の肩を回しながら首を捻った。枝を折るような音がする。
「管制官も減ってきてるもんな」
わたしが返すと、舌打ちをして「先週、また一人ワニを探しに行っちまった。まあ、実際こんな安月給ではやってられないけどな。俺の歳でいまさら他の職に移るってのも現実的じゃないしな」
ワニを探しに、というのはこの宇宙港で働いていた奴が首になったり仕事を辞めて姿を消した時に使われる謎の表現だ。そして、そんな下らない表現がこの場末の宇宙港にはお似合いだと思う。
ひとしきり愚痴を漏らした後で、ジョルドは去っていった。
静寂が食堂に戻ってきた。
シチューは相変わらずの味だった。
地下の格納庫へ行く途中でトイレに寄る。船内での老廃物はできるだけ少なく、ということをアストロノウツの教習所で習った。いまさらそんなことが船のスピードや燃費に影響を与えるわけはないのだが、そのとき素直に納得してしまったので、いまだにそれを守っている。
発着場へ続く廊下は細く長い。この先に何かが待ち受けているという緊張を、最初の頃はかき立てられたものだが、いまはただの暗い通路だ。
扉が開くと大きな空間が広がる。天井は遙か頭上で無骨な骨組みをさらしており、そこからいくつもの照明や換気装置がぶら下がっている。太いパイプが何本も縦横に走り、あちこちに置いてある端末につながっていた。
天井、壁からの無数の光は船の周りに集中しており、この広大な部屋の四方は薄暗くなっている。燃料と油の匂いがする。
ややくたびれた風体で横たわる巨大な船。船体には大きくヴィーナスと書かれている。名前のセンスもどうかと思うが、型式もそれに見合ったとても古いやつだ。うちの会社にもくたびれた船が二隻あるが、これよりは新しい。貨物専用船なので、大きさだけは立派である。今回お世話になる会社が創立時に購入した船の一つがヴィーナスだったという話だ。創業四十年。未だにそれが現役として稼働しているのだから、恐れ入る。
既に船はレーザーリングの上に乗っていた。
整備服を着てうろついているのは顔見知りのエンデだった。エンジニアとしての腕前は一流で、彼がもしどこか他の宇宙港に行くことになったりしたら、いよいよここも危ない。
「もう入っていいだろ?」
彼はうなずいた。なにも訊ねてこなかった。
口数の少ない奴は信用に足る人物だというのがわたしの判断基準の一つだ。これはおしゃべりなわたし自身にも適用できる。
船のハッチが閉まる。
聞き慣れた空調の音に包まれる。
実はこの何でもない些細な音がくせ者だ。例えば二人しかいない仕事のときなど、交代制なので基本的には一人きりで船内にいるわけだ。すると、出発時からずっと鳴り続けるこの空気の循環する音が突然気になってしまうことがあるのだ。あるいは、照明の色がどうしても我慢できなくなるというのも心が平穏な状態から離れつつあるという危険な兆候だ。そんなときには平常心を取り戻すために安静プログラムと呼ばれるゲームのようなものをやったり、トレーニングルームという名の狭くて殺風景な部屋で軽い運動をするように、と『宇宙飛行士の安全の手引き』には書いてある。しかし、誰もが知っていることだが、そんな時に一番確実な気分転換は酒だ。
また、一人きりでいると妙に気分が昂揚(こうよう)してくることがある。数万キロに渡って立つべき大地を失った空間に浮いている、それがなぜか異常なまでの躁状態へと結びつくのだ。地球という小さな星の上で起こっているすべての出来事がつまらない無意味なものであると確信できてしまう。そして、環境が変わったことからくる一時的な思い込みが過ぎると、自分は「宇宙の神秘」に触れられる、あるいは触れた、などと錯覚するようになってくる。
まあ、その程度のことなら、地上でもありがちな一時的な気の迷いなのかもしれないが、問題は我々が客の荷物を預かるただの運送屋であるということだ。そうでなくても使用している宇宙船というのは、まずたいていの場合は乗っている人間よりも遙かに大切なものだ。そういう人間に「調子よく」なられては困るわけだ。与えられた任務を全うすることこそが宇宙船に乗っている人間の第一に成すべきことであり、それ以外の悟りも天才的な閃きも、心の底からの絶望も、できれば他のところでやってほしいというわけだ。
そこで、そんな状態になったときにも効果的な精神安定プログラムが用意されている。聞くところによればやはり適度な運動による気分転換を行うだけらしいが、結局のところ、この場合の特効薬も酒だということを他の宇宙飛行士もわたしも知っている。
酒はあらゆるトラブルに効くし、同時にあらゆるトラブルの元になる。有史以来不変であろうこの事実を、小学校でしっかりと教えるといいかもしれない。
ハッチを過ぎてすぐに正面の壁にあるネームプレートを確認した。『搭乗予定者』のところに貼ってあるプレートを『搭乗者』と書かれた升目に持って行く。もちろんわたしが一番乗りだ。自分の名札を裏向きにして貼る。非番の人間は裏返しておく決まりで、そこには本来赤いインクで名前が書かれているのだが、あいにくわたしの札の字はもう消えかかっていた。裏返す度に「次に地球に戻ってきたら書き直そう」と思う。いまも同様だった。
口笛を吹きながら船内の廊下を歩く。まだ照明は足下でぼんやりと光っているだけだ。
この船は上から見れば円形になっており、扇形に十の区画に区切られ、全てが倉庫として使われている。船の周り、全体にぐるりと狭い通路が設けられている。貨物船としては珍しい構造の船だ。
なぜ、この船の通路が外側にあるのか、という問題については乗組員の間でもいろいろと好き勝手な憶測がある。空間を十分に活かす(それは宇宙船というものに於いては非常に重要な思想だ)のであれば、中央に通路というか、丸い部屋を設けて、その周りを倉庫で囲った方が効率がいいはずなのだ。それをわざわざ外にしたのは、宇宙を漂う小さな石ころなどの直撃を受けたときに、大事な荷物が破損するのを避けるためであるとか、温度変化を少しでも低くするため(つまり、廊下が宇宙空間と倉庫の間に介在する緩衝剤の役割だ)だとか、単に設計をしくじった船が安く売りに出ていたのを二束三文で買い上げたからだ等々、乗組員によるいい加減な説があった。まあ、古い船なので、あまり細かいことを考えずに造られたのではないかと、わたしは思っている。
一階は倉庫ばかりが並ぶ。その数はアルファベットのJまであり、かなり広い造りになっているが、タラップで連絡している狭い二階には操縦室しかない。ヴィーナス号の操縦室の天井はやけに低く、圧迫感がある。飛行士の心理状態への配慮をデザインに組み込む余裕がなかった時代の産物だ。ありがたいことにあと十二時間はその狭い空間に行く必要がない。
廊下のカーブに沿って小さなロッカーが並ぶ。わたしは一番左に荷物を放り込んだ。鍵をかけられるようになっているが、ヴィーナス号ではこの仕組みを使うものはいない。鍵は個人識別などではなく、鍵穴に鍵を差し込む前時代的な方式のものが設けられている。当然のことだが、それらの鍵はことごとく紛失してしまっている。
本当はつまらぬトラブルの元になり得るので、宇宙船内では施錠が義務づけられているのだが、馴染みの顔ばかりなので、いまさら必要はないだろう。そのことがお互いを信頼しているという意思表明であるような気もするし、貴重なものは身につけておくのが当然の習慣だという、暗黙の主張であるような気もする。まあ、どのみち船にそれほどたいそうなものを持ち込む奴はいないのだが。
ただ、銃に関しては別だ。持ち込みが許可された銃は、各自ロッカーに入れておくように決められている。船内で携帯するには船長の許可が必要となる。
1-Cと1-Dの間に狭い部屋がある。中へ入ると薄暗いオレンジ色の光に包まれる。背後で扉が閉まると、体中を覆っていた膜がなくなったような感覚を覚えた。音が消えたのだ。
耳鳴りがするほどの静寂に包まれる。
壁には折り畳み式のベンチがあり、その横に細長いロッカーのような睡眠装置が三人分。迷わずその一番左の扉を開ける。こういうものは使っているうちに自分のお気に入りの場所ができるものだ。
衣服を入れておくカゴもあるのだが、わたしは既に船内スーツに着替えていたので、そのまま中に入った。
体が白く淡い光に包まれる。蓋を閉めてダイアルを八時間後に合わせる。新鮮な空気が頭上からはき出され、川のせせらぎが聞こえてきた。だまされているとわかっているのだが、もう圧迫感は感じない。
突然、珈琲の粉を持ってこなかったことに気が付いてしまった。船内には共用品として冷凍乾燥した珈琲しかなく、はっきりいって飲めたものではない。だからいつもわたしは持参することにしているのだが、今回はすっかり失念していた。二日酔いになるとろくなことはないという証左を又一つ発見だ。今度から珈琲の粉を荷物に入れてから飲みに行くことにしよう。いや、鞄の内側に貼り付けた例のメモに書いておくべきか。それにしても二十日間、どうやって過ごせばいいのか。今から船を出て買いに行くとしても、宇宙港の売店にも冷凍乾燥品しか置いていないのだ。いまさら車に乗って街まで戻るのもあり得ない話だ。
ため息をつきながら右手のボタンに手を伸ばす。
静かにガスが出てきて、その臭いが鼻腔を刺激したと思った瞬間に、わたしの意識は遠のいていった。
高校の頃に見た西部劇映画のガンマンになっていた。
乾いた荒野を、拳銃を撃ちながら必死に逃げているのだ。
エレベータボックスを見つけて飛び込んだ。
なぜか「上」ボタンを押す。
どこまでも登っていくのだが、不意に、この先にはなにもないということを思い出して、焦燥と絶望に駆られる。
微かな振動。
半ば夢の中でそれを聞いていた。
意識が覚醒していく。
呼吸を整える。深く空気を吸い込もうと務める。
緩やかに音楽が流れてきた。そらぞらしいさわやかさを強調するようなクラシック音楽だ。誰のなんという曲か知らないが、作曲者もまさか何百年も後に宇宙空間で目覚ましに使われるとは思いもしなかっただろう。
急速に頭がはっきりとしていく。たしかこの装置は酸素の濃度も調節しているはずだ、というようなことまで考えることができる。
あまり気分がよくない。
目をもう一度閉じる。
必死に逃げ回っていた夢を思い出して思わず苦笑する。
最初の頃は宇宙船の発射時に寝ているなんてあり得ないことだった。毎回毎回が一大イベントだった。照射される高出力のレーザー。爆発的に膨張する大気に弾かれて上昇する機体。離れていく地表。生まれた星からの離脱。
宇宙船が、途上期よりもずっと安全になった(例によって死亡事故に遭う確率が一番高い乗り物は地上を走る車だが)とはいえ、やはり完全ということはありえない。出発の瞬間に寝ていても平気になったのは二年目ぐらいからだった。わたしのように派遣されて船に乗り込むものが発着時の操縦を任されることはまずない、という事情もあるだろう。三十回以上ともなると、とにかく自分の体調を最優先にするようになる。まあ、楽をしたがるということだ。
蓋を開けて部屋の中へ。大きく伸びをする。とにかく二日酔いは去ったようだ。気合いを入れて働くとしよう。
壁の時計を見る。交代の時間まであと一時間。もう月の軌道を越えた頃だろうか。
加速も終わったようで、時折進路を微調整するエンジン音が船体に伝わってくるだけだ。
静かだった。
船は確実に飛んでいる。微かに重力が弱くなっている。
部屋を出ようとしてふと隣の睡眠装置を見る。
オレンジ色のランプが扉のノブの横で点滅して「使用中」という文字を浮かび上がらせている。これは重量を感知して光る仕組みになっているはずだった。
見れば、部屋の隅のカゴに衣服が入っている。
誰かが眠っているのだろう。
そこで気がついたが、わたしの入っていたカプセルの扉にはランプが灯っていなかった。 本来ならば「空き」を意味するグリーンのランプがついていなければおかしいのだ。最初からそうだったのだろうか。わたしが一番乗りなのは確実だったので、特にそんな表示に注意を払わなかった。試しに蓋を開けて足を突っ込んでみる。体重をかけてもランプは消えたままだった。眠るための機能は正常に動作していたので、深刻な故障ではないようだが。
船の機関部は常にメンテナンスをしているので、この老体でも動き続けているが、睡眠用の装置などは基本的に「動けばいい」という程度に考えられている。もちろん長距離用の冷凍睡眠装置ともなると話は別だろうが。
とりあえず船長に報告だ。むしろ船のエンジンが動かなくたって構わないから、こいつにだけは心地よい睡眠を提供してもらいたい。
点灯しないランプに触れていて、ふと隣のカプセルの扉の下が汚れているのに気がついた。
珈琲か。と一瞬思った。
横着をしてカップを持ったままこの装置に入った奴がいるのか、それは少しうらやましいようでもあるが、寝てしまった後はどこに置くんだ? まだ完全には覚醒していない頭にはそんな考えが浮かんだ。
もちろん、そんなはずはない。
珈琲にしてはやけに濃度が高そうだった。このオレンジの灯りの下では正確な色はわからないが、タールのような印象を受けた。どこかシリンダか何かがやられたのか。油圧で動く装置があるとしたら、開閉部だろう。だとすると、いよいよ本格的にメンテナンスが必要だ。
とにかく、中の人間を起こした方がいいだろう。もしわたしと当番が同じハイダなら起こしてもいい時間だし、そうでないにしても、故障したカプセルを使っていつまでも眠り続けられても困る。
カプセルの蓋を叩く。
返事はない。
強く、何度も叩く。
カプセルの把手を握る。事故に備えられて鍵は設けられていない。
タールではない。
蓋を開きながら、不意にその正体に思い当たった。そして、それが正しいことはすぐにわかった。
中には機関士のハイダが居た。
その目は開かれていた。
しかし、彼は眠っていた。
もう二度と起きることはないだろう。
床の染みは彼が源流だった。
彼の両の膝から太股。さらにその腹も完全に染めて胸へと達している。
そこには撃たれたと覚しき穴が空いていた。
第2回へ続きます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
