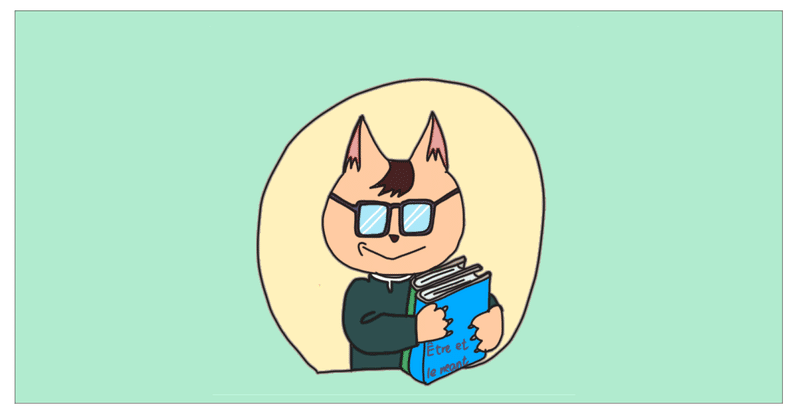
「芸術神学」批判序説 ~ 新しい公共劇場の在り方を模索するための省察 ~(4)
4.「芸術神学」の基本図式
なぜ人は芸術を通じて(こそ)「真理」に到達できるのだろう?
ここで、古典的な情報理論を援用すると、意外にも理解が進む。
(送り手) (受け手)
[情報]⇒[コード化]送信・・・・・・受信[脱コード化]⇒[情報]
(1)送り手は、相手に伝達したいメッセージをコード化(たとえば暗号化)し、送信する。
(2)受け手は、コード化された情報を脱コード化(解読)し、メッセージを受け取る。
非常に素朴な図式だが、これは芸術(批評)にも応用が利く。
(芸術家) (批評家)
[真理]⇒[作品]送信・・・・・・受信[批評]⇒[真理](⇒ 芸術愛好家)
(1)芸術家は作品として「真理」を結実させる。この「真理」がどこからやってきたのかについては後述する。
(2)批評家は、作品を批評し、そこから作品に内在する「真理」を抽出する。
(3)抽出された「真理」が、人々の前で示される。
ここで、まずは(「近代芸術」において)批評(批評家)が決定的な(特権的な)役割を担っていることに留意しておきたい。
芸術作品に内在する「真理」を抽出する作業(批評)を担えるのは一般人ではない。いわば専門家である。一般人には、作品の「意味」は分からないのである。「近代芸術」は批評とともに誕生したのであり、批評システムを支えたのがグーテンベルク(印刷技術)革命、要するに新聞・雑誌メディアの興隆である。この件について踏み込むと話が終わらなくなるので割愛するが、芸術に内在する「真理」の抽出作業は批評に委ねられていた、ということと、これを別角度から表現するなら、芸術の価値創造を担っていたのは批評だった、という点についてのみ付記しておくこととする。「事件があるのではない。出来事を事件にするのは新聞なのだ」とか豪語している新聞記者に出会ったことがあるが、そうであるなら、「芸術があるのではない。作品を芸術にするのは批評なのだ」とか豪語する批評家がいてもおかしくない。
さて、前掲した図式を念頭に置きつつ、芸術家が芸術作品に「真理」を宿すにしても、そもそもその「真理」はどこからやってくるのか?という疑問が湧くだろう。
そこで、さらに図式を変形していく。
まずは、神学的な図式から。
(神) (司祭)
[真理]⇒[聖書]送信・・・・・・受信[教会]⇒[真理](⇒ 信者)
(1)「真理」の源泉は、言うまでもなく「神」である。
(2)「真理」=「神の〈ことば〉」が「聖書」として結実する。「聖書」には「神の〈ことば〉」が内在している。
(3)「聖書」の「意味」を理解できるのは「教会(司祭)」だけである。
(4)「教会(司祭)」が、人々に「神の〈ことば〉」を伝えていく。
この図式を念頭に置きつつ、さらに変換していく。
(神)
↓
(芸術家) (批評家)
[真理]⇒[作品]送信・・・・・・受信[批評]⇒[真理](⇒ 芸術愛好家)
さて、勘の鋭い人はもう閃いたかもしれない。
念のため、解説する。
なぜ芸術家は「真理」を作品に結実できるのか? その理由は、彼/女が「天才」だからである。この場合、「天才」とは、いわば神的(神がかり的)インスピレーション(いわば天啓)により、神降ろし、ならぬ「真理」降ろしができる人のことである。それが、「天才」の「天才」たる所以である。
すなわち、
(1)「天才」である芸術家は、まさに「天才」であるがゆえに、その神的インスピレーションにより、「真理」を芸術として具現することができる。彼/女は凡人ではなく、特別な存在なのだ。
(2)(無知蒙昧な一般大衆に代わり)司祭=批評家(だけ)が、「聖書」ならぬ芸術作品の中に入っている「真理」を抽出し、開示する。
(3)開示された「真理」が、下々に示されて、広く普及啓発されていく。
これが、じつは「近代芸術」の根底的なフォーマットだ!(西洋的あまりに西洋的!)
何と言うか、「近代芸術」にまつわるエトセトラは、すべて西洋ローカルな一神教的土壌に親和的であり、逆からいうと、そもそも「近代芸術」はまさにTHE西洋でしか誕生し得なかったといえる。
(1)芸術家とは、(「神の〈ことば〉」を伝える)世俗化した「預言者」である。
(2)批評家とは、「聖書」=「芸術作品」の意味(「真理」)を伝える世俗化した司祭である。
(3)芸術愛好家とはすなわち、信者のことである。
余談だが、プロテスタンティズムが「聖書」を「司祭」の手から奪い、自らのモノとしたように(媒介者である「教会」権力を取っ払ったように)、現代アートの旗手たちは芸術作品を批評家の手から奪い、「みなさんがそれぞれ自由に解釈してください(司祭は不要!)」と門戸開放したが、これは遅れてやってきた宗教改革であるといってよいだろう。
以上、「近代芸術」がなぜ「真理」に到達できるかというと、それが「天才」によって創造されたものだから、である。
「天才」とは、かくも偉大な存在である。
ベートーヴェンはただの人ではない。「天才」である。
ゲーテはただの人ではない。「天才」である。
しかし本当に「天才」はいるのだろうか?
「天才」は「預言者」なのだろうか?
(神)
↓
(芸術家) (批評家)
[真理]⇒[作品]送信・・・・・・受信[批評]⇒[真理](⇒ 芸術愛好家)
この図式は、どこまで妥当なものだろうか?
フリードリッヒ・ニーチェ(1844-1900)が「神は死んだ!」と叫んだとき、この図式に、おそらくは最初の傷が入った。(ただしニーチェ本人は芸術愛好家である。)「真理」の身元引受人は他でもない「神」だからである。
マルセル・デュシャン(1887-1968)が便器に「泉」とネーミングして出展したとき、その傷は致命的なものになった。「聖書」が便器になってしまうと、そこからどのような「真理」を抽出してよいものやら、批評は途方に暮れてしまう。一夜にして、「近代芸術」も「(近代的批評)も「古典」にされてしまった、と言うべきだが、それはさておき、最終的に引導を渡したのはフランス現代思想だろう。
少し急ぎすぎたかもしれない。
ゆえに、まずは、フランス現代思想の世界へ誘いたいと思う。
そこで、いわゆる「近代芸術」が死ぬからだ。
芸術作品の中には「真理」が内在している、という「信仰」が終わる。
《またまたまた、つづく》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
