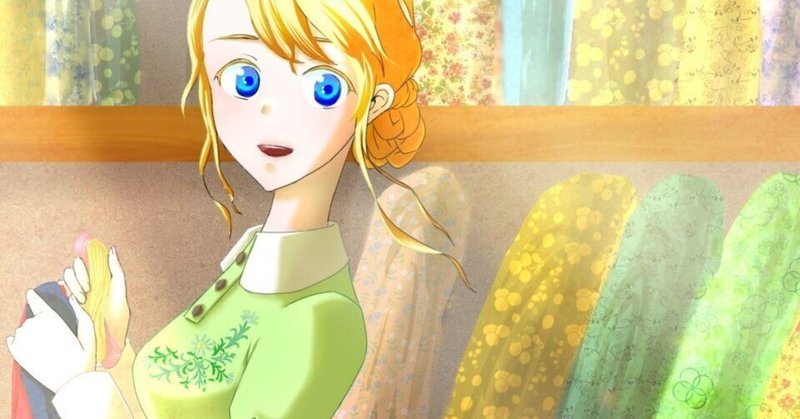
ボロ雑巾な伯爵夫人、やっと『家族』を手に入れました。〜世間知らずの夢の成就は、屋敷ではなく平民街で〜 第八話
自炊道具を買った私たちが次に向かったのは、食料品を売っている店が立ち並ぶエリアだった。
店があったのは、調理済みの物を売っている店――いい匂いが誘惑してくるエリアを抜けた先だ。
野菜、果物、肉に穀物。それぞれに扱うものが違う店が立ち並んでいる。見てみれば、例えば同じ野菜の店であっても取り扱っている品目が違うようだ。
野菜が売っている所を見るのが初めてだった事も相まって、物珍しさを抱きながら店の間を歩……こうとしていたのだけれど。
「あれ、珍しいなぁ、お前らが普通に歩いてるなんて」
「当たり前でしょ。悪い事しようとしてるわけじゃないんだし」
「よく言うぜ。今日は出店を壊すなよ?」
「うっせぇ黙れ! 大体なぁ、絡んできたヤツラがたまたまいつもよろけた先に、たまたま店があるだけだろうが!」
前を歩く二人に、店主たちが口々に話しかけるのが先程からずっと気になってしまって仕方がない。
口ぶりから、両者が顔見知りなのは、ほぼ間違いない。気安いやり取りが飛びかうものの素っ気ないノインや口の悪いディーダの言葉にも特に気分を害した様子もないのを見ると、結構気の置けない間柄なのだろう。
二人からは「食料品街は食い物を強奪しに行くための場所」だとあらかじめ教えてもらっていたため、てっきりあまりいい関係性は築けていないものと思い込んでいた。
今回はきちんとしたお客として出向くとは言えど、もしかしたら険悪な態度を取られてしまうかもしれない。そう覚悟をして出向いたのだけれど、どうやら杞憂だったようだ。
もしかしたらこの二人は、私が思っていたよりもずっと顔が広いのかもしれない。
「あぁ、この前の手伝いの報酬分、持ってくならあっちの廃棄予定のリンゴだぞ?」
「今日は客だ! 丁重にもてなせ!」
「ボクは貰っとくよ。さっき入り口で焼けた肉の美味しい匂いを嗅いじゃったから、ちょっとお腹減ってきたし」
言いながら、案内もされずに果物屋の裏に入り、口をモグモグとさせながら戻ってくる。その手には歯形が付いたリンゴが。どうやら貰ってきたらしい。
と、ここで初めて店頭に立つ人の内の一人が、私の存在に気がついた。
「あれ? そちらさんは?」
「「拾った」」
「「「「拾った?」」」」
大人たちの声が、ものの見事に重なった。皆目をぱちくりさせている。彼らにとって、それだけ非常識な状態を告げられたのだろうという事がよく分かる。
大人が子どもに拾われただなんて、驚く気持ちはよく分かる。けれど、如何せん間違っていないばかりに弁解の言葉を持てない。
集まった視線が痛い。注目されるのが苦手な私は、思わず身を固くする。
嫌な記憶が蘇る。
皆に注目され発言を期待された状況で、何度社交界で固まってしまった事か。そしてそれが、周りを何度呆れさせたか。迷惑そうな彼らの目を思い出せば出すほど一層、言葉は喉に詰まってしまう。
きっと今回も、彼らを呆れさせてしまう。失望されて、やがて期待もされなくな――。
「何言ってんだい。拾ったって、そんな猫じゃあるまいし。ねぇ? あんた」
二人の物言いをピシャリと諫めた女性の声は、私に「ごめんねぇ」と謝ってくれる。
驚いた。彼女は私を気遣わしげに見てはいるが、少なくとも私には失望も邪魔にも思っていないように見えた。
むしろ何も話せない私を迎え入れてくれている雰囲気さえ感じる。
そしてそれは、何も彼女だけではない。
「というかそれ、古びちゃいるけどドレスだろ。もしかして良いトコのお嬢様……にしてはちょと痩せこけすぎか?」
「その辺どうなんだい? ノイン」
「おいババァ! どうして俺には聞かねぇんだ!」
彼らはどうやら私に興味を持ってくれているらしい。決して話の輪から外すような事はなく、しかし離せない私に配慮してか、代わりにノインに尋ねてくれる。
私には、それが暖かな優しさに思えた。
社交界では、自分の意思を語れない者は置いていかれる。誰もが皆、自分や自分に近しい者への得のために動き、それができない人間を仲間として認めないような風潮が少なからずあった。
でも彼らは、そうじゃない。
彼らの仲間に入れてくれようとしてくれている心遣いが嬉しかった。
できれば話をしたかった。しかし、身の上に関係する話はできない。
どうしたものかと困っていると、ノインが「さぁ?」と何という事も無さげに肩をすくめてみせる。
「多分『元家猫の現野良猫』なんじゃない? まぁ本人は言いたくないみたいだし、ボクたちも詮索する気は無いけど」
彼の言葉に驚いた。
ノインが庇うように詮索する必要性を感じないと言ってくれた事ではない。元家猫の現野良猫という形容が、まるで育ちの良さを見透かしているように聞こえたからだ。
目を見張ると、ほんの一瞬チラリとこちらの様子を窺った薄桃色の瞳と目が合った。
喜怒哀楽がすぐに目に見えて分かるディーダとは正反対に、彼の目は人を観察する静かな目だ。
彼の目を見ていると、まるで全てを見透かされているかのような錯覚に陥る。
いや実際に彼は既に、色々な事を見透かしているのかもしれない。流石に私の素性そのものまでは、まだ彼も知らないだろうけれど。
「ボクらはあくまでも、ギブ&テイクの関係。それが保てれば十分だし」
「おいババァ! 俺にも聞け!!」
そんな風に答えた彼を眺めながら「バレないようにしなければ」と手をギュッと握り締める。
特に彼らは口ぶりからして、貴族や領主である伯爵家の事をあまりよく思ってはいないみたいだから。バレて彼らに嫌われたくない。
「それで? 今日は何を買いに来たんだい?」
「さぁな、作るのはこの女だから」
「作るって、もしかして一緒に住んでるのかい?」
「そりゃぁちょうどいい、ちょうどコイツラも野良犬みたいなもんだからな」
「とんだ暴れ犬だけどねぇ」
言いながら、街の人達が一斉に笑った。
からかい文句ではあるが、まったく陰険な感じがしない。カラッと乾いた晴れの日の洗濯物のような彼らの言葉は、屋敷で私が受けていたレイチェルさんからのジメついたからかい文句とは正反対だと言っていい。
そんな空気に緊張が薄れたからか、それとも気になるワードに好奇心が勝ったのか。
「あの、何故『犬』なのですか?」
気がつけば彼らに、そう尋ねてしまっていた。
私の突然の問いかけにも、彼らは嫌な顔一つしなかった。納得なのか、相槌なのか、「あぁ」という声の後に教えてくれる。
「この子達は妙なやつが来ると追い払ってくれるんだよ。喧嘩っ早いのが玉に瑕だけどな。いわゆるこの辺の番犬っていうやつさ」
「番犬……」
「他の領地は知らないが、ここは領主が動かないからね。そのせいで憲兵たちは怠惰なのさ。教会はたまに貧民相手に炊き出しやらやってるけどね」
「まぁコイツラはこうして俺たちに何かと恩を売っては自力で食料をどうにかしてみせるから、滅多に行かないみたいだがな」
ガハハッとおじさんが豪快に笑ってみせる。私も答えるように笑ったけれど、もしかしたら多少引きつった笑みになってしまっていたかもしれない。
私にとってはこの話、笑えるような事ではなかった。
まさか領主の領地経営への消極さが、人々の生活にここまで直接的に影響しているなんて。
貴族《私たち》の怠惰がここまで領民へのしわ寄せになっていたとは露ほども思っていなくって、当事者でありながらその事実を知らなかった自分自身も、その至らなさの尻拭いをしてくれているという教会にも、そして何より彼ら平民にも、申し訳が立たない。
己への恥じが心の奥底からせり上がってくる。しかしそれが圧迫感に変わる前に、「それよりも」というおじさんの声で我に返った。
「嬢ちゃん、今日は何が欲しいんだい?」
「えっ、えぇと……」
うちで買いなよ、と商売上手のおじさんが言い、隣の店のおばさんが「客の横取りはいけないよっ?!」と笑いながら応戦する。
並べられている品を見れば、おじさんのお店は果物屋さんで、おばさんのお店は野菜屋だ。それぞれの店を見比べながら、慌てて何を買おうか考える。
特に買う物を決めて来たわけではない。ただ、できるだけたくさん食べさせたい。
となると、とりあえず調理法次第で何にでもできそうなものを選ぶのが無難だろうか。味に飽きないように工夫しやすいものを選ぶのも良いかもしれない。
「じゃぁおばさんの所では、ジャガイモとニンジンとタマネギと……それから何か安くておいしいオススメはありますか?」
「あぁ、じゃぁこれなんてどうかねぇ? タケノコなんだが、今年はちょっと豊作すぎてね。そもそも料理するのに面倒臭いから、あんまり売れないんだよ」
彼女が「どうだい?」と言いながら、そのタケノコとやらを差しだしてくる。
流れのままに受け取ると、思ったよりもズッシリときて驚いた。
なんだかちょっと、木の枝みたいな見た目だ。少なくとも私は初めて見る。
「今日買ってくれるんなら、ちょっと安くしとくけど」
「え、良いんですか?」
「あぁ、タケノコは採ると鮮度が落ちるのが早くてね。どうせこのままじゃぁ私たちの腹の中か、それでも余れば捨てるしかない。買ってくれると、こっちも助かるんてtもんだよ」
なるほど。日持ちしないのは難点だけど、ジャガイモとタマネギはある程度日持ちがするから、使う順番さえ気を付ければ問題なさそうな気がする。
「じゃぁそれを、今日食べるので三人分の量くらい」
「まいどあり!」
元気のいい返答と共に、手際よく野菜が紙袋の中へと入っていく。その様を眺めながら、私は一つ大切な事を尋ねる事にした。
「ところで私、その品を料理した事が無いのですけれど、どのようにして食べるものなのでしょう。その、タケノコというのは」
彼女の手が、ピタリと止まった。こちらに向けられたのは、少し妙なものを見るような顔だ。
もしかして、普通は買うと決める前に料理方法を聞くものだったのかもしれない。今更ながら、自分の立ち回りの悪さを恥じる。
そんな私に予想外の言葉が投げかけられた。
「おやそうなのかい? この辺じゃよく食べるのに」
唐突に、自身の常識外れを自覚させられる。
どうしよう。変な子だと思われているかもしれない。
社交界で一人場の空気に浮いてしまっていた過去の自分を思い出して、ブワッと体中から汗が噴き出した。今にも人見知りが発動しそうだ。
いやしかし、聞いた事自体は正しかった筈である。
だって買って帰っても使い方が分からないのでは意味がない。ただの無駄遣いに等しいし、二人に美味しいものを食べさせてあげる事もできない。
どのタイミングであれ、聞かなければならない事だったのだ。自分にそう言い聞かせ、何とか平静を保てるように努力する。
と、その時だ。
「煮物にするといいと思うけど、下処理がちょっと面倒でね。家に帰ったらなるべく早く根元のこの固い部分と上のこの辺までを切り落として、皮をむいて、下茹でをしないといけないんだよ」
不思議がりはしたものの、おばさんは私の無知を決してバカにしたり嗤ったりしなかった。それどころか、とても詳しく教えてくれる。
「下茹で、ですか?」
「あぁ、アクが強いからね。下茹でしないと、えぐみが出てあんまり美味しくない。せっかくなら美味しく食べないと損だろ?」
「アク……」
アクとは何だろう。
私は所詮、最低限の食べものを得るために切ったり茹でたり焼いたりができるだけの人間だ。料理用語に馴染みがない。
思わず考え込むと、おそらく顔に出ていたのだろう。今度は驚いた顔をされてしまう。
「あんた、料理するのに灰汁取りも知らないのかい?」
「すっ、すみません……」
条件反射で、謝罪の言葉が口から洩れた。
咄嗟にフラッシュバックしたのは、屋敷で私を散々「貴女、そのような事も知らないの?」と嘲笑っていたレイチェルさんだ。
一体何度、彼女から「何でこんな事も出来ないんだ」「分からないんだ」と言われた事か。
忘れていた怖れが、足元から這い上がってくる。あぁきっとまた、私を、私の存在をすべて否定されてしまう――。
「不思議な子だねぇ。でもまぁ良いさ。人ってのは、失敗したり教えてもらって少しずつ知っていくものだからね。知らないんならこれから覚えていけばいい。素直にそういう経験を積めるのは良い事さ」
予想していた否定の言葉は一つもなかった。むしろ私を肯定するような言葉だと思った。
彼女のカラリとした笑顔に、無性に鼻の奥がツンとする。
何故だろう。日に焼けた肌と赤毛のぽっちゃりとした彼女とは似ても似つかない筈なのに、何故か今は亡きお母様を思い出す。
「私も昔、お母さんから色々と教えてもらったものさ。誰もが一人じゃ生きちゃいないんだ。こういうのは助け合いだからね。あんたもいつか、誰かに教えてあげたらいい」
お母様も、そうだった。
私が何か失敗をしてふさぎ込んでしまう度に「次頑張ればいいんだよ」と背中を優しく撫でてくれた。
私の最大の理解者で、最大の味方だった人だった。
責められなかった事に安堵して? それとも、他者の無知が許容できる彼女の心が温かくて?
分からない。両方かもしれないし。もっと他の感情なのかもしれない。
けれど無性に、ここに居ていいのだと言ってもらえたような、私という人間を肯定してもらえたような気分になった。
ダメだった。
「ありがとう、ございます」
何に対するお礼なのか、自分でもきちんと言葉にはできない。けれど、たしかに何かを貰った気がした。気がつけばお礼が口から零れて彼女に微笑む。
同じく零れそうになった涙をグッとこらえてた筈だった。なのに何かが頬を伝い、私は慌ててそれを拭く。
驚いたおばさんが「だ、大丈夫かい?!」と慌てて背中に手を沿えてくれた。しかしそれは逆効果だ。さすってくれる手の温かさに、更に目にジワリと熱が集まる。
「あー、そいつちょっと涙腺おかしくなってんだよ」
「よく泣くし、もう放っといていいんじゃない?」
呆れたような声の主は、泣き虫な私を知っている二人の子供たちである。
「えっ、そ、そうなのかい?」
「えぇ、大丈夫です……」
グスリと鼻を鳴らしながら目をグリグリと拭いていると「どこかが痛いとかいう訳じゃないんだね? っていうか、そんなに乱暴に擦ったら目の下が腫れちゃうんじゃないかい?」と、更に心配までしてくれた。
優しすぎた。もう涙が止まらなくなって、ドバーッと感情が垂れ流しだ。
それでやっと周りは慌てから苦笑に変わり、子供たちは二人揃ってわざとらしくも盛大なため息を吐く。
そうだ、いけない。ここには買い物をしに来たのだ。
皆を呆れさせている場合ではないと、私は自分を奮い立たせた。
「う、うぅ……ずびっ、おじさん、リンゴとプラムをください」
「お、おぉ、泣き止んでからでもよかったんだが、まぁいいちょっと待ってろ。オマケしておこうな」
「あ、ありがとうごさいま……ずびっ。それでお二人とも、何か他に食べたい物は――」
「肉」
「肉でしょ」
未だに私の号泣に戸惑いがちな面々とは裏腹に、二人はまったく動じない。きっちりと己の欲を主張をしてくれるが、むしろ今はそれがありがたい。
わかりました、それも買いましょう。
えぐえぐと言いながら、それぞれの店で私は必要な食品を買い集めていった。
店員たちが当たり前のようにディーダとノインに品物を渡すので、涙声で「持ちますよ?」と手を伸ばす。が、その手をペシッと叩かれた。
「もう最初の店で買ったやつ持ってんだろ!」
まるで「俺のものに手を出すな!」とでも言いたげだけれど、それを持っていてもただほぼ重いだけ。ずっと持っていなくても、帰ったらちゃんと皆で分けるし、むしろ労力の無駄遣いだ。
彼らが一番嫌いそうな事なのに。
「でももう片方の手は残っていますし」
「そっちは顔拭くのに忙しいだろ!」
「う、それは……」
言い返せなかった。グッと言葉に詰まっていると、スッと私達の横をすり抜けていくノインが、通りがかりに「まぁ、これだけの物をちゃんと買って堂々と街中を持ち歩くとか、早々できる事じゃないしね」と言い置いていく。
フンッと鼻を鳴らして彼に続くディーダ。素っ気ない言いぶりと態度なのに何故か二人から温かみを感じる気がしたのは、ただの私の気のせいか。
私はグシッと涙を拭いて、二人の後について最後の目的地へと向かった。
【各話リンク先】
第一話:https://note.com/rich_curlew460/n/n02b3af7df971
第二話:https://note.com/rich_curlew460/n/nc5a6a501aa1c
第三話:https://note.com/rich_curlew460/n/nf657217e33a7
第四話:https://note.com/rich_curlew460/n/n0bcd36a46767
第五話:https://note.com/rich_curlew460/n/n76ef05998ecb
第六話:https://note.com/rich_curlew460/n/n1da0c89af729
第七話:https://note.com/rich_curlew460/n/nd2f55ce8792d
第八話:https://note.com/rich_curlew460/n/n5b17d5a00e7f(←Now!!)
第九話:https://note.com/rich_curlew460/n/n1d1b17ac74db
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
