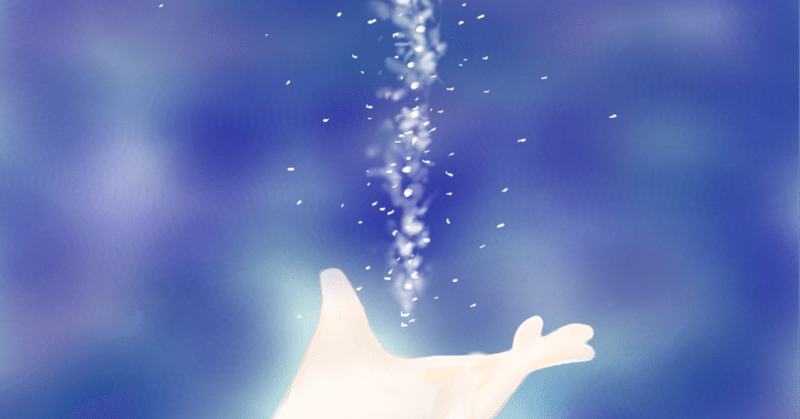
「死神使いの魔法使い(仮)」企画書
キャッチコピー∶「蘇りの業火」を求め、死神と魔法使いが仲良く出陣!果たして手にすることができるのか?
あらすじ∶魔法が廃れて久しい時代に、先祖代々の魔法の力で商売をする魔法使いがいた。すでに親はなく、自給自足生活の日々。その時、魔法使いの
もとに1人の死神が現れた。死神は、魔法使いの命を狩って帰らなければいけないため、命を狩る書類にサインをくれと言ってきた。しかし魔法使いは、
国王から「蘇りの業火」の探索を命じられており、この命令をやり遂げれば、国に魔術機関を作り、
そこの管理者になれるという契約も交わしたので、魔術機関を国の最高機関にできた後なら命を差し
出すと言った。死神はその話を快諾し、そのうえ
探索にも付き合うことを宣言し仲間となった。変な死神と素直で野望に満ちた魔法使いの不思議な探索が始まる。
第1話∶100年程昔。この国では魔法が使える者と使えない者が共存していた。しかし時の国王が他国との戦いの最中。魔法による敵の殲滅を命じたことから、魔法使い達と国王の間で意見が割れた。幸い
戦いには勝利したものの、国王の命に背いたこと
から、魔法使い達は国内での仕事を禁じられ、魔法を使えない者達と交流することも禁じた。そのため魔法使い達は他国に逃れようとしたが、国王直属の魔法使い撲滅隊に捕まり、国外へ逃れることもできず、ジワジワと数を減らしていった。
そして現在。魔法使いの数は激減したが、細々と
魔力を隠して人混みに紛れる生活をしていた。
その中で、国の西側、山と緑に恵まれた森林地帯の
奥に魔法使いが1人住んでいた。
彼は100年前、国王に魔法での敵の殲滅を拒否した
魔法使いの子孫だった。彼の先祖達は100年前以降、魔法使い仲間からも距離を置かれ、住まいを転々
とし、今の場所に落ち着いた。
国の恩恵を受けることなく自給自足生活。両親を
亡くし、1人、祖先が書き残した書物で魔法を勉強
しながら生活を送る毎日。たまに街へ出かけて、
薬草などを売り歩くこともあったが、国では医者の処方する薬が出回っていて、売れ行きは良くない。どんなによく効く薬草で作った薬でも、医者の薬に慣れた人達からは「怪しい薬」と敬遠されるのも
仕方ないことだった。
薬草を売り歩いているのを見つかると街を追い出されてしまうし、店を構えることもできないので、
薬効を体感してもらうこともできない。
彼の薬を買ってくれていた昔の馴染みも、街の
人間に見つからないように買ってくれていたが、
とうとう最後の1人も亡くなり、街での仕事も
なくなってしまった。
森の奥で1人。自然や動物達と生活することは嫌い
ではないが、たった1人でこの先も生きていくという現実に気分はふさぎ込むばかりだった。
そんな折、珍しく魔法使いの家に訪問者がやって
来た。仕立ての良い服に、磨かれた靴。剣を帯同した従者の同伴。身分ある者だとすぐにわかった。
しかし不用心に話しかけることはできない。魔法使いは静かに近づいていった。
従者を連れてやってきた男は、国王からの命令で
魔法使いを城へ連れて行くために来たこと説明を
した。
従者の視線に、断ることができない雰囲気を察し、魔法使いは、代々受け継がれてきた黒のマントをはおると、フードで顔を隠し、男達について、城へ
出向くことにした。
第2話∶謁見の間に通されると思っていた魔法使いだったが、つれて行かれたのは、よく手入れされた庭にあるガゼボだった。
そこにラフな姿でお茶を飲んでいる男性が1人。
こちらに気がつくと、ヒラヒラと手を振り、手招きをしてきた。
その男性こそ、国王だった。自分の前に魔法使いを座らせて茶を用意してくれた。お菓子も…。
国王相手にマントを着たままフードも取らないのは不敬にあたると思い、全て取り払い、茶をいただこき、お菓子を一口いただいた。
話の内容は魔法使いを迎えに来た男の話と同じ
だった。要は「蘇りの業火」を使い、病弱な息子に
時期国王にふさわしい強い精神と肉体を与え、息子が国王になることに、誰も反対しない状況を作る
ために必要な素材として、どうしても手に入れたい
ということだった。
国では、魔法使いが作る薬とは違う薬があり、それを使えばいいのではないかと言ったが、国王は
それが効かないから呼んだのだと言う。
国の世継ぎが身体の弱い男子だということは、森の奥住まいの魔法使いの耳にも入っていた。国王が
他国からも薬を調達していることも知っている。
だが、それでよくなったという話は流れてこな
かった。それどころか、次の世継ぎは誰になるのかという噂で持ち切りのようだった。
今の第1候補に上がっているのは国王の弟の息子なのだが、この息子は国王になることを望んでおらず、自分は従兄を支える立ち位置を希望すると公言していた。このことから、さらに後継について色々な憶測が飛び交っていた。
王妃は気落ちし、寝込む息子の側に付添、自室と息子の部屋以外、外へ出ることがなくなっていた。
だからといって「蘇りの業火」とは、あるかどうかもわからないものに頼るのは…と言い返すと、一冊の古びた本を魔法使いによこした。
その本には封印として付与された魔力の微かな片鱗と痕跡があったが、効力としてはすでに賞味期限切れ。そのため、国王も開くことができたと思われた。
ページも開かず見つめる。本の中身は見なくてもわかった。魔法使いの家にも同じ物、もちろんオリジナルがあるからだ。
2冊存在しているとは聞いていなかったことから、誰かが、オリジナルを勝手に読み、書き写して封印していたものと考えられる。
とにかくペラペラと読んでいくと、やはり同じ文面
同じ挿絵。完璧な写しだった。
しかしこの話は100年以上前のもので、魔法使い達
でさえ「昔話」として語られる類のもの。この話が本当の事だと知っているのも、家系最後の魔法使い
だけ。
国王はそこに書かれていることが、絵空事だとしても、できることは何でもしたい。と凄みをきかせて
魔法使いにつめよった。ガゼボの周りを取り囲み、息を潜める騎士達に気づいている魔法使いに、断る選択肢は用意されていなかった。
返事に困っている魔法使いに国王もただで頼むわけではないと言い、書面を出してきた。
手に取り読んでいくと、そこには、「蘇りの業火」を
献上後、速やかに城に魔術機関を設立し、魔法使いをそこの機関長とする。という文言が記されていた。
もちろんしっかりとしたルール作りの後、市井での魔術の使用も許可され、1世紀前の状態に近い国を目指す事を確約するという内容だった。
魔法使いは、これまで力を隠しながら街で生活するという肩身の狭い思いをしてきた魔法使い達が、己の能力を発揮できる日がくることを思い、悩んだ末に国王の頼みを受けることにした。
馬車に乗り、森の奥の家に戻った魔法使いは、
早速探索準備に取り掛かった。
必要最低限の暮らしをしていたため、かき集められる物は少なかったが、道中の資金は国が用意してくれるので、道々足りないものを補充していけばいい。
後は、攻撃型の魔術の勉強が必要だと、古びた書物を引っ張り出して、練習を始めることにした。
1人の生活なので、護りの魔術だけ使えれば充分。
魔法使いのいる森に入ってくる者などいないかったので、攻撃魔法は積極的に学んでこなかったのだ。
まず書物は持って行けないので、覚えるしか
なかった。
探索に出かけるのは1週間後、それまでに最低3つは覚えたいと気合がみなぎってきた。
久しぶりの高揚感に、月が昇ったことも忘れ、学びを深めていった。
次の日、覚えたことを実践していると、また知らない男が魔法使いを見つめていた。
赤黒く長い髪が、後でひとまとめにされ、ぼんやりとした真っ黒な瞳。病的に白い肌。それなのに唇は真紅。醸し出される雰囲気に、魔法使いは身構た。
男はゆっくりと魔法使いに近づきながら、ちょうど手を伸ばしてもギリギリ届かない距離で立ち止まり、「お前は魔法使いだな…」と聞いてきた。
すでに魔法を使っている現場を見られていたはずなので、反論することはできないと、頷く。
すると男は、自分は死神で、魔法使いの命を持って帰らなくてはならない。だからこれにサインをしてほしいとどこからか取り出したカマの上に書類を乗せて、魔法使いの前に差し出た。
人の首などアッサリ切れそうな、研ぎ澄まされた
カマ。魔法使いは手を切らないように書類を取り、
読み始めた。
読んだからと言って、はいそうですがとはなら
ない。魔法使いは1週間後、探索に出ることに
なっているのだから。
魔法使いは、その事を話しながら書類を燃やそうとすると、書類は火を弾き返し、死神のもとへと
戻った。
青白い顔が、さらに白くなっていった。そして両手で髪を鷲づかみにすると、困った困った!と慌てるのだった。
様子のおかしい死神に、距離を置いたまま理由を聞いてみると、死神は地面に両手をついてうなだれた
姿でポツポツと話しだした。
死神は、その世界では珍しく魂を狩るより、人と仲良くなるのが好きなのだとか。そのため、どの死神よりも仕事が遅い。
仲間からも仕事を取られる事があり、気がつくと
仕事の依頼をもらえなくなってしまったということだった。
死神の世界では仕事をしない者は、無に返される。
そんな事になれば生きた人間と話もできなくなる。
人間が大好きな死神は、どうにかならないかと、
上司に相談した所、長い付き合いということも
あり、最近めっきり数の減った魔法使いの魂を
1つ持って帰ってこいと言われたらしい。
しかし死神は寿命の残った人間の魂を狩っては
いけない事になっている。そのため、今回は特別な書類を持参したとなるわけだ。
見つけた魔法使いの寿命の残数が多い場合、本人との交渉で了承を得ることができた場合に限り、その場で狩り取ることができるという書類。
魔法使いは、死神に同情する気持ちもあるが、今は
この世界の魔法使いが、逃げ隠れせずに生きていける時代を取り戻す方が先なのだと、説明した。
死神は、魔法使いの話を聞くうちに、青白い肌に赤みが差し、ぼんやりとした瞳がキラキラと輝き始めた。そしてとうとう、自分を一緒につれていって欲しいと懇願してきた。
魔法使いは、旅に適していない体つきの死神を連れての道中を想像し、困ると断ったのだが、断れば断るほど喰らいついてくるので、観念して連れて行くことにした。
ただ死神ということは隠し、魔法使いの頼みで同行してもらうことになった親戚ということになった。
そして1週間後。攻撃魔法もなんとか3つ使えるようになり、見送る者もいないまま、死神と2人で国を
後にし、遥か遠い「蘇りの業火」のある
”不死の荒れ地“へと進む。
魔法使いにとって、死出の旅になることにも
ありや無しや…。
サポートいただけましたら幸いです。とても励みになります✨これからの活動の力になりますのでこれからもよろしくお願い致します🌸
