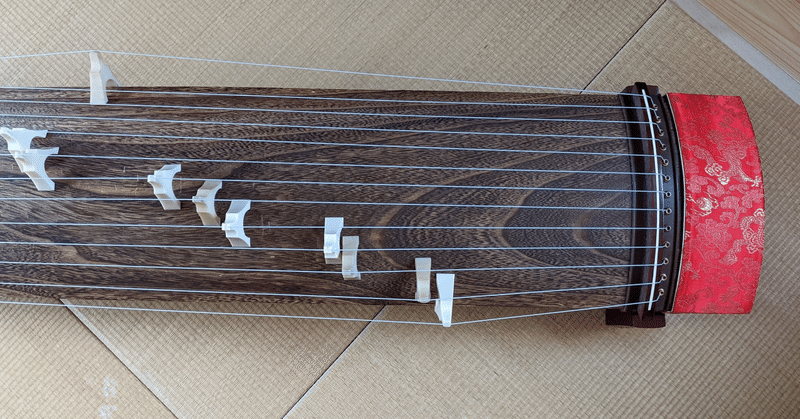
Photo by
honey_manya
日本音楽にふれる その2
箏曲の授業が終わりました。たった2時間ですが、和楽器にふれる時間はとても貴重でした。難しかった〜と言いながらも、楽しそうに演奏している生徒たち。何かができるようになることに、どこか満足そうな感じでした。
暗号?

これは箏曲の楽譜です。
筝は通常13本の弦の楽器を使います。
座って奥側から、
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 斗 為 巾
と、弦に名前が付いています。
楽譜の最初の部分は、「七 七 八」とあるので、七の弦、七の弦 八の弦
というように、弦を弾いていきます。
ギターのタブ譜に近いでしょうか?
◉という記号は、一拍お休み、休符になります。
巾の隣りカタカナのヲがついているときは、半音下げるという記号です。
この場合、左手で弦を半分くらい押しながら、右手で弾くことになります。
この半分くらいの加減が意外と難しいのです。自分の耳を頼りに、音を調節しなければなりません。
普段なら、五線譜を見ることが多く、このような楽譜を目にするだけでも、新鮮な気分になります。また、自分で音を調節して作り出すことも、ピアノとは違った感覚が得られます。
音楽って本当に奥が深いですね。
今度は、ウクレレとカリンバにチャレンジしてみたいです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
