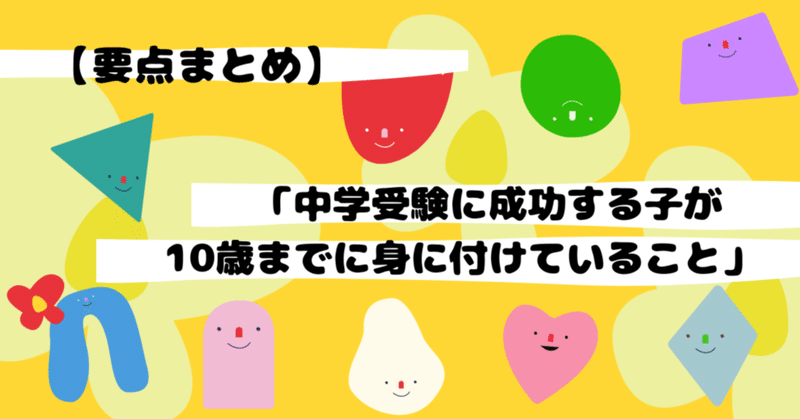
【要点まとめ】『中学受験で成功する子が10歳までに身につけていること』
現役保育士・日本語教師オススメ本
『中学受験で成功する子が10歳までに身につけていること』
タイトルに「中学受験」とあると、「うちの子は関係ない」と思われる方もおられるかもしれませんが、実際に読んでみると、受験関係なく参考になる点が多々ありました。
小学生のお子さんがいる親御さん方、ぜひ参考に読んでみてください。
Kindle Unlimited(読み放題)に登録すると、30日間タダで読めます!
登録はコチラから↓↓
低学年のうちに取り組みたいこと
1.小さい頃から生き物に触れておく
昆虫や動物、植物に触れる機会をなるべくたくさん作る。
そうすることで、観察力が養われ、おのずと「比較」「分類」ができるようになる。
仮に虫が苦手な子、興味のない子でも、桜は春・セミは夏など、季節ごとの代表的な動植物はおさえておくこと。
2.積極的に絵を描かせる
幼児期から絵に親しみ、低学年になったら、動植物に触れたときに、それらの絵を描かせる。興味があるなら、恐竜などでもOK。
絵を描くときに、こまごまと観察することで、発見・感動をもたらす。
また、絵を描くことで養われる注意力・集中力・識別能力は学力につながる。
3.記憶力を上げるには
日常的にかんたんな絵日記をつけたり、親子で交換日記をしたりする
かるたやカードゲーム(神経衰弱など)でトレーニング
親の質問で「思い出す」訓練
「今日の算数は何をやったの?」
「帰り道、○○ちゃんと何をお話したの?」など
4.しつけが学力を左右する
挨拶の習慣
時間厳守、整理整頓の習慣
朝型のリズムで生活
単語だけで会話をしない
単語だけ言えば相手にわかってもらえる習慣は、国語力の育成を阻害する。幼少期から文章で会話をすること。
✕「消しゴム」
○「そこにある消しゴムを取ってほしい」
5.その日やることを決める
1年生のうちは親が「今日はこれとこれをやろうね」と声掛け。
2~3年生になったら、1週間でやることを親が決め、その日にやることは子ども自身に決めさせる。
タスクが終わったら、シールやスタンプでチェックしても◎
6.習い事で伸ばせる力
オススメは「宿題」のある習い事
課題をこなし、上達する体験、「続けてよかった」という体験ができる。学校以外の人間関係が築ける
感情のコントロールを覚える
気分に左右されずに毎日決まったことをこなす練習になる。
持続力は、家での向き合わせ方次第。気分で動いてもいいことを覚えさせる機会になってしまっては本末転倒。
7.学校や家以外での学び
親子でお出かけ
体験教室など、日常とは違う世界
買い物をしながら学ぶ(単位、計算など)
旅行はプランを立てるときから一緒に楽しむ
子どもにはさまざまな経験、体験をさせるとともに、どんなときも親子の会話をたくさん持つことで、より多くを学び、知識を定着させることができる。
8.ご褒美はうまく活用する
ご褒美は必要なし!→自分から勉強に意欲を見せている子
ご褒美を活用する!→「ドリルやりたくない」などグズグズ言っている子
ご褒美は、やる前に提示して「目標」にさせるのがいい方法。
親子でルールを決めておく。
9.外で遊ばせる
文字を書くには体力が必要。受験も体力が必要。
幼少期から、体を動かす楽しさを覚えさせる。子どもが体を動かしたくなる環境を整えることが大事。
低学年のうちに、気を付けるべきこと
「先取り学習」は逆効果
低学年のうちは、算数と国語を徹底的にやるべき。
計算や漢字など、算数と国語に関する基礎をくり返しくり返し行って、確かな力にしていくことが正しい学習の順序。
基礎力がついていけば、やがて思考力はきちんと備わってくる。
「つるかめ算」や方程式を早々に教えるより、文章を読んで分析する必要のない図形や数の性質、パズルを学習する方が適切。親のかかわり方
【無意味に褒めない】
・好きなことをやっているときは、褒める必要はなし
苦手なこと、嫌いだったはずのことで頑張ったときが、褒めるべきとき
・結果でなく、努力したプロセスを褒める
【否定的な口ぐせに注意】
・「どうせ続かないよ」
「無理でしょ」
「(習い事や塾が)いくらかかっていると思っているの」
などの発言は、子どもの自己肯定感を下げる。
・ため息をつかない
【ピンチをチャンスに変える声掛け】
・諦めないことを覚えさせるのは低学年のうち
・「諦めそうになったとき」こそ「諦めない子ども」に育てるチャンス
少しヒントをあげる、休憩するなどして、最後まで取り組ませる。
そのうえで「あなたは諦めない子ね」と声掛けを。
低学年~中学年での勉強のしかた
1.読む
読書を押し付けるのは逆効果
本に気軽に触れ合うことから始める
本好きな人は、子どものころ、家にたくさん本があった場合が多い。図書館を利用する
本に触れることが大切なので、読めなかった本や途中でやめてしまった本があっても構わない。登場人物になりきって読んでみる
説明文にも触れる
幼少期の子どもが読む本は、物語がほとんど。図鑑やガイドブックも立派な教科書になるので、数行書いてある文章も読み聞かせたり、読ませたりする。
2.書く
ていねいな字は、必要な時だけで良い
「自分の名前だけ」など、ポイントを決め、ていねいに書かせる練習を。
声掛けは基本的に「ていねいに」だけにする。
きれいな字を書くことに集中して思考が止まってしまったり、思考の速さに書くスピードが追い付かず、思考を遮るおそれがある。絵日記で短い文章から
低学年のうちは2~3文の短文で十分。そのかわり、無理のない程度に毎日書かせること。毎日書くことで文章量も増え、長文も書けるようになっていく。
3.計算
「10歳の壁」というのを聞いたことがありますか。
一般に「10歳の壁」とは「抽象的なことや文章題で挫折すること」ですが、私は反復 練習にも壁を感じます。10歳までなら反復練習の習慣が身につきやすいです。
ところが10歳をすぎると、作業をくり返すことが苦痛に なってきます。10歳をすぎてから反復練習を習慣化するのはとても 難しいです。現に私の塾でも、10歳までは30分間の計算練習をする ことができた子どもたちが、10歳をすぎる頃からは、30分間の計算 練習をしていられない、ということがたびたび見受けられます。
10歳までに分数のかけ算・わり算を反復練習
分数のかけ算・わり算は小学6年で習うが、その時には反復練習を苦手とする年齢に達している。市販のドリルを使ったり、親が問題を作ったりして、小学4年までにどんどん練習させる。理屈でなく、ひたすら練習する
低学年の算数は、パズルがおすすめ
理想的な家庭環境
成績が上がる勉強場所は、「リビングルーム」
1人きりで勉強させないこと。
親の目が届きやすい場所で取り組ませる。
学習状況を把握するとともに、手が止まったときにヒントを与えるなど手助けができる。「積極的に学ぶ姿勢」は家庭でつくる
・親も読書をして感想を聞かせる
・一緒に問題を解いたり、わからないときは一緒に調べたりする
・子どもが「先生役」親が「生徒役」で復習させる
人に説明するとより深く理解できる
高学年での勉強のしかた
1.「丸つけ」と「解き直し」で成績が上がる
子どもの学力を左右するのは、丸つけと解き直しの習慣。
小学5年までは親が丸つけ、もしくは親が見ているところで本人が丸つけをする。
丸つけは、○か✕だけをつけることがポイント。
↓
✕のついた問題は、もう一度解かせる。
何度も解けないようなら、ヒントを出すか解き方を教える。
「解く→丸つけ→解き直し」で1セット。
2.毎日少しずつでも、必ず勉強する習慣を
高学年になったら、毎日必ず勉強することを習慣づける。
やる気があろうがなかろうが必ず勉強することを教え、習慣化。
ただし疲れている日は、分量は調整し、内容も易しめのものにして、あっさり終わらせる。
3.「勉強しなさい」と言っていい
勉強をしない子の親がしてはいけないこと
子どもが勉強する意欲を見せるまで待つこと
子どもが意欲を見せるまで待つ時間がもったいない。
子どもの学習意欲を高めながら、同時並行で最低限の課題に取り組む必要がある。「気分任せ」を覚えさせないこと
「気分が乗っていると勉強するが、乗らないとしない」としていると、中学・高校に入っていよいよ気分次第で動く人になってしまう。
高学年になったらむしろ親はしっかり言うべき。
4.かけ算・わり算も暗算させる
計算に限っては、筆算を書かずに暗算の訓練をするのが正解
「確実に」「ゆっくり丁寧に」でミスをしないのは良いことだが、入試ではそのスピードのなさが命取りになることが。
計算が速い子の計算ミスは直せるので、幼少期に育てるべきはスピード。成長してからミスを減らしていきましょう。
5.家庭環境
漢字一覧表・地図など、リビングやトイレの壁など目に入る場所に貼る
その日の調子よりも、生活リズムを優先する
睡眠時間はしっかり確保する
成功するために、家庭でできること
夫婦で教育方針をしっかり話し合い、決める
学校や塾に相談する
ただし、最初から最後まで学校や塾の仕事ではない。まずは家庭できちんとやらせる努力をし、うまくいかない場合だけ学校や塾に相談する。子どもの心を見極める
中学受験をするにしろしないにしろ、大切なのは、子どもが心をすり減らさないこと。
子どもの心に余裕があるか、いつもチェックすること。芸術センスを磨いて、学力を伸ばす
音楽や図工、体育も学力のために必要。
芸術的センスは、勉強のセンスに通じるものがある。
音楽で養われるリズム感、図工で培われる観察力や想像力、体育で身に付く筋肉や運動能力、どれをとっても学力に影響を及ぼす。
芸術分野の授業や、日常生活の遊びも、長期的に見れば学力向上につながっている。
10歳までは「読み・書き・計算」で土台をつくり、日常生活や学校生活での思考力、発想力、表現力を学ぶこと。それが10歳以降の成長につながる。勉強には順番がある
10歳になる前は、基礎学力を身に付けるために、反復練習など単純作業をするとき。低学年では、論理思考のトレーニングを勉強のメインにしないこと。日常会話でも、「主語・述語」をしっかりと
「受験のための勉強」にしない
子どもには、今取り組んでいることが、将来につながることをしばしば伝える。
勉強の目標は、短期的には中学受験合格、中期的には大学受験合格、長期的には「なりたい自分」になる。これを意識させてあげること。
くわしく読みたい方は、こちら↓↓
今ならKindle Unlimited登録で無料で読めます◎
Kindle Unlimited(読み放題)登録はこちらから↓↓
最初の30日間は、無料です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
