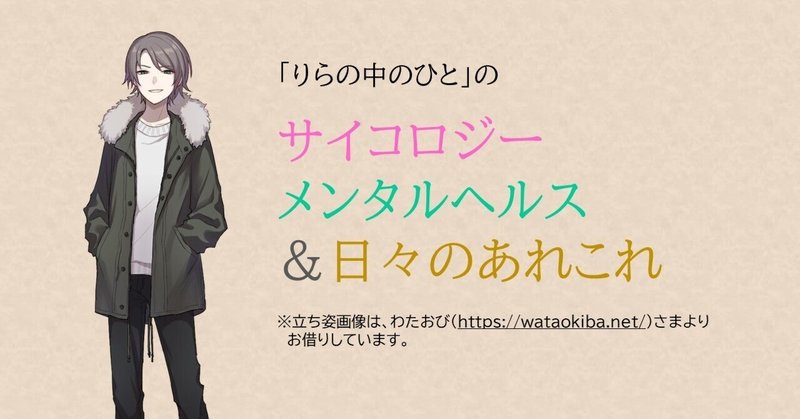
【シリーズ摂食障害Ⅲ・#4】 摂食障害と就労:就業場面での摂食障害の実態
【シリーズ摂食障害Ⅲ・#4】 摂食障害と就労:就業場面での摂食障害の実態
「サイコロジー・メンタルヘルス&日々のあれこれ」
摂食障害の症状が、当事者の社会生活に与える影響について連載しています。前回までは、低体重に対して医療が取りうる労作制限について、ガイドラインをもとに紹介しました。今回から、「摂食障害と就労」という大きめのテーマについて論じていきたいと思います。
1.就業場面での摂食障害について
労働者に対して雇用主(企業)は、労働における災害を予防するなど、労働者の安全と健康に配慮した、快適な職場を保つことについて配慮義務を負っています(労働安全衛生法、労働契約法など)。当然、雇用主(企業)による配慮義務の範囲は、労働者のメンタルヘルスにも及んでいます。
ただ、労働分野におけるメンタルヘルスへの関心は、うつ病や適応障害(職場での明確なストレスによるもの)などに限られ、摂食障害について注目されることはまれでした。それでも、いくつかの調査研究が行われ、近年では日本摂食障害協会による、当事者の視点からの調査なども行われています。以下、その内容や結果を踏まえ論じていきます。
2.国民のやせの状況
もろもろの議論の前提として、我が国の「やせ」の状況について、最初に触れておきます。
国民健康・栄養調査(令和元年)※1によれば、平成21年から令和元年におけるやせ(BMI<18.5)の者の割合は、男性では3%台後半~5%程度、女性では10%台前半~12%前半で推移しています。特に20歳代の女性では、やせの者の割合は、同期間では最大で29%(平成22年)、それ以外の調査年でも20%程度と、きわめて高くなっています。
就業場面での労働者のやせの状況も、概ね変わらないものと推測されます(法で実施が義務付けられている定期健康診断などで、データは捕捉されていると思われるのですが、それを引用した学術論文等を私が読めていないので、“推測”です)。やせの者全てが摂食障害であるわけではなく、また低体重でなくてもむちゃ食いなどに苦しむ摂食障害当事者もいらっしゃいます。ただ、労働者(を含む一般人口)の少なからぬ割合に、摂食障害の可能性が示唆される者が含まれる点を、強調しておきたいと思います。
3.事業所側でのアンケート調査※2とその結果
大阪産業保健推進センター登録事業所のうち、従業員数300名以上の事業所を対象とし、半数弱(537社)から回答を得た調査では、食行動ややせ・肥満についての顕在事例(相談を受けたなど事例化したもの)のある事業所は7.9%、潜在事例(事例化してはいないが心配な従業員がいる)のある事業所は24.3%でした。食行動異常での対応困難例のあった事業所は4.5%でした。
大阪の企業の従業員(メンタルヘルス講習参加者)への調査では、神経性やせ症が疑われる労働者の割合は0.27%(男性0.21%、女性0.50%)、神経性過食症が疑われる割合は0.21%(男性0.21%、女性0.22%)でした。「夜食症候群」(現在の診断基準ではおおむね「むちゃ食い binge-eating 障害」に該当する)が疑われる割合は12.9%(男性13.9%、女性10.2%)でした。
4.潜在事例が多いことが伺われる
この結果から読み取れることは、(少なくとも神経性やせ症については)実際の日本人の体形についてのデータと、職場において摂食障害が疑われるケース数との間に乖離が大きく、(そもそも心配の対象にもなっていない)潜在事例が多いのではないか、ということです。当事者が自らの疾病性に気づいていない、気づいていても援助や治療を求めない、周囲もやせ過ぎや食行動の異常(排出行為やむちゃ食いなど)に気付いていない、といった事情がありそうです。
ただし、のちのち触れますが、就業場面で当事者が直面する困りごとは多々あります。治療するしないにかかわらず、職場での困りごとへのケアや配慮を考え直す必要があるように思われます。
【引用文献】
※2 井上幸紀、岩崎進一、山内常生ほか 2010 摂食障害と就労 精神神経学雑誌112(8) pp.758-763.
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
