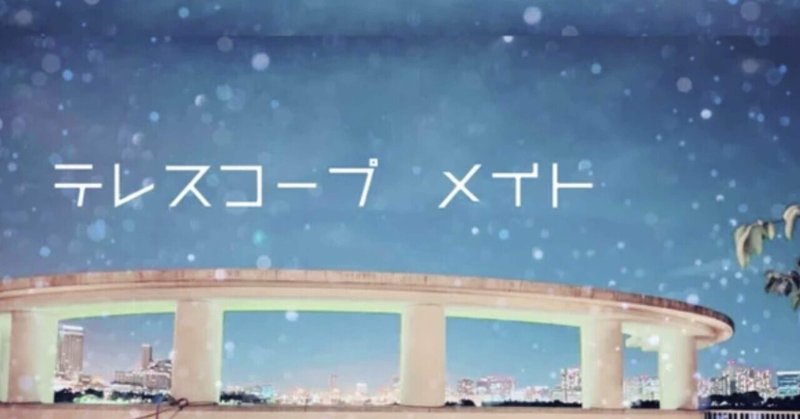
【テレスコープ・メイト】第4話-火のないところの煙‐
【第1話】
【第3話】
2070年9月。
伸弥は、その様子を、固唾を飲んで見守っていた。
ぐっ・・・・・
自分の中に、こらえようのない、怒りなのか、絶望なのか、哀しみなのか分からない感情の渦が駆けめぐる。
言葉にならない、声が漏れる。
◇◇◇
10.記録
聡一郎と伸弥が務める『テレス』の社内では、人事異動の話がささやかれていた。既に、個人的に社長室に呼ばれ、役職がひとつ上にあがった社員もいた。伸弥もつい最近、宇宙開発事業部の部長就任を命じられたばかりだった。
聡一郎と伸弥は、『テレス』がまだ駆け出しのベンチャー企業だった頃、初めて新卒採用で入社が決まった同期である。仕事ができて統率力のある聡一郎は、伸弥よりも先に管理職の仕事を任されるようになっていた。伸弥は、そのことを羨むような気はなく、むしろ、聡一郎がテレスの社長になるということは、社の誇りだとさえ捉えていた。
そんなふうに、同期の昇進を心から喜べるような、『テレス』は、働き心地の良い会社だった。
社員一人一人が自分の仕事に責任を持っている。それだけではなく、何か新しい事業を立ち上げようとしたときには、誰が先陣を切って切り開いていったとしても、大手を振ってついていきたくなるような、そんな社員が数多く揃う、恵まれた会社だった。
『テレスの仕事論』とか『テレス実践!採用の仕方』なんてメディアでも紹介されることもあったが、これは、日本を代表する大企業として名誉的なことであると、伸弥は鼻が高かった。
そんなテレスを、トップの座で守ってきたのは社長の延沢で、彼ももれなくそんな尊敬できる社員のうちの一人だった。誰もが、社長のことを、慕っていた。
しかし、そんな延沢も、今年で60歳になる。延沢は、月移住の身体訓練を50歳の頃から受け続けており、いつか月へ移住するのも時間の問題だろうと、そう思ってはいた。月移住の年齢制限は設けられてはいないが、医師の診断がなければ、そもそもロケットに乗ることが出来ない。
9月に入り、伸弥が聡一郎の役職であった宇宙開発事業部長に任命されたことで、聡一郎の次の役職はどこになるのかと、社員たちの話題は持ち切りだった。
中でも一番の有力な説は、延沢社長が退任し、月へ行く前に、聡一郎が社長に就任するのではないか、というものであった。伸弥も、社長になるなら聡一郎しかいないと、そんなふうに思っていた。
そして今日、ついに、聡一郎が、延沢から社長室に呼ばれたのだ。
これは、親友の華々しい門出だ!!!
どんな顔でお祝いしようか。
そんなふうに、ついにんまりしてしまうほころびを抑えつつ、伸弥は、社長就任の瞬間を映像に収めようと、社長室に向かう聡一郎の跡を追っていた。
伸弥は、社のムードメーカーだった。若干のお調子者は昔からの気質であり、延沢も、そんな伸弥のことを、何をしてもあまり咎めず、可愛がる節があった。
伸弥は、いつものようにゴープロを回す。
『君を、テレスの社長に任命します。』
その瞬間をとらえ、気の利いた音楽を流しつつ社長室に突入し、前社長と新社長で握手など交わしてもらう姿を収めよう。そんなふうに、思っていた。
つい、5分前までは――。
―――――――――――――――――✈︎
「私が、社長ですか…?」
中から、聡一郎の狼狽えた声が聞こえてくる。
何をそんなに、驚いているんだ・・?聡一郎が次期社長なんて、皆、周知の事実だったはずなのに。
2人は、伸弥の想像していた雰囲気とはまるで異なる様子で、なにやらずっと会話を続けている。声を殺しているようで、よく聞こえない。
その時だった。
「・・・田邊君!!
我々【人間】が絶滅危惧種に認定される日と、私たちがこの地球上に住めなくなる日・・・どちらのほうが、先に来ると思う?」
急に、延沢が大きな声を出した。
なんなんだ!?
伸弥は、思わず扉を少しだけ開けて、その隙間から、はっきりと、その声を聞いた。
「・・・地球がなくならないからこそ、人類の方が、先に滅びる。どうしてだと思う?」
「・・・・・・・・。」
「・・・人類が月に移住するために、我々が、地球の資源を、月へ、運んでいるからだよ。」
伸弥は、その言葉の意味を、まるで理解することができなかった。
社長が!?
一体、なんのために!?
「戦争や殺し合い、騙し合いや差別なんて、一切起こらないような・・・
そんな場所はもう、こうやって、新しい【星】をつくることでしか守れないし、人類は、変わることはできない。」
延沢の、悲しい声だけが響いた。
「地球は、変われなかったんだ。生み出しても搾取され、努力して稼いでもそれは結局どこかで起きている戦争のための資金となり、この地球に本当に必要な資源は、どんどんと消えていく。
・・・だから、その前に、月に、必要なものを、大切なものを、失くしてはいけないものを、送り続けてきた。・・・10年間、ずっと。」
伸弥は、静かに、ゴープロの電源を切った。
そして、ゆっくりと、自分のデスクに戻った。
◇◇◇
社長室を出ると、聡一郎は脇目も降らずに伸弥の下へ向かった。
「伸弥!」
オフィスルームにつくなり、伸弥に声をかける。
振り返った伸弥の唇に、少しだけ血がにじんでいることに気が付く。
物思いにふけると、伸弥は下唇をかむ癖があることを、聡一郎は知っていた。
「伸弥。・・ちょっと、話せるか。」
「あぁ・・・。」
聡一郎は、場所を変えて、伸弥に今延沢から聞いたすべてのことを、伝えようとしていた。こういうときに頼れるのは、同期であり、一番の親友である伸弥しかいなかった。
オフィスルームからも社長室からも一番遠い休憩室を選び、聡一郎は、話を始めようとした。
どこから話そうか。まだ、聡一郎の中でさえ、整理がついていなかった。
「ごめん。」
ふいをつくようにして、伸弥が、聡一郎に向かって頭を下げた。
「え・・・?」
「聡一郎。お前、俺、社長になると思ってたんだよ。その、呼び出しかなって、浮かれてた・・。社長就任おめでとうって、俺、そんな、いつもの勢いで、ゴープロ回してたんだ。
さっきの、、、、全部・・・聞いてた。」
ゴープロの再生ボタンを押す。
先ほどまでの、重く張りつめた社長室での2人の会話が、そのまま、再生された。
「・・・っは、、、」
聡一郎は、思わず、笑えてきた。
「ははは、伸弥、お前、、、ははっは。」
なんだか、身体の力が、抜けていくような気がした。
そして、もう、自分たちのやるべきことは、決まったんだ。そう、固く思った。
「・・・ありがとな。伸弥。」
怒りとも、哀しみとも、迷いとも、戸惑いとも言えない。
今、2人の間に、会話は何も要らなかった。
これまでの、延沢との10年間が、走馬灯のように流れてくる。
優しい社長だった。
いつも、テレスを誰よりも愛し、責任を持って、守ってきてくれた。
社員の皆が慕い、大好きな社長だった。
だけど、今、この事態を止めることができるのは、これを聞いてしまった自分と、たまたま聞いていてくれて、図らずとも会話の録音までしてくれていた伸弥だけだと、そう思った。
「これから、どうするべきなんだろう・・・。」
伸弥の声は、少し震えていた。
「警察に・・言うべきなんだろうか。」
いや、違う。
警察に行き捜査が始まってしまったら、我々とは遠いところで事実の解明が進んでいく。根本は、もっと違うところにあるんだ。
「伸弥。行こう、宇宙省に。」
聡一郎は、それしかない、と、咄嗟に思った。
◇◇◇
11.宇宙省
テレスが抱える仕事のうち、大きな利益を得ているのは2つ。
1つ目が、今年の4月に開発に成功したばかりの、『rocketjet』。ロケットのエンジンを旅客機に応用し、より速く・より遠くまで飛べる飛行機だ。1機目のおひろめ飛行では、羽田ーNY間を20分で繋いだことで、テレスの名前は世界にとどろくこととなった。
そして2つ目が、ライドテント。聡一郎と伸弥が所属していた宇宙開発事業部が、アメリカのNAZAと共同開発した月面テントのことだ。ライドテント内に、地球と全く変わらない重力を供給できるシステムが搭載されている。
テレスが、内閣府『宇宙省』より、rocketjetの運用を国と提携して進めていってほしいと打診されたのは、2055年のことだった。
それ以降、ずっと宇宙省とテレスは、rocketjetの運行やルール、航空法の改正に至るまで、沢山の会議を重ね、安全に運行できるよう伴走してきた。
当時、延沢が宇宙省からの打診を快諾した時は、少なからず、怪訝な顔をした社員がいたことも事実だった。
「私たちは、ずっと宇宙まで飛ぶことができる旅客機をつくるために、エンジンを改良し、製作と研究を重ねてきたんです。
それなのになぜ、今更我々のエンジンで、アメリカやヨーロッパに飛ぶ必要があるんですか?」
オンライン化が進み、海外との会議も容易に可能となった現在、わざわざ高い費用を出して「行く」ことに重きを置く必要などない。誰もがそう思っていた。そこへ研究費の投資をするのも、無駄な気がした。
そんな時に、よく延沢は言っていた。
「誰もが、オンライン化を図る時代になっただろう。”行く”ことを売りにする企業が、一気に少なくなったんだ。企業にとって、ねらい目をつけるのに必要なのは、そういう、”供給がすくなくなったところに投資する勇気”なんだ。ライバル企業が手をひけば、そこはテレス一強となるだろう。それが大切なんだ。20年後。いや、10年後には、テレスのエンジンは、世界のエンジンになる。見ていてごらん?」
いつも、楽しそうに、そんなふうに社員に声をかけていた。
延沢は、あくまでも、「行く」ことに、こだわり続けた。
それと、なにか、関係があるのか・・・?
そのカギを握っているのは、宇宙省かもしれない・・・。
◇◇◇
聡一郎は、内閣府宇宙省の河野にアポイントメントをとった。
テレスの次期社長として、最初の仕事だと思った。
「伸弥。河野さん、15時から20分だけなら空くって。社長になったのは、案外良かったかもしれない。こういう時に話が通るのが早いよ。」
延沢が言った通り、テレスはみるみるうちに世界のテレスに成長を遂げた。
rocketjetもライドテントも、日本が誇る2つの事業を担っているテレスは、宇宙省にとって大切な企業のひとつだ。聡一郎が、社長就任の挨拶に伺わせてほしいと電話をすると、無理に本日中に時間を調整してくれた。
―――――――――――――――――✈︎
「ようこそ、お越しくださいました。田邊聡一郎さん、速手伸弥さん。」
聡一郎と伸弥は、15時ジャストに河野の待つ宇宙省へと出向いた。
伸弥とともに河野に会うのは、これが初めてではない。宇宙開発事業部のツートップとして開発・研究を重ねてきた2人は、これまでも、運用に向けて何度か直接河野とは話したことがあり、面識があった。
「次期、社長だそうですね。」
河野の、物腰の柔らかい話し方は、先ほどまでの聡一郎と伸弥の興奮を、少しばかり沈めてくれた。
「・・はい。変わらぬご愛顧を」
「いい、いい。何か、聞きにきたんだね。」
話を遮るようにして、河野のほうから本題を切り出され、聡一郎と伸弥は、思わず顔を見合わせた。
「宇宙に関することが、この先の10年・・・いや、5年の間に、確実に、国民の中で、ものすごくシビアな問題になる。私も延沢くんも、危惧していたことだった。今、月移住者は、34人だったね。これで延沢くんが、月に行けば、35人か。」
「・・・もう、月移住の話は、ご存知だったんですね。」
聡一郎は、少しだけ驚く。
自分たちに話す前に、宇宙省には先に話を通していたのか。
聡一郎の中で、数時間前まで心から信頼していた延沢のことが、少しずつ、信用のおけない人物へと変わっていっていく実感があった。
「・・・あぁ。日本が危ないとなれば、アメリカ、フランス、シンガポール、カナダへ・・・地球が危ないとなれば、今度は月へ・・・人類は、そんなふうに、移動を繰り返す。
お2人は、そう、思っていますか?」
2人は、河野から急に問いかけられた。
「え・・・?」
「宇宙開発は、人類の夢であり、希望だと、延沢くんとは、何度もそんな話を重ねました。延沢くんは、よく言っていた。”だから、まずは月に行くために、人類がひとつにならなければならない”って。私は言ったんだ。一致団結なんていう思想が、もう古いんだよと。人間は、ひとつになんかなれない。だからこそ、その象徴として、いろんな人がいることを受け入れようと、2000年代初期~中期にかけて”多様性”なんていう言葉が使われるようになったんだろう。それでも延沢くんは聞かなかった。”河野さん、それは違います。人類は、ひとつにならなければならない。くだらない争いを続けている暇は、もうないんだ。人類全員で、月に移住できる明るい未来が必要なんだ。だからこそ、rocketjetを世界各国に向けて運行し、rocketjet専用空港をつくるべきなんだ。月人口が増えれば、ライドテントの増築も必要になる。月で争うことなく暮らしていけるようになるために、今から、全ての国が隣国にならなければならない。私は信じている。人類、皆、兄弟じゃないですか。争ってはだめなんです。”って。何度も、何度も、そう言いに来たのです。」
聡一郎と、伸弥は、顔を見合わせた。
じゃあ、なぜ・・・!?
”地球の資源を、月へと運び出している”
延沢は、そんな言い方をした。
しかも、10年もかけて、ずっと、運び出し続けてきたという。これまで、月での生活は100%人工都市として全て完結しているものと報道されてきた。そうではないとしたならば、報道されない、本当の月は今、どのような状況なのか…!?
河野は、知っているのだろうか。
知っているとしたら、どこまで知っている・・
知った上で、延沢を肯定し、力を貸しているのだろうか・・・
日本政府として・・・?
聡一郎と伸弥は、河野に、なんと切り出せばいいのか分からず、逡巡していた。延沢が言っていた全てのことを河野も暗黙の了解としているのだとしたら、国家として大変な問題を抱えていることとなる。逆に、知らない上で、ただ延沢の熱い思いに加担しているのだとしたら、これを知らせなければ、聡一郎と伸弥は延沢と同罪だ。
なんと言えばいい・・・
正解はなんだ・・・
必死に考えるものの、答えを出すのに腹を括ることが出来ない。
2人の目は、宙を泳ぐばかりだった。
◇◇◇
【第5章】
【企画書】
なぜこの作品を創りたいのか、という自分の中の道標を見失わないように、IntroductionとProduction noteを書きました。
◇◇◇
【 マガジン 】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 このnoteが、あなたの人生のどこか一部になれたなら。
