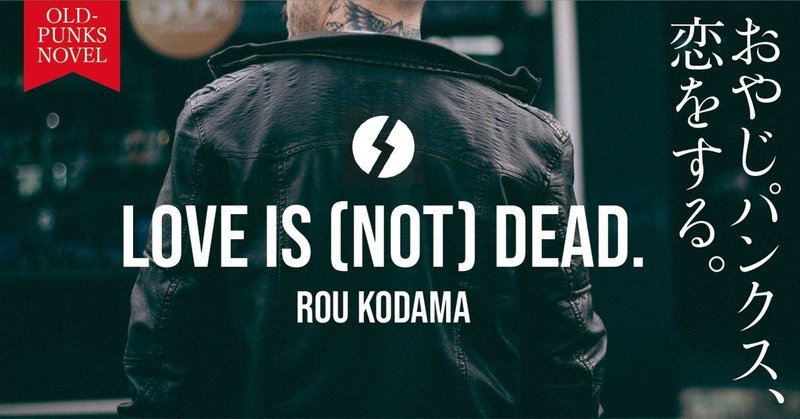
おやじパンクス、恋をする。#062
「どれどれ?」俺とiPhoneの間に顔を差し込んでくるカズ。「おお、おお、いいじゃん」感嘆の声。
「ちょっと、こら、どけよ」俺はその汚ねえ金髪の頭をどかして、画面に表示された集合写真、涼介タカボンと俺と彼女とが写った集合写真を見下ろした。
ああ、忘れてた。撮った撮った。俺がカウンターの端から手をいっぱいに掲げて、全員を撮ったんだった。
写真の中では、顔半分しか映っていない俺の向こう、手前に彼女、涼介、ボン、タカの順で座っている。
涼介タカボンはなんか死にかけの海藻みてえな、あるいはイケてない組体操みてえな、両腕をクネクネと揺らすようなポーズで映っており、背景がそんなバカ共なので余計に、その前で笑顔でピースをする彼女は可愛く、綺麗に見える。
「ちょっと貸せよ」俺の手からiPhoneを奪い、カズは写真を凝視して「いやー、いいわ。すげえ可愛いな。同年代にはとても見えねえよ」と感心したように言う。
俺は俺で、マジでカズが彼女を好きになっちまったらどうしようと不安になる一方で、自分の女を褒められるという男としては最高に嬉しい出来事をたっぷりと堪能した。まあ、まだ俺の女じゃねえけど。
「いやでも、実物の方がもっといいね。何て言うか、ムチムチして、セクシーだ」目を閉じ、腕を組んで言う俺。頭の中には俺が想像で作り上げた彼女の裸体が展開し、また股間に熱いものが集まってくる。
「あれえ?」
カズが突然言って、俺は目を開けた。カズは顔をしかめ、iPhoneの画面を傾けたり、自分の頭を傾けたりしながらその写真に見入っている。
「な、なんだよ、どうしたよ」何となく嫌な予感を覚える俺。
「もしかして彼女、倫子っていわねえか?」
「は? なんで知ってんだよ」驚く俺。
「やっぱり」
カズはそう言って、妙に沈んだ表情をした。俺は繊細だから、もうその顔を見た時点で心のなかに黒い網みてえな不安がブワッと広がった。なんだ、なんだよ、なんでそんな顔をしてんだよ。
「なんつうか」苦笑いを浮かべ、カズは頬をボリボリをかく。「こりゃまた、なかなかの女に惚れたもんだ」
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
