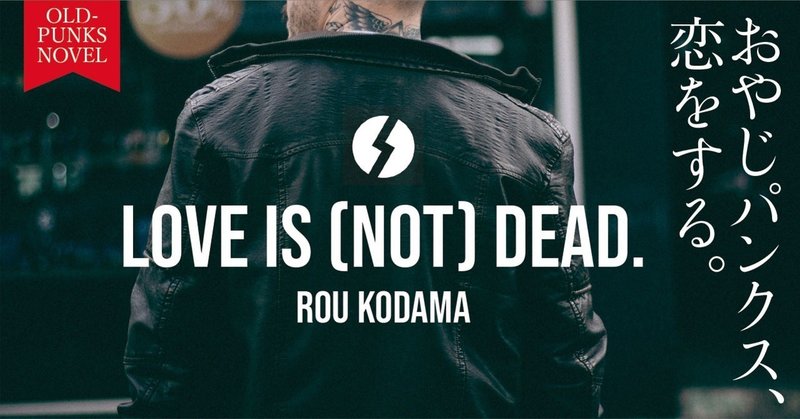
おやじパンクス、恋をする。#109
「そうだよ、めでたしめでたしってことじゃねえかよ」
「そうは問屋が卸さねえわけよ」とカズ。
「はあ? 問屋が何卸すって?」涼介が意味なく噛み付く。
「だから卸さねえって言ってんだろ」
「いや、だから何を卸さねえかって話を……」
「もういいよ、何の話だよ」と俺。
カズはギターを壁に立てかけると、あの怪しい巻きたばこを取り出して火をつけた。そしてそれをうまそうに吸いながら、こないだ雄大を連れてきた時に俺に話した内容を、噛み砕いて説明した。社長秘書の美樹本さんに頼んで調べてもらった、あれやこれやのことだ。
「ふうん、なるほどな」とボンはいち早く納得したが、涼介やタカはそれぞれに納得のいかなそうな顔をしている。
「梶商事は要するに、親父さんの代の頃とは違う会社になっちまったってことさ」と俺。
「違う会社?」とタカ。
「ああ、名前は同じでも、中身がすっかり変わっちまった。いまや梶商事は、嵯峨野のものになりかけてる。そうだろ?」
俺は彼女に言った。彼女はふうっとため息を付いて、頷いた。
「まあ、嵯峨野と既存社員との間でもいろいろあるんだけど、まあざっくりまとめるなら、そう言わざるを得ない状況ね。……ていうかあんたたち、いつの間にそんな情報通になってたわけ? 涼介がパーティーに現れた時点で、嫌な予感はしてたけど。出どころは……雄大?」
彼女はいつの間にか、ちゃんとしてた。酔った感じはなくなって、まるで会議中みてえな真剣な顔になってやがる。
なんとなく違和感っつうか不安っつうかがよぎったが、俺はカズとちらっと目線を交わして、「ああ、そうさ」と頷いた。
彼女に驚いた様子はなく、むしろ最初からそれがわかってたみてえに頷き返し、話を続けた。
「私は最初、嵯峨野のやり方に反対だった。既存社員も、やっぱり梶パパの下で働いていた人たちだから、反発してね」
「まあ、そりゃあそうだよな」
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
