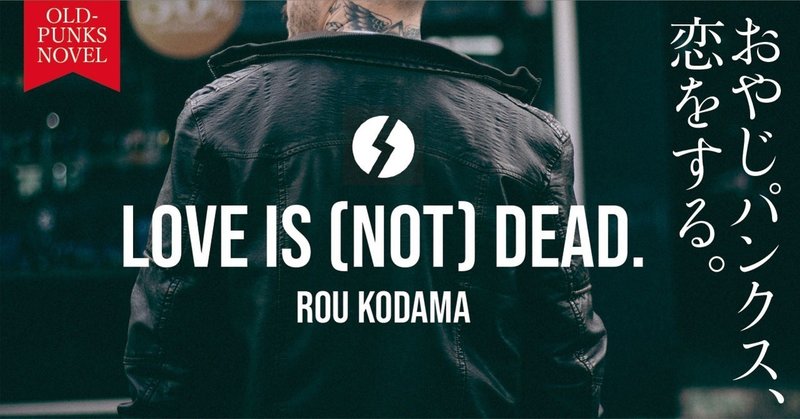
【エピローグ】おやじパンクス、恋をする。#246
「ちょっと、もう注文したの? 待っててくれてもいいのに」
伝票にペンを滑らせながら厨房へと入っていくおばちゃんを見て、彼女が言った。
「うるせえな、てめえが遅れるからだろうがよ。のんびり洋服選びやがってよ」
「あ、もしかして見えてた?」
カラカラと笑い、俺の隣に腰を下ろす。
「ああ、ああ。見えてましたよ。カーテンの隙間からバッチリな。つうか、ちゃんとカーテン締めるクセをつけとけって言ったろ」
「じゃあ私は――」
俺の言葉を無視して彼女がメニューを見始めたので、俺はカズに「それで? それで?」と続きをせがんだ。
カズは気難しい人間国宝みてえに目を閉じて腕を組み、頷いた。
「で、その間に俺様はだな――」
そう、ボンが嵯峨野とやりとりしている間、カズは自分の親父――じゃあなく、なぜかあの執事っぽい美樹本さんに電話をかけ、事情を説明した。だが、その反応はいまいちだったらしい。
「なんか意外にも他人事な感じだったんだよ。坊ちゃん、もう大人なんですから揉め事はもう……みてえなよ」
「あれ、そうなの? つうかなんで最初から達巳さんにかけねえのよ」
「バカお前、ウチの親父がどういう人間か知ってるだろうが。俺が助けてくれつって泣きついて、よっしゃ任せろなんてなると思うか?」
「あー、まあ、ならねえだろうなあ」
確かに、あの天下の神埼達巳が、“坊ちゃん”をそんな甘やかすとも思えねえ。むしろ、情けねえこと言ってんじゃねえ、つって激怒されそうだ。
「そんな親父もまあ、美樹本さんの言うことは割合聞くんだよ。だからそっち側から攻略することにしたわけ」
わかる? ここよここ、と自分のこめかみ辺りを人差し指でトントンする髭面次期社長。うぜえ。
「でもよ、美樹本さんもダメだったんだろ?」
「それがよ、ダメじゃなかったんだなあ」
「なんでよ」
「いやな、これはある意味ラッキーだったんだけど」
まあまあ坊ちゃん、と繰り返していた美樹本さんが、あるワードを聞いた途端、急変したらしい。
「なんだよあるワードって」
「……佐島さんだよ。その名前出したら、美樹本さんがいきなり怒り出してさ」
「つーことは、美樹本さんは佐島さんを知ってたのか」
「ああ、知ってるも何も――」
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
