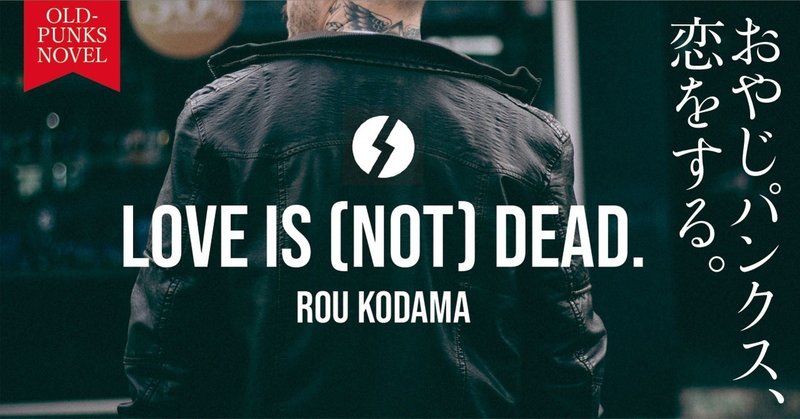
おやじパンクス、恋をする。#080
店の前で、いかつい爺さんがパイプ椅子に腰掛け、くわえタバコで新聞を読んでいるのが見えた。
細面に白い短髪、鋭い目つき。見ようによっては昔の俳優みてえだ。
だが悲しいかなその服装は、くたびれた白い下着シャツにステテコに雪駄っつう下町丸出しのスタイル。
店の中だと暗くて読めねえからっつって、堂々と公道に椅子を置いて新聞を広げてやがるんだ。まったく、相変わらずガラが悪いぜ。
「おーい、おやっさん」
俺が言うと、おやっさんはゆっくりと俺を見て、忌々しげな表情を浮かべてそのまま静止した。二秒、三秒、そして何も言わずにゆっくりと新聞に視線を戻した。
いや、おかしいじゃん。俺、客じゃん。
まあいいや、こんな対応にはもう慣れてる。なんたって二十年来のお得意様だ。
俺は勝手に店内にまでバイクを移動して、なんつうか、日当たりの悪さっつうよりは床に染み込んだオイルのせいなんじゃねえかと思うような、暗いピットに停めた。
「ちょっと見て欲しいんだけどさ」俺はおやっさんの背中に向かって言ったが、完全無視。「今日、どうしても使いてえんだよ。エンジンさえかかりゃ、なんとかするから」と一方的に言って、ピットの脇にあるボロボロのソファに転がった。
やがてチッ、と舌打ちが聞こえて、迫力ある顔がこちらを振り返る。
「このクソガキが、何時だと思ってやがる」
「八時半」俺はなんて事なく答える。
「チッ」
おやっさんは渋々といった感じで立ち上がると、俺の愛車のそばに腰を下ろし、点検を始める。
俺はタバコに火をつけて、もう何年も前から置きっぱなしのバイク雑誌を手にとって、グラビアページを眺める。
かわいそうに、アソコのとこにピンク色のペンでおめこマークが書かれている。今日び中学生でもでも書かねえようなアホな落書きだが、でも、何度見ても笑っちまう。
あのバカ、自分とこの店の雑誌にまでこんなことして、何が楽しいんだろうな。
「涼介は?」俺は笑いを噛み殺しながら言う。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
