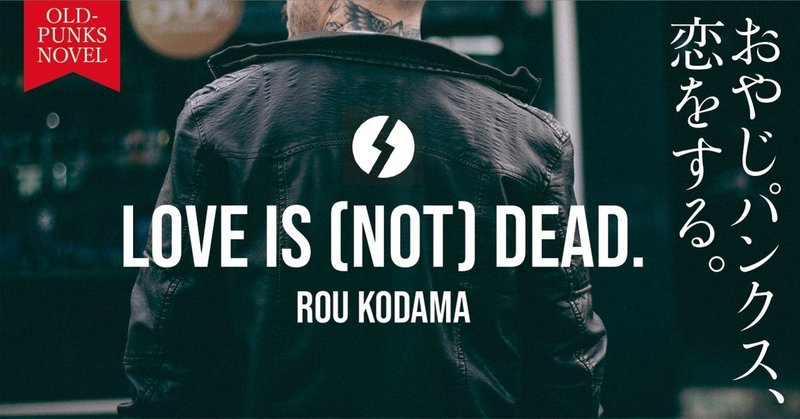
おやじパンクス、恋をする。#151
別段どこに行く予定もねえんだが、俺の足は自然と大通りから裏通りへ、人の少ない方向へと自動運転よろしく移動を始め、こっそり彼女を盗み見れば随分とスッキリした顔つきで楽しそうに歩いている。
何度か道を折れ、そこは古い商店街の跡地、御多分にもれずシャッター街と化して来年には取り壊しが決まってしまった一帯。さすがの彼女も変だと思ったのか、こちらをチラリと見上げた瞬間、俺はそこに偶然見つけた自動販売機が向き合った暗がりに彼女を連れ込んだ。
彼女の腕を引っ張って一番奥、つっても道路から二メートルくらいの壁に彼女を押し付けて、その首元に鼻先をうずめた。
そのまま首筋を上っていって彼女の柔らかそうな唇を奪おうとした瞬間、俺の尻ポケットでiPhoneがブビーブビーって激しくバイブし始めて、俺はもちろんそんなもん無視してやろうと鼻の穴ふくらませて彼女の唇めがけて猪突猛進、まさに童貞のガキ感満載の、とにかくことを済ましちまえばこっちのもんだと言うような焦りっぷりで、そんな一秒二秒っつう短い時間にあれいつの間にって感じで、全身がカーっと熱くなって球のような汗が額に浮かび始めて、余計に焦った俺は自分の唇をタコみてえにうにゅーって付き出して、その間も俺のケツではiPhoneが激しく身悶えしたままで、ああもう、クソ、見れば彼女はいたずらっぽい上目遣いで俺を見上げてて、やがてくすくすと笑い出した。
「電話、鳴ってるよ」
「あ? ああ、電話。いや、知ってるけど」
「出れば? 急用かもしれないし」
俺は仕方なくiPhoneを取り出した。こんな大事なときに水を指しやがって、どこのどいつだコラ――そして俺は、画面に表示された「涼介」って文字を見てため息をついた。
あのバカはいつもそうだ。自由業の身を最大限に活かして、相手の都合構わず連絡してきやがる。内容なんてあってないようなもんで、暇だから、ならまだましな方で、八つ当たりの対象にされたり、なんでもいいから俺を楽しませてみろみてえな、いやあんた何様? ってなことばっかで、まあ要するにあんまり気が進まねえ電話なわけだが、まあ仕方ねえ。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
