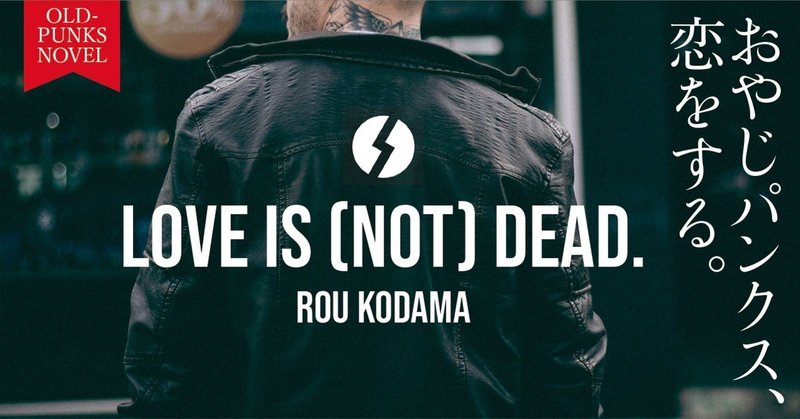
おやじパンクス、恋をする。#053
俺は“お坊ちゃま”に先導されて店に入ると、財布ん中から入浴チケットを取り出した。カズは割引券とか時には無料券とかをくれようとするんだけど、俺はそれを受け取らず、正規の値段で買ってる。
これは真面目に頑張ってるカズへの礼儀っていうか、ある種の投資っていうか、アルバムの曲ぜんぶYOUTUBEに上がってるけどCDはちゃんと買うみたいな、好きなアーティストに対するリスペクトとか応援に似てる感情なのかもしれねえな。
まあ、カズはそういう俺の対応を別に大袈裟にありがたがるわけでもなく、変なやつだなつって笑うだけだ。まあ、俺としてもそれでいいわけでさ。
とにかく俺は十枚五千円で購入したその回数券を一枚ちぎって、受付の姉ちゃんに手渡した。新しいバイトなのか、オレンジ色のモヒカン頭をした俺にギョッとしていたが、カズが「怖いよね―、こういう輩と付き合っちゃダメだよ」とか言いながら俺の肩を抱くのを見て、何をどう納得したんだろう、ホッとした顔をして「ごゆっくりどうぞ」だってさ。
「俺もうすぐ上がりだから一杯やろうぜ」ってカズの言葉に手で答えつつ、昭和の田舎町をイメージしたっていうレトロな食堂街の中を歩いて行った。
日曜の昼前ってこともあって客はそれなりに多い。
十時に開店した中華料理屋や洋食屋、たこ焼きやら焼きそばやらかき氷やらを売る売店なんかに囲まれる形で、フードコートよりは高級そうなテーブルが置かれている。その合間には細長い足湯スペースもあって、足をそのぬるま湯に突っ込んだままビールなんかを飲んでる親父もいたしりして、なるほどここは天国かも知れねえな。流行るのも分かる。
暖簾をくぐって男湯のスペースに入ると、脱衣所では既に良い感じに茹で上がったオッサンたちが、ほかほかと白い湯気をたたている。銭湯独特の雰囲気だ。
考えてみりゃ赤の他人同士が集まって素っ裸になってんだから、奇妙な光景だよな。裸の付き合いとかよく言うけど、確かにこんな状況じゃ、嘘は通用しそうにねえ。
そういう意味じゃ俺と涼介タカボン、そしてカズとの関係と似ているかもしれない。俺たちは信頼し合っているっていうより、全員が極度の感情露出狂というか、脱衣所で素っ裸になるがごとく考えていることを隠さねえから、もう建前とか嘘とかが成り立たねえんだ。
ちなみに俺以外の奴ら、涼介タカボンがここに来ねえのは、言うまでもなくその身体に描かれた「お絵かき」のせいで、立ち入りが禁止されているからだ。彫り物に興味がねえ訳じゃねえが、銭湯に来れねえってのは結構なデメリットだよなあ。
ともあれそろそろ酔いが身体に定着し、二日酔いの工程に入りかけていた俺は、勢い良く服を脱ぎ捨てると浴場に入った。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
