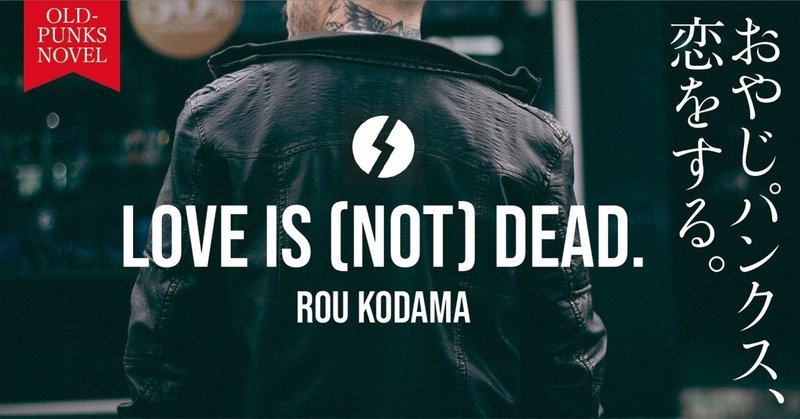
おやじパンクス、恋をする。#172
梶さんが亡くなった、という連絡を彼女から受けたのは、それから四日後の昼過ぎのことだった。
聞けば、俺が彼女の家に押しかける数日前から、梶さんはいつ亡くなってもおかしくないような状態が続いていたんだそうだ。
だが、さすが梶さん、医者が匙投げた状態でも何一つ弱音を吐かず、見舞い、というよりは最後の挨拶にやってくるいろいろな人間に、毅然とした態度を示しては、そして最後はスイッチがパチっと切れるみてえに、突然、亡くなったんだそうだ。
電話口の彼女は意外と落ち着いて、何度も大丈夫かと心配する俺に、「レッドブル飲んだから、平気」と冗談で返してくるくらいだった。
葬儀の手はずは既に終わっているとかで、もし都合が付けばとその日時と会場を告げた。自分の予定を確認するまでもなく、ああ、行かせてもらうよ、と答えて電話を切った。
仲間の中で梶さんを直接知っているのはカズだけで、涼介タカボンは名前を知ってるだけだ。
だけど、俺は全員に声をかけた。
実際に参列するかどうかってのは、それぞれの都合があるわけだからまた別の話で、なんつうか、彼女と切っても切れねえおっさんが死んだ、そのことを、俺と彼女とのことを(それぞれのやり方で)応援してくれた奴らに対してきっちり伝える義務がある気がしたからだ。
「昨日の夜遅く、梶さんが亡くなりました。葬儀は――」
そうメールを打つと、予想通り次々と電話がかかってきた。
元ぼっちで根暗な俺はどっちかっつうとメールをよく使う方だが、奴らは文字を打つ時間がうざってえと電話ばかりだ。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
