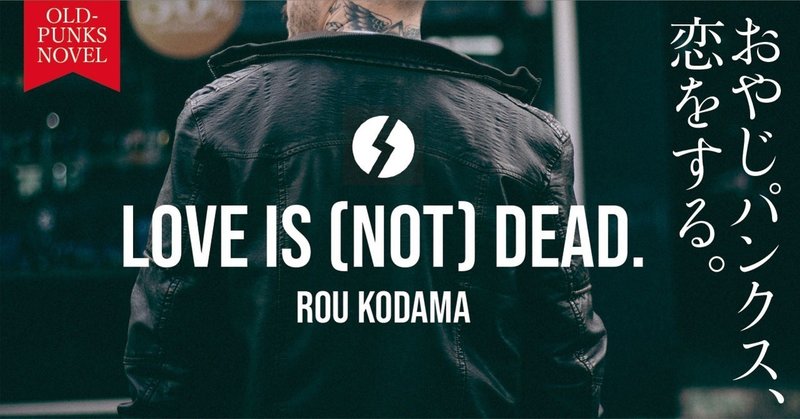
おやじパンクス、恋をする。#065
「いや、いつの間にか疎遠になった。親父と梶さんとの親交がなくなったとかじゃないんだろうけど、倫ちゃんが家に来たり、二人でどっかに遊びに行ったりとかはなくなっていった。俺が中学入った頃にはほとんど会わなくなってたんじゃねえかな」
カズが中学に入った頃。つまり……俺が彼女にくせえドブ川の脇で声をかけられた頃。
「なんで疎遠になったんだよ」
「いや、それはよくわからねえ。でも、単に年齢的なことなのかもな。中学1年なんて、女と遊んでるなんてクラスの奴らにバレたら何言われるか分かんねえみたいな年頃だろ。彼女といるのが恥ずかしくなってたんだろうな」
「ふうん。まあ、そういうもんか」
「最後に会ったのはいつかな……ああ、高校の卒業式かなんかの時だ。たまたま梶さんが家に来てて、珍しく倫ちゃんも一緒でよ。だけど、俺恥ずかしくてまともに彼女と話さなかった。適当に挨拶して、部屋に引っ込んじまった。それが最後。だからもう二十年近くは見てねえんだ、けど、分かるもんだなあ。彼女、変わってねえよ」
そう言ってカズはiPhoneに表示された彼女の写真を見る。
「ああ、だよなあ」思わず俺も同意した。
レストランの向かい、涼介に首根っこを掴まれて無理やり扉の中に頭をねじ込まれた時、目に入った彼女の顔を見て、一度だけ言葉を交わしたあの時の記憶が鮮やかに蘇った。
面影がある、なんてレベルじゃない。もちろん大人にはなっていたが、彼女はやっぱり、彼女のままだったんだ。
そこで俺はふと気付いた。つうことはさ……
「でも、つうことは、その梶さんっておっさんは、彼女の男って訳でもねえのか? 話聞く限りじゃ、男っつうより父親みてえな感じがするけど」
俺の言葉に、カズは一瞬表情を曇らせて、視線を落とした。そしてチラッと俺の顔を盗み見る。
「なんだよ、おい」
「いやよ」とカズは言いづらそうに続ける。
「なんだよ、言えよ」
「うーん」
「いいから、ほら」
「いや、はっきりしたことは分かんねえよ? 俺の話はだから、あくまで想像だけどな」
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
