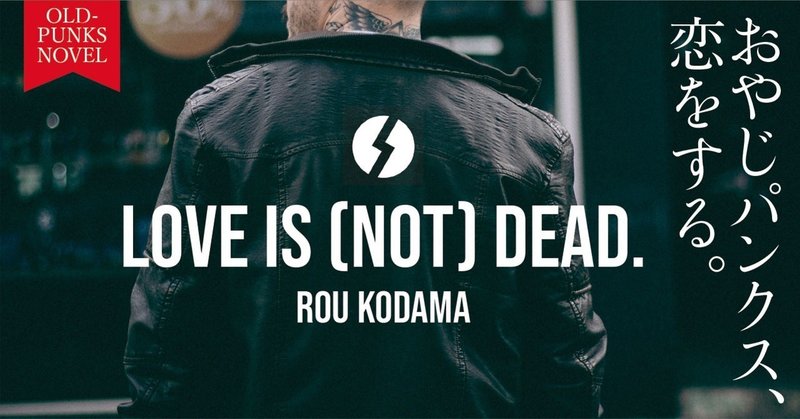
おやじパンクス、恋をする。#131
「このあいだ久しぶりに神崎と話したが、和弘がもう四十過ぎだってなあ。そら、歳もくうはずだ。雄大は男兄弟がいねえから、君らみたいな兄貴分がいると、俺も安心だよ」
「いえ、そんな」と俺。
「安心して死ねる」
梶さんはそう言って笑ったが、すぐに真顔に戻り、少しだけ視線を落とした。陶器製の灰皿を手に取り、トントンと弾く。
「そうだ、倫子のことだったな。あの子のことを、聞きに来たんだろう?」
不思議なもんで、唐突に核心に触れた梶さんの言葉に、俺は驚いたりビビったりはしなかった。梶さんの小さな目が、皺の間から、真っ直ぐに俺を見ていた。梶さんが自分を見ているということに、何とも言えない喜びがあった。
俺は梶さんを、好きになっていた。
人間、目を見りゃ分かるって言うが、確かにそうだと思える瞬間がある。
俺は、俺自身も気付かないくらいのスピードで、何かを――そう、何かを決意した。
「はい」
俺は言った。
「そうか」
梶さんは言って、若いやつにはとうていできそうもない、笑い顔にも泣き顔にも怒り顔にも見える複雑な表情をして、タバコをもみ消した。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
