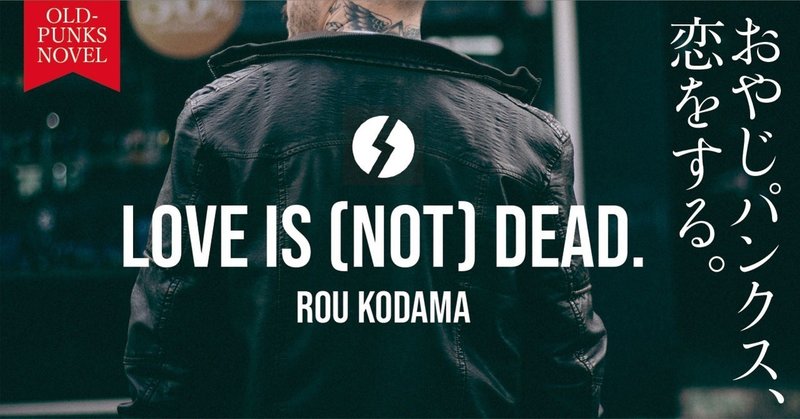
おやじパンクス、恋をする。#051
俺は再び大きなため息をついて、フライヤーを手に取ると、そのメッセージを書いている彼女の姿を想像しながら、ボールペンの跡を指先でなぞった。
……おいおい。
まるで少女漫画のシーンじゃねえか。いいオッサンが未練たらしく何やってんだよ気持ち悪い。
俺はわざと勢いをつけてフライヤーをカウンターの上に投げ置いた。とにかく外に出ないと。
窓が一つもねえここは、二十四時間夜のまんまだ。ガキの頃から宵っ張りだった俺に婆ちゃんはよく言ったもんだ。夜更かししたって構わねえが、朝になったらちゃんと外に出て、お天道様にご挨拶するんだよ。お天道様の光を浴びてりゃ何とかなる、眠くなったら昼寝すりゃいい、ってさ。
俺は狭い店内を忙しく動き回りながら片付けをしていった。それで気付いたが、帰る前に彼女は店の中を掃除してくれていったらしい。空き瓶やらジョッキやらはちゃんとシンクに置かれいて、洗われてこそいなかったが、水が貯められていて酒の嫌な臭いはしなかった。
俺は手早くそれらを洗って、簡単に金の勘定だけすると、もう一度冷たい水を胃に流しこんで、店を出た。
お天道様の光をギャンギャン反射してる金属扉には、昨晩書いた「本日閉店」と書かれたあの紙がまだ貼ってあって、その文字の下に「マスター初恋相手とSEX中」という文字と、今どき田舎のヤンキーも書かねえだろう女のアソコを象ったあのマークが、蛍光ピンクのマーカーペンで追加されてあった。
このペンは間違いなく涼介のものだ。なんでかよく分かんねえけどあいつは常にこのピンク色の蛍光ペンを持っている。競馬新聞に没頭する親父が、みんな昔ながらの赤青鉛筆を持ってるみたいに。
俺はその紙を乱暴に引っぺがすと、ぐしゃぐしゃと手の中で丸めた。怒ったわけじゃない。怒りなんて全くない。むしろ相変わらずの悪ふざけに大笑いしちまいそうな気分だ。
そう、これが俺らの日常だ。
俺らは多分、死ぬまでこんなことを続けるんだろう。この店を始めたのも、あいつらや他のバカどもとバカやるためだ。
別に、恋人なんていらねえよ。
俺は胸に刺さった小さな針を引きぬいて、そこいらに捨ててやった。昨日は楽しい夜だった。久しぶりの彼女と飲んで、楽しかった。それでいいじゃねえか。
夜通しのクーラーで冷えきった身体が、太陽の熱で少しずつほぐれていく。店に鍵をかけた俺は、時々利用するスーパー銭湯、つってもそこまでスーパーでもねえんだけど、駅前から無料バスが出てて便利だし、酒を抜くっていうよりは単純にでっけえ風呂でくつろぎてえって理由で、そのスーパー銭湯に向うことにした。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
