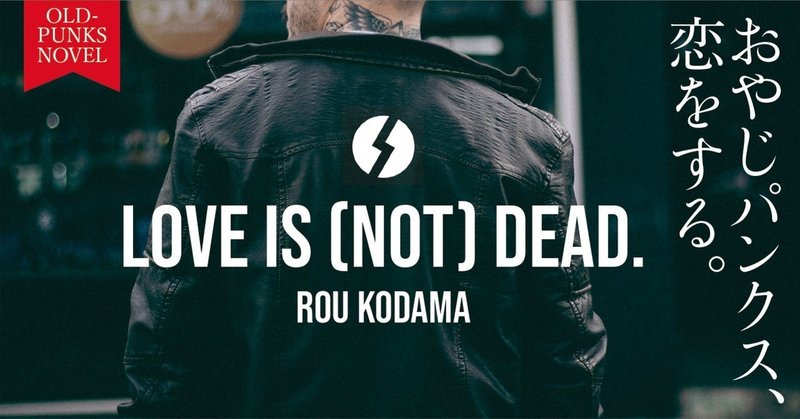
おやじパンクス、恋をする。#061
「で、それが誰なのか、お前は知らねえんだよな」汗をかいた瓶ビールを持って戻ってきたカズは、髭に覆われた頬をボリボリ掻きながら言った。
「まあな。金貸しだって話だけど、よく分かんねえ。ただ、七三分けの真面目なサラリーマンじゃねえことは確かだな」俺はあの小太りのバカのことを思い出しながら言った。
結果的には臆病なガキンチョだった訳だが、あのチンピラ風の格好や、携帯で話してた時の口調なんかを考えるに、俺らとはまた違った意味での反社会的な存在だろうことは想像できる。
そして黒幕はその「父親」だ。
俺の経験上、中途半端にツッパってる奴の親父は、割とガチで気合入っている場合が多い。まあ、カズの親父も然りだけど。
「ただ、彼女の親に金を貸してるくらいなら、もうそれなりの年寄りのはずだけどな」とカズ。確かにそうだ。
「まあ何にしろ、そこを攻略しねえことにはお前は彼女とズッコンバッコンできねえわけだ」
「クソ、なんて言い草だ」
俺は吐き捨てるように言ったが、実際問題カズの言う通りだった。やっぱりこれ以上の事を知りたければ、彼女に直接聞く以外に方法はなさそうだ。
だけど、彼女はそんなことをして、嫌がらないだろうか。
首を突っ込んでくるなと、俺を否定するんじゃないか。
実際、彼女の方から俺に連絡先を聞くこともなかったわけだし、彼女としては、一日付き合って適当に楽しんで、それで十分、それ以上はもういいわ、って話なんじゃねえのか。
「つうかさ」カズはそれまでとは違う口調で言った。
「なんだよ」と俺。
「写真とかねえのかよ。彼女、結構な美人さんなんだろう? しかも、外人風」
「てめえ、俺のハニーをそんな目で見るなよ」
「いやまだハニーじゃねえだろ。それ以前に、見てねえ。なあ、ほら、写真だよ」
そんなもん撮ってねえよ、と言おうとして、あれ? と思った。
何となく記憶の中に引っかかるもんがあって、俺はiPhoneを取り出すと「写真」のところを押した。
「あ」俺は思わず声に出した。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
