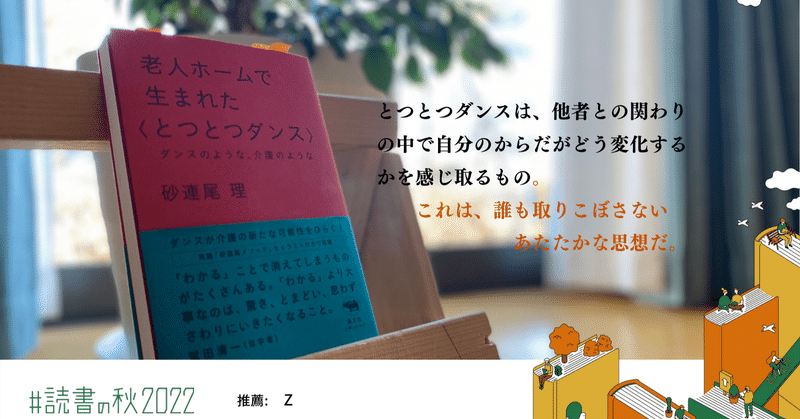
運命の本を携えて、そこらじゅうでダンスを踊ろう。
9月下旬のその日、下北沢にはどしゃぶりの雨が降った。
うるんだ目をした若者たちが何人もびしょびしょに濡れながら慌てて駅の構内に駆け込んでくるのを見て、にぎやかでカラフルだな、と嬉しくなった。
学生時代、毎日のように通っていた下北沢だけれど、15年ぶりに訪れた私は完全に浦島太郎状態。毎日のように通っていたのは南口のマクドナルドでアルバイトをしていたからで、それを選んだのは、この街のカラフルな空気が一番感じられそうな場所だったから。モノクロームな私の世界に少しでもこの街のカラフルな色が投影されたらいいなと思っていたのかもしれない。
シモキタは、ちゃんとカラフルなまま、素敵な街に生まれ変わっていた。
新生シモキタで友人と訪れた本屋。ふと目に止まったのが、カラフルなシモキタにぴったりな真っ赤に装丁されたこの本だった。
作者は「砂連尾理」(じゃれお おさむ)さん。お恥ずかしながらお名前を聞いたことがなかったし、どこからどこまでが名字なのかも、読み方もさっぱりわからなかったけれど、帯にかかれた鷲田清一さんの文字が胸にささった。
「わかる」ことで消えてしまうものがたくさんある。「わかる」より大事なのは、驚き、とまどい、思わずさわりにいきたくなること。
私はいつも何かをわかりたいと思っていて、でもいつもわからない、とも思っていて、だからいつも何かを追いかけているような気がしていたから、迷わず購入した。
長野の自宅に戻った後、しばらく寝かせてから読了し、衝撃をうけた。あのどしゃぶりの東京で、久しぶりに会った友人たちと話したことをつなぐような内容が、この本には描かれているような気がしたからだ。
コミュニケーションが成立するように見えたとき、実は大量のディスコミュニケーションが消えている。僕たちは、そこに目を向けることから始めようとしていた。(中略)意味の中で落ち着いてしまうものが、ディスコミュニケーションにより引き出される。
「できること」の差を競い合う現代社会において、「できないこと」に目を向ければ、彼女は「障害」を持ち「欠損」を抱えた身体として、ある意味「存在しない」もののように受け止められてきただろう。(中略)目に見えては「動かない」彼女の身体から出ている何かが、確かに僕を踊らせた。
あの日、私達は下北沢のビアガーデンで「無意味なことに時々とても救われる」と話し、高田馬場のウズベキスタン料理店で、「できてもできなくてもいいということが大事なのではないか」と息巻いた。
これはシモキタが引き合わせてくれた運命の本…!と息を飲みながら読み進め、思わず出版された時期を確認すると、2016年だった。
知らんかった。
こんなにも前に、自分と同じようなことを考え、本にされている方がいらしたなんて。
私はというと、2015年に出産した第三子ハルが重度の障害を持っていきていくことを知って、人生で初めて「障害をもって生きるということ」というテーマの蓋を開け、「はいこんにちは、はじめまして」と挨拶をする間もなく日常の荒波にもまれながらハルと他者や社会との関係について考え続け、間に相模原障害者殺傷事件という恐ろしい事件が起きて「いや、こわい。やめて!」と遠ざけたり、やっぱり近づけたりしながら、私にとってはようやくたどり着いた「できないことや無意味なことに落ちているものを大切にしたい」という考えなのだけれど。
(息継ぎをしないで読んだ皆さん、お疲れ様。)

じゃれおさん。
そんなおしゃれなお名前なのに、
なんでもっと早く言ってくれなかったん。
なんでもっと。
そんな気持ちで読み終え、赤い表紙を眺めながら罵った。
(赤い表紙に罪はないのだけれど。)
読み終わってから数ヶ月、無意味にリュックの中に忍ばせて持ち歩きながら、この本の存在をずっと文字通り背中に背負って反芻していたけれど、そろそろ肩こりも激しいのでリュックからおろしてやろうと思う。すぐに忘れてしまうので、反芻したことを残しておくべく、筆をとる。
そんなわけで、私にとってこの本は間違いなく今年一番カラフルに脳内に印象付けられた一冊になった。(2022年11月25日時点。)
「障害があるからこそ見える世界」に潜む線引き
障害のある方のアートが注目されたり、障害のある方の働き方を考えたりということが、社会の中で少しずつ増えてきた。こうした流れの中で、「障害があるからこそ見える世界がある」といったことが、書籍や映画、ラジオなど様々な形で発信され、とても心強く感じている。

着ているTシャツは第三子ハルが指先で描いた絵をプリントしたもの
と同時に、こうした中で話題にあがる「障害者」は、できないことはあれど何かしらの表現方法を持っているか、知的にコミュニケーションができる方たちを想定されていることも多く、不全感を感じることもあった。
我が家の第三子ハルは、言葉によるコミュニケーションは今の所できないし、自分の意志で思ったとおりに手足を動かすことも難しく(動くには動く)、明確な表現方法を持っていないし、知的にどの程度発達しているのかもわからないからだ。
「かわいい」だけで高貴な存在である赤ちゃん時代は終わり、独特の空気感をまとう少女時代もいつか終わりを告げることを、私はよく知っている。そうして周囲から注目されることが少しずつなくなっていったとき、わかりやすい表現や価値によって社会に働きかけることができない彼女は、社会の中に居場所や役割をちゃんとみつけられるのだろうか。彼女はどうしたら、社会の構成員として積極的に社会に参加していけるだろうか。(ケアされる対象としてだけではなく)
もしかしたら、それを一番確かめたいのは、未だに社会の一員としてのポジションを模索している私自身だったりするのかもしれない。そしてこれは、結果的に言葉が先行してしまっている「インクルーシブ教育(または社会)」を考える上でも非常に大事な観点なのかもしれないとも思う。
「とつとつダンス」という"思想”
「老人ホームで生まれた<とつとつダンス>」(晶文社)によると、「ダンスとはなにか」という問いを常にたずさえたダンサー・振付家の砂連尾さんが、ベルリンでの障害者とのダンスの経験を経て、京都の高齢者介護施設でダンスワークショップをはじめたのが「とつとつダンス」の始まりだという。

しかし、「とつとつダンス」は、介護の現場によくある、単なるケアの一種ではない。認知症や身体的に障害のある方、スタッフ、興味をもった子どもと大人、そしてダンサーである砂連尾さんが混ざり合うようにして、一見バラバラで無意味で不可解な動きしながら、かみあっているようないないような関わりのなか、一つのパフォーマンスをつくりあげるのが「とつとつダンス」だ。(説明がむずい…)
それはダンスという名のコミュニケーションのようでもある。
言葉がなくても、体に自由がきかなくても、目が見えなくても、耳が聞こえなくても、どんなにできないことがある人でもできる、からだとからだを開きあうコミュニケーション。からだとからだで感覚的に交わり合うことで、言語的な意味だけのコミュニケーションではこぼれ落ちてしまうものが、そこにはのっかってくる。
たとえば相手に好意を伝えたいとき、「好きだ」と言葉で伝えることもできるけれど、表情や距離感や息の温度や触れる感覚で、どう好きなのかが伝わることがあると思う。それは時々、「好きだ」と言葉で伝えることよりずっと奥行きのある表現だったりする。
こう理解したとき、私は安堵した。
だって、これなら、言葉がしゃべれなくて知的発達もよくわからなくて目が見えなくてからだも自由に動かすことができないハルも、排除されることはない。できないことが多いハルだけれど、ハルにも間違いなく、からだはあるのだから。
私達は、そこに「いる」ことや、そこに「ある」ことで、いつも何かを感じ取っているし、相手に何かを感じさせている。その道具は、言葉や絵や、これといって決められた形のものだけではない。空気を共にし、そこにいる/ある、ということが何よりも大事なことなのではないだろうか。
障害者は、いまの資本主義社会の枠組みから排除されがちな存在だが、彼らだけが持つ、この社会を生き抜いてきた知恵のようなものがある。そのことをベルリンで僕は感覚的に体感していた。また、生産性という点で、高齢者も社会的に価値が低いとされ排除されがちな存在だけれど、だからこそ彼らにもまた、僕たちが気づかない知恵というか何かがあるのではないだろうかと。
「とつとつダンス」は、他者との関わりの中で自分のからだがどう変化するかを感じ取るものであり、社会の中でどう生きるかということとかなり深いところで繋がり合っている、一つの思想だと思った。
誰もとりこぼさない、あたたかな思想だ。
「特別支援教育」に関する国連の勧告を、とつとつダンスから考える
2022年9月9日、国連の障害者権利委員会が、障害児を分離した特別支援教育の中止を含む改善点について日本政府に勧告をした。「強く勧告した」と各種メディアでは報道されており、その勧告の様子はドラマチックなものだったと伝え聞く。
私は後から知ったのでいくつかのメディアの報道からしか概要は知り得ないのだけれど、少なくとも文部科学大臣はこの勧告に対して、本人や家族に選択権があることや、通常学級での支援が不十分であることなどを理由に、特別支援教育の継続を表明している。
文科大臣の「中止しません」発言が否定的に取り上げられている記事が多いけれども、調べれば調べるほど、現場への教員配置のルールと必要人員にずれがありそうなことや、障害のある子を支援する「体制」など、問題は大変複雑に絡み合っていて、確かにすんなり「特別支援教育をやめましょう」と言えるものではない、というのも理解できる。
とはいえ国連の勧告も、目標とスケジュール、予算を含めた計画をたてていきなさいよ、といういわば方向性に関する勧告なわけで、今すぐやめろと言っているものでもなさそうだ。複雑な課題があるからこそ、計画と予算を、と勧告しているのである。それに対して、素直に「そうですね」と受け止めないのもなんだか子どもじみている。
そもそも「支援」とは、一方向なのだろうか。
そして、支援するのに必要なのは、本当に「体制」なのだろうか。

とつとつダンスでは、からだとからだを開き合い、誰かが誰かに対して一方向の作用を与えるのではなく、誰もが誰もに対して、そして誰もが誰もから、なんらかの作用をうけている。
というか、本来すべての人間関係は、そういうものだったんじゃないのだろうか。
空気をともにするからこそわかる/生まれるものがある。とつとつダンスで大事にされているような、「そこにいる」ということを感じ合う関係性が、今、圧倒的に足りていないような気がしてならない。
考えるべき課題はもちろんたくさんあるのだけれど、まずは、同じ空気をともにし、いる/あることを互いに感じ合う、ということを目標に設定するのはどうだろう。
見えていなかったものが見える、感じられなかったものが感じられる。お互いに、そこにいる/あるという状態が生み出すものは、計り知れない。それは、我々がどこかに忘れてきてしまったものを思い出すための、あるいはまだ知らない何かを知るための、扉になるかもしれない。
みんなそこらじゅうで踊ればいい
国連の勧告は、大前提として、教育現場においてマイノリティを分断し、なかったことのように錯覚し得る状況を作り出すことに問題を提起しているものだと私は解釈する。そしてこの分断は、教育のその先にある、社会の分断につながっている。だからこそ問題は大きく、深刻だ。
知らないことは決してニュートラルではなく、マイナスなのだ。恐怖を生み、それは時々憎悪に姿を変える。
私は8年前にハルを出産し、ハルと空気を共にしてきた。家族でインドに移住したときは、いつのまにかハル自身がメディアとなって私達家族を新しい社会とつないでくれたり、長男が不登校になったときは、生きる意欲をまっすぐに表現するハルの存在があったからこそ、型通りの考え方からはずれることが怖くなかった。

なによりも、ハルと過ごす時間は、一般的な社会のレールに乗れなかった自分自身の存在をやさしく肯定してくれた。ハルはもちろん支援が必要なのだけれど、同時に私達家族は、ハルに支えられている。それは、空気を共にして、たぶん砂連尾さんのいうところの「ダンス」を踊ろうとしてきたからこそ、なのだ。
一緒にいることで、相手を感じ、自分を感じさせる。
からだとからだを存在させ合うということをダンスと呼んでいいのなら、みんなそこらじゅうで踊ればいい。そこらじゅうで、ダンスを踊るようにあたたかな関係性が生まれたらいい。
一つ一つの関係性のあり方を、ダンスを踊るという名目のもと、自分も含め、人類全員に問いただしたい。
そして、きっとそれに一番救われるのは、やっぱり私自身だろう。
ね。
だから、
Shall we dance?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
