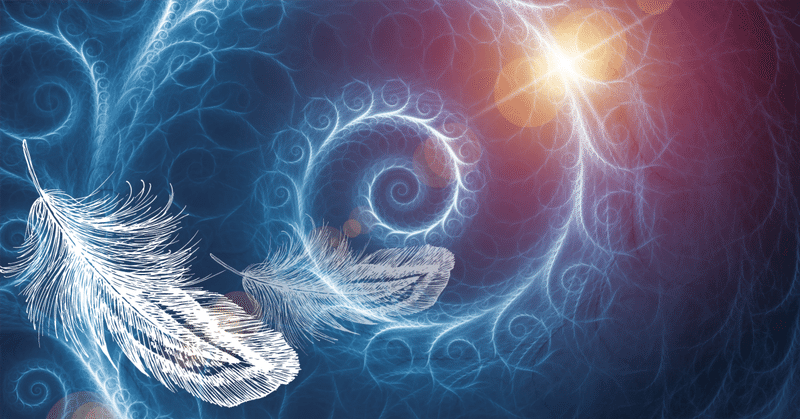
龍の淵に到るもの 羽生結弦の北京五輪「天と地と」
2022年2月10日北京五輪フィギュアスケート男子フリー、羽生結弦の「天と地と」はリアルタイムで見ることができなかった。前日練習のニュース動画で、羽生は転倒して足首を傷めたように見えた。試合前の最期の公式練習も早々に切り上げ、曲かけ前に氷を上がったと聞き「やはり」と思ったが、事実確定するのが嫌で考えないことにした。試合の時間帯は仕事と重なっていて、結果は何となく聞こえていたが、心を落ち着けて拝見したのは翌日になってからだ。
Yuzuru Hanyuのコールとともに颯爽と氷上に進む羽生。Beijin2022のロゴ上で構えた様子は顔色こそ青白いが成すべきことを知っている目だ。後退しながらスタートした数週間前の全日本選手権とは違い、羽生は前進で演技を開始。腕をクロスさせて挑みかかるような振りにはやはりこの方がふさわしい。
翻るようにターンしながらジャンプの軌道を描き、羽生は跳んだ。天に突き刺さるように高く、鋭く舞い上がった。前方に向けて踏切り、4回転半=1620度にはわずかに到らないかもしれないが1500度以上は確かに回っていたと思う。
右足で着氷し、次の瞬間に転倒したが、氷上に起き直る姿の滑らかさは成功したアクセルジャンプと何ら変わらず、流れは途切れない。ここが彼の凄いところだ。演技の2分40秒、あるいは4分の間に何が起きようとも、彼は支配力を失なわない。楽曲の元となった上杉謙信の物語を重ねながら追っている目には、続くサルコウジャンプの転倒から生じた揺らぎさえ、すべてを捨て去りたいという抑えがたい衝動に揺さぶられる謙信の葛藤のようにも見えてしまう。
羽生は鞭のように引き締まった体と恐るべきスケーティング技術を操り、全身を思うさまエモーショナルに撓わせ、国主としての義務と信仰心の間で翻弄され、揺れ動くヒーローをその身に憑依させてゆく。ステップシークェンスの終わり、琴の音で天を仰いだ羽生のすがるような眼差しが切ない。
しかし、高く差し伸べた両腕に剣を受け取った後の滑りはしたたかなまでに確信に満ち、その流麗なさまは深山幽谷を音高く流れる渓流のよう。重く、厳しく轟く琵琶と花吹雪を思わせる繊細な琴の旋律が交錯する「天と地と」は、直情的かつ重層的で変幻自在な羽生結弦の滑りそのものだ。
ラストジャンプはツイズルへとつながるトリプルアクセル。羽生のトリプルアクセルはいつだって美しいが、これまで見た中でも飛びぬけて高く、優美なアクセルジャンプだった。渦巻く星雲のようなスピンから身をほどき、天を仰ぐフィニィッシュ。その姿は空へと帰っていく何かと別れを惜しんでいるかに見えた。
普通の選手であれば、練習でも着氷していないジャンプが本番当日に成功する確率は低い。が、4回転半アクセルは競技人生の中で何度も跳べるとは思えないほど負担の大きいジャンプだ。ほかならぬ羽生結弦のことだから、怪我を回避できるぎりぎりの寸止め的な練習とイメージトレーニングによってをシミュレーションしておき、五輪当日のワンチャンスで完成させるような離れ業だってするかもしれないとどこかで思っていた。見方によっては4回転半アクセルの代わりに4回転ループを跳んだ2020年全日本選手権の「天と地と」の方がより美しくまとまった印象はあるかもしれない。「天と地と 2020」が優美な神楽であったとしたら、2022北京五輪フリーの「天と地と」は「理想の羽生結弦」に到達するための戦いそのものに見えた。三連覇への期待や度重なる怪我、端からはうかがい知れない様々な重圧がのしかかる五輪の、あの時、あそこでしか成しえない一期一会、唯一無二な羽生結弦の「天と地と」として完成していたと思う。
その後のインタビューで、やはり羽生は右足首をひどく痛めていたことを知った。
この完璧ではないけれど完璧以上に心に刺さる「天と地と」を見て、思い出したことがある。亡夫光太郎からはるか以前に聞かされた話で、光太郎が少年の頃、上の世代の若い能楽師が「道成寺」のシテを務める舞台を見た時のことだ。「絢爛たる挑戦 羽生結弦のロンド・カプリチオーソ」で触れた「石橋」と同様、「道成寺」は能楽師のイニシエーションとして重要な「披き物」の中でもとくに重いもののひとつ。ストーリーはよく知られた道成寺伝説に基づき、若い僧侶に恋して冷たくされた女が、僧侶が身を隠した寺の鐘を恨んで憑りつくという執心ものだ。
前半では白拍子の姿で現れた前シテが、舞の奉納を装ってじりじりと鐘ににじり寄る。舞台中央につられた大きな鐘が落下すると同時にシテは高く跳躍して鐘の中に姿を消し、中入りとなる。鐘に隠れたシテは暗闇の中、一人、装束を直し、面は前シテの寂しげな女面・曲見から恐ろしい角のある般若へとかけ替える。ワキ方が道成寺伝説を語り、呪文を唱えると、やがてじりじりと鐘が上がり始め、男への執着と鐘への恨みによって大蛇へと変身した女が現れる。
この日、鐘が上がり切ってシテが姿を現した時、あろうことか般若の角が片方、無残に折れていたというのだ。後シテが使う般若は、あらかじめ厳重に保護されて打杖などの道具とともに鐘の内側に仕込まれる。事前にシテ本人が念入りに確認し、その後は誰も触れることはない。いつ、どうして角が折れたかはわからないが、鐘の中で流儀の宝ともされる面の角が損じていることを発見した若いシテの動揺はいかばかりかと思う。しかし、舞台は止められない。幕府の式楽であった能は何があっても中断を許されず、かつてはシテが急病などにより舞台上で斃れても、後見がすぐに後を引き継いで続けるという決まりがあった。
角が折れた面を掛けて、シテは恋の怨みから大蛇と変じた女の執心を舞った。僧侶たちの祈りに責められ、自ら吹きかけた炎に焼かれる鬼女。片角の折れた般若が、のちに名人と呼ばれた人の舞姿をさらにすさまじく鬼気迫るのものにした。それまでに見たどの道成寺より執心深く、哀しく、美しい姿は何十年たっても忘れられないと光太郎は云った。
演者は修練を尽くし、魂を込めて舞台に立つ。けれどライヴでは何が起きるかわからない。幕が上がったその先は人智を超えた領域となる。
4回転半アクセルを跳ぶことと、羽生結弦らしい、羽生結弦にしかできないスケートを完成させることは「芸術とは確かな技術の上に成り立つ」「芸術的なアスリートでありたい」と語った羽生にとって現役の間にどうしても全うしたいものだったのだと思う。新型コロナウイルスの流行や度重なる怪我など様々な要素が絡んでその舞台が彼にとって3度目の、最後かもしれない五輪となったことも、人智を超えた天の配剤としか言いようがない。
ショートプログラム8位からの背水の陣、しかも傷ついた足で4回転半に挑むのは井戸の底から北辰を射るような、無謀ともいえる試みかもしれない。しかし、深く、孤独な暗闇の底だからこそ、常人には見えない真昼の星さえ視界に捉えることができるのだ。
その磧礫を翫んで玉淵を窺はざるものは 曷んぞ驪龍の蟠まれる所を知らむ
その弊邑に習うて上邦を視ざるものは いまだ英雄の宿れる所を知らず
「浅瀬で砂や石ころをいじって満足しているような志の低い者は、深い水底で龍が宝の玉を抱いていることなど知らない。小さな村に閉じこもって視野の狭い者は英雄が活躍する輝かしい世界があることを知らない。」
[和漢朗詠集 および 三都賦(左思著 文選 巻五)]
中国の文人、左思が著した晋時代のベストセラー「三都賦」の一節だ。高い志を持って理想を追い求める者への憧憬は1700年前も今も変わらない。進化を渇望する羽生結弦が2022年の北京で見せてくれた歴史的な挑戦もまた長く語り伝えられるに違いない。
関連記事
永遠を駈けるスターたち 「石橋」に見る神格化・アポテオシスの系譜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
