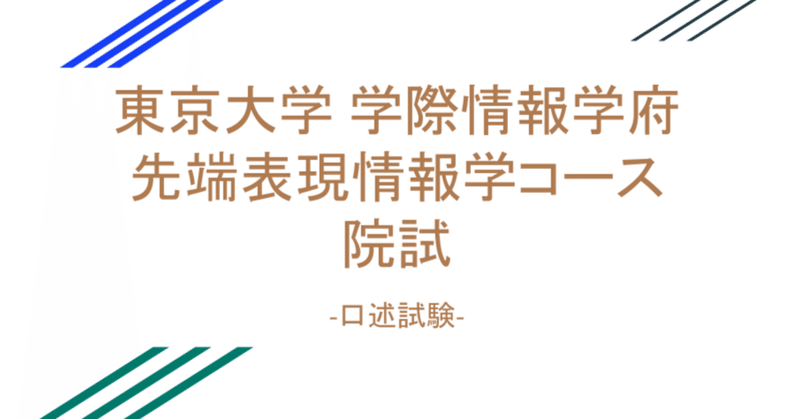
【東大 学際情報学府 先端表現情報学コース 院試】 口述試験
こんにちは、Ryopperです。私は2024年度に外部で大学院を受験しました。
受験した大学院は以下の二つです。
1. 東京大学 学際情報学府 先端表現情報学コース
2. 東京工業大学 情報理工学院 情報工学系
外部大学院受験をして感じたことは、院試は情報戦ということです。
外部生は情報が全く出回りません。私も非常に苦労しました。
来年度以降、大学院を受験する方に向けての記事を書きたいと思います。
本記事は【東大 学際情報学府 院試】 口述試験編です
口述試験概要
書類選考を通過した受験者は口述試験を受けることになります。
2024年度はZoomを用いてオンラインで行われました。
書類選考の通過発表から口述試験までは約1週間しかありません。
口述試験でも倍率は1.5倍程度あるので注意しましょう。
口述試験では、以下の2つが課されます。
研究計画に関するプレゼン(10分以内)
質疑応答(10~15分)
それでは、それぞれについて見ていきましょう。
研究計画に関するプレゼン
先ほどもありましたが、制限時間は10分以内です。
院試なので、制限時間に関してはかなりシビアです。
研究計画書で書いた内容をプレゼンすることになります。(スライド使用可)
書類選考を通過したということは、ある程度研究計画には自信を持って良いでしょう。あとは、それをうまく伝えることです。
私が口述試験を受験した時の面接官は、自分が第1~4希望にしていた研究室の教授でした。私の研究分野と近い教授もいれば、少し離れている教授もいました。
対策
一番の対策は、他人に聞いてもらうことです。
書類選考編でも書きましたが、いろんな人に聞いてもらいましょう。
スライドの構成, わかりにくい図, 不必要なスライド, 詳しく説明が必要な部分などに気づくことができます。
また、時間配分にも気をつけましょう。
Google スライドにはスピーカーノートがあるので、活用すると良いです。
Zoomで画面共有すると、重くてスライドが切り替わらないというハプニングがあるかもしれません。実際、口述試験でスライドが切り替わらないハプニングが起こりました。私は、スピーカーノートに目安時間を書いておいたので、対処することができました。
(実は練習の時に数回起こっていたので、対策済みでした。)
質疑応答
プレゼンが終わると、質疑応答が始まります。私の場合は、4人の試験官のうち、第一志望の教授を除く3人から質問を受けました。
10分~15分なので、4~6個くらいは質問に答えることになりそうです。
論理的に答えることができれば問題ないと思います。
対策
質疑応答に関しても同様に、多くの人に聞いてもらいましょう。
面接官は教授ですが、研究計画に疑問を持つ点は一般人とそこまで変わらないと思っています(ちょっと専門的になるくらい)。
私の場合は、研究室の友人、情報科学の教授、寮の友人、サークルの友人、高校の同期、など、だいたい20人くらいの人に聞いてもらいました。
面接で6個質問を受けましたが、5個は練習と全く同じ質問でした。
練習で受けた質問に関しては、その質問に回答する為のスライドを作っていたので、難なく回答できたと思います。
口頭のみの回答よりも、圧倒的に理解してくれると思います。
今回はここまで。
こちらの記事も併せてご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
