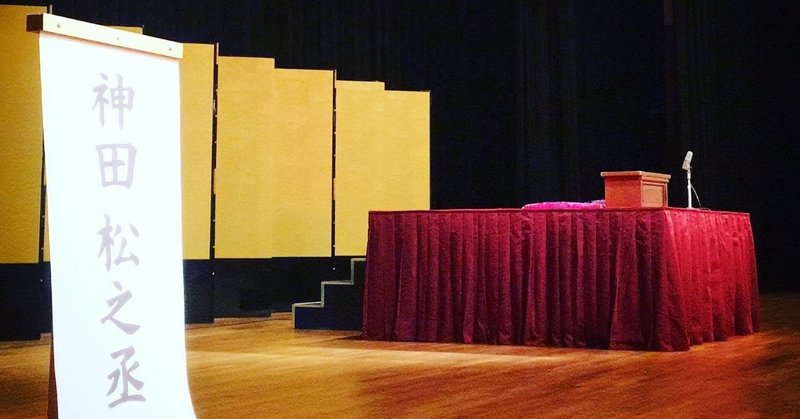
神田松之丞論
平成最後の日、神田松之丞さんの講談を観に行った。
すばらしかった。
その感想と、僕なりの『神田松之丞論』を書きたい。
僕は伝統芸能の人間ではない。
だからこそ、語ることができるものがある。
〝部外者だからこそ〟誰の気も遣わずに、思ったことをそのまま述べることができる。
演目は
扇の的
万両婿
中入
中村仲蔵
講談のおもしろさ
まるで、質の良いプレゼンを見せていただいたようで。
『扇の的』では、「講談の凄まじさ」を。
『万両婿』では、「講談のおもしろさ」を。
『中村仲蔵』では、「芸人、神田松之丞」を。
3種類の光の当て方で、それぞれの講談の魅力を提示した。
この3席というのは「地方だからこそ」というのもきっとある。
講談初心者にとてもやさしい内容で、僕にとってもそれがよかった。
ラジオという話芸
松之丞さんに惹き込まれたきっかけはラジオだった。
昨年の9月16日の回。
僕の誕生日。
何気なくラジオを聴いた。
題名はシンプルに「命(いのち)」と書かれていた。
「こんなハイクオリティのラジオ番組があるのか」
驚愕だった。
世の中にある番組で、今一番おもしろい番組に違いなかった。
一ヵ月ほどかけてラジオクラウドの音源を全て聴いた。
最初に聴いた「命」が一番、よかった。
ひとりでに何か運命めいたものを感じた。
ラジオを聴いて、講談を聴きたいと思った。
ラジオ芸と講談
松之丞さんのラジオにしても、講談にしても、共通して言えることは「物語を伝えるエンターテイメントである」ということ。
松之丞さんの語り口から愚痴だとか、ボヤキだとか形容されることが多いけれど、あの番組は「質の高い物語」である。
作品性の高い、何度でも聴き直せるラジオ。
ラジオ番組の話し手のことを〝パーソナリティ〟と呼ぶが、それこそ、番組にとって不可欠な要素は情報ではなく〝個人〟だと僕は思っている。
つまりは、「誰が、何を、話すか」というところがラジオの魅力の大きな要素である。
『問わず語りの松之丞』は、松之丞さんにしか語ることができない世界───パーソナリティが最も大きく反映されている。
松之丞さん講談を聴いて、古典の〝凄まじさ〟を知った。
演者の声と張扇の音で奏でられていく物語は、空間をも構築させる。
それは、とても立体的に。
「講談ってこんなにすごかったんだ」
講談という芸能に惹かれると同時に、古典の偉大さをも思い知り、畏敬の念を抱いた。
古典は、連綿と続く語り手たちがつくりあげたもの───名人上手の知恵と経験の結晶である。
〝物語〟も〝くすぐり〟も、幾千もの淘汰を繰り返されてできあがった膨大な集合知。
松之丞さんの講談を見た時に、ラジオの語りを思い出した。
松之丞さんのラジオには古典のエッセンスがまぶされている。
黒コショウをミルで挽くかのように、物語に、古典のエッセンスがまぶされている。
「ああ、なるほど、古典の活かし方───人類が残してきた叡智を、このように活かすことができるんだ」
そのような発見があった。
松之丞さんのラジオ芸をざっくりと分解すると、3層のレイヤーにわけることができる。
前 ・パーソナリティ
中 ・ものがたり
奥 ・古典
ラジオでは〝神田松之丞〟個人が一番前にある。
彼が物語を語り、その奥に古典の世界が垣間見える(語り、構成、テクニックなど)。
次に、松之丞さんの講談を分解すると、層の順序が変わっていることがわかる。
前 ・ものがたり
中 ・古典
奥 ・パーソナリティ
ものがたりが一番手前にあり、それを古典という世界観で表現する。
そして、一番奥にあるのは個人としての〝神田松之丞〟。
松之丞さんの『扇の的』を観て、最初に思い出したのは、立川談志師匠の『源平盛衰記』だ。
「あ、やっていることが同じだ」
そう思った。
僕の中での最大の称賛である。
古典の世界を見事に現代に表現している。
「一緒だ」と思ったが、よくよく思い返してみると、談志師匠と松之丞さんのアプローチは真逆だった。
談志師匠は「伝統を現代に」というスローガンで、軍記物の中に現代の要素を入れて新しい世界を表現した。
古典の持つ求心力のあるメロディにのせて、鋭い切れ味で、現代を挟んでいく。
その圧倒的な世界観に、心を鷲掴みされた。
あの時の快楽が松之丞さんの講談によって呼び戻された。
松之丞さんの場合は談志師匠の逆であることに気付く。
談志師匠が古典の中に現代を入れ込んでいったことに対して、松之丞さんは現代の中に古典を入れ込んでいった。
目の前に映し出された世界観は同じだが、ベースとなる領域が逆だったのだ。
半分は松之丞さんの戦略、もう半分は「そうせざるを得なかった」のではないかと想像する。
講談の危機的状況
30代の談志師匠は「落語は能や狂言と同じ道を辿るだろう」と行く末を案じていた。
腐りかけている業界を、いかに活性化させるか。
しかし、松之丞さんが伝統芸能の世界に入った頃は、講談は風前の灯火。
『絶滅危惧職…』という書籍からも分かるように、もはや〝講談〟というもの自体が9割方死んでいた時期なのではないだろうか。
世の中には講談に対する素養がこれっぽっちもない───談志師匠のように「古典に現代を落とし込む」ことさえできない状態だった。
だからこそ、現代に古典を落とし込む手法。
松之丞さんの懇切丁寧な物語への導入は納得ができる。
観客が迷子にならないように誘導灯を振りながら導いてくれる(地方だったということも大きな理由の一つではあるが)。
松之丞さんはプレイヤーだけでなく、解説者を含めた案内人も担っているのだ。
ジャングルクルーズの船長みたいに、一艘の船に観客を乗せ、講談(古典)というアトラクションをガイドする。
共有している世界観や、共通言語がない人に、おもしろさを届けることの難しさ。
プレイヤーであると同時に、伝道師でもあるのだ。
講談は着物、演者はモデル
談志師匠と松之丞さんに共通して言えることは、「古典へのリスペクト」だ。
古典のすばらしさを誰よりも理解しているからこそ、人に伝えたいし、継承していきたい。
アプローチは違うが、二人の作り上げる世界観が同じだということが、僕にとっては震えるほど感動的であった。
講談は鎧───もしくは、美しい着物である。
僕たちは、その鎧や着物の屈強さや、しなやかさや、美しさを観て、聴いて、感じる。
演者はその衣装を身につけるモデルだ。
松之丞さんには、それらの衣装(講談)に対するリスペクトが強い。
「この着物、こんなに美しいんです」
そのようにして、講談を敬いながら演じる。
ただ、その着物を良く見せるのはモデル次第なのだということを僕たちは知っている。
衣装を美しく見せるのは、モデルのポテンシャルだ。
モデルの身体に合わせて、着物の映え方が変わる。
手足が長い方が映える衣装(話)もあるだろう。
恰幅が良い方が映える衣装(話)もあるだろう。
だからモデルも服を選ばなければならない。
「この服が好き」だからと言って、それが自分の肢体と合うわけではない。
そして、モデルと着物の相性がドラマティックに融合した時、それは、最高の姿となる。
それがまさに、松之丞さんの『中村仲蔵』へと繋がっていく。
松之丞の憤り
松之丞さんによるこれらのアプローチはうるさがたの玄人客からすると野暮に映るのかもしれない。
語らずしても良い部分を語り、表面的な笑いを小刻みにまぶす。
端的に言えば、無粋なわけだ。
ここに、松之丞さんの苦悩があると想像する。
それらが野暮であることを、松之丞さんは誰よりも知っているはずだ。
講談に対する向き合い方、リスペクトの姿勢を見て、勝手ながら僕は思った。
そういう仕掛けを拵えなければ、本当に誰も講談を聴かない。
新しい見せ方や工夫をしない限り、講談は本当に絶滅してしまう。
愛がなく形を今様に変えているのではない。
愛があり余り過ぎて、そうせざるを得なかったのだ。
「誰よりも、オレが貢献している」
そう思っているに違いない。
多くの人へ広めるため、そして、講談を次の時代へと継承するため。
そこには、講談師だけでなく、批評家にも責任がある。
観たくなるような芸を見せてこなかった講談師、そして、足を運ばせたくなるような魅力的な批評を書いてこなかった批評家たち。
あらゆるものに対して憤りがある。
演芸というボーダーを越えて、あらゆるメディアで活躍する〝出る杭〟となって講談を広める。
内部がそれを叩いてどうする。
そして松之丞さんには確信がある。
「劇場まで足を運ばせることさえできれば、勝ちだ」
ホーム(それが寄席であれ、ホールであれ)に引き込んでさえしまえば、夢中にさせる自信が彼にはあるのだ。
『中村仲蔵』
血統のない歌舞伎役者の話。
歌舞伎の世界では血筋がものをいう。
家柄のない者は才能や実力にかかわらず名題(役者におけるヒエラルキーの最上位)になれない。
つまり、それは大きな役をもらえないことを意味する。
中村仲蔵。
彼は、機転を利かせて自ら招いたピンチをチャンスに変えて、実力を示していった。
そして血筋を持たないにもかかわらず仲蔵は、ついに名題にまで上り詰める。
工夫によって、平凡な幕を名場面に変える。
今まで、色んな人が演った『中村仲蔵』を見てきた。
立川志の輔師匠が一番好きだった。
それは仲蔵に、〝立川志の輔〟の姿を見たから。
立川流は寄席で落語ができなかった。
新作落語を拵えて、あるいは積極的にメディアに露出することで落語の魅力を広めた。
そんな志の輔師匠の姿が仲蔵と重なった。
「古典以上の何かを感じた」
先ほど、「モデルと着物の相性がドラマティックに融合した時、それは、最高の姿となる」と書いた。
まさにこの現象である。
古典の奥のパーソナリティが垣間見える。
それが成功した時、古典であるはずのものが「その人にしか語ることができない物語」となる。
そして、松之丞さんの『中村仲蔵』
観客全員が、仲蔵の姿に〝神田松之丞〟を重ねた。
工夫によって、プレイヤーでありながら、伝道師になり、講談を広める孤高の芸人の姿を。
物語の力
ストーリーの力で伝えることができる。
そこに本音を潜ませることも。
普段ならば恥ずかしくて言葉にできないことさえ、物語を通して下拵えして伝えることができる。
松之丞さんの『中村仲蔵』から受け取ったメッセージ。
仲蔵は報われなければいけない。
逆境の中で闘い、工夫に工夫を重ねて、世の中を驚かせた(それは外だけでなく、業界の内部までも)。
仲蔵が報われた瞬間は、工夫となるアイディアを発見した時でもなければ、舞台でその工夫を形にした時でもない。
彼が報われたのは観客に「堺屋!日本一!」と声をかけられた瞬間なのだ。
観客の声を聴くまで、仲蔵はまるで暗闇の中にいるようにびくびくしていた。そのトライアルが合っていたのか、しくじってしまったのか。不安と恐怖に怯えていた。
それを救ったのは、観客の声援。
「堺屋!日本一!」
それが言葉となり、空気を震わせて、ようやく報われた。
新しい工夫には向かい風が吹く
それが伝統芸能の世界ならばなおさらのことである。
僕たちができることは一人でも多くの観客が「よかった」と言葉にして発信することだ。
感動しているだけでは伝わらない。
新たなトライアルの背中を押すのは、観客一人ひとりの熱狂であり、言葉なのだ。
僕は松之丞さんの理想とする講談の世界を観たい。
講談がより一般化し、インフラが整った状態で演る「これぞ理想の形」という松之丞さんの講談を見たい。
立川談志は「オレが落語だ」と言った。
ラジオの中で、松之丞さんは「オレが講談だ」と冗談めかして言ったが、その半分は本音だと思う。
〝神田松之丞〟は〝神田伯山〟となり、そして、〝講談〟となっていくだろう。
「ダイアログジャーニー」と題して、全国を巡り、さまざまなクリエイターをインタビューしています。その活動費に使用させていただきます。対話の魅力を発信するコンテンツとして還元いたします。ご支援、ありがとうございます。
