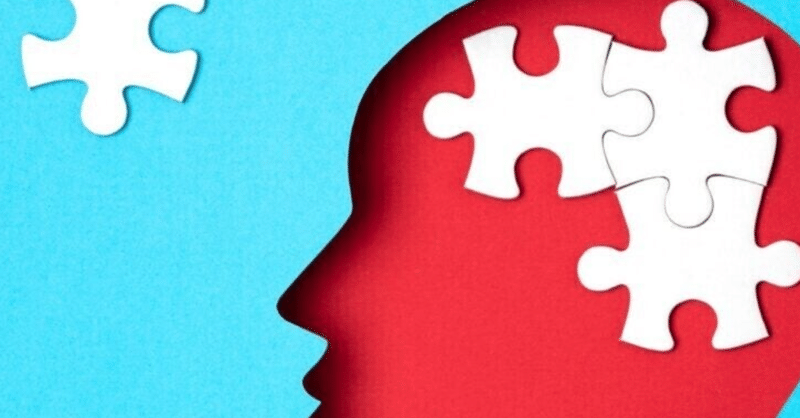
思考の型を使って、プレゼンする-日之影町教育委員会の皆様とディスカッションしました。-
1月下旬のこと。
日之影町の教育委員会に依頼を受けて、新富町の取り組みを紹介させていただく機会を得ました。新富町教育委員会教育推進コーディネーターとしての仕事の1つだとも思っています。
さて、今回依頼いただいた内容は、高校の無い町という共通点を持つからこそ、高校生以降とどのようにつながっていくか、という点中心に話してほしいという依頼がありました。次の3つをお話しました。
(1)しんとみ学び塾
(2)国際交流プログラム
(3)大学生向けのスタディツアー
ただ、事例を話すだけでは、もったいない、と思い、大学院で学んでいるし一工夫しなければと思い、考えたときに次の思考の枠を思い出しました。
パターン・ランゲージとは上記のサイトには次のように書かれています。
パターン・ランゲージは、もともと1970年代に建築家クリストファー・アレグザンダーが住民参加のまちづくりのために提唱した知識記述の方法です。アレグザンダーは、町や建物に繰り返し現れる関係性を「パターン」と呼び、それを「ランゲージ」(言語)として共有する方法を考案しました。彼が目指したのは、誰もがデザインのプロセスに参加できる方法でした。町や建物をつくるのは建築家ですが、実際に住み、アレンジしながら育てていくのは住民だからです。
続けてこんな事も書いています。
「パターン」は、いわば文法のようなものをもっており、決まったルールで書かれます。どのパターンも、ある「状況」(Context)において生じる「問題」(Problem)と、その「解決」(Solution)の方法がセットになって記述され、それに「名前」(パターン名)がつけられる、という構造をもっています。このように一定の記述形式で秘訣を記することによって、パターン名(名前)に多くの意味が含まれ、それが共通で認識され、「言葉」として機能するようになっているのです。
なるほどと思いました。なので、これまでの自分の実践をパターン・ランゲージで明らかにしなければならないとされている「型」に沿って、
①どのような状況(新富町の背景)
②その中で問題となっていることはなにか?
③その上で我々は何をしたのか?
④その結果どうなったか?
の4点について言葉にし、整理した上で情報共有をすることとしました。自分自身の気付きとしてもあまり明らかに仕切れていなかった部分を見つけたり、なるほどこういう整理があるのか、ということも感じたところでした。やはり「型」って大事よね、と思うところです。
実施後の感想としては、一番大きく聞こえたのは、「高校がない、海外とつながっていない、などを、全く言い訳にされていない。むしろ、だからどうしていくか、ということを新富町は考えていらっしゃるんですね」とおっしゃっていただいたことでした。正直、私自身、この3年間、できない、むずかしい、やって意味あるの?いう言葉と向き合ってきたと思います。でも、やったらできるものだし、やったら見えてくるものはあると思います。その一端を感じていただけたのは良かったなともう次第です。
最後に、今回の情報提供として作った資料のテーマが、
これからの教育への『試されごと』を考える
でした。色々と広がる教育への試されごとですが、学校はもちろん、地域をつないで色々と挑戦したり、もちろん、試行錯誤したりできると良いなぁと思うところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
