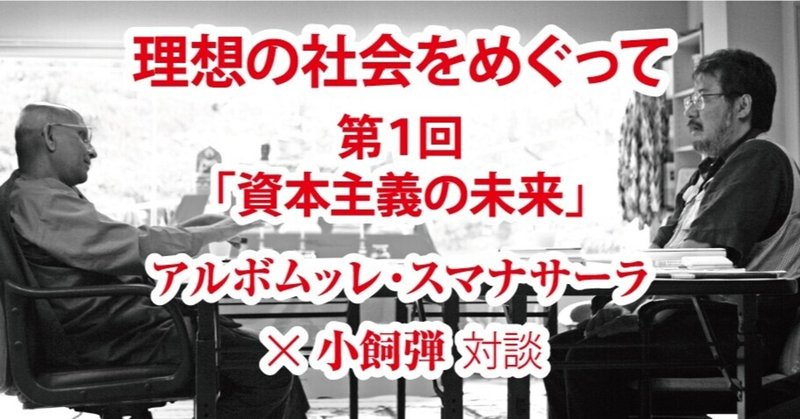
理想の社会をめぐって(第1回)
第1回 「資本主義の未来」
アルボムッレ・スマナサーラ×小飼弾対談
全人類が悟るとき
思考実験
小飼 ご著書の中で、長老は「仏教は心の科学だ」とおっしゃっていますね。その言葉で私はひじょうにすっきりしまして、それから仏教を科学的にとらえてみようといろいろと考えてみました。
まずお聞きしたいのは、これは思考実験なのですが、人が皆、悟ってブッダになったら、いったいどうなってしまうのかということです。人はだれでも悟り得るわけですよね。
スマナサーラ 仏教というのは純粋論理ではないのです。プラクティカルに、実際どうなるのか、ということを考えます。たとえば、経済成長率10%を達成するにはどうしたらいいのか。そして具体的な計画を立てて、いざ実行するとどうなるのか、ということを問題とします。純粋論理は数学とまったく同じで、現実には実施されないのです。
理論として考えれば、すべての人が悟ってしまったら、という問いは成立します。しかし、現実的には存在し得ないと考えます。世界の人口はどれくらいか。その中で、仏教に興味を持つ人はどれくらいいるのか。実際、たいした数字にはならないでしょう。そしてその中で、悟るための修行をしてみようという人、悟りを開くまでにいたる人となると、さらに少なくなります。
以前にも「いっさいの生命が悟りに達したらどうなるのでしょうか」と聞かれたことがあります。私は「生命は無制限にあるのだから、いくら悟っても生命が減るわけではないのだよ」と答えました。結論を言いますと、それは論理的にはいい質問なのです。しかしプラクティカルに、現実的にいうと、そんな心配はしなくていいよ、ということになります。
小飼 この質問は、単純にいうと「みんなが出家したらだれが托鉢に応じるのか」という素朴な疑問から発しているわけなんですが。ブッダの教えというのは、ブッダが生まれたところでは一度なくなっていますよね。これは私の仮説というより妄想なのかもしれませんが、それがどうしてかというと、あまりに多くの人が悟ろうとしたために、悟りに関心のない人たちにやられてしまったのではないかと思うのです。ブッダの王国が滅ぶ状況がそれに似ている。
そこで、悟らない人が一定の数以上いないと、悟る人は出てこないのではないかという疑問を持ったのです。悟る人も、悟らない人にある種の依存があるのではないでしょうか。
すべての生命は依存して生きている
スマナサーラ この世界では、すべての生き物が互いに依存して生きています。たとえ悟りに達しても、肉体がある限りは生命同士の関係があります。依存ということではなくて、お互い関係して生活しているということですね。
仏教は、実際に生きている社会と対立しないようにすることに、ひじょうに気をつかっています。
出家ということでいえば、ブッダはだれに対しても出家を認めているわけではありません。その人の、能力や責任を考えます。マガダ国の国王は悟りに達しましたが、ブッダは彼に出家しろとは言いませんでした。自分の父親も、出家させてもよかったのに、出家させませんでした。彼らには、社会で果たさなければならない義務があり、出家してしまっては、社会がうまくいかなくなってしまいます。
仏教は幸福を語っていますから、たとえ虫一匹でも、不幸になることは言わないのです。
そういうことからいっても、「すべての人が出家してしまう」という仮定は成り立たないのです。われわれ仏教徒の中でも、その志のある何人かは出家しなさい、残りは在家で修行しなさい、としています。
出家には2種類あります。ひとつは、人生に対してあまり疑問を持っていない人の出家。こういう人が出家者として成功するかは、また別の問題です。もうひとつは、真剣に目的を持っていて、達成したいと思っている人の出家。
考えてみてください。なにかで成功するためには、あらゆるものをカットしなくてはならないのです。これは俗世間でも同じことです。ヒマラヤを制覇しようと思ったら、酒を飲んで酔っ払って、などと遊んでいるわけにはいかないでしょう。子どもたちが遊ぼうと言ってきても、「ごめんね」といって自分の訓練をしなくてはならない。まわりにいる家族もたいへんですし、友達の応援も必要になってきます。われわれは俗世間においても、なにか目的を決めたらいろんなものをカットすることになります。
ですから、解脱しようと本気で思う人も、在家生活をやめることになるのです。
現実的に見ると、そういう人々は社会においても、出家生活においても、問題なしに自分の目的に達するのです。
初期仏教ではいつでも、「すべての生命が幸福でありますように」ということを念じるのであって、「すべての生命を悟りに導きます」といった観念的なことは言いません。その代わりに「生きとし生けるものに悟りの光が現れますように」と念じます。日本仏教でも「一切衆生の成仏を願う」などとよく言われるのですが、そのために具体的になにを行っているのか定かではありません。念じただけでは他人が解脱しないのです。ですから、初期仏教では一生懸命、他人に仏教の真理を語ったり、修行方法を教えたり、実践する方々を応援したりするのです。具体的なやり方なく、衆生の成仏を願うとだけ唱えても、スローガンにとどまるのではないかという気がします。

だれもが幸福を勘違いしている
「幸福」とはなにか
小飼 よくわかりました。では、次の疑問なのですが「幸福とはなにか」ということです。一般的にはまず、幸福といい、不幸という。幸福のほうが先にあって不幸という言葉ができたということなのかもしれませんが、私にはこれがピンとこないんです。不幸というか、痛いことや嫌なことというのはよくわかるんです。一方、幸福はそういうことがない状態としか言いようがないのではないかと思うのですが。
スマナサーラ そのとおりです。私たちに理解できるのは、不幸だけなのです。
お釈迦さまは、生きることはたたかうことである、とおっしゃいました。なにをやっても納得しきれないのです。「うまくいった、最高だ」と一度は思っても、結局は満足できません。頑張ってヒマラヤ登頂制覇に成功したとしても、それにかかったあらゆる苦労などを引き算してみると、不満だらけということになりかねません。
われわれが生きるということは「苦」の連続です。「苦」というのは「苦しみ」とは意味がちがいます。なにについても不満を感じてしまう、納得がいかないということです。もう少しなにかないのか、といつも思ってしまう。いつも不満を感じながら生きています。ですから「幸福」というのは、おっしゃったとおり「苦がない」ことであるわけです。
食べるためのご飯がない人の第一の「苦」は空腹です。空腹な人にご飯を与えれば、「私は幸せだ」と言います。しかし、はたしてそれは本当に幸福でしょうか。三食きちんと食べられる人でも、時間がたって夜になったらまたお腹が空きます。あるいは、独身でいるのがさびしいから苦しみをなくそうと思って、結婚します。結婚したら結婚生活が苦しくて、という具合にきりがないのです。
幸福は人によりちがう
スマナサーラ 幸福はなにかといったら、その一つひとつの苦を乗り越えることです。しかし、それは相対的な幸福であって絶対的な幸福ではありません。
小飼 要は「不幸なときに比べたら、いまのほうがいいだろう」ということですね。
スマナサーラ 私がよく言うたとえ話があります。1円も持っていないホームレスの人がいて、2日も3日もご飯を食べていない。そういう人が公園で1万円を見つける。そうしたら、ものすごい幸福を感じることでしょう。しかし億万長者が護衛の人といっしょに公園を散歩していて1万円を見つけたとしても、おそらく拾わないでしょう。つまり、億万長者にとっては1万円札を見つけるということは幸福ではありません。
小飼 お金で幸福を得るというよりも、なにかものを手に入れて幸福を得るというアプローチはどんどん難しくなってきていますよね。貯金が0円のときは1万円で幸福になれたのに、1万円持っているときは2万円必要だ、ということになってきりがなくなる。
スマナサーラ きりがなくなって、さらに不幸になってしまうのです。
私たちの欲望にはきりがないのだから、そんなことは放っておいて、まずは落ち着けということです。いまあるもので幸せだ、と思ったらどうでしょうね。そうすれば問題は一発で解決するんです。
ホームレスの人でも、ガードの下に寝るところを見つけたときに、「今日はだれもいなくて空いてるな」と思えば、心のやすらぎはあるはずです。
満足する技術
小飼 私も、お金がないころ、「こんなにお金がないのに楽しくやっているおれってすごいかも」と思っていたし、お金ができると、「お金ってこんなにかんたんにつくれるんだ」と思いました。私はかんたんに幸せになれるタイプなのかもしれません。
スマナサーラ そのとおりです。現実でうまくいっていると思える人がいつでも幸福なんです。
お釈迦さまがおっしゃった幸福になる秘訣は、いつでも、どうなっても満足を感じなさい、充実感を感じなさいということです。「ないない」というのではなく「これぐらいはあるじゃないか」というふうに考える。これは単に思考の問題であって、客観的な問題ではないのだと理解する。
西洋世界は物質中心でしょう。彼らは世界中を不幸に陥れています。戦争の世界を生み出しています。この戦争の世界は東洋人がつくったものではありません。
小飼 1万円の次には2万円、というのは西洋的な考えなのですね。
スマナサーラ イギリスという国を考えてみましょう。他の国々を獲って財産を奪って、それでも足りなくなったりする。あげく植民地を管理できなくなっても手放そうとしない。世界一の大泥棒で、多くの人々を殺し、土地や財産を奪っているわけです。そういう過去がありながら、なにか争いがあると、いまだに偉そうなことを言っています。
そういう思考は東洋ではそれほどありませんでした。やっぱり幸福というのは単純に心の問題なんです。だから心の科学なんです。
知られていない心の方程式
小飼 心の問題ということでひとつありがたいのは、心の状態というのは物理学的にいうと保存されませんよね。
スマナサーラ うん。
小飼 保存されないということは、「100不幸があったら100幸福を持ってこないとイーブンにできないということではない」ということですよね。心は急に気の持ちようで幸福になったり、ということがありますよね。心は物みたいに、あげたらなくなる、ということがないと思うんです。
スマナサーラ そうそうそう。1万円で与えられる幸福の量にしても、計算できるものではありません。
小飼 西洋社会のいちばんの錯誤というのは「幸福というものは人にあげると減る」と勘違いしていることではないかと思います。
スマナサーラ そうですね。逆に、人に幸福を与えると、どんどん増えるものです。
10あげたら、こちらには100のプラスなのです。数学とはちがうのです。数学は10あげたら10マイナスなだけです。しかし、われわれは人に10あげたら、そのあげたあなたはプラス1万だというのです。なぜかといえば、心理学だからです。心とはそういうものなのです。
仕事を見つけられない人に仕事を紹介してあげれば、仕事がなくて困っていた人は活躍して生き生きする。それを見ている自分も、楽しくなる。そうやって幸福度は上がっていきます。
人にあげれば増えるというのが、仏教の方程式ではふつうのことなのです。
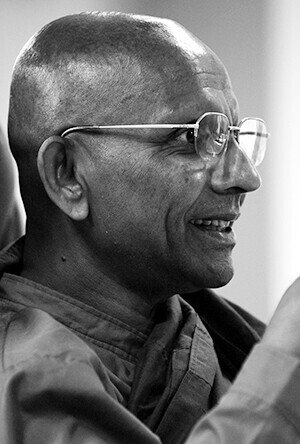
資本主義の未来
お金の賢い使い方
小飼 資本主義というのは、ものを手に入れる、人間が使えるものを増やすという点では最高のシステムです。これ以上の方法というのは見つかっていないし、これからも見つからないと思います。
しかし、「物を手に入れてどうするの」という問いにはなんの回答も与えてくれていない。これを言うとよく顰蹙をかうのですが、お金をつくるのは実はかんたんです。
スマナサーラ みんながそうではないでしょう。自分にあるもので満足している人にとっては、少し増えただけで「儲かった」、ということになるでしょうが。
小飼 私には、100万円つくるよりも、1万円で幸せになるほうが高等なテクニックに見えます。お金は一次元ではかれます。0円から100兆円まで、ただの数字の量ですよね。
スマナサーラ そうですね。
小飼 ですから、本を書いても、本を売ってもお金に替えることができます。お金は、なにをやってつくってもいい。そういう意味では、複雑なものをかんたんにするということが、お金をつくるという行為であるといえます。
そうやって考えると、お金を使うよりもつくるほうがかんたんなのです。お金を使うというのは、多いか少ないかしかないものを、いろんな形に変えることですからつくるよりずっと難しいのです。
スマナサーラ うん。
小飼 実際のところ、その稼いだお金でなにをするのか、というほうがずっと難しいと考えます。資本主義というのは、お金を使う方法についてはなにも言っていません。ひとつだけ言っているのは「お金を使うと、お金を増やせますよ」ということだけです。資本主義の世界においていちばん賢いお金の使い方というのは「もっとお金をつくるために、お金を使おう」なのです。
お金が「価値」に変わる瞬間
スマナサーラ 現在の世界は、中国でもどこでも、北朝鮮以外は資本主義になっています。しかし、仏教というとくべつな思考パターンを持っている私たちから見ると、笑ってしまうところがあります。
資本主義というのは俗世間のものだから、観念的に語ることができます。自分に能力があったら、働いて金を儲ければいい。しかし、お金というものは財産です。財産というのは地球上のものだから、リミットがあります。能力のある人が金をどんどん取ると、能力のない人から奪うことになります。
たとえば自分が金脈の上に暮らしていても、だれかが買わなかったら1円にもならない。
小飼 他者がいるから、お金というものに価値が生まれます。自分ひとりしかこの世にいなかったら、お金というものは本当に無価値です。
スマナサーラ お金を儲けるということは、だれかから取るということです。そうすると、弱い人から強い人にいくことになる。そういう言葉でいいかわかりませんが。
つまり、能力のない人から能力のある人に流れていく。たとえば、能力のある人は本を書き、ない人は本を読むでしょう。本を書いた人はお金をもらい、読む人は払う。やはり能力のない人からある人に流れるのです。
資本主義の最後の姿
スマナサーラ 資本主義の行き着くところについてお話ししましょう。
能力のない人は経済的にどんどん衰えていって、生きていられなくなります。そして残った人々で、さらに資本主義社会をたたかう。さらにまた能力のない人が消えていく。観念的にいえば、この繰り返しで残るのはたったひとりということになります。
しかし、最後に残った人というのは、実はひとりではありません。かなり凶暴な人がふたり残ります。ひとりが毒を盛ろうとすれば、もうひとりは相手を刺し殺そうとする。つまり、相討ちになって結局だれも残らないのです。これはお釈迦さまが語られたエピソードです。
資本主義とは、そういう道をさしているのです。最終的にみんな消えてしまえというメッセージを秘めている。小飼さんの言うとおり「お金をどう使うのか」という問いへの答えはありません。
もうひとつ、きわめて大きな問題は、人間の欲にはきりがないということです。資本主義は、「儲かれば欲が消えるのか」ということを考えていないということです。実験していない。1円もない人は100円で喜びますが、100円持っている人にとっては「千円なければ」ということになるのです。この経済システムに、仏教者はニコッと笑って「どうぞやってください」と言います。それで人間の苦しみを消すことはできませんよ、無駄骨ですよ、というわけです。
仏教は民主主義を応援しますし、共産主義、社会主義、資本主義などなどの政治経済システムに対して、反対も賛成もしない立場です。どんな主義であっても現実的には躓いてうまくいかないことになるのです。それは欲、怒りなどの感情に支配されている無知な心の指導で生きるからなのです。
資本主義は他者を認める仕組みか
小飼 資本主義の弁護をするわけではないのですが、資本主義にはよいところもあると思うのです。お金を使いたいという欲求がある以上、他者を認めざるを得ません。受け取ってくれる人がいないと成り立たないので、少なくとも買い手と売り手という関係ではお互いを尊重するのではないでしょうか。
スマナサーラ おっしゃるほど美しいものではないのではありませんか? それは、互いに人の弱みを握っているということでしょう。
小飼 お互いの弱みに立脚しているけれども、お互いの弱みに立脚するがゆえに、純粋な戦争モデルよりはましだと思うのです。
スマナサーラ ……。私は戦争とそんなに変わらないと思いますね。
小飼 悟れない人のあいだでも、またお金の原理を知らない人でも、お金を使いたい人というのは、少なくとも相手を殺そうとはしませんよね。その代わりに、相手に物を売りつけよう、あるいは買おうとするのではないでしょうか。相手を殺してしまっては、それはできないですから。
スマナサーラ 「資本主義の人は人殺しをしません」といっても、現実はちがうと思います。自分が持っているものや、能力を相手に売って財産を得るという常識的なやり方もあるし、常識的な生き方にうまく乗れない人々も、また、あえて乗りたくない人もいるのです。うまく乗れない人々はかわいそうです。あえて乗りたくない人々は、社会と平和と秩序に対しては危険な存在です。
資本主義の病理
スマナサーラ 常識にうまく乗れない人々は社会の貧困層になるのです。乗りたくない人々は、法律を犯したり人を脅したり殺したりまでして、財産を得ようとするのです。たとえば、厳密なセキュリティシステムで守られた家を見たら、「どうすれば、このセキュリティシステムを破って家の品物を盗めるのか」と考えるでしょう。
資本主義は豊かな人間をつくると同時に、貧困に陥る人も犯罪にあふれている社会もつくるのです。どんな政治経済システムであっても、この病気はついてくると思います。
小飼 それはどうでしょうね。
スマナサーラ 程度の問題なんですね。今日のインドの新聞にも、お金が入ったカバンを奪おうとしてカバンを持った人を撃って逃げたという記事が載っていました。この人はお金を手に入れるためならなにをやってもいいと思ったということです。
小飼 それはずいぶんもったいないお金のあつかい方ではないでしょうか。
スマナサーラ それはその犯罪者の資本主義ではないでしょうか。ほとんどの人々は法律や宗教、道徳観などでいくらか管理されています。ですから、そんなことまでしないで、相手を尊重するような形をとるかもしれません。
しかし、仏教が解説する心理からみれば、やっぱり「弱い人から奪う」という法則は消えないのです。

お金の本質
お金という概念、お金の意味
小飼 お金というものは、本来貯め込んでも意味がないと思うのです。人に受け取ってもらってはじめて価値を生むものではないかと。
スマナサーラ ですから、そもそもお金そのものには意味がないのです。お金は、人工的な概念です。概念とはどうでもいいことで、もともと意味がないですから。
小飼 はい。そこでひとつたとえ話をします。たとえばご飯はどうでもいいものではないですよね。
スマナサーラ ご飯は概念ではありません。
小飼 ですが、お金があるおかげで作れるご飯が増えたということはたしかなことです。
スマナサーラ それはちがうと思います。たとえば私の前に弁当があるとすると、私がお腹が空いていたらこの弁当は必要です。この弁当が700円だとすると、700円というのは観念的な概念です。
小飼 たしかにそうです。しかしそのお金という概念があるおかげで、ご飯を作っていない人も、ご飯にありつけるわけですよね。ご飯を自分で作らなくても、人にご飯を作ってもらってその代わりにご飯に相当するなにかを作ろうという……。
スマナサーラ むかしはそれでもよかったでしょう。ある人は畑や田を耕してご飯を作り、別の人は家を作っていっしょに仲よくご飯を食べる、ということはあったでしょう。
小飼 家を1軒建てると、その人はご飯をどれくらいもらうべきだろうという疑問が出てきます。そうやってお金というものは生まれたはずなのです。
スマナサーラ 家を建てるのに1年かかったなら、建ててもらっている人は建てる人の家族も含めて、1年間のご飯を提供したはずです。
小飼 賢い人はそう考えるでしょう。しかしそうでない人は「いや、自分はご飯2年分に値する仕事をした」と考えるかもしれません。そういう喧嘩がいくつも起きた結果、「じゃあ、なにかものさしを持ってきましょう」ということになって、そのものさしがお金に化けたのではないでしょうか。
感覚が価値を決める
スマナサーラ 現代社会に起こる問題が、その視点から見えてきます。「自分が2年分の仕事をした」と、どういう計算をすれば出てくるのか。
小飼 感覚ですね。
スマナサーラ そうです。感覚であり欲です。ちょっと筆を動かして絵を描いて、「これには20万円くらいの価値がありますよ」というのもそれです。それは描いた人が勝手に思っているにすぎません。そんな価値があるわけがない、という人がいるかもしれません。だれかが「これを10万円で売ってくれませんか」と言い出す可能性もあります。
そういったことは人間の心の問題です。心は限りない欲で思考しているのです。
小飼 お金が曲がりなりにもうまくいった理由というのは「欲をもって、欲を制する」ようにはたらくからだと思います。「おれはあれが欲しいが、あいつはこれが欲しい」というように、お互い欲しいものをつき合わせる。そして、双方が納得したところで、お互い手に入れたかったものを交換する、ということを続けているわけです。
スマナサーラ それは欲しいものがお互いになければ成立しませんね。たとえば、ある人がプログラマーで金が欲しくて、もう一方がだれかにプログラムを作ってほしいという場合は成立します。ですが、お互い金が欲しいだけだったら成立しない。
心理学を物理学にするツール
小飼 実は仕事をするとき、私は、請求書に金額を書くときが、いちばん嫌なんです。
仕事そのものは楽しい。できそうなものがあると、思わず作ってしまったりします。しかし、それには値段をつけなくてはいけない。いくらになるか決めないと、商売になりませんからね。ですから純粋な仕事というのは、お金を介した経済ではあり得ません。仕事には、作るという部分と、それをいくらにするかという部分があって、後者の作業というのがものすごくつらい。
スマナサーラ それは値段をつけるという作業が、まったく論理的ではないからでしょうね。いまは物理的な金というものは消えて、ほとんど数字だけのものではありませんか。それは純粋数学になっていますから、論理的ではっきりしています。しかし値段をつけるという行為は、まったく数学ではない。人間の感情、希望や欲やプライドというのは、数字に当てはめることはできません。
「仕事は楽しいけれども、これをどれくらいの数字にするのか」というのは、ばかばかしいしできないことなのです。できないことをやろうとするのは、論理型の人間にとってはものすごく嫌な気分になることです。
逆にいえば、小飼さんは自分の仕事に自負がおありだと思いますが、それを数字にはしたくないのではありませんか? だからといって500万円、1千万円という値段をつけると、これも成り立たない。お金の世界はそうならざるを得ないのです。
なんの役にも立たないがらくたに1千万円の値段がついたりすることがありますが、それは役に立つから払ったのではなく、自慢するために払ったのです。
小飼 お金というのは、おそらく心理学を無理やり物理学にするためのツールなのです。
スマナサーラ 理屈が通らないところに無理やり通そうとして、悩みや苦しみが生まれています。
小飼 そうやって考えると、へんな言い方ですが、われわれは悩み苦しみが好きなのではないかと。人間は、悩んだり、苦しむほうが得意なのではないでしょうか。
(つづく)※全4回
小飼弾[著]『働かざるもの、飢えるべからず』(サンガ、2009)第2部より転載。
2022年2月1日(火)、スマナサーラ長老と小飼弾さんの13年ぶりの対談をオンライン開催決定!
「人間を超える~光の速度は遅すぎる」
https://peatix.com/event/3140576/view
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
