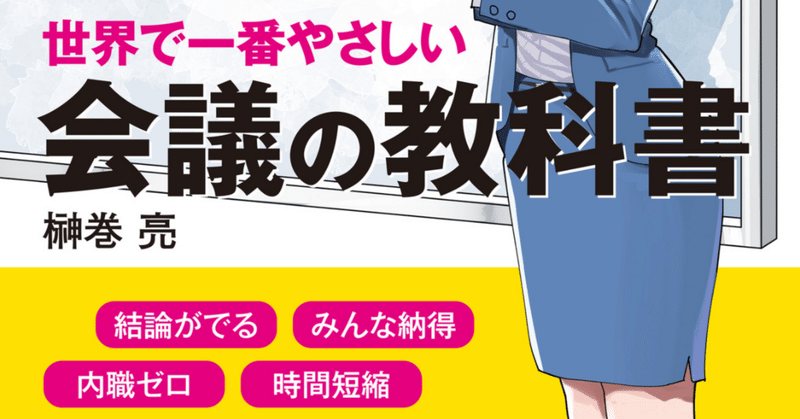
#106 学び ファシリテーションについて構造を学び直してみた話
今日は久々に仕事のない週末なので手を付けられていなかったファシリテーションについて学び直しした内容をメモとして残しておきたいと思います。
いきなり、ファシリテーション?どうした?って感じもするのでなぜ、学び直そうと思ったかの背景も含めてまとめています。
ファシリ好きだけど我流なんだよねっていう自分と近いタイプのヒトや、そもそも苦手って人にも少しでも参考になれば幸いです。
数年前に、学んでいた時の参考本として紹介されたのが 世界で一番優しい会議の教科書だった事を思い出したので参考にリンクを残しておきます
なぜ、ファシリテーションを振り返ろうと思ったか
それは、先日オンライン会議で若手が自らファシリをします!こう言う機会を使ってファシリ能力を鍛える!とメチャクチャポジティブな動きをしてくれていた中で、いろいろ気づきがあったという背景があります。
そもそもとして問いを立ててみる
ファシリテーターの役割って?
自分は参加者とならずに、参加者の知見、能力を最大化し複数人で答えを導き出すヒトとして理解をしています。だからファシリの差で出てくるアウトプットに差がでる事が普通なので、やるからには準備、フォローを含め全力でと思っていいつも望んでおります。
複数人で考えるメリットは?
自分だけでは考えられない視点を得られる。出したアイデアを複数結び付けて思いもよらない結論を導き出すことができる。
人数にもよるが、複数のお題について考える事ができる。ざっくりこの辺りがメリットとして挙げられるかなと。
複数人で考えるデメリットは?
もうこれは、仕事でも起こるのですが、予定調和的になって複数で集まった意味があったのか?となってしまうみんなで考えなく時間のムダになる
複数アイデアが出ても、対立軸を収束できずに何も決まらない。声が大きいひとの意見で物事が決まってしまう。(やる意味はとモチベーションが下がる)この変があるあるなデメリットかなと。
という事は、メリットを最大化させつつ、良い課題解決に結びつけつつ、デメリットをいかにコントロールするかがファシリに求められるテーマの一部になるかなという事で、それぞれの会議の準備からクロージングまでの流れの中で何をすると良いのかなどを抑えていきます。
シーン別押さえておくポイント
準備編
一番最初に考えるべきは、そもそも会議をやる目的は?かなと。
まずは、これがないと何ともならない。なので自分が参加するときには事前にAGENDAがないものは基本的にはでない、または確認するかなと。
ここがクリアになれば、目的に対してどんな状態になっていたいか?を決めること。参加者に会議の冒頭ゴールを提示するって言い方かもしれません。
状態が定義できた場合には、この状態にもっていく為にはどんな人が参加しなければいけないか?その意思決定に対して実行フェーズになり巻き込むべき人がいるのか?など分析を開始。
で、どんな環境で行う事が一番最大の効果を発揮するか場の検討、時間の検討などの詳細設計にはいるのかなと。
人間関係や、午前、午後どちらがよさそうか、持っていきたい状態に対してどのぐらい時間がかかりそうかの見積もりなど。
事前準備など会議が始まるまでにどのぐらい時間がかかるか?
次のアクションをどの頻度で行うかなど、できる限り当日決めなければいけない量を下げておく必要があるというのが自分のやり方。
人によっては、想定内か、想定外かがすぐにわかるレベルまで準備しておくことというのも聞いたことがあるが、言っていることは結構近く、当日瞬発力を使って対応すべきことを極力少なくするという事かなと。
参加前に何かを対応してもらう必要があれば十分な時間を確保する事。できない場合は、事前に個別で依頼を掛けて、ふたをあけてみると参加者のレベル感が違うという事を避ける!根回しが重要。
実行編
上記の準備さえできていれば、グランドルールの説明。
自分の場合は、人の意見を途中で遮らないとか、正解不正解はないのでなんでも意見を出してOK,その人の意見にかぶせるのは歓迎など意見が出やすいように心理的安全性を高める。
または、軽くストレッチなどを行いながら一体感を造るようにアイスブレイク的な事を実施。
あとは、時間的な制約を確認しゴールの共有をしてスタートという状態。
自分としてはもっとも大変なケースは意見を言ってもらう所と、話が長いケースをどこで巻き取るかという匙加減。
ま、ここが腕の見せ所なので、自分としては今日のゴールと残り時間を常に参加者に見える所に置く所が重要と思っています。
時間に対して進捗が共有されていれば最悪の場合カットインできるし、泳がせたり、少しガイドしたりと調整ができるので。
ファシリとはちょっとずれるが、インタビューなど感情表現をいれて問いをいれると結構意見を引き出しやすいので、ここはつかえるかなと。もし意見が出ない場合は参考まで。
でも、ここは誰を参加者として迎えるかの設計の方が寄与度が大きいとは思っています。犬猿の仲の人たちを呼んでも意見が出る気もしないですし、上司部下の関係もそれに近いかなと。
あと、最近はオンラインで後輩が何度も言っていた、つたないファシリで迷走させてしまい、といった断りは使って一度、基本いらないし言わないと誓った方が場としてしまると感ましたので自分自身も気を付けていきます。
フォローアップ編
最後に会議で結論づけた内容について、参加者に確認していき、特にこれまでに発言がなかった人たちについては意識的に声を発してもらうおうと思っています。
なぜ、発言しなかったか(流れについてこれていない?発言にリスクを感じている?手が上げづらいなど)の分析はその場で必要がありますが。
なぜならば、自分がこの会議に参加する必要があると思って厳選して依頼をかけて参加してもらっているからです(何となく参加して内職をしているという人を割けるように心がけています)
結構次への具体的アクションと担当決め。これが大事で、議事録なども今はオンラインでタイムリーに録音しておきシェアする事、やる事リストを決めて、参加の感謝とともにフォローを入れるなどやってこそ会議の意味があるのかなと。
まとめ
改めてファシリテートについて色々学び直しをしてみたが、当日の対応も含めて結局どれだけ準備をしたかの影響度が高いと感じました。
安定した複数人の脳を使った問題解決を図るために、準備の項目についての項目のブラッシュアップを続けていきたいと思います。
特に生成AIや拡張機能を使っての生産性向上をしたいと思って色々探しているのでまた、別のタイミングでnoteにでも同行できたらと思います。
最後に、最近ファシリテーションではなく、インタビューの時なのですが、オブザーバーを立てて、インタビュー設計、準備状況、本番の雰囲気や所作など全体のフィードバックをする担当をつけていてトライをしています。
これがヒトの追加分工数はかかるのですが、自分の活動を客観的に知る事ができてチームとしての底力アップに寄与しているなと実感しています。
もしチームで動く時があれば、ファシリ、インタビューそれ以外でもオブザーバーに客観的に見てもらい自分の姿を知る事による改善効果が計り知れないので是非是非お試しください。
改めて今回ファシリテーションの押さえ所を構造的に振り返りできてスッキリできたので、他の学びの振り返りにも展開していきます。
同じような悩みを抱えている方一人にでも届けば幸いです。
ではでは
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
