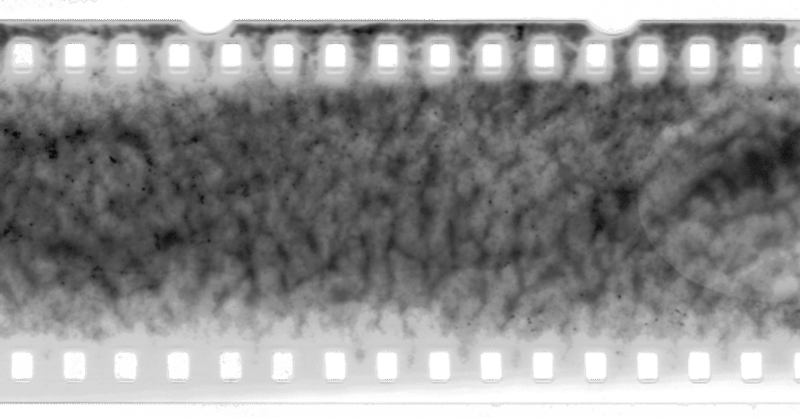
「小説」代替品のセックスで「描写注意」
大人向けの描写があります。
良い子になりたいと思った。
本当にそう思っていたのです、お父さん。
荒い息が聞こえる。耳元でだ。まるで聴覚からでも犯したいというものを感じる。私の股を割入って、打ち付けているのは男だ。まるで救いを求めるように私にしがみついている。挿入された熱い男のそれは、私の中をぐちゃぐちゃのどろどろにしていく。最初に挿れた時は確かに押し入れたような気がしたのだ。だけど何度も何度も、抉るように。そうしていくうちに私は男に慣らされていく。男のための肉の布団になるのだ。
「気持ちいい、気持ちいいよ……」
かすれた低い声が聞こえた。余裕のなさが伝わってくる。ノボリツメテイル。そう、男、名前はユウキだ。ユウキは私の唇を塞いでくる。止めて欲しい、息苦しくて、そして何より気持ちいいから。冷静にユウキの動きを見ているように見えて、私は熱にうなされてるかのようにおかしかった。割れ目からあふれ出る花蜜は、相手の腹の下の毛をぐちゃりと濡らしているだろう。綺麗に敷かれていたシーツには、おねしょのような、つめたいものが広がっている。体を重ね、まぐあい、腰がびくびくすると、これがでる。これが出そうになると、とても恥ずかしい。だってもう私は十六歳だ。高校生にもなっておねしょみたいにしか見えない、水たまりを作りたくない。あのひくつく感覚があると、おびえが走る。頭の中で「違うの」と「出てる」が乱舞する。
「やだ、やだっ……う、嘘なの……」
嘘じゃない、出ている。あ、あ……ああっ、なんてこと。そこに追い打つように、ユウキが小さく笑う。嫌みな笑いじゃない、ちょっと嬉しそうな、征服感がにじんだ声。
「何が、嘘なの?」
「違う、違うの……」
お互いが全てを把握している。しかし会話は一向にかみ合わない。やがて戯れのような会話は終わる。そんなモノより欲しいものがあるだろうと。私もユウキも互いを求める。ユウキの動きが激しくなった。
「い、いきそ……」
そんな言葉を息を吐くように言うと、私の言葉を待たずに激しく動く。こらえ性のない。私という蜜に溢れた肉壁はそんなに気持ちいいのか。心がぶるぶると震える。私も……気持ち、いいから……どうか、私を……ミンチ肉みたいに潰して欲しい。欲にまみれて、クソみたいな顔で地面に吐かれた白濁を舐めたくなるように……はっ……はあ……ああっ。台本みたいなセリフではなく、まるで喉が止められないと言った様子で嬌声を出す。ユウキはその声に誘われ、煽られ……強く私の腰を引いた。動きが、止まる。ぼんやりとしたまま、頭がぐらぐらと揺れているようと思いながら、ユウキを見る。ユウキは出している。私のナカに。ゴムがそれを防いでくれているけど。私は良い子でいたくて、避妊だけしっかりしていた。せめてこの情事を知られないようにと。
ユウキはいったい、どこの誰なのかが分からない。連絡先も知らない。
ただ毎週水曜日の、駅前のビル前で、ピンク色のイヤホンをつけてぼんやりと立っている。その存在を知ったのはクラスでも、浮いている子だった。
何か明らかに変わっていたわけではない。ただなんとなく浮いていたのに、あるときからそれ以上に、教室できゃいきゃい騒ぐ私たちとは歴然と違っていった。彼女は誰もいない教室で電子たばこを吸っていた。その唇は淡いラベンダー色に染まっていた。彼女はたばこを吸っていることにびっくりして荷物を落とした私を見た。真っ赤な夕焼けを背景にして。
その赤さは、まるで彼女を濡らしているようだった。彼女は私を見て、咥えていたたばこから口を離した。
「あなたって、好きな人、いるでしょ」
それは誰も知らないことだった。誰にも知られたくないことだった。
私はそれの思いを隠しきれなかったのか。私はとっさに核心を突かれるのは駄目なようだった。彼女は私の顔を見て……少し憐れんだ。
「それって、許されない恋なんでしょ」
「何の話?」
「顔に書いてるの。きっと、その相手は許されない人だろうって」
「よく分からない」
「だけどね、貴方の恋は熟れすぎている。いつ爆発したっておかしくない」
まるで占い師みたいだ。なんでこんなに私のことが分かるのだろう。事情は詳しく知らないはずなのに、私の感情は言い当ててきている。私はなんだか疲れていた。私の抱える思い、私の恋の狂おしさに頭がパンクしそうだった。今日は帰りたくない。家に近づいたら、それだけで私のショーツは静かに濡れていく。
「私の良い人、紹介してあげる。その人、いくらでも突っ込んでくれるよ」
「え?」何を?
「それが手に入らないなら、代替品のセックスをしたら? だってその人とセックスできないんでしょ」
小さく嗤ってしまった。私の心の底から欲望という水を掬いあげているようだ、彼女は。そうだ、私はその人とセックスをしたかった。あの人に抱かれたかった。愛を込めて、欲を込めて。腕の中で寝たかった。私を抱いて、そんな優しい抱き方じゃなくて。激しく私を貪るように。いつもつけている立場も、仮面も、全て外して……何もかも破綻しても良いから! 私をがむしゃらに愛して。
砂漠で十字架にはりつけられて、太陽に殺されても構わないから……!
私は目をつむり、それからゆっくりと目を開けた。
「何が望みなの? そんなこと、言い出すなんて」
彼女は密やかに口元を歪めた。
「私、暴くのが、大好きなの」
「……悪趣味」
「しょうがないじゃない。たまらなく好きなんだから」
彼女は電子たばこをセーラ服のポケットにしまった。そして私の顎を掴んだ。
動けない、そんな力が入っていないのに。困った、私に向けられる視線があまりに強い。まるでヘビだ。捕食する蛙を見定めている。
「口を開けて」
「え」
「望みがあるとしたら、あなたとキスがしたいの」
「えっ」
「ずっとね……思ってたの」
戸惑いのあまり半開きになった唇に彼女は自分のそれを押しつける。抵抗の間もなく、私の口腔をまさぐる。なめらかな動きの舌は私の全てを検知しようとする。
「あ……くっ……んんぅ」
キスは初めてだった。まさか女性からされるとは考えてなかった。けれども突然のキスなのに私の頭の中は揺れる。ぐらぐらと細く痩せ細った欲望の枝に灯が点る。おいしい……おいしいのだ。電子たばこのバニラの味。ふわふわとした酸欠に近い感覚。それがあまりに胸の奥を溶解していく。理性を地の底へと堕とすのだ。何だろ世界の色が、塗り替えられていく。彼女は、立っていられなくなった私を教室の冷たい床に転がす。そして口元の透明な雫を指で拭う。
「やっぱり……すごく、おいしい」
床の感覚を感じながら、私は彼女を涙目で見つめた。彼女が私を導く淑女に見えた。煉獄を彷徨う男を導く古典のそれのように。でも私が導かれていく先は天国じゃなくて、私を溶かして犯していく、甘美な溶液だ。
ユウキは一息つくと、着替え始めた。時間が迫っていた。私たちは二時間ぎりぎりまで、頭がおかしくなりそうなくらい交尾をしていたらしい。私もシャワーを浴び直して、きちんとたたんでいた下着に手を通す。
ユウキの肩は細かった。触って力を入れたら簡単に折れそうだった。ユウキはほっそりとした後ろ姿を私に見せながら、ふわんとした、印象のない声で言った。
「君ってさ、すごい濡れるけど……なんだろ、されるがままって感じだね」
「されるがまま?」
「うん、なんか海に漂ってるだけの丸太っぽい」
「何それ」
私はシャツのボタンをとめる。ユウキのふわふわした声が、するりするりと血液中に入り込んでくる。ユウキは顔だけこちらに向けた
「君は……堕ちてこないね」
「堕ちてこない?」
「僕のとこに来る人、皆堕ちたがるんだよ。どうしようもないところに」
「……」
「どうしたの?」
私はユウキを睨んでいた。何でだろう、何で睨みつけているのだろう。代替品に過ぎないくせに余計な口をと思っているのだろうか。いや、そうじゃない……彼は純粋に疑問なのだ。体を重ねる度にベットの上で溺れているのに、息継ぎできなくなるほどに感じているのに。私がまるで壊れる一歩手前で足踏みしていることに。どこの誰かも分からない男と体を重ねる……それだけでリスクを背負う。だけどそうせざる得ない、女、いや男もいるだろう。彼はたくさんの人の、心の身投げに立ち会ってきた。立ち会ってきて、分かるのだ、堕ちる人間の、息詰まりそうなほどに、花腐る匂いを。きっと、それは……私からも……。
私はそっぽを向いた。そして感情をぎりぎりに殺しながら、言葉を吐く。
「時間、近いよ」
家に帰ると、夜の七時だった。お母さんが、またちょっと遅くなってと、少し怒るかもしれない。お父さんはまだ帰ってこないだろう。それなりに偉くて忙しいお父さんだから。ところがドアを開けると、玄関先でお父さんが飼い猫の雪の背中を撫でていた。心臓が飛び出るほど驚いて、私は目を見開いたまま、一歩後ろに下がった。心の準備が出来ていなかった。本当に、出来てなかった。
「お、とうさん」
「お、待っていたぞ。帰り、少し遅いんじゃないか」
「ごめん……友達と勉強してたら遅くなって」
「それは感心するが、ほどほどにな」
お父さんはぽんぽんと私の頭を撫でるように叩いた。高校生なのに、子供みたいに扱う。でもお父さんとお母さんの間に生まれた唯一の子である私は、お父さんにとって、本当に可愛い娘のようだった。そう、とても可愛い……。
私は頬が熱くなるのを堪えるように唇を結ぶ。それから心をなだめて、出来るだけ平静な振る舞いをする。私はお父さんを見た。
「珍しいね。こんな時間いるなんて」
「ああ、今日は病院に同行しててね。早く帰ってきたんだ」
「同行? 誰の」
「母さんとだよ」
どうして、お母さんの病院にお父さんが同行しているんだろう。何か、あったのだろうか。私はざわざわと心の底が波打つように感じた。ざわざわ……まるで嵐が来る前の、風に揺れる小麦畑のようだ。
「何かあったの?」
「それは、母さんに聞いてくれ」
お父さんは楽しそうだった。とても嬉しそうだった。わくわくを堪えきれないという顔だ。ぞっとした、病院に行ったのに、どうしてそんなに嬉しそうなのか。背筋が氷の指でなぞられているようだ。もしくは死刑を宣告される被告のようだ。私は口元を押さえたくなる衝動を堪え、そろそろとお父さんに導かれてダイニングへと向かう。そこにはお母さんが、バラ色の頬で、満面の笑顔で立っていた。そして私にとって裁きを下すように、私の手を握った。
「聞いて……あなたに、弟妹が出来るわよ!」
え?
「赤ちゃんが出来たんだよ、母さんに」
ええ?
「……どうしたんだい? ×××」
私の名前を呼ばれた気がする。だけど、それは上手く聞き取れない。
私の中で今、何かが爆発した気がする。大きな心の柱が、ぽきりと折れた気がする。いや気がするじゃない。私の中で、終わってしまった。お父さんとお母さんは、まだ男と女だったのだ。お母さんの中に白濁した粘液を注入して、卵に植え付けた。それが、命となって実を結んだ。泣きそうだった、叫びそうだった、そんなの嘘だって、嘘なんだよって、お母さんのお腹を殴りたかった。
私の好きなお父さん(男)に、抱かれないでよ!
どうして、お母さんなら、それが許されるのよ……って。
私はどんなことがあっても、抱かれないのに。
性欲のはけ口にもなれないのに。
お父さんは、善良な男、優しい男、ただそれだけの男だ。
私はその男に、燃えるような恋をした。小さい頃から、ううん、生まれてその目を見た、その瞬間から!
愛して……愛して……娘じゃなくて女になりたかったのに。
どうして私は、娘として、お父さんに出会ってしまったのだろう。
私は精一杯、笑みを浮かべた。そして大げさなほどに拍手をした。
「おめでとう! お母さん。すごく、嬉しいよ!」
お父さんとお母さんは顔を見合わせて、それからほっとしたような表情を浮かべた。
「良かったよ、喜んでくれて」
「さっきはびっくりしすぎちゃったのね」
二人は納得する。私は胸の奥が煮えたぎっている。地獄の釜のようだ。内側から燃やされている。どうか私を燃やして欲しい。お母さんがいなくなって欲しい、消えて欲しい。そこの床で、絶命して転がって欲しい。十六年間子供を産まなかったから、油断していた。もう二人に、夫婦関係という契約はあっても、男女関係はないと思っていたのに。これは私のエゴイズムだ、私の勝手だ。理不尽を祈ろう。嫉妬で頭がおかしくなりそうだ。それでも心が事実によって責められていく。二人は愛し合っている。二人は愛し……合っている。そんなの嫌だ、私の愛した男なのに。私は今すぐだって、お父さんと唇を重ねて、その腰の上に跨がってしまいたいのに。
ユウキに開発されていく私は、ずっとそこの女より、良いナカをしている。
私は二人に笑い続けながら言う。
「私、ちょっと着替えるね」
そして自分の部屋がある二階に行くフリをして、家を出て行った。
駅前へと向かって、駆け出した。家から離れるほどに涙があふれ出てくる。
悲しい、いや心が潰されてしまいそうだ。悲鳴が出る。夜になり暗くなった外、どこからか犬の遠吠えが聞こえた。私は犬に憧れた。
犬だったら、父の中にある倫理を、平気で壊して乗り越えてしまうのだろうか。ああ、好きというのは頭をおかしくする。それともおかしい頭が、恋で悪化しただけなのだろうか。分からない、分からないよ。だけど分かることは一つ、あった。私は家族の側にいられない。この愛は、あの普通の幸せに溢れた家を壊していく。せめて、私という間違った娘を消してほしい。どうかどうか、なかったことにして欲しい。そうでなければ、私は、私は……もう、いい子でいられない。二人の愛を前にして、正気でいられない。
「あれ、どうしたの? また来るなんて」
駅前で、ピンクのイヤホンをつけたユウキが、私を飄々とした目で見ていた。
私はユウキをまっすぐに見る。駅前のはずなのに、断崖絶壁にいるような気分だった。私は崖先に足をかける。
「お願いが、あるの」
「なんだい?」
私は終わるだろう、堕ちるだろう。だけどその前に、私は……せめてお父さんの顔を思い浮かべて抱かれるのだ。
「私を孕ませて」
代替品のセックスで。
小説を書き続けるためにも、熱いサポートをお願いしております。よろしくお願いいたしますー。
