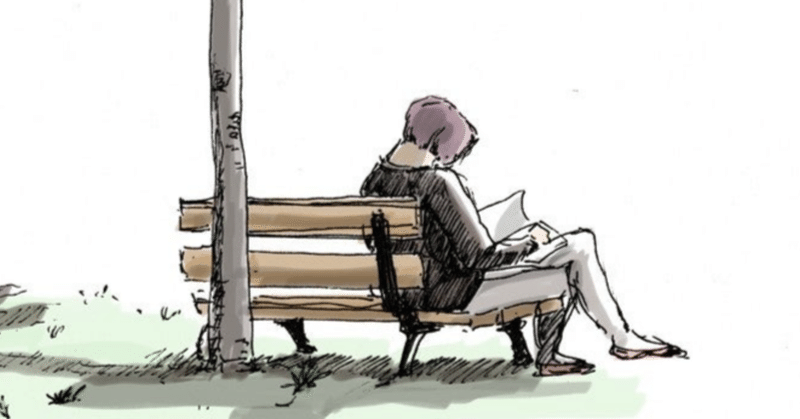
「グラッサー博士の選択理論」の紹介-選択理論心理学の基本書-
選択理論がわかる本の紹介#1
初めに、選択理論とは
この本は、ウィリアム・グラッサー(米国の精神科医。1925~2013)
が提唱した選択理論心理学の「母なる書」といわれる一番の基本書です。
原本の題は「選択理論」(Choice Theory)。
初めての人は、「選択理論」という言葉を見ただけで、「難しそう」「何か、よくわからない」と感じるかもしれません。
選択理論のセミナーや勉強会に出ると、「選択理論」という用語が飛び交っていますが、初心者には、何のことか分らず、「選択=洗濯」と連想して、「頭を洗濯されるのかな」と思ったり、「得体の知れない怪しさ、うさんくささ」を感じるかもしれません。
本の原題が「Choice Theory」なので、「選択理論」でしかたがないのかもしれませんが、せめて、「行動の選択の理論」です、とか「自分の行動の選択のしかた」、「自分の行動は、他者からコントロールされて決まるのでなく、自分が選択している、という考え方」という意味での「選択理論」です、と説明されれば、わかりやすいと思います。
グラッサーは、1925年に米国オハイオ州で生まれた精神科医であり、精神医療の新しいカウンセリング手法である『現実療法(リアリティセラピー)』で広く影響を与えると共に、公教育にも関心を持ち、教育において上質の追求をする改革を試み、『クオリティ・スクール』という本を著しました。
選択理論は、リアリティセラピーというカウンセリングの理論的土台であるだけでなく、精神医療の分野、個人の生活、学校運営(クオリティスクールが有名)や、刑務所内での矯正教育、ビジネス、組織運営、メンタルヘルスなどで、広く活用されています。また、あらゆる人間関係で活用が可能です。
現在では、選択理論とリアリティセラピーは、米国だけでなく、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ヨーロッパ、日本、韓国、ブラジル等、世界中に広がっています。(日本選択理論心理学会のHPはこちらです)
ところで、話は変わりますが、選択理論のセミナーや、カウンセリング(リアリティセラピー)のセミナーに出た人は、「選択理論で、一番大事なのは人間関係です。選択理論で、人間関係が良くなります」という説明を受けます。
グラッサーは選択理論で、「あらゆる不幸の源は不満足な人間関係に起因する」と述べて、人間関係の改善、良好な人間関係こそ、人々を不幸からすくうものだとしています。
選択理論を学び始めた人は、最初は、グラッサーの分厚い本には手を出さないので、講師から教わったことを、そのまま理解して、実践していれば、それはそれで、問題はなく、自分の生活でいろいろと成果を上げることができます。
ところが、学習者が、選択理論の学びを進めて、この本を含め、グラッサーの本を読みだすと、よくわからないことが、いろいろ出てきます。
選択理論は「行動の内的コントロールの理論」
まず、選択理論は、出発点は「人は、なぜ行動するのか。どのように行動を選択するのか。そして、どのように自分の行動をコントロールしているのか」を説明する内的コントロール心理学の理論です。
ところが、この本の副題は「個人の自由のための新しい心理学」(A NEW PSYCHOLOGY OF PERSONAL FREEDOM)です。
そこで、まず、「自分の行動選択のしかたの理論」が、なぜ、「個人の自由のための理論」であるのか、その関係が分りにくいです。
また、この本の原本の表紙には、「あなたが生きたい人生を選択することと
、あなたが必要とする人と親しい関係でいつづけること」(Choosing the life you want to live and staying close to the people you need)というフレーズが記載されています。
選択理論の出発点は「自分の行動選択のしかたの理論」なのに、なぜそれが「個人の自由のための心理学」と関係し、また、「あなたが必要とする人と親しい関係でいつづけること」という「良好な人間関係」に関係してくるのかがわかりにくいです。
つまり、「自分の行動選択のしかたの理論」と「自分の自由」と「自分の良好な人間関係」の、3つの関係がわかりにくいということです。
普通に考えれば、「良好な人間関係を保つには、自分の自由ばかりを優先させることはできない」ということになり、「自分の自由」と「良好な人間関係」は、一方を重視すれば、他方をがまんしなければならないトレードオフの関係ではないか、と思う人も多いでしょう。
この点については、「本人の行動をコントロールできるのは本人だけ」だと理解し、「外側から本人に与えることができるのは情報だけ」だと理解すると、過去の情報も、新しい情報も、本人には単なる情報に過ぎず、本人は外側から入ってきた情報を、自分の内的行動システムで処理して、自分の行動を選択している、つまり、自分の行動は、すべては「自分の選択」によるものだ、ということがいえます。
このように、選択理論では、本人の行動は、外側の他者や環境、状況が決めているのではなく、あくまで、本人が自分の内側の「行動の内的コントロールシステムとしての脳」によって決めている(選択している)、と考えます。
自分が不幸である場合も、それは外的要因によるものではなく、自分自身が自分の内側で、不幸になる選択をしているのだし、
自分が今現在、マイナスの心理状況にあるのであれば、それも、自分自身が選択している、ということです。
そして、本人は自分で不幸になる行動、考え方、ものの見方を選択をしているのだから、今から未来に向けて、今の選択とは異なる、幸せになる行動、考え方、ものの見方を選択をすることができる、とします。
人がコントロールできるのは自分の行動だけである
そして、その一方で、
選択理論では、人がコントロールできるのは自分の行動だけである、他者を外側からコントロールすることはできない(他者を変えることはできない)、と考えます。
自分が自分の行動を内的コントロールしているのと同じように、他者も本人の内的システムで行動をコントロールしているのだ、人が自分の外側から受け取るのはあくまで情報であり、人は自分に入ってきた情報を処理して、自分の内的システムで行動を選択している(決めている)、と考えます。
以上が、選択理論の「行動の内的コントロールの考え方」です。このように、選択理論は、「本人の内的コントロールによる行動選択」について説くものです。これが出発点です。
外的コントロール心理学とは何か
そして、この考え方の対極にあるのが、「人は自分の行動を、外側の他者や状況、環境によってコントロールされて、決められている」と考える「外的コントロールの考え方(外的コントロール心理学とか、外的コントロールの信条と言われます)」です。
例えば、多くの人は、「誰かにひどいことを言われたので落ち込んだ」といいますが、これは、その人が「自分の行動(行為、ものの見方、考え方、気分、感情など)は、自分の外側の他者によって決められる」という「人の行動についての、外的コントロールの考え方」を持っている(採用している)ということになります。
これに対して、「人の行動についての、内的コントロールの考え方」である選択理論では、「誰かにひどいことを言われたので落ち込んだ」のではなく、「自分が、自分の内的コントロールによって、落込みという行動を選択した」と考えます。
そして、「自分は、落込みも選択できるけれど、元気になる選択もできる。元気になるための行動や、考え方、ものの見方を選択すれば、自分の気分や感情も間接的にコントロールできる」と考えます。これが選択理論の「行動の内的コントロールの考え方」です。
人の長く続く心理的な問題の原因は、現在の人間関係にある
また、選択理論では、人の長く続く心理的な問題の原因は、現在の人間関係にあると説いています。
「自分にとって、身近で大切な人間関係をよくすること」で、愛と所属の欲求や力・自己価値の欲求をはじめとする5つの基本的欲求を満たすことができます。
にもかかわらず、私たちは、
「相手の言動が自分の気分が悪くしているのだから、相手が変わらないと自分の気分はよくならない」とか、「相手がしゃくに障って気分が悪いから、自分が相手を変えてやろう(自分は相手を外側から変えることができる)」という「外的コントロールの考え方」を、お互いが無意識に採用しているために、仲たがいが起き、互いの抵抗や反発、逃避などを招き、互いに欲求を満たされず、不幸になっているのだ、とグラッサーは考えました。
しかし、このように「相手が変わってくれないと、自分も変われない」「外側の状況が変わらないと、自分の気分や感情も変わらない」、「自分の行動は外側の他者や状況によって決められているので、自分は行動を自由に選ぶことはできない」(つまり、自分が外的コントロール心理学を採用している)となると、自分が不自由になります。
なぜ、「個人の自由のための新しい心理学」なのか
これに対して、「自分の行動は、自分の内的システムで、自分が決めているし、決めることができる」という選択理論の内的コントロールの考え方を採用すると、「自分の行動は自分が自由に決められる。どんな状況にあっても、自分には自分の行動を自由に選択できる余地がある」と考えることができます。
このように、選択理論の「行動の内的コントロールの考え方」を採用することで、「自分は、今以上に自分の欲求を満たせる行動を選択でき、今以上に、人間関係をよくして、より自由に、幸せに過ごすことができる」ということが、グラッサーが、選択理論を「個人の自由のための新しい心理学」と名付けたゆえんであると思います。
人は自分の行動に責任がある。だから自由になれる
「人はあらゆる行動を、本人の内的システムで選択している」。だから、私たちは、自分がいま置かれている状況や、理不尽な相手、辛い過去など、自分の外側のことによって(自分の外側のことに振り回されて)、自分の状況や、気分や感情を決められているのではない。
自分の行動や考え方、気分や感情は、誰かのせいや、何かのせいではなく、自分が選択しているのだ。だから、私たちは、自分がとっている行動の責任がある。私たちは自分の基本的欲求を自分で満たして、未来に向って幸せになれる行動をとっていく責任がある、
というのが「選択理論」のスタンスです。
このようにみてくると、選択理論は「本人に行動の責任がある」と、非常にきびしいことを説いているように感じられるかもしれないですが、本当にこの「本人(自分)に行動の責任がある」というスタンスに立ちきったら、自分の行動は、何にも、誰にも左右されず、「自分の人生の舵を自分でコントロールしている」と感じられる真の自由が手に入る、ということになります。
選択理論の活用領域
出発点として「人は内的コントロールによって行動を選択している」と考える「選択理論」は、カウンセリングなどの対人支援や教育、人や組織のマネジメントの基礎理論として使うことができます。また、個人だけでなく、夫婦、親子、上司と部下、教師と生徒などを含むあらゆる人間関係に活用することができます。
「グラッサー博士の選択理論」には、家庭、学校、職場、地域での豊富な活用実例が挙げられています。
この本には、先生と生徒、上司と部下、夫と妻、親と子供といった人間関係に、選択理論を応用することにより、良好な人間関係をつくるための考え方、よりよい人間関係を構築し不幸をなくすための考え方や方法が書かれており、実際の結婚生活、職場、学校、地域社会などでの具体例、カウンセリングでの会話例も多く掲載されています。
第13章の「選択理論の10の原理」
なお、「グラッサー博士の選択理論」がもう1つ重要なのは、グラッサーが、この本の第13章において、「自由への道」という見出しのもとで「選択理論の10の原理」をまとめていることです。
「選択理論の全体像」をつかもうとするときには、この第13章を、原書を含めて、何度も熟読して理解することが、最重要であり、近道だと思います。
第13章で、グラッサーは、概ね、次のようなことを述べています。
・本書を通して、私たちが自分の人生で、外的コントロール心理学を選択理論に置き換えるなら、どれほど多くの自由が得られるかを私は強調してきた。ここで私は、「選択理論の10の原理」と私が呼ぶものに焦点を当てよう。このような原理を通して、私たちは「自分の自由の範囲(「自分の自由域」-筆者の用語)」を定義し、また、再定義することができる。
・私たちがコントロールできるのは自分の行動だけだ、と実際に意識し始めると、(このように意識転換すると)自分が思っている以上に、たくさんの自由を持っていることに気づく。
しかし、現実は、多くの人が、このような意識転換をすることができず、できないこと(相手をコントロールすること)をしようとして不自由になり、それにより、自分と相手の欲求が阻害され、満足できる人間関係が持てず、長期的な心理の問題を生じさせている。
それゆえ、人々は、外的コントロール心理学をやめ(手放して)、選択理論(10の原理)を採用してこれを信条とし、行動や思考の内的コントロールによって、自分の自由の範囲を広げ、満足できる人間関係を持てるようにしよう。
選択理論の全体像としての「選択理論の10の原理」
第13章の「選択理論の10の原理」を簡潔にまとめますと、筆者としては、次のようなものになると考えます。
第1の原理: 人は自分の行動をすべて選択している。そして、 人がコント
ロールできるのは自分の行動だけである。
第2の原理: 外から人に入ってくるものは全て情報である。人が他者に与え
ることができるのも情報だけである。情報をどう知覚して対応
行動を選択するかはその人の自由である。
第3の原理:人の長期間続く心理的な問題は、人間関係が原因である。
第4の原理:問題のある人間関係は、現在の人間関係である。
第5の原理:過去の苦痛や、いやな思い出を探索しても、現在の問題解決の
役には立たない。また、自分が過去の犠牲者になる選択をしない
限り、過去の犠牲者になることもない。
第6の原理:人は5つの基本的欲求(愛所属、力/自己価値、自由、楽しみ、
生存)を満たすべく行動する(行動が内的に動機付けられる)。
第7の原理:人は、脳内にある「上質世界」に貼付けられた願望のイメージ
写真を満足させることでのみ、基本的欲求を満たせる。
第8の原理:人がすることはすべて行動であり、行動は4つの要素(行為、
思考、感情、生理反応)からなる「全行動」である。
第9の原理:全行動は「○○行動をしている」「○○行動を選んでいる」と動
詞的に表現され、最も認識しやすい要素によって 「~行動」と呼
ばれる(例、行為行動、感情行動)。
第10の原理:人が直接変えられるのは行為と思考である。感情と生理反応
は、行為と思考を変えることで間接的にコントロールできる。
なお、重要なこととして、グラッサーは、「10の原理」の説明の後に、次のような意味のことを述べています。筆者なりにまとめますと、
私たちが、「人は自分の行動だけをコントロールできる(他者を外側からコントロールすることはできない)」という、選択理論の原理を採用せずに「基本的欲求」「上質世界のイメージ写真」「全行動」というアイデアを使うと、私たちの行動は、「相手に対する外的コントロールの行動」となり、相手との人間関係も、自分の自由な生き方も、うまくいかないであろう。
逆に、私たちが、「人は自分の行動だけをコントロールできる(他者を外側からコントロールすることはできない)」という、選択理論の原理を採用し、「基本的欲求」「上質世界のイメージ写真」「全行動」というアイデアを使って、自分の行動を内的コントロールすると、相手との人間関係を良好にでき、自分の自由な生き方も確保できるであろう。
そして、上記の「10の原理」を見てみると、
・第1と第2の原理が、「人の行動の内的コントロールの考え方」について
・第3から第5の原理が、「人の精神的な健康と幸せにおける、人間関係の重要性」について、
・第6から第10の原理が、「行動の内的コントロールシステム」としての「脳の働き」について、
というような、いわば、3部構成になっている、といえるでしょう。
そして、第13章の最終パラグラフで、再確認として、グラッサーは、私たちが、「人がコントロールできるのは自分の行動だけである」という選択理論の原理(第1の原理)を採用してはじめて、「10の原理」を「選択理論の土俵」の上で使うことができ、私たちが、人間関係を良好にでき、自分の自由な生き方も確保できる、と述べています。
以上が、グラッサーの選択理論の最も重要な「全体像」を簡潔に示したものであると思います。
長文になりましたが、上記の文章が、皆さんが「グラッサー博士の選択理論」を読み進めていく際の参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
