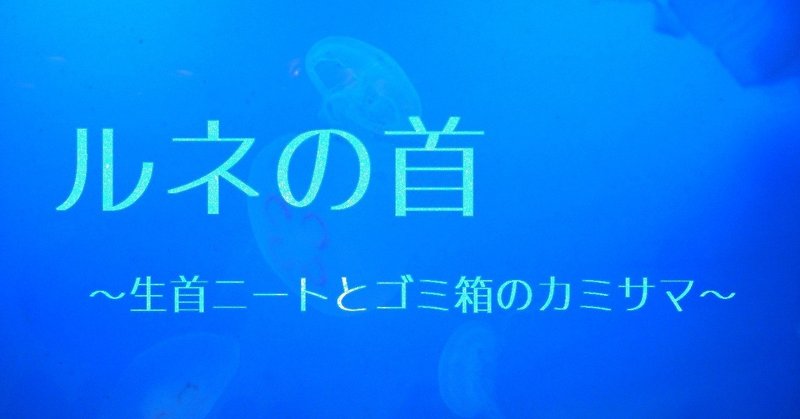
ルネの首 #16 カミサマの居場所
「こんなところにいた」
セツェンが、屋根の下から身を乗り出してきた。イサたちに居場所をきいたのだろう。
戻ろうとしたら、セツェンも屋根に上がってきた。
ナオの隣に腰を下ろす。
「ここの屋根に上ったのは初めてだ」
「そうなの?」
「ここ、アズの自宅だから、ずっと通ってるのにな。いい家に住んでいるって思うだろ」
隠れ家ではなかったらしい。確かに、隠れ家というには上等な住居だとは思っていたけれど、まさかの自宅。
いいのだろうか、自宅に重大な秘密っぽいルネを匿っていて。自宅だからいいのか。監視がないから。
「アズはあれで、けっこうなお嬢様なんだよ。育ちはこっちだから、あんまりそう見えないけどな」
「うん。めっちゃ普通にお姉ちゃんだなって感じ」
「お姉ちゃんって呼んでやれば? アズは喜ぶぜ?」
「弟がグレてお姉ちゃんって呼んでくれないもんね」
「ナオ、お前な……」
セツェンの苦虫をかみつぶしたような顔を見て、ナオはくつくつと笑った。ルネも笑っているらしい。コポリと泡が漏れる音がした。
「セツ兄に、聞こうと思ってたんだ。ぼくの兄弟のこと」
「ん? お前の兄弟?」
セツェンは、ナオがどうしてそんな話をしだしたのか、見当もつかないようだ。当然だ。ナオは彼に、イサたちを助けに行く直前に、思い出したことをまだ話していなかった。セツェンと、出会った日のこと。
「ぼくを拾った時、セツ兄言ったよね。妹だけでも、って」
「あ、ああ……言った、かもな。あの時は焦ってたから」
セツェンは、あからさまに「失敗した」とでも言いたげな顔をしながら、しどろもどろと答えた。誤魔化せばいいのに、本当に嘘のつけない性格だ。
だからこその、セツェンである。ナオがずっと頼りにしてきた、この下層の奥底から引っ張り上げてくれた手を持つ人。多分、今までずっとナオの『カミサマ』だった。
「ぼく、兄弟の名前も顔もうろ覚えだけど、イサたちを探している時に、なぜかパッとセツ兄がぼくを抱えて逃げた時のこと思い出したんだ」
「どうしてだよ、ホント」
「わかんないよ。セツ兄とアズさんを見てたからかな。でも、ああ、セツ兄はきっと、ぼくの兄弟のこと知ってたんだな、って。今思えば、兄弟が研究所に売られた話して、すぐ諦めろっていったのも、知ってたからだよね」
あの日、混乱した下層の街で、ナオはセツェンを見つけた。鮮やかな青と緑に染まった髪を見つけて、そこで目があった。ナオはセツェンの髪に驚いただけだったけれど、セツェンは知っていたのだ。
だから、セツェンはナオを連れて逃げた。
「トキだよ」
「ん?」
「お前の兄弟の名前。トキ、だ。研究所で一緒だった。あそこはろくな場所じゃなかったけど、トキはいいやつだった。ナオって妹がいる。下層に戻れたら、様子を見に行ってほしいって頼まれた。よく似てたからすぐわかった」
「……そっか」
「でも、お前を拾ったのは俺の個人的な意思だよ」
ただ、友達の妹だったから、拾った。そんな理由だけで、何年もナオを守ってくれたわけじゃない。それだけなら、他の子供を拾ってくる必要はない。
セツェンにとって、子供たちを守ることが生きるための支えだったなら、子供たちが『カミサマ』の代わりだったのなら、頑なに一人で戦っていた気持ちもわかる気がする。
そうしないと、立てない。人は何かを信じなければ、空っぽのままでは生きていけないから。
「ぼく、兄弟のことは全然覚えてないのに、親よりも優しかったのは覚えてる」
「それでいい。トキも喜ぶ。お前を拾った俺も嬉しい」
「セツ兄も嬉しいの」
「そりゃ、俺にとってもお前は、下の子もだけど、家族みたいなものだから。アズとは少し違うけどさ」
「そっか」
「だから、今回は俺がナオにお礼を言わないといけないんだ。イサとエミルのこと、諦めないでいてくれてありがとうって」
「あはは、そんなこと!」
今までどれだけセツェンに助けられてきたかわからない。
まるでそれが当前みたいだったのに、ほんの一回返したくらいでお礼なんて。
セツェンが自分のために頑張っていたのでも、子供たちを守るという信念にすがることで生きていたのだとしても、助けられてきたのは事実だ。
「ぼくはカミサマを信じてないけど、多分ずっとずっと、セツ兄のことをカミサマみたいに思っていたんだ。役に立ちたいけど、全然届かない。近くにいるのに遠い」
セツェンはルネに「話したのか?」と尋ねたが、ルネは『流れで』と悪びれもせずに答える。
「いいから聞いて、セツ兄。ぼくはね、勘違いしてたんだ。セツ兄のこと全然わかってなかった。自分のこともわかってなかった」
存在しないものはわかりようがない。信じようがない。
だから『カミサマ』なんて、自分には絶対に縁がないし、わからなくてもいいと思ったのだ。
ルネを小脇にかかえて、ナオは屋根の上にすっくと立ち上がった。あぐらをかいていたセツェンは、行動の意味を測りかねたのか、首を傾げた。
「セツ兄、ぼくはね、とても役に立つよ!」
「……んん?」
突然の宣言に、ナオを見上げたセツェンはぽかんとした様子で口をあけた。ますます首が傾く。
「すごく役に立つ! ルネくらい、厚かましく言うよ! ぼくはとてもセツ兄の役に立つ!」
ルネが『おい……』と言ってきたが、無視する。
「セツ兄がどうにもならない時はぼくが手を貸す。それにぼくはこれからどんどん賢くなる。もしかするとセツ兄よりも賢くなるかもしれないので、めちゃくちゃ役に立つ!」
「そ、そうか……」
「だから、セツ兄をもうカミサマにしない。セツ兄の仲間になる!」
「……いや、今でも仲間は仲間だろ」
真顔で返されたが、「違う!」と続く言葉をさえぎった。
「全然わかってない、セツ兄。もう、全然。一人で何でもやってるじゃん。全然だ! 仲間ならもっと頼れよな!」
セツェンはここで、ようやく、ナオの言いたい事を多少なりとも理解したらしい。
小脇にかかえたルネが一言。
『だ、そうだが……どうするんだ? セツ』
「はは、はぁ……カミサマか……そうか、カミサマか」
セツェンは困ったような顔で笑ったけれど――。
「俺のカミサマはもういないけど、俺がカミサマでいる必要もないよな」
「そうそう。カミサマ分業制でいこうぜ」
「分業とか、難しい言葉を覚えたなぁ」
『僕の功績をたたえてくれていいぞ』
「「調子にのんな」」
セツェンとナオの声が綺麗にハモる。
『酷い仲間たちだ。生首に冷たい』
「じゅうぶん生首に優しいだろ、ぼくら」
ケラケラと笑い飛ばした。
この下層で、人間たちはネズミのように生きている。
隠れ住み、時に争い、時に追われ、理不尽に食い散らかされて、上層のおこぼれをかじりながら生きている。
目の前に広がるのは、ゴミ箱と呼ばれる街。その名の通り薄汚くて最悪で――だけど、嫌いではない。
こんな場所でも、生きていける。信じていける。
信じられる心の支えが『カミサマ』だ。だから、誰だってカミサマになれるし、誰もカミサマにならなくていい。
「いつか……俺のカミサマだった人の話もしような」
「うん、聞かせて」
『それは僕も聞いて良い話か?』
「お前が上層に帰ってなければな」
『それはそれは、下層にいる楽しみが増えたな』
カミサマはいないけど、どこにでもいる。
このゴミ箱の街にも。
ルネはどこからきて、どこへ行くのか。セツェンは今まで何を背負ってきていたのか。
わからないことたくさんのことを、これから知っていく。
そして信じるものを、選ぶのだ。
「ルネ先生、これからも頼むぜ」
『任せろ、僕は役に立つ」
「ぼくもお前に、罵倒語を教えるのに役立つぜ」
『教えなくていい!』
ルネの反論を見て、セツェンは笑っていた。
まるでただの十五歳の少年のように、お腹を抱えて笑っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
