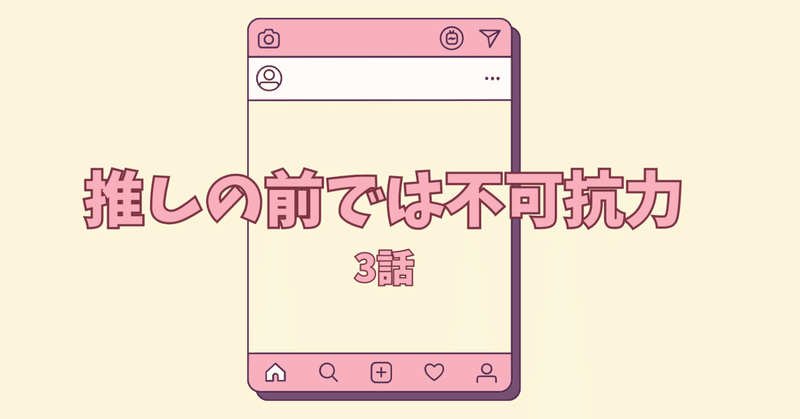
推しの前では不可抗力 3話
次の日は学校を休んだ。ネットの特定厨はすごい。SNSもろくにやっていない私の名前と学校を突き止めた。くまPがそこに通っていることも、朝日陽という名前であることも晒された。
モザイクなしの写真たちは今も拡散され続けている。コメント欄には「こんな芋女が彼女なわけないじゃん」「ブス」「◯ね」と悪意の槍みたいな鋭い言葉たちが立ち並ぶ。初めて息のしかたが分からなくなる。昨日の夜以降見るのをやめたけど、家にいるとその言葉たちが脳内をぐるぐる回って、心臓の音がずっと耳の奥に響く。
テテテレレレン♪
「……もしもし」
「いる、大丈夫?じゃないと思うけどしっかり!」
「うん……。ありがと。学校どんな?」
「ずっと上級生とか他のクラスの人が見に来てごった返してるよ」
「ごめんね……迷惑かけて」
「私は大丈夫。しばらく学校休んでたほうがいいかもね……」
「転校しないといけないかなぁ」
「朝日くんは転校するかもね……」
「……」
自分が招いた結果だけど、悲しくてたまらない。朝日くんにはもう会えないだろうな。……やっぱり最初に聴かせてくれた生歌、録音しとくんだった……。
じわぁ。目尻からボロボロと雫が落ちる。とめどなく流れて、枕が段々と冷たくなる。
「うっ……う」
ガチャ。
「!お母さん」
「……。大丈夫よ。お母さんがどうにかする」
「…………。アンチって怖いんだね」
「アンチは怖いわよ。彼らはくまPにもいるかにも別にそこまで怒ってない。というかほぼ興味すらないの。ただ煽ってるだけ。なんて言えば人が傷つくかしか考えていないの」
「どうすればいいの……?」
「風向きを変えるのよ」
「風向き……?」
「いるかはどうしたい?私の娘として公表すれば、この一件の流れにのっているかの顔も売れる。そういう活動に興味があるならそうする。でもそうじゃないなら、いるかについては触れずにやってみる」
……考えたこともなかった。部屋の角に置かれた金色のメダルに目が行く。私の母、岸くるみは「クルミ」として活動する現役動画配信者だ。フォロワー100万人を超える超有名クリエイターで、アパレルブランドを国内外に展開、自著の書籍も毎回ベストセラー入りをするトップインフルエンサー……。
「私は……今表に出たいとは思わないかな……」
「分かった。そしたらちょっと今日の夜配信するから。できることはやってみる」
「最近のアンチについて」
母は優しそうなその見た目とギャップのあるストレートな物言いが人気となり、ご意見番のようなポジションを確立している。同じ家の中にいるのに、画面越しに母をみるのは小さい頃から当たり前の習慣になっていて、もはやなにも違和感がない。
「私ね、10代の時に初めて炎上を体験したんですけど、ほんっとに意味がわからない炎上の仕方をしたのねwww」
「アンチって、してる側はほぼ面白半分だと思うの。あとは、鬱憤をどこかにぶつけたいだけみたいな。だけど、言われてる側って、気にしなくて良いって分かっていてもアンチの言葉をそのまま受け止めちゃうのね。1人にブスって言われたら、その言葉が忘れられなくて、どんなに時間が経っても、ふと寝る前とかに頭をよぎるの。そのたった一言にずっと縛られちゃう。最近10代の子も容赦なく晒されてるけどさ、大人が止めないとダメだよね。」
――
配信終了後、くまPが晒された写真の投稿には瞬く間に100件以上の投稿を消すことを求めたコメントが殺到。多数のスパム報告によってアカウントがBANされ、その投稿も消えた。
くまPの個人情報は、元の投稿が削除された後もいくつかのSNSアカウントやネット掲示板で掲載されたが、それらも全てBANされ、どのSNSでも拡散されなくなった。確固たる証拠はないが、クルミの発信によって世の中が動いたことは一目瞭然だった。
「……お母さんすごい。ありがとう……」
「くまP、お友達なんでしょ?」
「うん。たまたま編入してきて同じクラスになって……」
「連絡はとってる?」
「ううん……。たぶんもう連絡来ないと思う。学校もやめちゃうだろうし」
「……いるかは?学校行ってみる?」
「うん。明日から行く」
「強いなぁいるかは。でも無理しちゃダメよ。あと、いざとなったらクルミを使いなさい!(笑)」
「お母さんが強すぎるんだよなぁ(笑)」
学校のことくらいは自分でどうにかしないと。メッセージアプリを開いて一番上のツバメとのトークをタップする。
「明日から行くよ。心配かけてごめん」
「まじ!もうぼっち嫌だよ〜!駅から一緒行こ!」
「ツバメ様心強いです……」
「ジュース奢ってくれ」
「仰せのままに」
ふふっ。安心する。スマホの中のSNSは全て消して、ツバメと話すためのメッセージアプリだけを残した。SNSを見ないだけでも、少しは心が落ち着く。ほんと一人でも友達がいてよかった……。
――
みんながいる教室に入るのが怖くて、朝7時に集合することにした。
「いる!!!」
「おはよう」
「久しぶり!なんか……痩せたね……お疲れ……」
「まじ……?ダイエットできたのは嬉しいわ……(笑)」
「学校しばらく休むと行きたくなくなるよね〜」
「うん。今結構やばい……」
「大丈夫大丈夫!うちのクラスそんな治安悪くないから!ねっ」
まだ人がまばらな教室に入り、席につく。
「あ、おはよう!岸さん大丈夫?」
「うん……!色々とお騒がせしました……」
「ねぇ岸さん!くまPとは付き合ってないの!?」
「え……付き合ってない!断じて!」
「え〜!でもすごいよね朝日くん超有名人じゃん!」
純粋に気にかけてくれる子、ゴシップ情報を聞き出したい子、色々なタイプがいるけど、思ってた以上に普通に接してくれるクラスメイトたちにほっとした。
「いるかちゃん〜!寂しかったよ〜!」
まりあちゃん。この前から、あからさまに朝日くんに近づくためのだしに使われていて、ちょっと苦手だ……。
「ね、ちょっと話そ!こっち来て!」
「え、どこいくの!?」
――
まりあちゃんに強引に腕を引っ張られていくと、空き教室についた。
「ねぇ、みんなと話した?」
「あ、うん。みんな優しくて……」
「ふーん、みんな怖いなぁ。裏ではすごい言われてるんだよ」
「え?」
「ほら」
まりあちゃんが自分のスマホの画面をぐいっと近づけてくる。目に飛び込んできたのは、メッセージアプリのグループチャットだった。
グループ名 4E裏(12)
「陰キャすぎない?w」
「このアンチナイスすぎる」
「てか朝日イケメンだよねやっぱ」
「岸さん金でも渡してた?www」
「一生学校来ないでほしい」
うっ……。怖い。胃酸が喉に上がる。重力が突然倍にでもなったみたいに、身体がずんと重くなる。
「私はやめろって言ってるんだけどみんな聞かなくて……。ごめんね……。あ、いるかちゃんがあとで先生に言えるようにスクショ送っとくね。私は友達だからねっ!」
「……」
教室に戻っていく彼女の背中をただぼうっと眺める。送られてきた画像には、彼女以外のクラスメイトが好き放題言っている部分が切り抜かれている。友達だから、なんて白々しい。先生に言いに行く気力もない。ツバメがいてくれても、こんな状況じゃさすがにキツい。このまま帰ろう……。
「いるっ!」
振り返ると、朝日くんがいた。
「……!なんで……」
少し茶色かった髪は真っ黒になり、短髪になっている。色んなところで誠意を見せる必要があったんだろう。
「うっっ……っごめん。私のせいで……可愛い茶髪が……」
「泣かないで。俺が悪かった。この前、いるも不安なはずなのに俺ひどかったよね……ごめん。ってか可愛い茶髪ってなに(笑)」
「分かんない……ズズッ」
「携帯持つよ、ティッシュある?」
「ありがとう……」
朝日くんが私のスマホに目をやったまま硬直する。
「……なにこれ」
「あ、いやこれは……」
「……」
……こんな怖い顔の朝日くん初めてみた。真顔で向こうを眺めていたと思ったらぱっとこちらに向き直る。しゃがみ込んで、私の顔を覗く。朝日くん、こんなに優しい目だったっけ……。
「いる、俺この学校にいてもいい?」
「へっ?転校しなくていいの……!?」
「いるが嫌じゃなかったら、俺はここにいたい。いるもここにいてほしい」
「でも……」
「大丈夫!」
二カッと歯を見せて笑う。こんな状況でそんな風に笑えるんだ……。
「強いなぁ」
「ん?なんて?」
「あ、ううん。でも、大丈夫っていっても……」
「大丈夫。風向きを変えるんだよ」
「えっ……」
「俺にまかしとけぃ!」
――
「えー!この度はお騒がせしてしまって本当にごめん!知っている人も多いと思うけど、歌い手としてくまPっていう名前で活動してます、朝日陽です!改めてよろしくお願いします!」
「いるかは、俺が編入してきた日にくまPだって気づいてたんだけど、隠していてくれた大事な友だちです!だからネットにあるようないかがわしい関係じゃありません!それは別にどうでもいいと思うけど!(笑)とにかく、ぜひまたこのクラスで仲良くさせてください!ということでお詫びに歌います!あ、撮影は色々あったから今日はNGで……!ちゃんと聴いててね!♪〜」
――
「くまPよ、今この状況であの子を救えるのはお前だけだ。女の子一人、ちゃんと救えなくてどうする。そのフォロワー数はただの数字じゃないんだ。影響力って言うだろ?みんなの心の風向きを変えるのはお前の仕事だ」
そんなこと、考えたことなかった。ずっと自分が楽しくて歌ってきた。
誰かのために歌うのは、たぶん今日が初めてだ。
ありがとうほんとうありがとう
