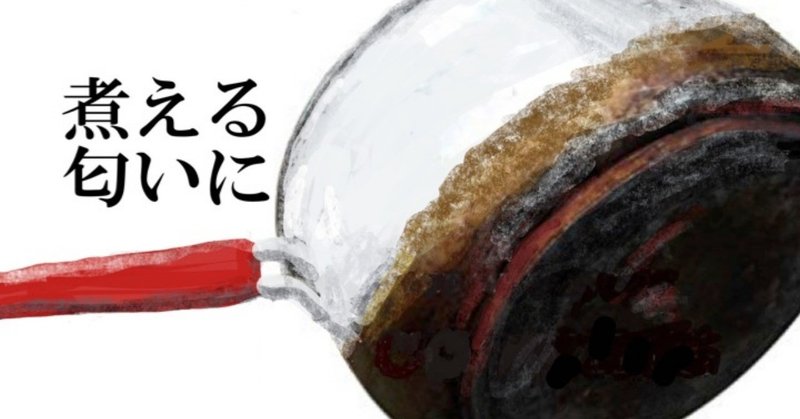
煮える。炊ける。みんなで食べる
「煮炊きの煙は、人の心を暖める」宇江佐真理による時代小説『卵のふわふわ』(講談社)の内容紹介は、この一行から始まる。
そうね、いま、煮炊きの煙は見えない。でも、煮る、炊く、焼く、茹でる、蒸すといった料理の手順は昔と変わらない(チンするという方法も増えたが)
住まいは、料理をして、食べる場である。家事の中心は、食事を用意することであり、家族とは共に食べるメンバーをいうのかも知れない。
1895年のパリ、世界で初めて映画が有料上映された。フランスのリュミエール兄弟が撮影した。その一作が「赤ちゃんの食事」。https://www.youtube.com/watch?v=QP0oz5gEQ34
リュミエールの兄夫婦が、コーヒーを飲み、娘にビスケットを持たせる。赤ちゃんは、食べようとするが、ふと手を伸ばす。たぶん、撮影しているリュミエールの弟夫婦に「あげる」という仕草をしている。
リヨンの春、自宅の庭で朝食をとるリュミエールの兄一家の後では、木々が揺れている。風は強く、赤ちゃんの着ている白い服のエリが、彼女の顔をおおってしまう。
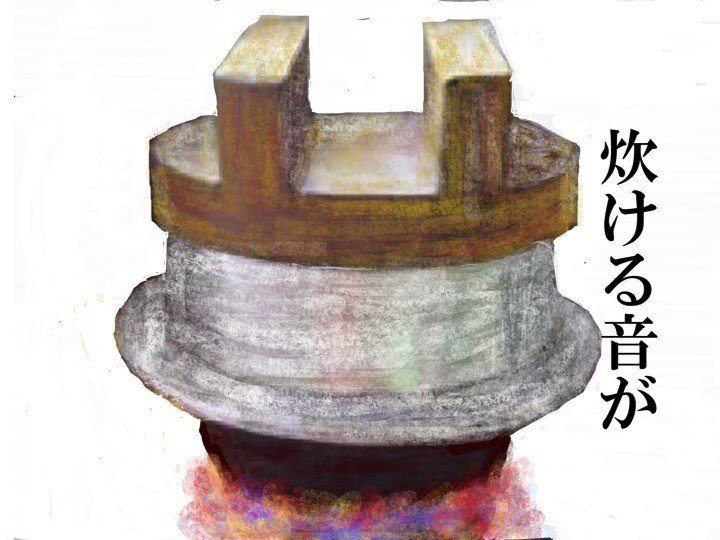
煮る匂い。炊ける音。その背景には、いま、料理を作っている人と、まわりの人との関わりがある。「赤ちゃんの食事」に、煮炊きは出てこない。だが、食べることの意味は、伝わってくる。
単にビスケットを差し出しただけだが、赤ちゃんと叔父叔母との交流が見える。赤ちゃんの白いエリが風にはためく春の朝を、家族たちは、ずっと覚えているだろう(ちなみに赤ちゃんとして「主演」したリュミエールの娘は23年後、スペインかぜで亡くなっている)。
食べるものを用意する。共に食べる。これほど、人と人の関係を近づけるものはない。住めば都も遷都する。食べることが、生活の中心にある家は、幸せと言えるのではないか。
東京カンテイマンションライブラリ関沢のコラムより
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
