海の防人(BFC4応募作)
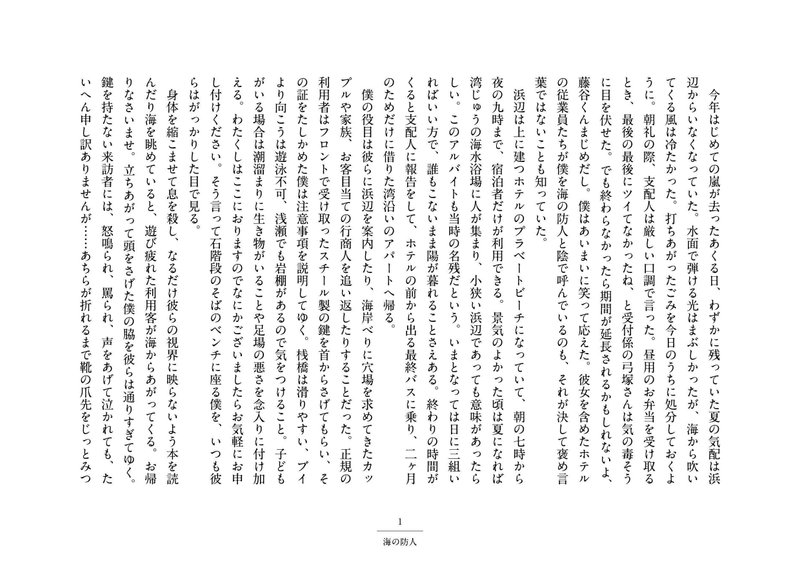


海の防人
今年はじめての嵐が去ったあくる日、わずかに残っていた夏の気配は浜辺からいなくなっていた。水面で弾ける光はまぶしかったが、海から吹いてくる風は冷たかった。打ちあがったごみを今日のうちに処分しておくように。朝礼の際、支配人は厳しい口調で言った。昼用のお弁当を受け取るとき、最後の最後にツイてなかったね、と受付係の弓塚さんは気の毒そうに目を伏せた。でも終わらなかったら期間が延長されるかもしれないよ、藤谷くんまじめだし。僕はあいまいに笑って応えた。彼女を含めたホテルの従業員たちが僕を海の防人と陰で呼んでいるのも、それが決して褒め言葉ではないことも知っていた。
浜辺は上に建つホテルのプラベートビーチになっていて、朝の七時から夜の九時まで、宿泊者だけが利用できる。景気のよかった頃は夏になれば湾じゅうの海水浴場に人が集まり、小狭い浜辺であっても意味があったらしい。このアルバイトも当時の名残だという。いまとなっては日に三組いればいい方で、誰もこないまま陽が暮れることさえある。終わりの時間がくると支配人に報告をして、ホテルの前から出る最終バスに乗り、二ヶ月のためだけに借りた湾沿いのアパートへ帰る。
僕の役目は彼らに浜辺を案内したり、海岸べりに穴場を求めてきたカップルや家族、お客目当ての行商人を追い返したりすることだった。正規の利用者はフロントで受け取ったスチール製の鍵を首からさげてもらい、その証をたしかめた僕は注意事項を説明してゆく。桟橋は滑りやすい、ブイより向こうは遊泳不可、浅瀬でも岩棚があるので気をつけること。子どもがいる場合は潮溜まりに生き物がいることや足場の悪さを念入りに付け加える。わたくしはここにおりますのでなにかございましたらお気軽にお申し付けください。そう言って石階段のそばのベンチに座る僕を、いつも彼らはがっかりした目で見る。
身体を縮こませて息を殺し、なるだけ彼らの視界に映らないよう本を読んだり海を眺めていると、遊び疲れた利用客が海からあがってくる。お帰りなさいませ。立ちあがって頭をさげた僕の脇を彼らは通りすぎてゆく。鍵を持たない来訪者には、怒鳴られ、罵られ、声をあげて泣かれても、たいへん申し訳ありませんが……あちらが折れるまで靴の爪先をじっとみつめつづける。この二ヶ月の間、僕が必要とされたことは一度もなかった。
漂着物の後始末は果てがなかった。巨大な流木たちはひとりで運ぶには重すぎたし、空き瓶、小枝や海藻はふだんと比べ物にならないほど流れ着いていた。とても終わりそうもないが、弓塚さんの言う延長になるとも思えなかった。先月代わったばかりの若い支配人はアルバイトじたいを撤廃したがっていたからだ。いつもどおりパラソルとビーチチェアは設置していたが、浜辺とゴミ捨て場を往復している間も利用客は現れなかった。
浜辺へ続く石階段を降りる途中、暮れはじめた沖に一艘の舟影が浮かんでいるのが見えた。舟のゆくえを目で追っていると、白波も立てずに揺らめきながら、こちらへゆっくり向かっていることに気づいた。もしかしたら他の船着場と間違っているのかもしれない。たまにそういうことがあるとマニュアルには記されていたが、はじめてのことだった。
桟橋の先端で舟が近づいてくるのを待っているうち、乗っているのが黄色のワンピースを着た、髪の長い、女性だとわかった。エンジンの駆動音もオールを漕いでいる様子もなく、嵐が残していった風だけを頼りに進んでいるようだった。木製の小舟だった。よく目を凝らしてみると、とがった顎やしなやかな腕の向こうにぼやけた海が見えた。まばたきしてみても、やはり彼女の肌を通して陽を浴びたさざなみが見えた。
僕が桟橋から動けないでいると舟はゆるやかに着岸し、彼女は頭を深々さげた。風向きが違って難儀してしまいました。「はあ」いつもなら岬からまっすぐ潮に乗れるはずだったんですが。困ったように笑い、海の向こうを指さした。腕はなめらかに動き、ワンピースの裾が風に揺れた。彼女の首からスチール製の鍵がさげられていることに気づいた。
手を貸してくださる? 申し出にどう応えるべきか迷っていたら、彼女の表情がくもり、僕は咄嗟に手を伸ばした。「申し訳ありません。桟橋からいらっしゃるお客様ははじめてだったもので……」ほほえみをたたえた彼女は、僕の手を握り返した。温もりはなかった。長細い指は僕の手のひらのなかでやわらかく発光していて、それから、やはり彼女は軽かった。すこし力をいれて引っ張りあげるだけでその身体はふわりと浮きあがり、むしろ注意を払わなければそのまま青空に飲みこまれてしまいそうだった。
桟橋に降り立った彼女に、僕はいつもと同じ手順で注意事項を説明した。彼女はひとつひとつにうなずいたあとで、これを返してきますので舟を見ていてもらえませんか、と胸元の鍵を持ちあげた。それなら代わりに。言いかけたところで彼女は首を横にふった。ようやくですので。晴れやかに笑ったかと思えば、あっ、と声をあげた。帰りは鍵がないので通してもらえますでしょうか。「心配には及びません」僕は胸を張って答えた。ありがとうございます。彼女はふたたび頭を深々さげ、漂着物の隙間をぬうように歩き、石階段をゆっくりあがっていった。
日が沈んでも僕は桟橋から動かなかった。海風が吹くたび波の砕ける音にまじって舟はぎいぎい鳴ったが、同じ場所に行儀よく留まっていた。客室も二階の大広間も屋上の露天風呂もすべてが暗闇に包まれ、星々がよく見えた。石階段の頂上にやわらかな光をみつけて僕は立ちあがる。お待ちしておりました。口のなかで何度も唱える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
