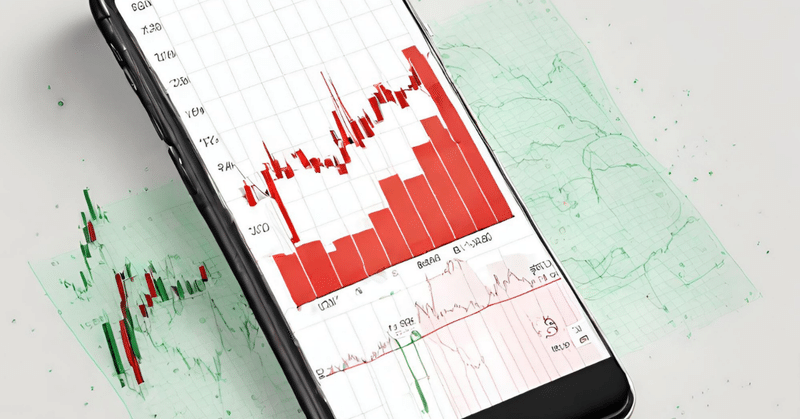
006投資信託をみてみるか
いま、あなたの心の中には、どの様な音楽が流れていますか。
前回は、「投資信託の仕組み」のうち、投資信託の分類とその関係者についてお伝えしました。
今回は、前回からの続きで投資信託のより具体的な仕組みなどについて見てみましょうかね。
投資信託については、前回のとおり多くの分類方法がありました。
そのうち、投資信託に関わる法的根拠などについて、契約型投資信託を例に投資信託委託会社における投資信託設定の流れを見てみましょう。
その前にまずは、投資信託に関する法律である「投資信託及び投資法人に関する法律」(投信法)を見てみましょう。
投信法は、投資信託に関するルールなどが定められています。
どの法律も最初に定義が記載されています。
前回、投資信託には「契約型」と「会社型」があり、その「契約型」の投資信託には、「委託者指図型」と「委託者非指図型」に分かれているとお伝えしました。
その「委託者指図型」のうち、主に有価証券で運用する投資信託を「証券投資信託」と定義しています。
皆さんが知っている投資信託と呼ばれるモノは、この証券投資信託となります。
それでは、投資信託委託会社(資産運用会社)における、一般的な投資信託開発プロセスについてお伝えしたいと思います。
①準備段階
・販売会社を通じて投資者ニーズを探る ・業界/金融市場動向の調査/分析 ・投資対象や運用方針の原案策定 ・提供可能な商品アイデアの策定とバックテスト等 ・パフォーマンス/リスク等の検証 ・投資対象国や市場等の法制度 ・税制リスク等の洗い出し ・投資者ニーズと商品案の擦りあわせ ・商品設定に向けた事務手続き
②商品案の具体化
・法令/諸規則(投資信託協会)および社内規則等への抵触等についてコンプライアンス(弁護士含む)チェック ・当初設定予定日/信託約款届出日等の実現可能なスケジュール調整 ・信託報酬の決定(リスクリターンや類似戦略との比較など)・商品設定の機関決定(投資委員会等)
③商品化
・投資信託約款作成 ・目論見書作成 ・有価証券届出書作成 ・販売用資料の作成 ・投資信託約款の当局届出 ・保管銀行口座開設 ・受託銀行との投資信託契約締結 ・有価証券届出書の届出(EDINET)・社内システム設定 ・ほふり銘柄登録 ・投資信託協会登録 ・販売会社との販売契約締結(システム接続)
④商品のメンテナンスと開示
・投資者ニーズ確認 ・組成時の期待リターンが投資家のコストに見合っているか ・組成後も想定通りに運用し、コストに見合うリターンを提供できているか ・商品が想定する投資家に提供されているか ・法制度への対応 ・市況動向の変化への対応 ・適切な商品性を保つためのモニタリングと必要に応じた信託約款変更の検討 ・運用報告書(法定開示) ・有価証券報告書(法定開示)・月次報告書
特に④商品のメンテナンスが、金融庁が投資信託委託会社に求める「プロダクトガバナンスの強化」だと言えます。
それでは一般的な公募投資信託を例に、主な書面の法的根拠および法定要件等を見ていきます。
~投資信託約款~
投信法第3条(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)の規定により、「委託者指図型投資信託契約は、一の金融商品取引業者を委託者とし、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。」とされています。
また、投信法第4条(投資信託契約の締結)には、「金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下「投資信託約款」)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。(2)投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。(以下略)」とされています。
よって、契約型・委託者指図型の証券投資信託は、その設定にあたり必ず、「受託者」と「投資信託契約」を締結する必要があり、あらかじめ「その内容を内閣総理大臣に届出」する必要があります。
~有価証券届出書~
「金融商品取引法」(以下「金商法」)には、一般投資者の投資判断の前提資料を提供するための制度として開示制度(ディスクロージャー)があります。1998年の金融制度改革により、投資信託受益証券(受益権)についても、金商法上の開示制度の適用を受けるようになりました。
金商法第4条第1項に「有価証券の募集又は有価証券の売出しは、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない」と規定しています。
また、その記載事項は、金商法第5条第1項に「前条の規定による有価証券の募集又は売出しに係る届出をしようとする発行者は、その者が会社においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない」と規定されています。
さらに、この有価証券届出書は金商法第8条第1項に「第四条の規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる」と規定されており、同条第2項に「前項の期間内に訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第五条第一項の規定による届出書の受理があつたものとみなす」と規定されており、有価証券届出書の訂正を行った場合は、その訂正届出を受理した日から、改めて15日を経過した日が効力発生日となると規定されており、有価証券届出書の作成にあたっては、過誤のないように慎重な作成が求められています。
有価証券届出書は、EDINET(関東財務局)を利用し届出を行います。
※訂正有価証券届出書の提出後に、監督官庁が「期間短縮依頼書」の受理承認した場合は、その限りではありません。
~目論見書(「投資信託説明書(交付目論見書)」/「請求目論見書」~
有価証券届出書の届出と同時に目論見書を作成し、有価証券届出書の効力発生日以降に(販売会社を通じて)購入を検討する投資者に交付します。
目論見書の法的根拠と要件は下記の通りです。
金商法第13条第1項に「その募集又は売出しの規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない」と規定されています。
なお、目論見書には次の2種類があります。
1)交付目論見書(金商法第13条第2項第1号イ)
◆有価証券届出書の記載事項のうち、投資者の投資判断にきわめて重要な影響をおよぼすものとして内閣府令で定めるものを記載します(特定有価証券開示府令第15条第1号・2号)。
2)請求目論見書(金商法第13条第2項第2号イ)
◆有価証券届出書の記載事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響をおよぼすものとして内閣府令で定めるものを記載します(特定有価証券開示府令第16条第1号・2号)。
これらの法定要件に加え、投資信託協会「交付目論見書の作成に関する規則」に記載項目・記載内容等の定めがあります。
~販売用資料~
一般に「販売用資料」とは、“投資信託の販売に係る投資勧誘資料として販売会社が投資者に対して、主に商品説明を行うために用いる資料”を指します。
したがって、投資信託委託会社の法定作成物である目論見書や運用報告書も、広い意味では販売用資料の一つです。
しかし、実務上は、目論見書や運用報告書とは別に、投資信託委託会社は投資信託に関する情報を掲載した資料を作成することが多く、その作成物を販売用資料と呼ぶことが多くあります。
なお、これらの資料はいずれも、「広告等」に該当し、金商法の定める広告等の規制の対象となります。(金商法第37条第1項)
改めて販売用資料の法的な位置づけについて見ていきます。
前述のとおり、販売用資料は、金商法で定める広告等の規制の対象に該当します。
しかしながら、金商法の条文上には、この「販売用資料」という文言は見当たりません。
そこで、「販売用資料」の条文上の根拠については、金商法第13条第5項の「何人も、第四条第一項本文の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」に該当すると考えられています。
すなわち、販売用資料は、名実ともに金商法の定める広告等の規制の対象となります。
広告等の規制については、法令の定めに加え、投資信託協会「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」「広告等に関するガイドライン」の規制があります。
~運用報告書~
投資信託約款と同様に、運用報告書の根拠法は投信法となります。
投信法第14条第1項に「投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない」と規定されています。
なお、法改正に伴い、2014年12月以降に作成期日を迎えた運用報告書は、「運用報告書(全体版)」と「交付運用報告書」に分冊して作成することとなり、受益者への交付義務があるのは「交付運用報告書」となります。
また、実務上は販売会社を通じて「交付運用報告書」を受益者に交付する事となりますが、交付義務はあくまで投資信託委託会社の責任となります。
運用報告書の記載要件は、「投資信託財産の計算に関する規則」(第58条・第59条)および投資信託協会「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則・細則・委員会決議」等の定めがあります。
~有価証券報告書~
金商法第24条は「有価証券報告書の提出」について規定しています。
しかし、投資信託の場合は、同条第5項の読み替え規定により、「募集が行われた場合には、特定期間(信託計算期間)ごとに、有価証券報告書を当該特定期間(信託計算期間)経過後3か月以内に(関東財務局長に)提出しなければならない。計算期間が6か月に満たない場合(四半期ごと、隔月、毎月決算、日々決算ファンド)は、特定期間を6か月とするとしています(特定有価証券開示府令第23条第1項)。
ここまで、投資信託の商品開発からメンテナンスまでのプロセスと、法令等に基づく書面等の根拠などについて見てきました。
この「投資信託をみてみるか」のシリーズもここまでとさせて頂きます。
また、違う側面から、投資信託についてお伝えしたいと思います。
本日の1曲は、浜田省吾さんの「AMERICA」です。
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
