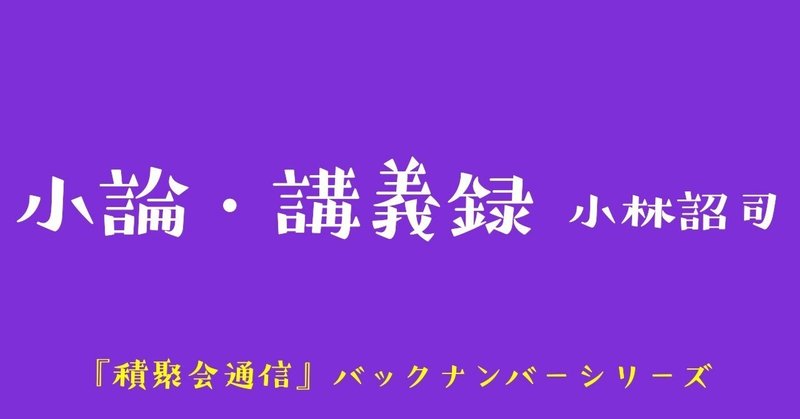
灸をする(7)
積聚会名誉会長 小林詔司
『積聚会通信』No.12 1999年5月号 掲載
古くから禁灸日というのが『鍼灸聚英』を始めいろいろな文献にあるが、『養生訓』ではこれを意味のないこととして避けている。
それはともかくとして、大気にも体にも灸に適したり適さない状況があることは確かである。
灸をするときは風や寒に中らないこととして、大風、大雨、大雪、陰霧、大暑、大寒、雷電、虹などのときは避けるように書いてある(『養生訓』巻第八、39)。
これは今の言い方をすれば低気圧のときは灸をしないということになる。
あるいは大気が湿っているとき、体が湿っているとき、さらにいえば体が濡れているときは灸が適さないということである。
これは一理あることで、体が湿っていれば火の透りが悪いことから灸の効果が落ちると考えられる。
艾も古くて乾操しているものほどよいのは、それだけ火の透りがよいからである。
しかしこれらのことは養生として灸をする場合であり、緊急の場合にはこのようなことをいっておれないのは当然である。
また灸に適さない体の状態もあるとして、次のような内容の記載がある。
それは、食べ過ぎたとき、非常に空腹のとき、酒に酔っているとき、ひどく興奮しているとき、非常に気が鬱いでいるときや不幸のときは適さない、である。
食ベ過ぎたときは気の充実度が高く、灸は熱い。非常に空腹であれば気力は弱く、これも灸の熱に耐えられない。酒に酔っているときも気の巡りは激しいのであるから灸を熱く感じる。同じことは興奮しているときにもいえる。また気が鬱いでいるときなどは気力が弱いのであるから、灸熱にこれも耐えられないのである。
同様のことでスポーツの後や風呂上がりの直後にも灸をしないのがよい。
さてではどういうときに灸をすればよいか、それは天気が晴れていて、さらには空気が乾燥しているときと言う。
そして食事の直後や直前を避け、しらふの時であり、精神的にもあまり不安定でない状態が望ましいことになる。
面白いのは施灸の3日前と7日後は房事をつつしめと書かれていることで、これは房事後3日は気の消耗が激しい、また施灸の後7日は灸による気の巡りが不安定ということと思われる。これなどは如何にも養生的で、若い人には無用のことに思われる。
しかし養生の面から考えれば、房事の後にはむしろ早く灸をしたほうが体にはプラスであろうし、房事の前にも灸をした方が体力の消耗は最小限に防げると考えられる。むしろ「房事に灸」は積極的に考えてよいことである。
この節の最後は、冬至の前5日、後10日の15日間は灸をしないこと、としているが、これは禁灸日を意味ないこととしている論と相いれない印象を受ける。
この冬至は旧暦であるが、今の2月の節分の頃は当時あまりにも大気の冷えが強かったのであろうか。そうであれば最初の「灸をするときは寒に中らないこと」という内容と一脈通じることになる。
