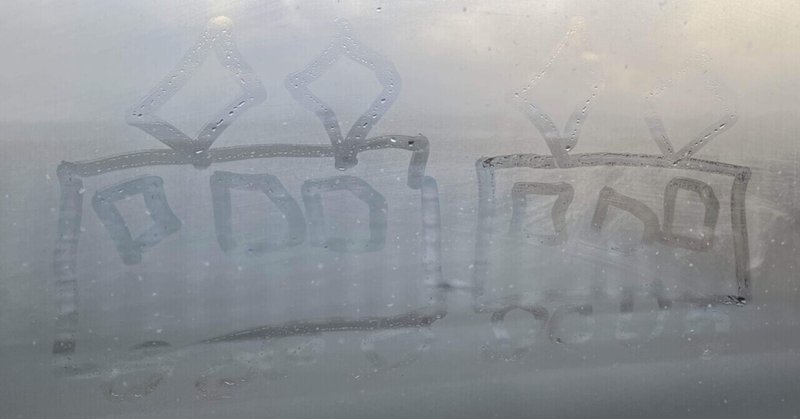
ランジャタイと脱構築
『ランジャタイのオールナイトニッポン』を聞いていて、いわゆる「賞レースのお笑い」には無い瑞々しさをとても感じた。
アニメ『忍たま乱太郎』のジングルが繰り返される無意味な時間や、ウッチャンナンチャンの南原さんのボイスをフィーチャーしたコーナーを聞いて、笑いながらとても不思議な感覚があった。
「ウケた/スベった」という事実がお笑い界の大樹の太い幹になっている現代において、ランジャタイはその構造自体を破壊しているようで、とても魅力的に見える。
現代思想の「脱構築」という、少し古い言葉がしっくりくる。
脱構築とは、システムによって否定されたものを「肯定」する思想なのです。
社会の中で抑圧されたものを肯定することで、あり得るかもしれない「もう一つの可能性」を提示すること。
ランジャタイのネタは、お笑いのシステムで「面白くない」と否定されたものを「肯定」し、「それが面白かったかもしれない可能性」を提示しながら進んでいくのだ。
ネタ中には、同じフレーズがしつこいくらいに繰り返される。ウケていようがウケていなかろうが、関係ない。
>>「おさらばぽんぽん」「絶対家帰ったらやって」
>>「最後は笑顔でさよならしよう」「絶対そのほうがいい」
やりとりの中で発生したフレーズを、何度も何度も繰り返すことで、明後日の方向に向かっていく。フリや構成といった「上手な漫才」に必要不可欠な要素を無視して進んでいく。「面白くない」とこちらが否定したものをあえて肯定し、その先にあるものを提示し(ようとし)てくれる。
お笑いを見るときに、客側は勝手にいろんな前提を作っている。「このボケは面白い/面白くない」「この設定は分かる/分からない」「台本っぽいな/アドリブっぽいな」など、勝手にシステムを決めて、判断するようになってしまった。
ランジャタイのネタは、そこから脱出して、新しい場所へ連れて行ってくれる。いわゆる「お笑い賞レース」に出来始めた勝利の方程式を「脱構築」して、新しい価値を提供してくれるのだ。そこが彼らのネタの魅力である。
しつこく繰り返されるフレーズ以外にも、偶然生まれる間や、ツッコミのタイミングのブレ、国崎さんの臨場感ある動きと、伊藤さんの言葉選びの上手さ、など、後付けで「面白い」というポイントを見つけていくことは可能だ。しかし、所詮それは後付けで、ネタ中はそれよりも「自分がどこに連れて行かれるかわからない(=構造の外側に連れて行かれる)」という不安が、スリリングな面白さにつながっていく。
昨年のM-1で立川志らくさんが「イリュージョン」と評した理由も、そんなところにあるのではないだろうか。
ランジャタイのネタの作りは昔からあまり変わっておらず、時代に合わせたりしたつもりは無いという。
ジェンダーレス、ダイバーシティ、様々な境界が薄らいで、無くなりつつある今、笑いに求められるものも変わってきている。
「すべらない/すべる」「フリに応える/あえてスカす」といった暗黙の了解を脱構築し、システム外側に連れて行ってくれるランジャタイのネタが、今、福音とともにお笑い界に迎えられている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
