2018年ベストアルバム10選
2018年に好きだったアルバムを10枚、順不同で選びました。
なお、ここで選んだ10枚以外でも Meshell Ndegeocello、Angelique Kidjo、Caitlin Canty、Kamasi Washington、Marcus Strickland、Gabriel Kahane、David Crosby、Jeff Tweedy、Lera Lynn、Mary Chapin Carpenter、The Nels Cline 4、Richard Thompson、Elvis Costello、Boz Scaggs、Thom Yorke らのそれぞれ2018年にリリースされたアルバムは同じくらい好きだったし、2017年にリリースされながら聴き逃してた Brian Blade & the Fellowship Band、Dori Freeman、Chris Hillman、Valerie June、Randy Newman、Steve Winwood(ライブ盤) なども愛聴しました。

・The Broken Instrument/Victory
2018年を振り返って、特に印象的だったのが、女性シンガーソングライターによる充実したアルバムが多かったことで、中でも白眉だったのが本作。
デトロイトの音楽一家に生まれたというヴィクトリーことヴィクトリー・ボイドは、Jay-Zが主催するレーベルのロック・ネイションからミニアルバム「 It's a New Dawn」を2017年にリリースしてデビュー。本作は彼女のアイドル的存在であったニーナ・シモンから大きな影響を受けて制作されており、その歌詞からアルバムタイトルの由来ともなっている「Feeling Good」のカバーも収録されているが、アレンジはオリジナルから大胆に改変され、早くもその非凡さを発揮している。
続いて、2018年に満を持してリリースされたフルアルバムが本作「The Broken Instrument」。
フォーク、ジャズ、R&B、ゴスペル等をハイブリッドした音楽性には、確かにニーナ・シモンの影響を感じさせられる一方で、ボサノヴァ風の⑤、リンダ・ルイスを彷彿とさせる抜群にポップな⑧、組曲となっている⑪~⑬などもあり、そのソングライティングの多様さとクオリティの高さに舌を巻く。更に、アレンジもほぼ全て彼女が手掛けているというのだから恐れ入る。
普遍的魅力ある歌心に満ち、高度に洗練されていながらも親しみやすさを併せ持つ本作は、どういった精神状態にあってもスっと入ってきて、聴く度に新鮮な感動を覚える。
今回選んだ10枚は、何れも甲乙付け難く好きなアルバムだが、最も愛聴したのが本作であった。

・The Lookout/Laura Veirs
1973年生まれ、オレゴン州ポートランド出身のシンガーソングライター。1999年にリリースされたデビューアルバムから数えて本作が10枚目のスタジオアルバムとなるので、結構なベテランと言えるが、寡聞にして自分が知ったのは本作から。
そもそも注目したきっかけが、アルバム収録曲(⑤Watch Fire)でスフィアン・スティーヴンスと共演しているという記事を見かけたからなのだが、彼女の浮遊感あるヴォーカルに即魅了されてしまった次第。
タッカー・マルティーヌがプロデュース(ほか、ドラム、ミックス、カバーデザイン等で全面協力)した本作は、フォーク、カントリーをベースにした彼女のソングライティングセンスに加え、例えば80年代~90年代の4AD所属のアーティストが纏っていたような耽美さが加味された、絶妙のバランスに仕上がっている。
本作のコンセプトは“大切なものの儚さ”とのことであり、確かに"儚"という漢字が端的に示す通り、人が触れれば壊れてしまう夢の美しさと脆さを併せ持つ印象もある。
中でも③は彼女の卓越した作曲力とアコースティックギター、ペダルスティールギター、ピアノのアンサンブルが完璧にマッチした傑作であり、年間通して愛聴した。

・Encore/Anderson East
1988年生まれ、アラバマ州アセンズ出身のシンガーソングライター。
2015年にエレクトラ(正確には同レーベル内のLSC)からリリースされたメジャーデビューアルバム「Satisfy Me」が、(ライブハウスでアンダーソンのライブを観てぶっ飛んだと言われる)デイヴ・コブのプロデュースによりフェイム・スタジオでレコーディングされた、と書けば、その音楽性も何となく想像もつくわけだが、果たして、マッスルショールズのマジックが未だ健在であることを証明するかのような仕上がりで、感動させられた。
そして、引き続きデイヴ・コブをプロデューサーに迎え、彼のホームグラウンドとも言えるナッシュヴィルのRCAスタジオでレコーディングされた本作は、デビューアルバムが単なるフロックではないことを痛感させられる見事なものとなった。
海外の音楽メディアでは、ザ・バンド、ヴァン・モリソン、オーティス・レディング辺りが比較対象とされており、アンダーソンの振り絞るようなヴォーカル、特に②、③、⑤といったスローな曲は、なるほど、先に挙げた偉大な先輩たち同様に(人種等関係なく)ソウルフルと形容したくなる。また、バッキングに関しても全盛期のブッカー・T & The MG'sを彷彿とさせるほどの盤石さ。
アンダーソンのような比較的若いアーティストがロック~ソウルの伝統を引き継ぎ、一定のコンテンポラリーさを併せ持つこのようなアルバムを制作したことには、とても頼もしく思うし、ライアン・アダムス、クリス・ステイプルトン、エド・シーランといったゲストの豪華さからも、彼が如何に期待されているアーティストであるかが窺えるのではないか。

・All the Things That I Did and All the Things That I Didn't Do/The Milk Carton Kids
LA出身のケネス・パテンゲイルとジョーイ・ライアンによるデュオ、5枚目となるスタジオアルバム。前作「Monterey」と同様にジョー・ヘンリーをプロデューサーに迎え、ナッシュヴィルのハウス・オブ・ブルーズ・スタジオでレコーディングされている。
デュオというフォーマットやメランコリックなメロディを美しいハーモニーで聴かせる音楽スタイルから、サイモン&ガーファンクルやエヴァリー・ブラザーズと比較されることの多かった彼らであるが、いよいよその本領が発揮されたと言える本作に対して、従前同様の比較をすることはナンセンスだろう。
元来持っていたソングライティングセンスに加え、フォーク、ブルーグラス、カントリー等をしっかりと咀嚼したアメリカーナ系のアレンジが施されるプロダクションはジョーが最も得意とするところであり、まさに自分が待望していたようなアルバムとなった。
時にメランコリック、時にスケール感のあるメロディにリヴォン・ヘンリーの柔らかなサックス~クラリネットが絶妙に絡む楽曲の数々からは、聴いた瞬間に(行ったこともない)アメリカの広大な風景が目に浮かんでくるようで、現代におけるザ・バンドの最良の後継者と言いたくなるほど。
なお、ジョーは彼らの音楽に対し、「聞いているうちに二人の声はひとつに溶け合い、さまざまな体験をくぐり抜け、さまざまな思いを味わったただ一人の人物となって、聞き手の心に強く迫ってくる」との賛辞を送っているが、然りであると思う。

・In the Blue Light/Paul Simon
ポール・サイモンがソロ活動を始めて14枚目となるアルバム。2018年のツアーをもってツアー活動を引退する宣言をしており、年齢的なことを鑑みても若しかしたらこれがラストアルバムになるかもしれないというこちらの感傷的な思いも吹っ飛ばすような快作となっている。
本作はサイモンがソロ活動を行うようになってからリリースされたアルバム、具体的には、3枚目の「There Goes Rhymin' Simon」から12枚目の「So Beautiful or So What」の中から、"必ずしも有名ではない"がサイモンお気に入りの10曲で構成されたセルフカバー集となっている。
オリジナルのアレンジから本作でどのようにリ・アレンジされたのか、簡単に例示してみれば、1曲目「One Man's Ceiling Is Another Man's Floor」は、オリジナルから更にブルージーにした上でジャズの要素を加味、3曲目「Can't Run But」は、オリジナルにあったアフリカン・パーカッションのポリリズムを取り除く代わりに、yMusicによる室内楽風アンサンブルを導入、5曲目の「Pigs, Sheep and Wolves」、これもオリジナルはアフリカ音楽的なポリリズムを用いた曲であったのに対し、曲の持つブルースのフィーリングを活かし、ニューオリンズ・スタイルのジャズへと昇華されている。
レコーディングメンバーにウィントン・マルサリス、ビル・フリゼール、ジャック・ディジョネット、スティーヴ・ガッドら、ジャズ界の大物が参加しており、どの曲でも一定のジャズ的なアレンジはなされてはいるものの、単なるジャジーなセルフカバー集などではなく、各曲の持つポテンシャルを再定義し、ジャズとジャズが様々な音楽の要素を取り入れて進歩していったプロセス、ひいては、アメリカ音楽が進歩していったプロセスそのものを一枚のアルバムで再現しようとするかのようなチャレンジ精神すら感じてしまう。
これは余談かもしれないが、2015年に亡くなってしまった、ニューオリンズのブルース~R&B~ジャズを通じてアメリカ音楽を総括したかのような活動を行っていた(と思ってる)アラン・トゥーサンの遺作となった「American Tunes」(プロデューサーはジョー・ヘンリー)のラストに収められた曲がサイモンの「There Goes Rhymin 'Simon」収録の名曲「American Tune」。
「In the Blue Light」と「American Tunes」の両アルバムにビル・フリゼールが参加していることは何とも示唆的であると思う。

・Vanished Gardens/Charles Lloyd & The Marvels + Lucinda Williams
チャールズ・ロイド&ザ・マーヴェルズ名義での初のアルバムとなる「I Long To See You」を2016年にブルーノートからリリースして以来、2枚目となるアルバム。
1960年代から活躍し続ける大ベテランのロイドに関しては、お恥ずかしながら、名盤「Forest Flower」程度の知識しかなかったわけだけど、ザ・マーベルズのメンバーにビル・フリゼールやエリック・ハーランドらが名を連ね、また、デビューアルバムがウィリー・ネルソンやノラ・ジョーンズがゲスト参加したアメリカーナ路線と聞けば、これはもう自分が最も好物とするところで、実際、ロイドの太くブルージーなテナーサックス(時にフルート)は、フリゼールのギターとグレッグ・レイズのペダルスティールギターによる柔らかく包み込むような音像との相性も抜群で、即座に愛聴盤となった。
そして、前作同様、ブルーノートからドン・ウォズのプロデュースによりリリースされた本アルバムは、なんとアメリカーナの重鎮ルシンダ・ウィリアムズとの共同名義盤。この時点で出来は保証されたようなものだろう。
ルシンダは偶数の曲目で参加しており、中でも最終曲として収録されているジミ・ヘンドリックスのカバー「エンジェル」は、ロイドとフリゼールの美しいインタープレイにルシンダの深みある歌声が絶妙にマッチした至高のコラボレーションとなっている。
それとちょっと興味深かったのが、前作に収録されている「Abide with Me」は、アメリカでは葬儀の際によく演奏されるトラディショナル曲だが、ジャズファンからすれば、セロニアス・モンクの名盤「Monk's Music」のオープニングを飾る曲として、ジョン・コルトレーンらによる演奏も印象的な曲として、お馴染みであると思うが、本アルバムでも、また、モンク作、コルトレーンとの共演も印象深い「Monk's Mood」が収録されており、ロイドがこの二人の関係性に強く惹かれていることが窺える。
そして、本アルバムにおけるロイドのソロにおいても彼流のシーツオブサウンドと呼称したくなるような(とても齢80とは思えない)素晴らしいソロを聴くことができる。
なお、先に書いたアラン・トゥーサン「American Tunes」にはロイドも参加している。
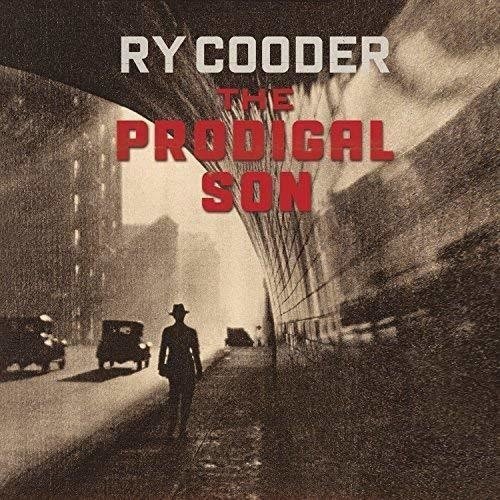
・The Prodigal Son/Ry Cooder
自分にとってライ・クーダーは、ザ・バンド、ビル・フリゼール、ジョー・ヘンリーらと同様にアメリカ音楽の豊潤さを指し示してくれる道標的なアーティストなわけだが、正直、ここ何作かは、やや堅苦しさを感じてて、熱心には聴いてなかった。なので、約6年振りとなるスタジオアルバムが古いゴスペル曲のカバーを中心とするものであるという事前情報を耳にしても特段興味をそそられなかったのだけど、実際、聴いてみると、レイドバックした中にゴスペルに端を発し、ブルース、フォーク、カントリー、ブルーグラス等のアメリカンルーツミュージックを再構築した、これぞライ流のロックンロールと言いたくなる曲に満ちた会心の一作であった。
アルバム収録曲は11曲の内、8曲がゴスペルのスタンダード曲で、残り3曲がライのオリジナルとなっている。
ゴスペルに関する知識が浅薄なので、オリジナルとなるアーティストもブラインド・ウィリー・ジョンソンくらいしか知らず、これを機に新旧両バージョンを聴き比べてみたところ、どの曲も大幅に印象が異なるというものではなく、原曲のテイストをきっちりと残しながら、ライならではのハイブリッドな感覚、今回は特にカントリー~ブルーグラス寄りのアレンジがなされることで、重さが丁度良い感じに中和され、とても聴きやすい仕上がりとなっている。
例えば、ブラインド・アルフレード・リードの「You Must Unload」のオリジナルのアレンジはギターとフィドルによるシンプルなカントリータッチのものであるのに対し、ライの手にかかれば名曲「Across the Borderline」を彷彿とさせる曲として蘇り、カントリーの源流にあるケルトミュージックへの繋がりまで感じさせてくれて感動的だ。
レコーディングに際しては、主にドラムを担当する息子ヨアキムとの共同作業色が強いようで、アルバム名のThe Prodigal Son(放蕩息子)というのも皮肉が効いているが、実際、二人の関係性が良好なおかげで本作のレイドバックした雰囲気が醸成されているのだと思う。
ともかく、今でもライの代表作と言えば、1970年代にリプリーズからリリースされた諸作というイメージが強いが、本アルバムはそういった過去の名作と比較しても何ら遜色はなく、まだまだ現役であることを堂々と示した新たなる代表作と言えるので、暫くライから遠ざかっていたという方にこそ是非聴いていただきたい。
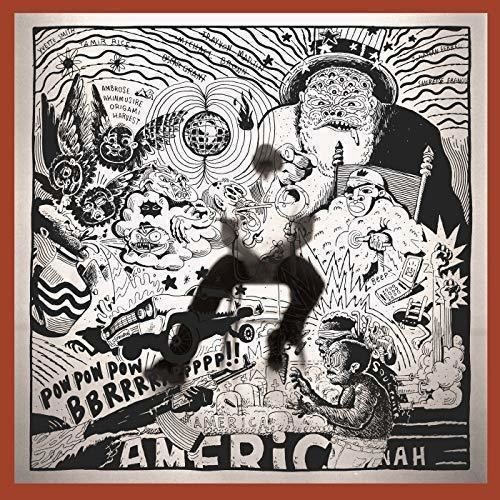
・Origami Harvest/Ambrose Akinmusire
現代ジャズにおける最重要トランぺッターであると思っているアンブローズ・アキンムシーレのスタジオアルバムとしては、「The Imagined Savior Is Far Easier To Paint」以来約4年ぶりとなる新作。とは言え、2017年に充実のライブ盤「A Rift in Decorum: Live at the Village Vanguard」、Blue Note All-Stars名義での「Our Point of View」のリリースがあったので、それほどインターバルがあったという印象は受けない。
さて、日本人からすれば若干奇妙に感じられるこのアルバムタイトル「Origami Harvest」について、アキンムシーレは「"Origami"は黒人たち、特に男性は、その型に合うか否かに関係なく、さまざまな形で社会に屈しなければならない、ということを表している。」と述べている。
そして、アキンムシーレのセルフプロデュースとなる本作の内容はと言えば、これまでになくコンセプチュアルであり、挑戦的なものとなっている。
まず、中心となるレコーディングメンバーが、アキンムシーレ(トランペット)、サム・ハリス(ピアノ)、マーカス・ギルモア(ドラム)、クール・A・D(ラップ)、ミヴォス・カルテット(ヴァイオリン×2、ヴィオラ、チェロ)と、この時点で既に変則的であるのだが、アキンムシーレが語るアルバムコンセプト「相反すると思われるもの同士を隣に配置するような"両極端"についてのプロジェクト」のとおりに、アカデミックさとプリミティブさを兼ね合わせたハイブリッド仕上がりになっていると言えるだろう。
聴く限りの印象として、作曲面においては、推敲に推敲が重ねられ、演奏面においても、特にミヴォス・カルテットのパートは細部までディレクションがなされていることが窺える。その上で、クール・A・Dのラップとアキンムシーレのトランペットがインタープレイを繰り広げる関係性で入り、また、リズム面をほぼ一手に任されたマーカス・ギルモアによるドラムは、基本的にタイトに、時に激しいソロで全体を牽引する。
こういった特殊なコンセプトが見事に昇華されているのも、コンポーザーとしてもインプロヴァイザーとしても極めて高い資質を持ち、また、ジャズに限らずヒップホップやオルタナティヴロックなど様々な音楽の影響を受けていることを公言しているアキンムシーレならではだろう。
アキンムシーレは、最も影響を受けたアーティストとして、ジョニ・ミッチェルを挙げているが、ジョニが1970年代にジャコ・パストリアスやウェイン・ショーターらジャズアーティストと共演し、それまでに培っていた音楽性とジャズを果敢にハイブリッドさせ、シーンを牽引していったその姿勢には、やはりアキンムシーレのそれと共通するものを感じてしまう。
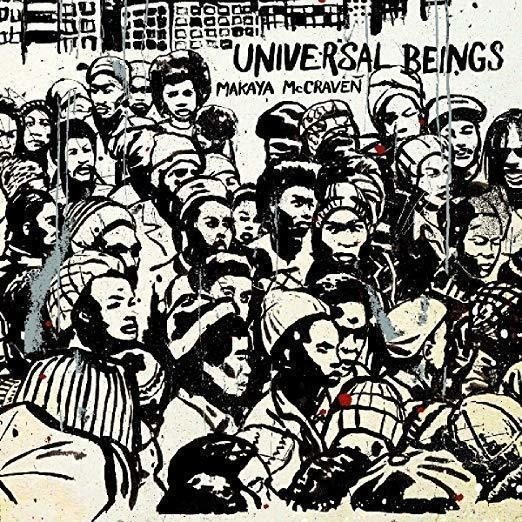
・Universal Beings/Makaya Mccraven
2017年に日本でもリリースされたジェフ・パーカーの「The New Breed」は、トータスを始めとするポストロック的な、ポップにしてアブストラクトなインストゥルメンタルに、J・ディラ~マッドリブ以降を感じさせてくれるシンコペートするビートを兼ね備えた音楽性が新鮮で愛聴していた。そして、同アルバム収録曲「Logan Hardware」のリミックスを担当していたのがマカヤ・マクレイヴンであり、また、2015年にリリースされたマカヤのデビューアルバム「In the Moment」にもジェフ・パーカーが参加していることもあって注目していたのだが、内容的にもやはり素晴らしいものであった。更に2018年に「Where We Come From」というタイトルでライブ音源を加工したミックステープ(Spotyfyとかでも配信されている)等も併せて、そのビート・サイエンティストという異名に相応しい音楽性に底知れぬポテンシャルを感じていた中でリリースされたのが、このセカンドアルバム「Universal Beings」。
まずはCDだと11曲+11曲+ボーナストラック2曲、全24曲の2枚組というボリュームに驚かされる。アーティストが2枚組以上のアルバムを出すということは、往々にして才気が溢れて止まらず、たとえ整合性を欠いていたとしても、そこに込められた熱量に圧倒されるものであり、本作もまたその例に漏れない。
アルバムは①~⑥が「New York Side」、⑦~⑪が「Chicago Side」、⑫曲目~⑯曲目が「London Side」、⑰~㉒が「Los Angeles Side」と四つの都市でレコーディングされた四つのパートで構成されている。
本アバム四つのパート全てが異様なテンションと情報量で、なかなか聴き尽せないところもあるのだが、自分としては、ハープとバイオリンとのアンサンブルも美しい「New York side」、ループするリズムが次第に熱を帯び、強烈なインプロヴィゼーションに昇華されていく「Chicago Side」が特に気に入っている。
その音楽スタイルについて、ざっくりとした印象では、マカヤのドラムはリムショットとシンバルで細分化したビートを変幻自在にループさせながら、時に、J・ディラ~マッドリブ的なシンコペートするビートの上に、フェンダーローズやヴィブラフォンで空間を埋め、ダブルベースとのアンサンブルでグルーブを生み出すといった感じになろうか。その中で、マイルス・デイヴィスを始めとするジャズの伝統に対する深い造詣を感じさせてくれるのもまた頼もしいところだ。
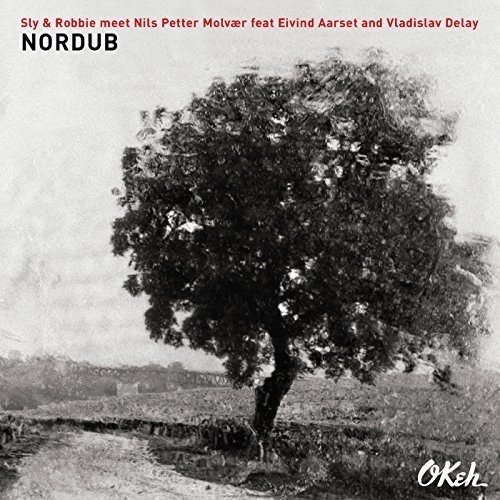
・Nordub/Sly & Robbie meets Nils Petter Molvær + Eivind Aarset + Vladislav Delay
ECMからリリースされた「Khmer」「Solid Ether」において、ジャズ、エレクトロニカ、ドラムンベース、オルタナティヴロック等を独特な手法でハイブリッドし、一躍ノルウェージャズ界の寵児となったニルス・ペッター・モルヴェルだが、2014年にOKehに移籍してリリースされた「Switch」以降、再び充実期に入っている印象を持っている。特にここで共演したゲイル・スンドストゥルのペダルスティールギターとの相性が存外素晴らしく、その深い音像には聴き惚れてしまうほどであり、また、2016年にリリースされた「Buoyancy」でも更なる進化をとげ、感動させてくれた。
そんなモルヴェルが今回共演相手に指名したのが、なんとレゲエ界の大御所中の大御所であるスライ&ロビー。殆ど接点がなさそうな両者だけに果たしてどうなることやら…などというこちらの偏見もあっさりと杞憂に終わる、素晴らしいアルバムとなった。
モルヴェルのディストーションをかけ、くぐもった、そして時に鮮烈なハイノートを聴かせるトランペット、スライ&ロビーの反復するヘビーなリズム、盟友アイヴィン・オールセットの極端なディレイとフィードバックにより空間を幻想的に埋めるギター、そしてヴラディスラフ・ディレイによる陰影と奥行きのあるダブ処理された音響デザインの組み合わせは、まさにコラボレーションならではの、1+1が2を超え、ジャンルを横断するスリルに満ちたものとなっている。
考えてみれば、モルヴェルがこれまでに追求してきたサウンドスケープの源流にダブがあるというのは道理であり、スライ&ロビーとの共演も不思議ではないのだが、それは後付けの理屈であって、やはり両者が共演したことに関しては、慧眼であったと言うしかない。
本作はジャズとしてもレゲエとしても非常に聴き応えのあるアルバムになっていると思うが、例えば、マーク・スチュワートらOn-U周辺のアーティストやPILの「Metal Box」、或いはマッシヴ・アタックの「Blue Lines」辺りが好きな方なら様々な刺激を受けるのではないかと思う。
