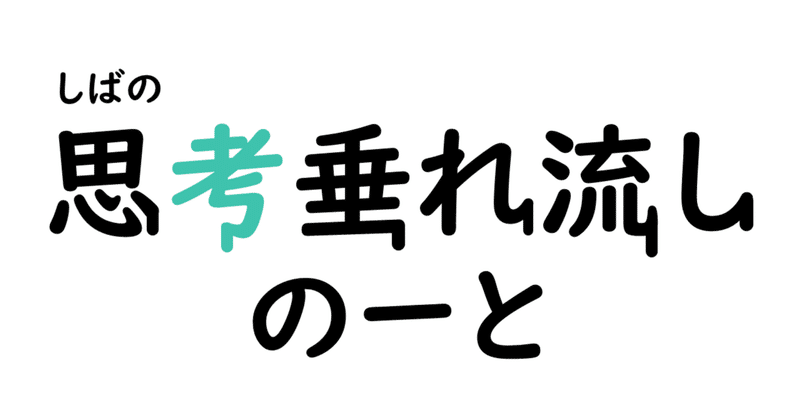
“教育”と”社会”の接続に向き合う民間企業の功罪
“教育”と“社会”をつなげる。これは、自分自身が今向き合っている現業の1つの大事なテーマである。
”教育”は日本だと文部科学省の管轄、 “社会”は日本だと経済産業省の管轄と分かれている。最近では教育においても「個性を大事に」という類の言葉をよく耳にするようになったが、未だに問題ややることを先生や親から指示されることが多く、それらを忠実に守ることができる人が評価される傾向にある。(学校という集団に対して一定の学力を教授することが求められている組織上、“教育”というフィールドにおいて上記の価値観が一定支持されるのは合理的であるともいえる。)一方で、社会に出ると自ら意思決定をし、課題を見つけ、行動できる人が評価されるケースが多くなる。これらのギャップがもたらす不協和音は、”教育“から”社会“のフィールドに出てまだ数年と、日が浅い自分の周りでは至るところで聞こえてくる。
そんな課題観で“教育”と“社会”をつなげようと思って、またそれを民間の立場で日々現業に向き合っているわけだが、果たしてこれは胸を張って善といえるのだろうか。今日は「問いからはじめる教育史」という本をもとに、一度立ち止まって考えてみたいと思う。
教育というのは今では一般的には子どもを対象にしたものを指すことが多いが、この「子ども」という言葉は最初から存在していたものではない。中世では、7歳以上は「小さな大人」とみなされていたなど、新たな労働力としての見方が強かったそう。
“教育”と”社会“との関係性でいうと、熟練者が指導をし、実地訓練を通じて学習を積み重ねる従弟制度という仕組みで結ばれていた。11世紀のヨーロッパでは「ギルト」と呼ばれる同業組合がこの制度を担い、営業の権利を独占しながら教育を行っていたことから、当時は人によってどのような教育を受けるかは様々で、各ギルドで使えることを教育していた。
このことからも当時は”教育“と”社会“は色濃く結びついており、「社会で活躍するため」という前提での教育が行われていたといえる。一方で教育内容や方法には大きな差異があり、劣悪なものも少なくなかったそう。児童労働という点や、教育と社会双方に貫徹する差別、抑圧、排除、搾取が発生していたという課題があった。
それでは現代のように子どもと大人の間に境界線を引くようになった要因は何だったのか。その代表は学校、とりわけ公教育においての学校という存在であろう。
公教育の生まれた背景は、読み書きができ規律に従順な労働者が求められるようになったもの(アメリカ)、中産階級と労働者階級の対立や葛藤の結果として生まれたもの(イギリス)、新制度学派と呼ばれる国民国家として機能ではなく、一流の文明国である象徴としての公教育を築いたもの(ヨーロッパ諸国)など、地域によって異なる。ただ、19世紀~20世紀のヨーロッパにおける産業革命に代表される通り、時代が進むにつれ、単純労働より高度な知的技術が必要になった。次第に児童労働の価値が減少、少産少死社会となり、少なく生んで教育投資をすることの方が有利という考え方が広まったことで、労働から教育への比重が増えていった。
この社会変化と学校・公教育の浸透により、児童労働の割合が減少したほか、公教育という正規のカリキュラムにのっとった教育プログラムによりリテラシーが向上、困難な家庭環境の子にとっても暖房や照明など保護膜として作用するようになった。
こうして「子ども」を教育に集中する環境をつくるため、学校という形で意図して社会と分離させたのである。
ここまでで切り取っているのは教育の歴史のごく一部であり、かつマクロ的に流れを追ってきたとはいえ、上記のような歴史を経てきた教育業界において、今自分は民間企業という立場で社会と教育を接続させようとしている。過去に社会課題に向き合い、教育を変化させてきた者の気持ちは容易に想像することができる。我々は、社会とせっかく切り離した教育の世界を、再び社会につなげ合わせようとしているのだ。加えて、資本主義社会において民間企業という立場でビジネス(よいサービス=よい教育)を追求し、提供していくことは、お金を持っている人に届けることとなり、格差を広げることにもつながりかねない。
もちろん、貧富の差に関わらず質の高い教育が受けられる方法はないかと日々模索している。公教育より理想の教育が追求できる自由な環境として民間を選んでいるという私は思ってしまい、今身をおいている。ただ、今の自分の営みは結果的にある種の罪の側面を持ち合わせているのも、一方でまた事実なのである。
私は上記の功罪をそのまま受け止めたいと思った。そして、独断論にならず、かといって相対主義で何もしない状態にもならないために、その”罪”の面のせめてもの償いとして、定期的に「ただ歴史の揺り戻しにならないためにはどうすればいいかを考えること」をしていきたい。時代は繰り返される”波”のようなものだと私はとらえていて、波の中でいかに過去に戻りきらず、過去よりbetterな方向にたどり着けるかが時代の前進に繋がると思う。そしてbetterな方向にたどり着くためには、過去にどんなことが起こったのか、歴史を学んでおくことが1つの羅針盤になると考えている。最後に、「問いから始める教育史」にて記されている歴史についての解釈が、個人的に紹介したい。
歴史学は「現在は今とは別の姿でもありえた」という偶有性の感覚と、「にもかかわらず~という経緯の結果として現在がある」という因果性の理解の両方を私たちに与えてくれます。このことは、私たちが現在に付き従うのではなく、正面から立ち向かうために、必要不可欠な条件を構成します。なぜなら、そうした歴史感覚を持ったときのみ、私たちにとって、世界は変革可能な対象として立ち現れるからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
