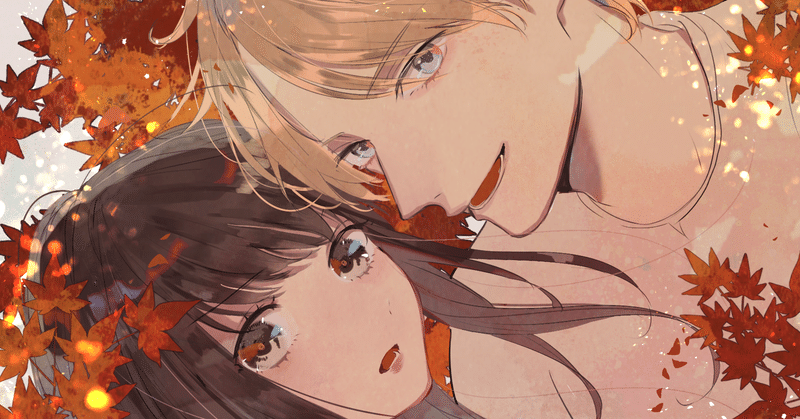
ヒーローじゃない13
「まあ、沢山作ってくれたのね! ありがとうアマネちゃん」
昨日作ったアップルパイと午前中に作った林檎ジャムを持って宮前家を尋ねると、家にいたのは七都子一人だけだった。力也はここから車で三十分ほどかかる町からヘルプ要請が入ったので不在、ひめのは幼稚園と習い事の体操教室だ。ちなみにいつもはアマネと一緒にいる筈のチアキも今この場にはいない。今日は彼が夕方の巡回当番に当たっているからだ。
手製のお菓子を喜ばれるのは純粋に嬉しい。作った甲斐があるし、次はもっと美味しく作れるようになりたいという向上心も湧く。
「今年も駒沢さんに沢山貰ったから。味見はチアキがしてくれたから多分大丈夫、美味しいって言ってた」
「ふふ、すっかり懐かれちゃったわね。知ってる? 男の人は胃袋を掴まれると弱いのよ」
「力也さん見てれば分かる、七都子さんしか目に入ってないもの」
パイもジャムもひめのが帰ってきた時に開けた方が良いだろうと一旦冷蔵庫にそれらをしまっていると、いつものようにテーブルで仕事をしていた七都子のからかい混じりの声が飛んでくる。彼女が言うと説得力がある。女性は料理が出来なければいけないなどという前時代的な価値観を持っているわけではないが、それでも力也が七都子に惚れて結婚を申し込んだ要素の一つだということは知っているし、アマネも彼女の料理は格別だと思っている。
二人の馴れ初めについて、実の所あまり詳しくは知らない。三年前にアマネが来た時にはもう結婚していたし、ひめのも生まれていたのだ。
元々都心で働いていた力也が若気の至りからオイタをして左遷され、その結果この町で七都子と出会いゴールインしたと聞いたくらいだ。『結婚以外は今ん所まんま俺たちと一緒だな、お前とチアキ』とにやにや顔の力也に言われたことがあるが、冗談ではない。少なくとも力也は自殺願望など持ち合わせてはいなかっただろう。
「そうねえ、あの人は……ちょっと変わってるから。チアキ君も少し似た感じよね」
「ええ? 正反対にしか見えないけど」
屈強な大男と痩躯の優男。見た目もそうだが性格的にも似ているようにはとても見えない。冷蔵庫の扉を閉めてパソコンの前に座っていた七都子の隣に腰掛けると、彼女はタイピングしている手はそのままでくすくすと笑う。
「アマネちゃんと一緒にいる時のチアキ君とか、特に似てるなって思うわ。安心出来る居場所になってるのね、きっと」
「私の隣が?」
「そう」
七都子の言葉で、昨日チアキとした会話を思い出す。アップルパイを食べながら、甘い香りに満たされながら。それでも、彼は今も生きる理由を見出せないでいる。今すぐに自殺をしないのは、アマネの説得とフォローのお陰でとりあえず見送っているだけだと言っていた。そんな彼を変えられる何かを、アマネは持っていない。安心出来る居場所になれている自覚もない。
「私、何もしてない。何も……してあげられてなんかない」
「それが、チアキ君にとっては心地良いのかもしれないわ。人が望む距離感なんてそれぞれだもの」
「だと良いけど」
苦味を帯びた笑みを零した所で電話が鳴る。宮前家の固定電話だ。作業を中断して電話を取りに行く七都子をなんとなく眺めていると、受話器を耳に当ててすぐに彼女の様子が険しくなる。
「はい宮前です……ええ……はい、ええっ? バスがっ?」
さっと血の気が引いた様子にただならぬものを感じて、アマネも席を立って七都子の傍に寄る。二言三言会話を続けていた七都子は真っ青な顔でこちらを向いた。
「アマネちゃん、バスが……バスが襲われたって。魔獣に!」
「バスって……どのバス?」
「それがひめのが乗ってる幼稚園バスみたいで……!」
取り乱している七都子の言葉にアマネは息を呑んだ。
幼稚園や習い事教室の送迎は専用のバスがある。最寄りのバス停はすぐ近くにあるので、七都子はいつもそこでひめのの送り迎えをしていた。彼女の手が離せない時はアマネが代わりに行くこともある。
そのバスが魔獣に襲われた? ありえない、と眉間にシワを寄せる。確かに魔獣は人間を襲うが、自分より強いモノには近づかないし手を出さない筈だ。人は魔獣より弱いが、人が作る文明の利器は奴らの力を超える。ミサイルや重火器といった兵器、車や飛行機といった乗り物も当てはまる。バスなどは良い例だ。あんな大きな乗り物より力がある魔獣が生息するのは、この国では北端にある地域だけだ。
「と、とにかく行かないと、ひめのが……!」
「待って、落ち着いて! 七都子さんが行くのはダメ。ここは私と……あ」
そこまで考えて、そういえばチアキも力也も今はいないことを思い出す。普段は二種の自分を放っておくのは良くないと口々に言うくせに、こういう肝心な時にいないだなんて! アマネは胸中で舌打ちをする。
アマネだけ現場に行ったとして、魔獣には高確率で遭遇するだろう。ほんの少し準備さえすれば、身を守る術もバスを守る術もなんとかなる。しかし、魔獣を倒すことは出来ない。そんな状態でいつ戻ってくるかも分からないチアキや力也が来るまでの間どれだけ持ち堪えられるのか。魔獣の種類にもよるが、現時点ではあまりに不明確すぎる。
それは七都子も分かっているようで、受話器を握りしめている手がかたかたと震えていた。
「あの人は……今から電話しても戻ってくるまで三十分はかかるわ。チアキ君は連絡さえ取れればもしかしたら……?」
「ダメ。チアキ、スマホ持ってないの。連絡したくても出来ない」
「そんな……」
項垂れる七都子を見て、ぎゅっと拳を握りしめる。迷っている暇は、ない。車体はある程度強化されているとはいえ、もし今もバスが襲われているとしたらそのうち強化ガラスを突き破って魔獣達が中に入り込んでしまう。中にいるのは運転手と保育士、それに何十人もの園児達。彼らは魔獣から身を守れない。誰かが行って助けに行かなければならない。
──防衛戦は、得意だ。一種の二人がいつ来るか分からなくても、来るまで耐えてみせる。
「分かった」
呟くと、七都子がはっとした様子で顔を上げる。その目を、アマネはまっすぐ見つめ返す。
「私が行く。だから……心配しないで、七都子さん」
装備一式を身につけて車で現場に到着すると、バスからは煙が上がっていた。宮前家に電話が入ってから既に十分近く経っていた。
遅かったか、と歯を噛んで車から降りて駆け寄ると、入り口を固めていた保育士の女性がアマネの姿を見るなり安堵した。
「ああ、アマネさん……っ! 待っていました!」
「遅くなってすみません、状況は?」
「魔獣はもういません。バスの強度に救われました……ただ、エンジンがやられてしまって。ここから動けないんです」
煙が上がっているのは故障が原因ということか。とりあえず大きな怪我人もいないようで安堵する。バスの中で待機していた判断は正しいだろう、もしも大人数で外に出て避難しようとすればまた魔獣に襲われてしまう危険性があるからだ。生身の人間が魔獣と相対してただで済むとは思えない。
「応援を呼びます。移送手段が確保出来るまでここから動かないで下さい」
「分かりました」
「魔獣の特徴、伺えますか。あとどの方向に逃げたかも」
その問いに、保育士は目に見えて困惑の表情を浮かべた。
「それが……飛んでいました」
「飛んでた?」
「ええ。明らかにバスよりは小さかったんですけど……おかしいですよね、この辺に鳥型の魔獣なんて生息してない筈なのに」
保育士の言葉に、先日チアキと交わした会話が脳裏を過ぎる。
見知らぬ羽根、魔獣の痕跡、そして北米で起きた渡り鳥型魔獣の大量繁殖。いない筈の鳥型魔獣が、こんな所にいる原因。魔獣の生態系になんらかの異常が発生しているのかもしれない。何年かに一度はそういう異常現象が起こるのでそれ自体は珍しくない。問題は、周辺の町が飛ぶ魔獣に対する対策が薄いことだ。加えて外来種、鳥型の頭の良さを考えればバスのような大きい乗り物でも計算して襲ってくる可能性は十分にある。
とにかく二人が戻ったら逃した魔獣だけでもすぐに駆除しないと、と考えるアマネに園児の一人が駆け寄ってくる。
「姉ちゃん、ひめのはっ? ひめのは一緒じゃないのかっ?」
「えっ、ひめのちゃん?」
そういえばバスの中に彼女の姿が見当たらない。バスの外も見回すが、人の姿はどこにもなかった。
「ひめの、ここからなら家が近いからパパ達を呼んで来るって窓から出て行ったんだ! だから……!」
「そんな!」
「っ、まずい」
魔獣にとって人間の子供は恰好の獲物だ。しかも飛んでいるなら捕捉もされやすい。
悲鳴を上げる保育士に七都子へ連絡するよう伝えてから、急いで走る。焦燥に走る身体を真っ赤な夕日が照らし出す。時刻はもう、夜に差し掛かろうとしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

