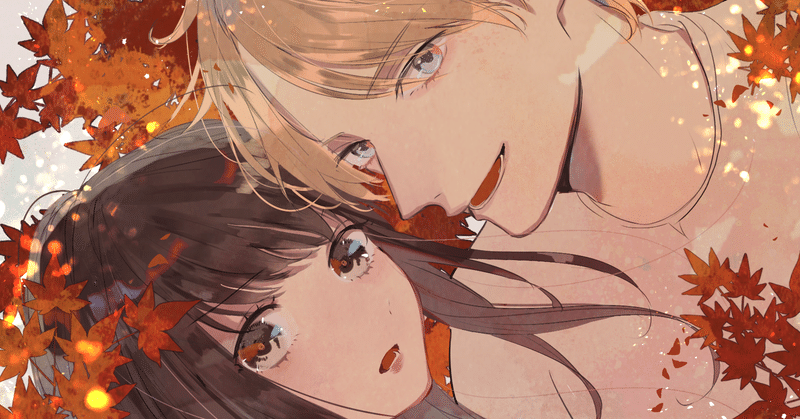
ヒーローじゃない18
三十分程弱火にかけていた鍋の中身を底から木ベラでぐるりとかき混ぜる。ふうわりとした湯気と共に林檎の甘酸っぱい匂いがアマネの鼻腔を擽った。水気もそれなりに飛んで煮詰まっているし、色も蜂蜜に似た丁度良い塩梅。これならもう大丈夫だろう。
鍋を火から下ろして粗熱を取る間は手持ち無沙汰になるので、その間に[向こう]の様子でも見に行こうとエプロンを取ってキッチンを後にした。
今日は自分の家ではなく、駒沢の家のキッチンを借りて料理をしていた。毎年収穫する駒沢の林檎をおすそ分けして貰う代わりにアマネは自作の魔獣避けオイルを提供しているが、その他にも林檎を使った料理を作ってあげるのが常だった。
二年前に奥方を亡くした駒沢はヒーローを引退し、それからずっと一人でこの林檎園を守っている。家事その他はなんとかなっているようだが、流石に細やかな作業やコツが必要になるお菓子作りは全く向かないようで。そんな彼のリクエストを毎年聞く形になっている。
パイ、ジャム、コンポート、ケーキ。林檎料理のレパートリーが増えたのは駒沢の林檎のお陰だ。あの美味しい果物でなければ再現出来ないだろう。
駒沢の家を出て暫く歩くと、やがて一つの建物が見えてくる。横開きの扉を開けると、同時に風を切るような鋭い音が鼓膜を揺らした。
木目が連なる広い道場の真ん中で、チアキが淡々と素振りをしている。聞こえは単純だが、彼が持っているトレーニング用の剣は通常の何倍も重いことは既に知っている。アマネでは両手を使っても満足に持ち上がらなかった。
それをまるで細い木の棒でも振っているように軽々と扱えている辺り、彼もれっきとしたヒーローなのだということを改めて感じた。力也の化け物染みた筋力には及ばないだろうが、チアキも相当力がある。
扉から背を向けて素振りをしているチアキは、相当集中しているのかアマネに気付く様子はなかった。なんとなく声をかけるのも憚られてじっと見ていると後ろから「おや、アマネちゃん」と声をかけられる。
振り返ると、今となっては珍しい胴着姿の駒沢が立っていた。
「あ、ごめんなさい。勝手に入って」
「良いんだよ。そっちは終わったのかい?」
「うん、駒沢さんリクエストは全部作ったつもり。今冷ましてる所だから、ちょっと休憩」
「ありがとう。後で家内にもあげてくれると嬉しいな」
にこにこと機嫌良さそうに笑う駒沢に「勿論」とアマネは首肯する。
アマネの林檎料理は奥方も気に入ってくれていた。彼女も料理は上手い方だったが、勘と目分量で作るレパートリーの方が得意だったのでお菓子は向かなかったのだ。たった一年だけの付き合いとなってしまったが、それでもアマネは彼女のことが好きだったし、奥方もまたアマネを可愛がってくれた。
「チアキ、どう?」
問いかけると、駒沢は視線をアマネからチアキに移しつつ感心のため息を吐き出した。
「さすが、特級ヒーローは次元が違うね。一度手合わせしてみたけど、今の僕じゃ相手にならなかったよ」
「現役だったら違ってた?」
「もう三十歳くらい若ければね」
おどけたように笑って、駒沢は廊下を歩いて道場を離れていく。どうしようか一瞬迷って、結局アマネは彼についていくことにした。雰囲気的にチアキのトレーニングは暫く終わりそうにないし、ここにいては邪魔になるだけだと思ったからだ。
後ろを歩くアマネを特に気にする様子もなく駒沢はゆったりと、しかし背筋はぴんと伸ばして歩き続ける。やがて縁側に到着すると彼はそこに腰掛けた。目前には小さな庭があり、こちらも林檎園と同じくらい良く手入れされている。手が回らない所は業者に頼んでいるらしいが、それでも半分以上は駒沢が一人でこの敷地を管理している。林檎園も、家も、道場も、彼にとっては大切な思い出が詰まっている場所だからだ。
「道場は、もう開けないの?」
隣に座りながら問いかけると、駒沢は「そうだねえ」と穏やかに返した。彼は西洋剣術も東洋剣術も一通り嗜んでいるが、剣道は自らが師範を務められるほどの腕前だ。現役だった頃、ヒーローとしての職務の傍らあの道場で地元の子供達に剣道を教えていた。引退した駒沢の後釜も、弟子の一人だと聞いたことがある。
その道場も、彼がヒーローを辞めたと同時に閉めてしまったので、今はほぼ無人だ。最低限の手入れはアマネも手伝っているが、それでもたまにあの道場が賑わう景色を思い出す。不思議なものだ、それだってたった一年くらいしか見ていなかった筈なのに。
「今は林檎を作るので精一杯だからね。だからチアキ君に来て貰えるのは嬉しいよ、道場はたまにでも使った方が良いからね」
「迷惑になってないならまあ、良かったけど」
鳥型魔獣に襲われてから、チアキは本格的にトレーニングを再開し始めた。たった三週間剣を握らなかっただけでも彼にしてみればブランクを感じて、それがどうにも悔しかったようだ。この辺りでは剣に詳しい駒沢と、彼が持っている道場がチアキのトレーニングには最適だろうということで、チアキは勤務の合間にお邪魔しているようだった。
今日はアマネも駒沢に用事があったので一緒に来たが、どうやら迷惑はかけていないようでひそかに安堵する。変な所で世間ずれしているチアキが駒沢を困らせていないかと少し気になっていたのだ。
「最近は、あまり目の敵にしなくなったね」
チアキに対する当たりの強さだということはすぐに分かった。思わず苦笑すると「責めてるわけじゃないよ」と駒沢は穏やかに続ける。
「アマネちゃんの気持ちも……一種ながら、理解はしてるつもりだよ。君についてる枷はあまりに重く、そして強固だ」
「そんな大層なものじゃない、私が我が儘なだけ。それに……チアキの方が、よっぽど厄介な枷をつけてる」
話は続けつつ、アマネは庭にぼんやりと目線を向ける。からりとした日差しに池の水が照らされている。どこかから舞ってきた紅葉がひらりと池の中心に落ちて波紋を広げた。
「きちんと話をしたんだね」
「ううん……なんか、タイミングが掴めないっていうか。話をさせてくれない雰囲気じゃないんだけど、私は知っちゃいけないことを知ったのにあっちは普通の態度だから。余計に分からなくなっちゃって」
「……それが彼にとっての[日常]だから、だろうね」
核心めいた言葉に目を伏せる。
駒沢の言う通りだ。チアキの目に映る世界はいつでも死という概念があって、それを疑問にすら思わない。アマネも魔獣を相手に仕事をするので当然危険を伴うこともあるが、チアキは比べ物にならないくらい過酷な世界で生きていた。そんな世界から命ごと逃げ出したいと思ってしまうくらいに。
彼の傷を目にしてから、もうすぐ一週間。未だに、チアキとその話は出来ていない。
「アマネちゃんが踏み込むしか、ないんじゃないかな。きっと彼にそれは無理だよ、本来なら踏み込む覚悟が必要だということももう分からないだろうから」
「そうだね……私も、そう思う」
後ろの床に手をついて、アマネは庭から空へと視線を移す。先ほどと変わりない、秋晴れの空だ。
人々を取り巻く世界はこんなにも違うのに、空はいつだって一つだけだ。こんなに穏やかな日々を過ごしているその裏で、誰かが血を流して死んでいるかもしれない。そう思うと爽やかな晴天を素直に喜べなくなる。
分かっていた筈だ。ヒーローになる時に散々教わってきた筈だ。それなのに、本当の意味では理解していなかった自分をアマネは恥じた。
そんな自分が、彼になんと言って話を切り出せば良いのか。それもまだ、分からない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

