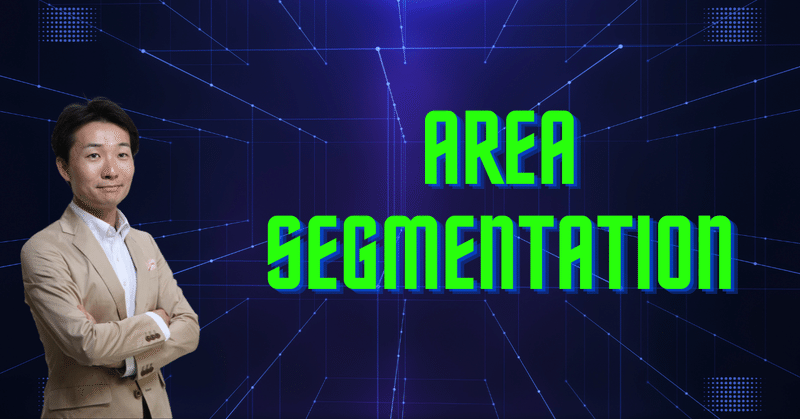
効率化をしたいなら、分割すればいい!OSPFのエリア分割
「管理するカタマリが大きすぎるのって、管理しずらいよね?」
はい、こんにちは!松井真也です。シリーズ「基礎から分かる!ルーティング大全」第13回でございます。
前回は、OSPFパケットについて解説しました。合計5タイプあって、ネイバーの確立、トポロジー情報の交換、情報の更新(要求、更新、受信応答)という流れで、LSDBが作られるのでした。
さて、今回は、OSPFのエリア分割についてお話しします!リンクステート型アルゴリズムでは、交換し管理するトポロジー情報が膨大になりがちで、これを克服するために、ネットワークを複数の「エリア」に分割するのでしたね。これにより、ネットワーク全体の効率が向上させます。

が、イメージがなかなか湧きませんね?もう少し具体的に知りたいですね?では続きをどうぞ!
小さく管理して効率化
まずは、OSPFにおけるエリア分割の必要性についてお話ししましょう。
大規模なネットワークでは、ルータ間で流通するトポロジー情報の量が増大します。これにより、LSA(Link State Advertisement)の流通量が増え、経路計算に必要なリソースが大幅に増加します。
これを効率的に管理するためにはどうしたらいいでしょうか?
そう、管理単位を小さくすればいいわけです!OSPFではネットワークを複数のエリアに分割し、それぞれのエリアで経路計算を行います。これによって、全体の計算量とネットワークの負荷を削減できます。
会社における部署の分割とちょっと似ていますよねw。
エリア分割と役割分担
次に、エリアとその種類について説明します。OSPFネットワークでは、ルータの種類によって異なる役割があります。
OSPFネットワークは、中心となるバックボーンエリア(Area 0)と、それに接続する複数の標準エリアで構成されます(本当は、もっと細かい分類があるのですが、基本を押さえることを優先して単純化します)。

1)バックボーンルータ
バックボーンエリアは、文字通り「背骨」にあたる役割を果たします。異なるエリア間でルーティング情報は、このエリアを経由して伝達されます。
このバックボーンエリア内、そして各エリアの境界にいるのがバックボーンルータです。
2)エリア境界ルータABR(Area Border Router)
ABRは、バックボーンエリアと標準エリア間のルーティング情報を伝達します。図で分かる通り、ABRは、バックボーンルータを兼ねています。
3)代表ルータDR(Designated Router)
DRとそのバックアップBDR(Backup Designated Router)のみが、そのエリア内で、エリア間の情報を保持して効率化します。
4)内部ルータ
内部ルータは、自身のエリア内でのルーティングに特化して、エリア内のトポロジー情報のみ持ちます。
5)AS境界ルータ(AS Border Router)
他のAS(RIPやBGPなどが利用されています)との境界に立つルータです。
エリア分割の利点と課題
以上、エリア分割について見てきましたが、このエリア分割の最大の利点は、ネットワークをスケールさせやすいこと、経路計算・管理の効率性が向上することです。大規模なネットワークでも、エリアごとに経路計算を行うことで、全体のパフォーマンスを維持できます。
が、しかし、エリア分割すればネットワークの設計と管理を複雑になるため、適切な計画と知識が必要になります。設計を誤れば、逆にパフォーマンスが低下したり、管理が困難になるおそれがあります。
はい、本日はここまで!今回はOSPFのエリア分割について知りました。いくつか文献を読みましたが、この詳細な設定は、とても難しいです。私にはよく理解できませんでした…。もっと勉強しないとね!
次回は、OSPFをやっと離れて、AS間のルーティングプロトコル「BGP4」を紹介します!
では、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
